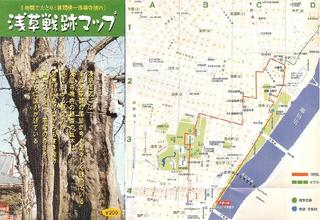kan-haru blog 2008
< 総合INDEX へ
車体上げ作業実演
主工場を見ていると車体上げ作業実演(再掲拡大構内地図E)を開始するとのアナウンスがあり、この日1回目の11時30分からの実演を見学しました。
先ず、作業を実演するメンバーの紹介の後、車体上げの電車を牽引して運ぶ車両牽引車(アント)の登場です。牽引車は、軌陸両用型で車体を上げる車両の線路までゴムタイヤで走行し、線路上に来ると鉄輪をセットして電車を迎えに行き、車体を持ち上げるジャッキーの所まで誘導して牽引します。

車体上げ車両牽引のアント(左:作業メンバー、中:ゴムタイヤで移動のアント、右:電車を牽引する線路に鉄輪セットのアント)
隣の工場から車両を牽引して、持ち上げジャッキーの位置で車体を固定してアントは切り離され元に戻ります。

持ち上げ車両を誘導して牽引するアント(左:隣の工場から車両を牽引、中:ジャッキーまで車両を牽引、右:ジャッキー位置で車両をセット)
車体持ち上げのため左右4ヶ所のジャッキーの制御設定を行い、設定後持ち上げ動作により車体が自動制御により持ち上がり始め、所定の高さに到達すると停止します。
車体の持ち上がっていく高さは、写真のジャッキーに備えてあるランプの光の位置で解ります。

車体持ち上げ作業(左:ジャッキーの持ち上げ制御セット、中:車体をジャッキーが持ち上げ中、右:車体持ち上げ完了)
車体の持ち上げで外された台車は、トラバーサーに積んで保管場所に運ばれます。

台車をトラバーサーで運搬(左:台車を運ぶトラバーサーが接近、中:トラバーサーが台車の前で止まる、右:台車をトラバーサーに引き上げる)
持ち上げ車体の前・後方に、ホークリフトで仮台車を運び車体の下に移動して、台車の位置に設定します。

仮台車のセット(左:ホークリフトで仮台車を運ぶ、中:持ち上げ車体の下に仮台車を運ぶ、右:仮台車の位置をセットする)
仮台車が置かれると、持ち上げジャッキーを下降させて車体を仮台車に乗せます。

持ち上げ車体を仮台車上に降ろす(左:ジャッキー下降制御セット、中:車体が仮台車に降下中、右:ジャッキー降下完了)
仮台車上に置かれた車両は、その車体の修理・整備のためトラクターによって押して移動し、ピットまで運ばれます。

仮台車の車体をピットに移動(左:移動トラクタの登場、中:車体を押して移動、右:車体修理のためピットまで移動)
主工場部品展示
主工場部品展示(構内地図D)は、車体上げ実演を行った大きな主工場内に展示してあり、電車の主な構成部品が見られました。展示部品を見ると、電車がどのような機能を持った部品で作られているのかが解ります。
台車はかなり複雑な構造であり、主電動機は高速で走る割合に小型で、パンタグラフは昔のひし形と比較すると非常に簡単で見るからに軽量化されたことが解りました。

電車構成部品1(左:台車、中:モーター、右:パンタグラフ)
冷房装置は薄い構造だがかなり大型です。電動空気圧縮機はブレーキ系統には欠かせないもので、連結器は先頭車用ものと中間車用では構造が異なっています。

電車構成部品2(左:冷房装置、中:電動空気圧縮機、右:連結器)
主制御装置は、電車の中枢部品で運転台の操作で電車の速度を変えたり、止めたりなどの制御を司る装置です。静止型補助電源装置は、パンタグラフから受けた直流1500ボルトを変換して、直流の24、100ボルトと交流の100、200、440ボルトを作る装置です。バッテリーは、停電の時や始発前の電源として蓄電しておく機器です。

電車構成部品3(左:主制御装置、中:静止型補助電源装置、右:バッテリー)
< 総合INDEX へ
・毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(6月分掲載Indexへ)
・カテゴリー別Index イベント総目次 2008年版、2006・2007年版 へ
<前回 イベント 京急ファインテック久里浜事業所 京急ファミリー鉄道フェスタ2008 その2 へ
次回 イベント 京急ファインテック久里浜事業所 京急ファミリー鉄道フェスタ2008 その4 へ>
< 総合INDEX へ
車体上げ作業実演
主工場を見ていると車体上げ作業実演(再掲拡大構内地図E)を開始するとのアナウンスがあり、この日1回目の11時30分からの実演を見学しました。
先ず、作業を実演するメンバーの紹介の後、車体上げの電車を牽引して運ぶ車両牽引車(アント)の登場です。牽引車は、軌陸両用型で車体を上げる車両の線路までゴムタイヤで走行し、線路上に来ると鉄輪をセットして電車を迎えに行き、車体を持ち上げるジャッキーの所まで誘導して牽引します。

車体上げ車両牽引のアント(左:作業メンバー、中:ゴムタイヤで移動のアント、右:電車を牽引する線路に鉄輪セットのアント)
隣の工場から車両を牽引して、持ち上げジャッキーの位置で車体を固定してアントは切り離され元に戻ります。

持ち上げ車両を誘導して牽引するアント(左:隣の工場から車両を牽引、中:ジャッキーまで車両を牽引、右:ジャッキー位置で車両をセット)
車体持ち上げのため左右4ヶ所のジャッキーの制御設定を行い、設定後持ち上げ動作により車体が自動制御により持ち上がり始め、所定の高さに到達すると停止します。
車体の持ち上がっていく高さは、写真のジャッキーに備えてあるランプの光の位置で解ります。

車体持ち上げ作業(左:ジャッキーの持ち上げ制御セット、中:車体をジャッキーが持ち上げ中、右:車体持ち上げ完了)
車体の持ち上げで外された台車は、トラバーサーに積んで保管場所に運ばれます。

台車をトラバーサーで運搬(左:台車を運ぶトラバーサーが接近、中:トラバーサーが台車の前で止まる、右:台車をトラバーサーに引き上げる)
持ち上げ車体の前・後方に、ホークリフトで仮台車を運び車体の下に移動して、台車の位置に設定します。

仮台車のセット(左:ホークリフトで仮台車を運ぶ、中:持ち上げ車体の下に仮台車を運ぶ、右:仮台車の位置をセットする)
仮台車が置かれると、持ち上げジャッキーを下降させて車体を仮台車に乗せます。

持ち上げ車体を仮台車上に降ろす(左:ジャッキー下降制御セット、中:車体が仮台車に降下中、右:ジャッキー降下完了)
仮台車上に置かれた車両は、その車体の修理・整備のためトラクターによって押して移動し、ピットまで運ばれます。

仮台車の車体をピットに移動(左:移動トラクタの登場、中:車体を押して移動、右:車体修理のためピットまで移動)
主工場部品展示
主工場部品展示(構内地図D)は、車体上げ実演を行った大きな主工場内に展示してあり、電車の主な構成部品が見られました。展示部品を見ると、電車がどのような機能を持った部品で作られているのかが解ります。
台車はかなり複雑な構造であり、主電動機は高速で走る割合に小型で、パンタグラフは昔のひし形と比較すると非常に簡単で見るからに軽量化されたことが解りました。

電車構成部品1(左:台車、中:モーター、右:パンタグラフ)
冷房装置は薄い構造だがかなり大型です。電動空気圧縮機はブレーキ系統には欠かせないもので、連結器は先頭車用ものと中間車用では構造が異なっています。

電車構成部品2(左:冷房装置、中:電動空気圧縮機、右:連結器)
主制御装置は、電車の中枢部品で運転台の操作で電車の速度を変えたり、止めたりなどの制御を司る装置です。静止型補助電源装置は、パンタグラフから受けた直流1500ボルトを変換して、直流の24、100ボルトと交流の100、200、440ボルトを作る装置です。バッテリーは、停電の時や始発前の電源として蓄電しておく機器です。

電車構成部品3(左:主制御装置、中:静止型補助電源装置、右:バッテリー)
< 総合INDEX へ
・毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(6月分掲載Indexへ)
・カテゴリー別Index イベント総目次 2008年版、2006・2007年版 へ
<前回 イベント 京急ファインテック久里浜事業所 京急ファミリー鉄道フェスタ2008 その2 へ
次回 イベント 京急ファインテック久里浜事業所 京急ファミリー鉄道フェスタ2008 その4 へ>