人麻呂の自然感 春を詠む
柿本人麻呂は、職業人としては技術系官僚としてトップの位置にあたる四位の高官に昇り詰めた人物です。一方、和歌においては多面の歌人です。恋人と情熱をラブレターの詩で詠いあげ、職場では荘厳な公式な挽歌で儀礼を整えます。それでいて、人麻呂は、一人のときには世界で最初に自然の美に価値を見出し、その美しさを日本人の感性で詠い挙げています。ここでは、和歌の専門家は全く評価しませんが、私の好きな「自然を愛する人麻呂」の一面を紹介します。
さて、人麻呂歌集を眺めていると、春の花の歌が少なく霞を詠ったものの方がかえって目に付きます。巻十三に人麻呂歌集の歌として中春の躑躅や山櫻を比喩に取り上げた歌や、巻十一に有名な晩春の山百合を歌ったものもあるのですが、いま一つ、私にはしっくり来ません。どうも、人麻呂は、歌からすると早春の夕べの霞の懸かった情景が好きだったようです。その中で、私の好きな歌を以下に載せます。
これは、人麻呂が感じた自然の風景を、故事や漢語の技巧を駆使することなく、そのまま和歌にしたものと思っています。そして、そこには人間の姿は、ありません。世界初の人間の介在を必要としない、自然の美の世界です。この人間の介在を必要としない自然の美の感性は、日本人特有な感性で、中国では盛唐でやっと現れるテーマです。
集歌1812 久方之 天芳山 此夕 霞霏微 春立下
訓読 ひさかたの天の香具山このゆふべ霞たなびく春立つらしも
私訳 遥か彼方の天の香具山よ、この夕べに香具山の一帯に霞が朧げに棚引く、春になったらしい。
集歌1816 玉蜻 夕去来者 佐豆人之 弓月我高荷 霞霏微
訓読 玉かぎる夕さり来れば猟人の弓月が嶽に霞たなびく
私訳 トンボ玉のように色の移り変わる夕刻になると、猟人の弓のように輝く弓月が嶽に霞が棚引く。
何気ないように思えるこれらの歌は、淡いパステル画の風景に似ています。強い光の中での歌ではありませんが、光のコントラストが大変美しい歌です。そこが、好きなところです。
最初に普段の解説と違って、これらの歌については、特に原文の漢語と訓読の両方で、歌を鑑賞してください。また、「久方之」や「玉蜻」の詞を枕詞としている解説もあるようですが、歌の重要なキーワードとなりますので、原文の漢語が持つ意味を重視してください。さらに、人麻呂は巻向の穴師から倭の平地を眺めて、これらの歌を詠ったと思っています。
さて、集歌1812の歌は、立春(現在の2月上旬)をやや過ぎた夕暮れに巻向方向から西方、やや遠くの香具山を眺めての歌です。歌の「久方之」から、人麻呂は大和盆地の遠景を切り取って詠っています。その大和盆地の暮慕の中に香具山は、赤い夕日の光で山容の輪郭を茜色で縁取られ、山体は陰となり暗く大和の藤井ガ原の葦原に浮かんでいます。周囲の葦原は、早春ですからまだ枯れ葦で、夕日にやや黄金の茜色に染まっている情景です。しかし、早春ですから葦原に緑はありません。この情景で香具山の周りには霞が懸かり、一層に風景は朧げを増しています。さらに、「霞霏微」からはその日の気象が分かります。このとき、上空は澄み切って、風はありません。季節は現在の厳冬の時期にあたりますが、気持ちが緩むような寒さがやや和らいだ穏やかな春日の夕暮れです。もし、場所が合えば、その夕日は香具山から沈みます。人麻呂は、晩秋から初春の夕日の太陽が赤く見える時期にしか見えない大和の、この茜と陰のコントラストの風景を立春の景色としています。私は、絵画的にも大変美しい自然の情景と思っています。
意訳文でなく、こころで「パステルカラーの静止絵画」として感じたい歌です。
次に、集歌1816の歌は、集歌1812の歌より少し時間が入ります。早春の夕暮れに弓月が嶽の峰は、次第に夕日に照らされる茜の部分を狭めて、稜線だけが茜色に染まる一瞬の情景です。もう、香具山の葦原に光はありません。日没後すぐに香具山から目を返して、弓月が嶽の稜線にだけに光がある情景です。人麻呂は早春の淡い夕日に稜線が照らされ移ろう情景を「玉蜻」と云い、落ち逝く夕日に細く照る光の山の端を「弓」としています。その光の「弓」は時間の経過で、次第に青暗い残光の闇に消えていきます。その光色の変化を思ってください。その光の変化が、人麻呂の云う「玉蜻」なのです。そして、その消え逝く光の下の山裾は春霞に覆われて暗く朧な情景です。このように、大変美しく時間と光を感じさせる歌です。
集歌1812の歌がパステルカラーの色彩美しい静止絵画の世界なら、この歌は動画の世界です。それも「光と闇の動画とそのコントラスト」です。
もし、集歌1812や集歌1816の歌が、同じ日に詠われたものならば、夕暮れのわずか三十分位の大和盆地の情景を、連続写真のように切り取ったものとなるのではないでしょうか。そして、この自然への感性が、大和朝廷を取り巻く人々の共通のものだったと思われます。これが、大和の風流なのでしょう。人麻呂が花の歌をあまり作らなかったのも、この感性かもしれません。直接的な静止した彩色美の花よりも、移ろい行く自然の動的な一瞬毎の情景美に、より価値を見出していたのでしょうか。個人的には、この感性を好む立場です。
秋の歌になりますが、この人麻呂の光への感性がよく現れているのが、次の歌ではないでしょうか。
集歌1068 天海丹 雲之波立 月船 星之林丹 榜隠所見
訓読 天の海に雲の波立ち月の船星の林に漕ぎ隠る見ゆ
私訳 天空の海に雲の波が立ち、三日月の船が星の林の中に漕ぎ出し、見え隠れするのが見える。
秋の夕闇の中、西の空の上空に雲間に浮かぶ月があります。歌の「榜隠所見」の「榜」の漢字が示すように、人々が声を嗄らして船を波を立てながら漕ぎ往くのではありません。帆を揚げて滑るように静かに三日月の月の船は進むのです。つまり、上空の雲は帶雲のように月の下にあります。また、屋外照明のない時代ですから、天空の星は降るように明るくあちこちにあります。
私はこの光と比喩の感性が好きです。その三日月の船に乗るのが、七夕の夜に恋人に会いに行く月人壮士です。今は新暦の七夕ですが、本来は月齢七日の夜の行事です。
榜:本来は「木の棒を大地に立てる」が意味のようです。大地に立てた棒に公布を付けたところから、立て札・高札の意味が派生してきます。また、木の棒から棒杖、笞の意味合いも出てきたようです。そこから、梶や櫓とは意味合いが違うと考えています。それで、船に棒を立てるイメージから帆柱です。万葉集では大船には「榜」の漢字を多用しますから、ガレー船のようなオール漕行ではなく、帆走をしていたと思っています。ただし、専門家は「榜」を櫂を漕ぐ意味合いに捉えているようです。
さて、これらの歌は、およそ人麻呂が三十歳前半の歌と思われます。時代性として、このような美的感性を持つ人麻呂は、「隠れ妻」と人を介しての歌の遣り取りで、愛を育んでいます。「隠れ妻」にとって、人麻呂は美的感性の面で手強い相手ではなかったでしょうか。想像で、漢詩が読める家持の時代ぐらいまでは、「隠れ妻」たちと同様に人麻呂をきちんと理解していたと思います。
古今集時代では、さて、どうでしょうか。もし、解説で「玉蜻」を枕詞としていたら、その人は「たまかぎる(玉蜻)」と「ひらがな書き」した新古今集以降と同じ感性の人です。ただし、紀貫之は「古歌の目録の歌」から推定して、十分に人麻呂の漢字表記のすごさと人が介在しない自然の美の感性を理解しています。
ここまでに説明したように、集歌1816の歌は「光」が重要なテーマの一部です。その「光=玉蜻」を枕詞として単なる修辞として棄てたら、何を歌に見つけたのでしょうか。たぶん、「人麻呂の歌の何処がいいのか判らない。なぜ、歌聖なのだろうか」と思うのではないでしょうか。飛鳥の人々が楽しんだ蜻玉(とんぼだま)の光のように、光色が色々と変化する、その雰囲気や夕暮れの光の中でのコントラストの美しさは、どうなるのでしょうか。
和歌心の薄い素人は、こんな風に妄想を膨らませて、もう少し人麻呂の歌や万葉集歌を愉しむことが出来ます。
もし、週末に時間があれば、落ち往く夕日を眺めてみてください。真夏の夕日は力強く白黄色に輝き夕日でもまぶしいのですが、晩秋から初春の太陽は赤く直視できるものです。その差を感じていただけたらと、思っています。そして、暮れ行く時間帯での照らされる東のビルや山の端の光の変化を楽しんでください。その光の移ろいと移動の早さにビックリすると思います。そして、その光の移ろいのショーが終わった後に、急に肌寒さを感じ、人恋しくなると思います。
仏教は空色論で「人が思うから自然は存在する」と論破しますが、大和人は人が想うが想うまいと、自然は美しく存在するのです。そのひねりが、次の大伴旅人と読み人知れずの感性です。
集歌341 賢跡 物言従者 酒飲而 酔哭為師 益有良之
訓読 賢(さか)しみと物言ふよりは酒飲みて酔ひ泣きするしまさりたるらし
私訳 戒律を求め、人の性について賢そうに議論をするより、破戒の酒を飲んで酔って泣く方が人の性の本質を突いているようだ。
集歌442 世間者 空物跡 将有登曽 此照月者 満闕為家流
訓読 世間(よのなか)は空しきものとあらむとぞこの照る月は満ち闕(か)けしける
私訳 現世の世界は空間認識に基づく仏教理論では空であるらしい。ところが、それにも関わらず、今、照っている月は満ち欠けする。
専門家が何と云ようと、万葉の時代から日本人は自然の美を素直に感じ、高度に表現するのです。
柿本人麻呂は、職業人としては技術系官僚としてトップの位置にあたる四位の高官に昇り詰めた人物です。一方、和歌においては多面の歌人です。恋人と情熱をラブレターの詩で詠いあげ、職場では荘厳な公式な挽歌で儀礼を整えます。それでいて、人麻呂は、一人のときには世界で最初に自然の美に価値を見出し、その美しさを日本人の感性で詠い挙げています。ここでは、和歌の専門家は全く評価しませんが、私の好きな「自然を愛する人麻呂」の一面を紹介します。
さて、人麻呂歌集を眺めていると、春の花の歌が少なく霞を詠ったものの方がかえって目に付きます。巻十三に人麻呂歌集の歌として中春の躑躅や山櫻を比喩に取り上げた歌や、巻十一に有名な晩春の山百合を歌ったものもあるのですが、いま一つ、私にはしっくり来ません。どうも、人麻呂は、歌からすると早春の夕べの霞の懸かった情景が好きだったようです。その中で、私の好きな歌を以下に載せます。
これは、人麻呂が感じた自然の風景を、故事や漢語の技巧を駆使することなく、そのまま和歌にしたものと思っています。そして、そこには人間の姿は、ありません。世界初の人間の介在を必要としない、自然の美の世界です。この人間の介在を必要としない自然の美の感性は、日本人特有な感性で、中国では盛唐でやっと現れるテーマです。
集歌1812 久方之 天芳山 此夕 霞霏微 春立下
訓読 ひさかたの天の香具山このゆふべ霞たなびく春立つらしも
私訳 遥か彼方の天の香具山よ、この夕べに香具山の一帯に霞が朧げに棚引く、春になったらしい。
集歌1816 玉蜻 夕去来者 佐豆人之 弓月我高荷 霞霏微
訓読 玉かぎる夕さり来れば猟人の弓月が嶽に霞たなびく
私訳 トンボ玉のように色の移り変わる夕刻になると、猟人の弓のように輝く弓月が嶽に霞が棚引く。
何気ないように思えるこれらの歌は、淡いパステル画の風景に似ています。強い光の中での歌ではありませんが、光のコントラストが大変美しい歌です。そこが、好きなところです。
最初に普段の解説と違って、これらの歌については、特に原文の漢語と訓読の両方で、歌を鑑賞してください。また、「久方之」や「玉蜻」の詞を枕詞としている解説もあるようですが、歌の重要なキーワードとなりますので、原文の漢語が持つ意味を重視してください。さらに、人麻呂は巻向の穴師から倭の平地を眺めて、これらの歌を詠ったと思っています。
さて、集歌1812の歌は、立春(現在の2月上旬)をやや過ぎた夕暮れに巻向方向から西方、やや遠くの香具山を眺めての歌です。歌の「久方之」から、人麻呂は大和盆地の遠景を切り取って詠っています。その大和盆地の暮慕の中に香具山は、赤い夕日の光で山容の輪郭を茜色で縁取られ、山体は陰となり暗く大和の藤井ガ原の葦原に浮かんでいます。周囲の葦原は、早春ですからまだ枯れ葦で、夕日にやや黄金の茜色に染まっている情景です。しかし、早春ですから葦原に緑はありません。この情景で香具山の周りには霞が懸かり、一層に風景は朧げを増しています。さらに、「霞霏微」からはその日の気象が分かります。このとき、上空は澄み切って、風はありません。季節は現在の厳冬の時期にあたりますが、気持ちが緩むような寒さがやや和らいだ穏やかな春日の夕暮れです。もし、場所が合えば、その夕日は香具山から沈みます。人麻呂は、晩秋から初春の夕日の太陽が赤く見える時期にしか見えない大和の、この茜と陰のコントラストの風景を立春の景色としています。私は、絵画的にも大変美しい自然の情景と思っています。
意訳文でなく、こころで「パステルカラーの静止絵画」として感じたい歌です。
次に、集歌1816の歌は、集歌1812の歌より少し時間が入ります。早春の夕暮れに弓月が嶽の峰は、次第に夕日に照らされる茜の部分を狭めて、稜線だけが茜色に染まる一瞬の情景です。もう、香具山の葦原に光はありません。日没後すぐに香具山から目を返して、弓月が嶽の稜線にだけに光がある情景です。人麻呂は早春の淡い夕日に稜線が照らされ移ろう情景を「玉蜻」と云い、落ち逝く夕日に細く照る光の山の端を「弓」としています。その光の「弓」は時間の経過で、次第に青暗い残光の闇に消えていきます。その光色の変化を思ってください。その光の変化が、人麻呂の云う「玉蜻」なのです。そして、その消え逝く光の下の山裾は春霞に覆われて暗く朧な情景です。このように、大変美しく時間と光を感じさせる歌です。
集歌1812の歌がパステルカラーの色彩美しい静止絵画の世界なら、この歌は動画の世界です。それも「光と闇の動画とそのコントラスト」です。
もし、集歌1812や集歌1816の歌が、同じ日に詠われたものならば、夕暮れのわずか三十分位の大和盆地の情景を、連続写真のように切り取ったものとなるのではないでしょうか。そして、この自然への感性が、大和朝廷を取り巻く人々の共通のものだったと思われます。これが、大和の風流なのでしょう。人麻呂が花の歌をあまり作らなかったのも、この感性かもしれません。直接的な静止した彩色美の花よりも、移ろい行く自然の動的な一瞬毎の情景美に、より価値を見出していたのでしょうか。個人的には、この感性を好む立場です。
秋の歌になりますが、この人麻呂の光への感性がよく現れているのが、次の歌ではないでしょうか。
集歌1068 天海丹 雲之波立 月船 星之林丹 榜隠所見
訓読 天の海に雲の波立ち月の船星の林に漕ぎ隠る見ゆ
私訳 天空の海に雲の波が立ち、三日月の船が星の林の中に漕ぎ出し、見え隠れするのが見える。
秋の夕闇の中、西の空の上空に雲間に浮かぶ月があります。歌の「榜隠所見」の「榜」の漢字が示すように、人々が声を嗄らして船を波を立てながら漕ぎ往くのではありません。帆を揚げて滑るように静かに三日月の月の船は進むのです。つまり、上空の雲は帶雲のように月の下にあります。また、屋外照明のない時代ですから、天空の星は降るように明るくあちこちにあります。
私はこの光と比喩の感性が好きです。その三日月の船に乗るのが、七夕の夜に恋人に会いに行く月人壮士です。今は新暦の七夕ですが、本来は月齢七日の夜の行事です。
榜:本来は「木の棒を大地に立てる」が意味のようです。大地に立てた棒に公布を付けたところから、立て札・高札の意味が派生してきます。また、木の棒から棒杖、笞の意味合いも出てきたようです。そこから、梶や櫓とは意味合いが違うと考えています。それで、船に棒を立てるイメージから帆柱です。万葉集では大船には「榜」の漢字を多用しますから、ガレー船のようなオール漕行ではなく、帆走をしていたと思っています。ただし、専門家は「榜」を櫂を漕ぐ意味合いに捉えているようです。
さて、これらの歌は、およそ人麻呂が三十歳前半の歌と思われます。時代性として、このような美的感性を持つ人麻呂は、「隠れ妻」と人を介しての歌の遣り取りで、愛を育んでいます。「隠れ妻」にとって、人麻呂は美的感性の面で手強い相手ではなかったでしょうか。想像で、漢詩が読める家持の時代ぐらいまでは、「隠れ妻」たちと同様に人麻呂をきちんと理解していたと思います。
古今集時代では、さて、どうでしょうか。もし、解説で「玉蜻」を枕詞としていたら、その人は「たまかぎる(玉蜻)」と「ひらがな書き」した新古今集以降と同じ感性の人です。ただし、紀貫之は「古歌の目録の歌」から推定して、十分に人麻呂の漢字表記のすごさと人が介在しない自然の美の感性を理解しています。
ここまでに説明したように、集歌1816の歌は「光」が重要なテーマの一部です。その「光=玉蜻」を枕詞として単なる修辞として棄てたら、何を歌に見つけたのでしょうか。たぶん、「人麻呂の歌の何処がいいのか判らない。なぜ、歌聖なのだろうか」と思うのではないでしょうか。飛鳥の人々が楽しんだ蜻玉(とんぼだま)の光のように、光色が色々と変化する、その雰囲気や夕暮れの光の中でのコントラストの美しさは、どうなるのでしょうか。
和歌心の薄い素人は、こんな風に妄想を膨らませて、もう少し人麻呂の歌や万葉集歌を愉しむことが出来ます。
もし、週末に時間があれば、落ち往く夕日を眺めてみてください。真夏の夕日は力強く白黄色に輝き夕日でもまぶしいのですが、晩秋から初春の太陽は赤く直視できるものです。その差を感じていただけたらと、思っています。そして、暮れ行く時間帯での照らされる東のビルや山の端の光の変化を楽しんでください。その光の移ろいと移動の早さにビックリすると思います。そして、その光の移ろいのショーが終わった後に、急に肌寒さを感じ、人恋しくなると思います。
仏教は空色論で「人が思うから自然は存在する」と論破しますが、大和人は人が想うが想うまいと、自然は美しく存在するのです。そのひねりが、次の大伴旅人と読み人知れずの感性です。
集歌341 賢跡 物言従者 酒飲而 酔哭為師 益有良之
訓読 賢(さか)しみと物言ふよりは酒飲みて酔ひ泣きするしまさりたるらし
私訳 戒律を求め、人の性について賢そうに議論をするより、破戒の酒を飲んで酔って泣く方が人の性の本質を突いているようだ。
集歌442 世間者 空物跡 将有登曽 此照月者 満闕為家流
訓読 世間(よのなか)は空しきものとあらむとぞこの照る月は満ち闕(か)けしける
私訳 現世の世界は空間認識に基づく仏教理論では空であるらしい。ところが、それにも関わらず、今、照っている月は満ち欠けする。
専門家が何と云ようと、万葉の時代から日本人は自然の美を素直に感じ、高度に表現するのです。













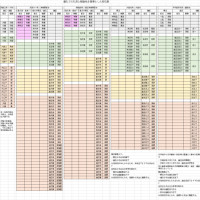






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます