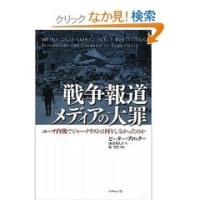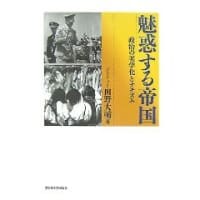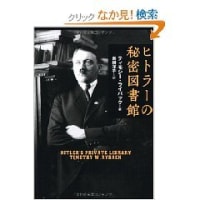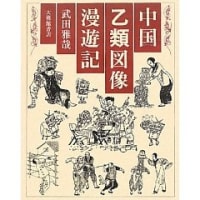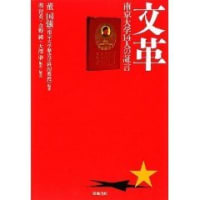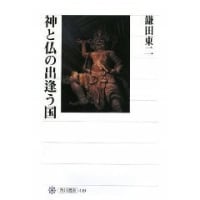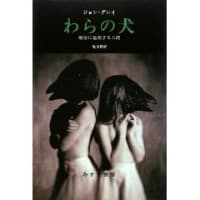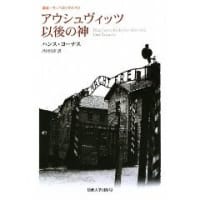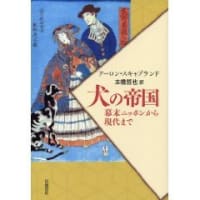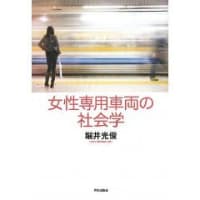ニュルンベルクはナチの党大会が行われた都市で、第二次世界大戦後は、国際軍事裁判所がドイツの主要戦争犯罪人22人に対して裁判を行った場所でもある。1946年に判決があり、12人に絞首刑、3人に終身刑が言い渡された。本書はこのニュルンベルク裁判を扱った内容で、そこに著者のフアミリーヒストリーを絡めるという重層的内容だ。著者の祖父レオン・ブフホルツはレンベルク(ウクライナ西部の都市)に生まれたユダヤ人で、迫害に苦しめられた。著者は祖父と家族の事跡をたどって、この時代のユダヤ人が受けた様々な困難を描く。そして同じレンベルクに生まれた二人の法律家、ハーシュ・ラウターパクトとラフアエル・レムキン、さらにナチの閣僚で法律家のハンス・フランク(彼は1942年8月、レンベルクに二日滞在していくつかの演説をした)の事跡を追って最後に三人がニュルンベルク裁判で合流するという仕掛けになっている。
レンベルクにかかわる四人の人生を描く故、伝記四人分の分量になり、500ページを超える大部の本になった。白水社ならではの本である。レンベルクはリヴィウ、ルヴォフ、ルヴフ、レンベルクと1914年から1945年にかけて支配者が八回も変わった所で、激動の歴史を持つ。登場人物はハンス・フランクを除いてこの地で育ったユダヤ人である。
ラウターパクトは国際法の専門家でケンブリッジ大学教授、ニュルンベルク裁判で「人道に対する罪」を初めて導入した。一方ラフアエル・レムキン(アメリカに亡命)は「ジェノサイド」という犯罪概念を作り出した法律家である。「ジェノサイド」も本裁判の起訴状に採用された。今では聞き慣れたこの二つの言葉も当時はまだ無名で、戦争裁判で戦勝国がこのような罪名で敗戦国の幹部を裁くこと可能なのかどうか疑問視された側面もある。「ジェノサイド」は「人道に対する罪」よりさらに強い意味を持ち、民族の絶滅を意味するものだが、ラウターパクトはこのレムキンの言葉に批判的だった。集団のアイデンティティーを、犠牲者としても加害者としても法律の問題として扱うことの危惧を持っていたのではないかと著者は推測する。
ある集団を保護しようとする法律の意図が(ポーランド・マイナリティー条約がそうであったように)、急転直下激しい反動を生むのをラウターパクトはかつてレンベルクで目の当たりにしたのだ。部族主義が持つ強烈な力を強化するのではなくそれを制限するために、たまたま属している集団の素性などとは無関係に個人一人ひとりの保護を強化したいという願いによって動機づけられているのだ。集団ではなく、個人に重点を置くことによって、ラウターパクトは集団が相互に反目しあうエネルギーを減衰させようとした。それは合理的で啓蒙的、理想主義的な見解だったと著者はいう。よって一人ひとりの個人が、残虐行為を見て見ぬふりをせぬ法の下で保護される権利を有することになる。そして彼は被告人たちに的を絞っていく。自分たちの救命のために「国家のために行為した者は何らかの形で刑事責任から免除される」という通用しない時代遅れの国際法にすがる被告人を断罪する。被告人とりわけハンス・フランクはラウターパクトの家族の殺人に最も直接に関与していた男だった。フランクは直接には処刑に関与していなくても、「殲滅の罪」の「直接の代理人」だった。後のアイヒマン裁判でアイヒマンはただ命令に従っただけで自分は無実だと釈明したが、ラウターパクトの論では言い逃れできないことになる。結局フランクは絞首刑になった。
ニュルンベルク裁判が終わった後、政界や公の議論の場所では。ジェノサイドという言葉が勢いを増してきて、ジェノサイドが「犯罪のなかの犯罪」と位置づけられるとともに、集団の保護の方が個人の保護よりも上位に位置づけられるようになったと著者はいう。しかし、ジェノサイドという犯罪を立証するのは難しく、その過程で犠牲者集団の連帯意識が強烈になる一方で、加害者集団に対する否定的感情が高まり、集団間の対立を激化させる可能性を高める危惧を否定できない。昨今のポピュリズムの跋扈と民族主義の台頭による世界の分断化を見るにつけ、今一度ラウターパクトの意見に耳を傾けるべきではないか。
レンベルクにかかわる四人の人生を描く故、伝記四人分の分量になり、500ページを超える大部の本になった。白水社ならではの本である。レンベルクはリヴィウ、ルヴォフ、ルヴフ、レンベルクと1914年から1945年にかけて支配者が八回も変わった所で、激動の歴史を持つ。登場人物はハンス・フランクを除いてこの地で育ったユダヤ人である。
ラウターパクトは国際法の専門家でケンブリッジ大学教授、ニュルンベルク裁判で「人道に対する罪」を初めて導入した。一方ラフアエル・レムキン(アメリカに亡命)は「ジェノサイド」という犯罪概念を作り出した法律家である。「ジェノサイド」も本裁判の起訴状に採用された。今では聞き慣れたこの二つの言葉も当時はまだ無名で、戦争裁判で戦勝国がこのような罪名で敗戦国の幹部を裁くこと可能なのかどうか疑問視された側面もある。「ジェノサイド」は「人道に対する罪」よりさらに強い意味を持ち、民族の絶滅を意味するものだが、ラウターパクトはこのレムキンの言葉に批判的だった。集団のアイデンティティーを、犠牲者としても加害者としても法律の問題として扱うことの危惧を持っていたのではないかと著者は推測する。
ある集団を保護しようとする法律の意図が(ポーランド・マイナリティー条約がそうであったように)、急転直下激しい反動を生むのをラウターパクトはかつてレンベルクで目の当たりにしたのだ。部族主義が持つ強烈な力を強化するのではなくそれを制限するために、たまたま属している集団の素性などとは無関係に個人一人ひとりの保護を強化したいという願いによって動機づけられているのだ。集団ではなく、個人に重点を置くことによって、ラウターパクトは集団が相互に反目しあうエネルギーを減衰させようとした。それは合理的で啓蒙的、理想主義的な見解だったと著者はいう。よって一人ひとりの個人が、残虐行為を見て見ぬふりをせぬ法の下で保護される権利を有することになる。そして彼は被告人たちに的を絞っていく。自分たちの救命のために「国家のために行為した者は何らかの形で刑事責任から免除される」という通用しない時代遅れの国際法にすがる被告人を断罪する。被告人とりわけハンス・フランクはラウターパクトの家族の殺人に最も直接に関与していた男だった。フランクは直接には処刑に関与していなくても、「殲滅の罪」の「直接の代理人」だった。後のアイヒマン裁判でアイヒマンはただ命令に従っただけで自分は無実だと釈明したが、ラウターパクトの論では言い逃れできないことになる。結局フランクは絞首刑になった。
ニュルンベルク裁判が終わった後、政界や公の議論の場所では。ジェノサイドという言葉が勢いを増してきて、ジェノサイドが「犯罪のなかの犯罪」と位置づけられるとともに、集団の保護の方が個人の保護よりも上位に位置づけられるようになったと著者はいう。しかし、ジェノサイドという犯罪を立証するのは難しく、その過程で犠牲者集団の連帯意識が強烈になる一方で、加害者集団に対する否定的感情が高まり、集団間の対立を激化させる可能性を高める危惧を否定できない。昨今のポピュリズムの跋扈と民族主義の台頭による世界の分断化を見るにつけ、今一度ラウターパクトの意見に耳を傾けるべきではないか。