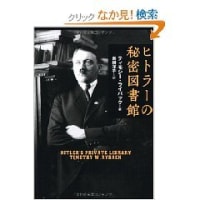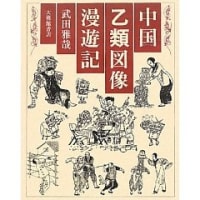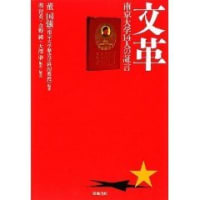本書は第170回直木賞受賞作。「新たな熊文学の誕生‼ 各所で話題沸騰!身体の芯をえぐられるような死闘の連続!」と腰巻にあったので買ってみた。熊の小説と言えば、吉村昭の『羆嵐』が夙に有名だが、それと比べてどうかという興味もあった。吉村作品は明治期、北海道の天塩の開拓村が巨大なヒグマに襲われ多数の死者を出した事件をもとにしたもので、ヒグマの恐ろしさを実感させるほどの筆致であった。ヒグマにさらわれた妻を懸命に探した夫が発見したのは無残な妻の姿であった。「おっかあが少しになっている」という夫の言葉がすべてを語っている。私はこの小説を再読・三読した。
本書の舞台は北海道、時代は日露戦争前夜。猟師の熊爪は人里離れた山中に独居し獲物が獲れた時だけ町へ下りて肉や毛皮を商う。ある日熊爪は熊に襲われた瀕死の男を救う。男と熊の死闘、男の右目が熊の一撃でつぶされたが、その男の手当てを迅速に行う手際は、山で暮らす人間の特性がよく出ている。自然相手に暮らす人間の強さというかなんというか。文明化されない人間の原質が書かれている。熊の恐怖というよりは主人公熊爪の存在感の方が大きい。熊爪は肉や毛皮を売りに行く大店で盲目の少女陽子を見初める。そして同居して子供を設けることになるのだが、この男女関係はまさに野生動物のそれを彷彿とさせる書き方だ。陽子はすでに大店の主人良輔との間に子供を宿していたが、山に連れて来たのである。そして今度は自分の子供を孕ませる。
その間のまぐわいを次のように描く。「だからその夜も熊爪は陽子を思うさま抱いた。陽子は子がダメになるかも知れないから困る、と言ったが、知ったことではない。良輔の子が腹にいた時は言われるままに堪えたが、自分の子なら良いではないか。きっと耐えられるし、耐えられなければそれまでだ、という感覚があった。腹の子を自分の身体の延長と見なし、熊爪は甘え切っていた。それに、陽子の温かい体に突っ込んでいる間は、余計なことを考えずに済む。たとえこれが夢であっても、快楽に溺れる夢ならそれでいい。体よりも思考が先に融けて、夢もない眠りの果てに愚鈍な朝がくる。いつものように熊爪は熊の毛に包まれて覚醒した。」ここはなかなか力が入った書きっぷりで、他のエロティックな小説の表現にはない迫力がある。この後熊爪は陽子に刺殺されるのだが、この展開はシュールで読者にはわかりにくいだろう。陽子に殺されることを甘受するというその諦念が奈辺に由来するのか。ここら辺が想像力を搔き立てるところで、読みのポイントになるが、陽子が雌熊になって熊の毛に包まれた熊爪を殺すというアナロジーなのかもしれない。「新たな熊文学の誕生‼」とはこれを指して言っているのだろう。だとすると熊はただのヒグマではなく、ここでは厳しい自然の象徴で、その中でのたうち回る人間の営為を描いているということになる。この点でノンフイクション的要素の大きい吉村昭の『羆嵐』とは一線を画している。だとすると長編ではあるが、芥川賞の方がふさわしいのではないか。
本書の舞台は北海道、時代は日露戦争前夜。猟師の熊爪は人里離れた山中に独居し獲物が獲れた時だけ町へ下りて肉や毛皮を商う。ある日熊爪は熊に襲われた瀕死の男を救う。男と熊の死闘、男の右目が熊の一撃でつぶされたが、その男の手当てを迅速に行う手際は、山で暮らす人間の特性がよく出ている。自然相手に暮らす人間の強さというかなんというか。文明化されない人間の原質が書かれている。熊の恐怖というよりは主人公熊爪の存在感の方が大きい。熊爪は肉や毛皮を売りに行く大店で盲目の少女陽子を見初める。そして同居して子供を設けることになるのだが、この男女関係はまさに野生動物のそれを彷彿とさせる書き方だ。陽子はすでに大店の主人良輔との間に子供を宿していたが、山に連れて来たのである。そして今度は自分の子供を孕ませる。
その間のまぐわいを次のように描く。「だからその夜も熊爪は陽子を思うさま抱いた。陽子は子がダメになるかも知れないから困る、と言ったが、知ったことではない。良輔の子が腹にいた時は言われるままに堪えたが、自分の子なら良いではないか。きっと耐えられるし、耐えられなければそれまでだ、という感覚があった。腹の子を自分の身体の延長と見なし、熊爪は甘え切っていた。それに、陽子の温かい体に突っ込んでいる間は、余計なことを考えずに済む。たとえこれが夢であっても、快楽に溺れる夢ならそれでいい。体よりも思考が先に融けて、夢もない眠りの果てに愚鈍な朝がくる。いつものように熊爪は熊の毛に包まれて覚醒した。」ここはなかなか力が入った書きっぷりで、他のエロティックな小説の表現にはない迫力がある。この後熊爪は陽子に刺殺されるのだが、この展開はシュールで読者にはわかりにくいだろう。陽子に殺されることを甘受するというその諦念が奈辺に由来するのか。ここら辺が想像力を搔き立てるところで、読みのポイントになるが、陽子が雌熊になって熊の毛に包まれた熊爪を殺すというアナロジーなのかもしれない。「新たな熊文学の誕生‼」とはこれを指して言っているのだろう。だとすると熊はただのヒグマではなく、ここでは厳しい自然の象徴で、その中でのたうち回る人間の営為を描いているということになる。この点でノンフイクション的要素の大きい吉村昭の『羆嵐』とは一線を画している。だとすると長編ではあるが、芥川賞の方がふさわしいのではないか。