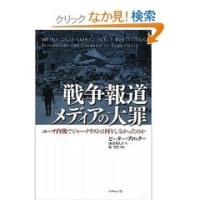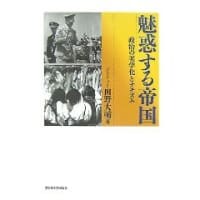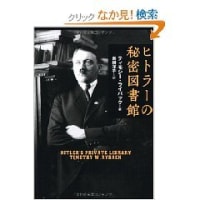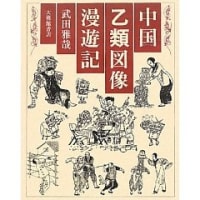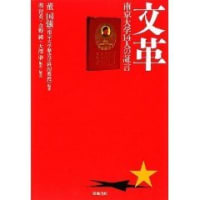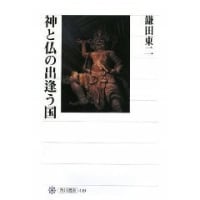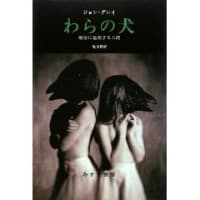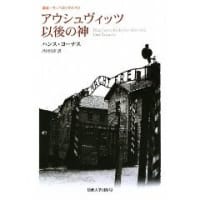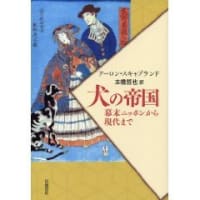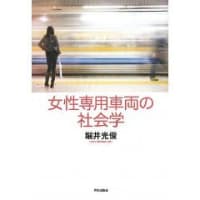タイトルが面白いので読んでみた。津村氏は2009年に『ポストライムの舟』で芥川賞を受賞、その後も順調にヒット作を出している。私は彼女の熱心な読者ではないが、時々読んでは人間関係の描き方がうまいなあと感心することがことが多い。津村ワールドというべきものを持った有能な作家だと言える。本書は大学卒業後14年間働いた会社をストレスでやめた後、非正規で就いた五つの仕事について述べたもの。主人公は作者の分身と思われる女性だ。目次は、第1話 みはりのしごと 第2話 バスのアナウンスの仕事 第3話 おかきの袋のしごと 第4話 路地を訪ねるしごと 第5話 大きな森の小屋での簡単なしごと となっている。これらの「しごと」を著者は実際体験したのだろうか、本当にこれらの仕事があるのだとしたら、世間は広いものだと言わざるを得ないし、著者が想像で描いたとすればそれはそれですごい能力だ。
学校教育を終えたあとの関門は就職ということになるが、就職は生きる糧を手に入れる手段で非常に重要になってくる。したがって高校などでも生徒は就職に有利になるようにと、よりレベルの高い大学を目指すという風潮が一般的だ。最近の中高一貫校の人気はそれを助長している。よりレベルの高い高校、大学に入れば将来は保証されるということだろうが、どっこい社会はそう簡単ではない。職場に入ればそこでの人間関係や取引先の人偏関係に悩まされることになる。そこをどうクリアーするかが大きな問題である。高学歴であってもコミュニケーション能力の不足で、脱落していく人間も多い。逆にそれほど高学歴でなくても持ち前の根性と愛嬌で出世していく人もいる。
本書の主人公は大卒の三十代半ばの女性で、バリバリのエリートではなくごく普通の人間として描かれており、読者は感情移入しやすい。その彼女が14年間務めた会社を辞めて、進路を転換したのだ。一大決断と言えるが、逆に言うとそれをせざるを得ないほどストレスが溜まっていたと言えよう。このように日々ストレスフルな環境にいれば、結婚云々の話はなかなか難しくなるのは想像に難くない。女性の高学歴化によって晩婚化は定着し、これが少子化問題に拍車をかけていることは間違いない。自分にそこそこの収入があれば、無理に結婚する必要もないのだろう。これは一種の文化的成熟の結果であり、歯止めをかけるのは難しいだろう。
本書の五話を読むと、それぞれの職場には上司もいれば同僚もいる。その人間関係の中で仕事をするわけだが、仕事そのもののストレスに加えて、人間関係のストレスが大きくなってくる。これは私の経験からも言えることだ。馬が合わない、そりが合わない人間と仕事をせざるを得ない時ほどつらいものはない。こうした人間関係をスムーズに乗り越えるすべは、高学歴だからと言って身についているわけではない。ここが人生のダイナミズムで、いわばカオスの中でのたうち回らざるを得ないのである。「この世にたやすい仕事はない」とはよく言ったものだ。
この五つの職場で主人公は働いた。そこに現れる上司・同僚はいずれも存在感があって、作者の体験が投影されていて共感できる。第5話の最後の主人公の述懐、「どんな穴が待ちかまえているかはあずかり知れないけれども、だいたい何をしていたって、何が起こるかなんてわからないつてことについては、短い期間に五つもの仕事を転々としてよくわかった。ただ祈り、全力を尽くすだけだ。どうかうまくいきますように」を読むと、その健気さに落涙しそうだ。若者よ健闘を祈る、そして幸福をつかんでくれ‼
学校教育を終えたあとの関門は就職ということになるが、就職は生きる糧を手に入れる手段で非常に重要になってくる。したがって高校などでも生徒は就職に有利になるようにと、よりレベルの高い大学を目指すという風潮が一般的だ。最近の中高一貫校の人気はそれを助長している。よりレベルの高い高校、大学に入れば将来は保証されるということだろうが、どっこい社会はそう簡単ではない。職場に入ればそこでの人間関係や取引先の人偏関係に悩まされることになる。そこをどうクリアーするかが大きな問題である。高学歴であってもコミュニケーション能力の不足で、脱落していく人間も多い。逆にそれほど高学歴でなくても持ち前の根性と愛嬌で出世していく人もいる。
本書の主人公は大卒の三十代半ばの女性で、バリバリのエリートではなくごく普通の人間として描かれており、読者は感情移入しやすい。その彼女が14年間務めた会社を辞めて、進路を転換したのだ。一大決断と言えるが、逆に言うとそれをせざるを得ないほどストレスが溜まっていたと言えよう。このように日々ストレスフルな環境にいれば、結婚云々の話はなかなか難しくなるのは想像に難くない。女性の高学歴化によって晩婚化は定着し、これが少子化問題に拍車をかけていることは間違いない。自分にそこそこの収入があれば、無理に結婚する必要もないのだろう。これは一種の文化的成熟の結果であり、歯止めをかけるのは難しいだろう。
本書の五話を読むと、それぞれの職場には上司もいれば同僚もいる。その人間関係の中で仕事をするわけだが、仕事そのもののストレスに加えて、人間関係のストレスが大きくなってくる。これは私の経験からも言えることだ。馬が合わない、そりが合わない人間と仕事をせざるを得ない時ほどつらいものはない。こうした人間関係をスムーズに乗り越えるすべは、高学歴だからと言って身についているわけではない。ここが人生のダイナミズムで、いわばカオスの中でのたうち回らざるを得ないのである。「この世にたやすい仕事はない」とはよく言ったものだ。
この五つの職場で主人公は働いた。そこに現れる上司・同僚はいずれも存在感があって、作者の体験が投影されていて共感できる。第5話の最後の主人公の述懐、「どんな穴が待ちかまえているかはあずかり知れないけれども、だいたい何をしていたって、何が起こるかなんてわからないつてことについては、短い期間に五つもの仕事を転々としてよくわかった。ただ祈り、全力を尽くすだけだ。どうかうまくいきますように」を読むと、その健気さに落涙しそうだ。若者よ健闘を祈る、そして幸福をつかんでくれ‼