1月28日(土)、寒さをついて東陽町の江東文化センターまで出かけ、江東オペラ公演『ラ ボエーム』を観た。娘が主宰するオペラ創作集団「ミャゴラトーリ」公演への出演メンバーの一人、バリトン歌手薮内俊弥君がマルチェッロ役で出演するので、応援を兼ねて出かけたのだ。全体としては「まあ、まあ」という感じであったが、彼は好演でひときわ光った。それはさておき…
このオペラを見る度に、何と悲しい物語だろうといつも思う。1830年ごろのパリには、貧しいが夢だけは追うボヘミヤンと呼ばれる芸術家たちが集まっていた。ここにも、詩人、画家、音楽家、哲学者の四人が、屋根裏に一緒に住んでいる。想像を絶する貧しさで、部屋の椅子を次々に薪にして暖を取る有様だ。誰かが仕事にありついた少しの稼ぎで、全員が夜を徹して飲む。それでも、クリスマスの夜はカルチェ・ラタンに繰り出す夢は捨てない。
下階に住むお針子ミミと、ふとしたことから恋に落ちた詩人ロドルフォは、既に重い病を抱えるミミが貧乏な自分と一緒では死を早めると別れを決意する。「夢だけでは生きていけない」と別れを決意する歌は、夢に生きる若者が歌うだけに悲しい。つらい冬にあって「春四月の最初の太陽が私のもの」と自己紹介したミミは、せめて冬は一緒にいて春別れようと望み、一緒に居れることだけを願い 「この冬がもっと長ければいいのに」 と謳う。何とも悲しい。大好きな春は別れの時なのだ。
時がたって、ミミはいよいよ死期を感じ 「せめて最後はロドルフォのそばで」と、親友ムゼッタに連れられて四人の住む屋根裏に現れる。そのやつれ果てた姿を見て、ムゼッタは指輪を、哲学者はコートを…、とみんな自分の持ち物を出し合って、ミミのために薬と医者を用意する。しかしみんなにみとられて、ミミはロドルフォの腕の中で息絶える。
オペラには悲劇が多く、悲しい物語が多い。しかし多くは貴族や上流階級の話である。それに比し「ボエーム」は最下層の人々の物語だけに救いがない。しかも夢多い若者たちの話だけに悲しさが増幅する。ただ、このような若者たちが、19世紀から20世紀にかけて新しい文化、芸術を生み出してて行ったのであろう。いつもそこに救いを求めて気持ちを収めるのだが…。
振り返って今の世はどうか?


















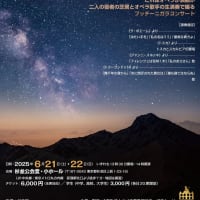

でも、だからこそそこから、私たちは「いかに生きるべきか」を感じ取ることが出来るのだと思います。ボエームは本当に悲しい物語だけど、やはり私は「あのように生きたい」という青春の瑞々しさとほのかな灯りのようなものを、いつもボエームから感じています。
翻って現代日本の若者はどうか? 夢を持っているのか? それを育む「愛と友情」を持っているのか? 『ラ ボエーム』を演じようとする人たちは、もちろん持っているのでしょうね。