第四部定理五二について説明したときに少しだけ触れていることですが,この定理Propositioは,単に理性ratioから生じる自己満足acquiescentia in se ipsoが,人間にとって最高の満足であるということだけを意味しているのではありません。同時にそれは,人間にとって最高の徳virtusであるということを意味しています。なぜなら,スピノザは,人間にとっての徳というのを,人間が働く力agendi potentia,すなわち能動actioと同一視するからです。第四部定義八をみてみましょう。

「徳と能力とを同一のものと私は解する。(Per virtutem, et potentiam idem intelligo. )言いかえれば(第三部定理七により),人間について言われる徳とは,人間が自己の本性の法則のみによって理解されるようなあることをなす能力を有する限りにおいて,人間の本質ないしは本性そのもののことである(ipsa hominis essentia, seu natura.)」。
理性は精神の能動actio Mentisです。ですから人間の精神mens humanaが理性によって事物を認識するcognoscereというとき,それはその人間の精神が十全な原因causa adaequataであるという意味です。それがこの定義Definitioでいわれている,人間が自己の本性の法則のみによって理解されることです。よって理性から生じる自己満足が人間にとっての最高の満足であるならば,それは同時に人間にとって最高の徳であるということにもなるのです。
一般的には,徳というのは,人間の外部にあるものというように把握されているかもしれません。しかしスピノザはそのようには理解せず,人間の本性からそれを定義します。ただし,この場合の本性には少しの注意を要するかもしれません。
第三部諸感情の定義一は,欲望cupiditasを人間の本性と等置します。スピノザはここではこの意味において徳を本性と等置するのではありません。そこには能動と受動の相違があると考えておくのが妥当だと思います。つまり人間が受動的である場合には,欲望がその人間の本性であり,人間が能動的である場合には,徳いい換えれば理性がその人間の本性なのです。だからこの観点において,欲望と理性,あるいは欲望と徳は,反対概念であることになります。
ただし,第三部定理五九から分かるように,能動的な欲望というのも存在します。その意味で欲望が人間の本性とみられる場合には,上述の条件はすべて成立しないと考えるべきでしょう。
自由意志voluntas liberaを神Deusの本性essentiaに帰すると,神には可能な事柄がいくつかあって,そのうちひとつを意志によって選択することになります。厳密にいうとひとつでなくても構わないのですが,可能な事柄として残余の部分が残らなくてはいけません。そうでないとその意志を自由意志と規定することができなくなるからです。したがって神の力potentiaのうちには,可能であるけれどもなさない事柄が必ずあるということになります。
これに対して,神に必然性necessitasを帰すると,神の力のうちにある事柄はすべて現実化されます。他面からいえば,神はなし得る事柄に関してはそのすべてをなすということになります。そのように考えれば,可能だけれどもなさない事柄があるというのは,なし得る事柄のすべてを神はなし得ないという意味であることが理解できるでしょう。
このとき,意志と必然のどちらが最高に完全な神に相応しいかといわれれば,僕は迷わずに必然の方を選択します。つまり,なし得る事柄のすべてをなし得ないというよりも,なし得る事柄のすべてをなすという方が最高に完全な存在であると考えるのです。矛盾めいて聞こえるかもしれませんが,神はなし得る事柄のすべてをなすという言明は,神にはなし得ない事柄は何もないという言明に等置できると僕は考えるからです。第一部定理三五は,神はなし得る事柄をすべてなすという意味に理解することが可能だと僕は考えます。一方,第一部定理一六は,神の本性の必然性から無限に多くのinfinitaものが無限に多くの仕方で生じることを明示しています。ですから等置できるかどうかは別にしても,神がなし得ることのすべてをなし,かつ神になし得ないことは何もないということは,『エチカ』では両立しているといえます。
ただし,必然と不可能が対義語であることには留意してください。僕は神が不可能な事柄を必然的にnecessarioすることができるといっているのではありません。むしろ不可能である事柄が必然的な事柄になるということはないから,神にはなし得ないことは何もないという意味が成立するのだと考えているのです。虚偽falsitasが真理veritasになるとか,無が有esseになるというのも,同様の意味であり得ないことです。

「徳と能力とを同一のものと私は解する。(Per virtutem, et potentiam idem intelligo. )言いかえれば(第三部定理七により),人間について言われる徳とは,人間が自己の本性の法則のみによって理解されるようなあることをなす能力を有する限りにおいて,人間の本質ないしは本性そのもののことである(ipsa hominis essentia, seu natura.)」。
理性は精神の能動actio Mentisです。ですから人間の精神mens humanaが理性によって事物を認識するcognoscereというとき,それはその人間の精神が十全な原因causa adaequataであるという意味です。それがこの定義Definitioでいわれている,人間が自己の本性の法則のみによって理解されることです。よって理性から生じる自己満足が人間にとっての最高の満足であるならば,それは同時に人間にとって最高の徳であるということにもなるのです。
一般的には,徳というのは,人間の外部にあるものというように把握されているかもしれません。しかしスピノザはそのようには理解せず,人間の本性からそれを定義します。ただし,この場合の本性には少しの注意を要するかもしれません。
第三部諸感情の定義一は,欲望cupiditasを人間の本性と等置します。スピノザはここではこの意味において徳を本性と等置するのではありません。そこには能動と受動の相違があると考えておくのが妥当だと思います。つまり人間が受動的である場合には,欲望がその人間の本性であり,人間が能動的である場合には,徳いい換えれば理性がその人間の本性なのです。だからこの観点において,欲望と理性,あるいは欲望と徳は,反対概念であることになります。
ただし,第三部定理五九から分かるように,能動的な欲望というのも存在します。その意味で欲望が人間の本性とみられる場合には,上述の条件はすべて成立しないと考えるべきでしょう。
自由意志voluntas liberaを神Deusの本性essentiaに帰すると,神には可能な事柄がいくつかあって,そのうちひとつを意志によって選択することになります。厳密にいうとひとつでなくても構わないのですが,可能な事柄として残余の部分が残らなくてはいけません。そうでないとその意志を自由意志と規定することができなくなるからです。したがって神の力potentiaのうちには,可能であるけれどもなさない事柄が必ずあるということになります。
これに対して,神に必然性necessitasを帰すると,神の力のうちにある事柄はすべて現実化されます。他面からいえば,神はなし得る事柄に関してはそのすべてをなすということになります。そのように考えれば,可能だけれどもなさない事柄があるというのは,なし得る事柄のすべてを神はなし得ないという意味であることが理解できるでしょう。
このとき,意志と必然のどちらが最高に完全な神に相応しいかといわれれば,僕は迷わずに必然の方を選択します。つまり,なし得る事柄のすべてをなし得ないというよりも,なし得る事柄のすべてをなすという方が最高に完全な存在であると考えるのです。矛盾めいて聞こえるかもしれませんが,神はなし得る事柄のすべてをなすという言明は,神にはなし得ない事柄は何もないという言明に等置できると僕は考えるからです。第一部定理三五は,神はなし得る事柄をすべてなすという意味に理解することが可能だと僕は考えます。一方,第一部定理一六は,神の本性の必然性から無限に多くのinfinitaものが無限に多くの仕方で生じることを明示しています。ですから等置できるかどうかは別にしても,神がなし得ることのすべてをなし,かつ神になし得ないことは何もないということは,『エチカ』では両立しているといえます。
ただし,必然と不可能が対義語であることには留意してください。僕は神が不可能な事柄を必然的にnecessarioすることができるといっているのではありません。むしろ不可能である事柄が必然的な事柄になるということはないから,神にはなし得ないことは何もないという意味が成立するのだと考えているのです。虚偽falsitasが真理veritasになるとか,無が有esseになるというのも,同様の意味であり得ないことです。










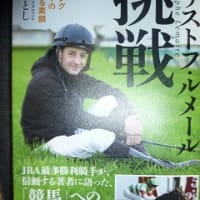



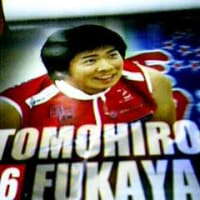

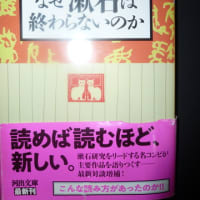

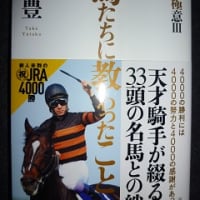
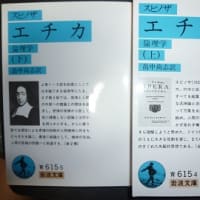





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます