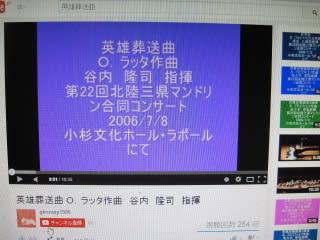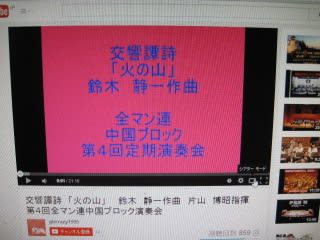古本で高橋和巳の全集を買ったが、なかなか読み進められない。今3巻の途中までいったが、20巻以上もあるので、このペースだと完読するのに後7年間はかかるだろう。
高橋和巳は私の親と同世代。生きていれば80代半ばである。
第二次世界大戦の終戦の時は10代半ばであった。高橋和巳の父親は大阪釜ヶ崎に隣接した地域で町工場を経営していたが、第1回の大阪大空襲の際に家屋・工場が焼失。焼け跡を彷徨う(高橋和巳略年譜、編・太田代志朗を引用)。
この時の体験が元で、処女作「捨子物語」が書かれた。
釜ヶ崎と言えば、数年前に大阪へ小旅行をしたときに、何も知らなかった私は千円で泊まれる宿があるからと、旅費を浮かせるためにここに3泊したことがある。
この地域は日雇い労働者の町で、この宿は労働者がその日暮らしをするための簡易宿泊所であった。
朝から労働者が道端で酒を飲んでいるような町であったが、高橋和巳はこの貧民街の近隣で育ち、決して裕福ではなかった貧しい暮らしぶりが「捨子物語」から読み取ることができる。
「捨子物語」は全体に暗く、最終章の大空襲の様は物凄くリアルで悲しい。これを読んだ時、実際に体験した人でないと書けないと思った。
次に読んだ彼の代表作「悲の器」も暗く、しかも考え方が難解で、一気に読むことなど不可能であり、しばし読解を中断させられた。
今日紹介する「散華」という小説も暗く難解な小説である。
「捨子物語」や「悲の器」を読んだ後がそうであったように、この「散華」(さんげ)も何度も意味を考えさせられる内容であった。
第二次世界大戦での特攻隊の生き残りであった主人公の大家は、電力会社で用地買収の仕事をしていたが、四国と本州を結ぶ高圧海上架線を建設するために、瀬戸内海の小さな孤島を買収する仕事を命じられる。
この孤島には、かつて国家主義者として戦時中の青年達に「散華の精神」を説き、終戦と同時に世の中との関わりを一切拒絶し隠遁した、中津という名の老人が独り住んでいた。
「散華の精神」とは、個を自覚的に捨て、民族の運命に殉ずることを求め、特攻隊などによる死を美化、正当化する思想、論理のことである。
中津は国家主義者として多くの若者にこの精神を説きながらも、彼らとともに運命を共にしなかったことに責任を感じ、一切の社会的交流から隔絶する生き方を選んだ。
そして戦争に死んだ青年たちを祭る神棚に位牌を置き、自ら彫った仏像に読経することで、自分の罪を償う生活をしていた。
「しかし私は、自分の方から助けを求めたことはなかった。わたしはいつ死んでもよかったのだ。ただ自分で自分の命を絶つべき理由はみつからなかった。(中略)しかしわたしの苦痛は他者の同情によって癒えはしない。それがどんな苦痛であろうと、わたしの苦痛でありかぎり、わたしはそれを大事にするだろう。」
大家はこの老人を立ち退きさせるために何度かこの孤島を訪れるが、強固に拒否される。
しかしこの中津という老人と、食糧のための小蟹を取ったり、美しい自然に触れていくつれ、次第に中津に親近感を抱くようになる。
ある時大家は孤島の海岸で泳いでいるときに、潮の流れにさらわれ溺れてしまう。気が付いた時には、中津の家で介抱を受けていた。中津に命を救われたのである。
中津も大家に対し次第に心を開いていくが、大家はついに会社の命令のために中津に会いにきていることを切り出した。
大家の真意にこれまで気付かなかった中津は激怒し、なおも立ち退きのための交渉を進めようとする大家に対し、日本刀を抜き、振りかざした。しかし中津は本当に大家を斬るつもりはなかった。
大家はこの対決で、特攻隊の苦しみを吐露する。回天という人間魚雷の中でじっとうずくまって出撃を待っているときの気持ちを。
「おれはいまは一介の俗物にすぎない。しかし、それゆえに、一人高しとして孤独を守る人間を本質的に信じないんだ。あなたには解るか。やがて死んでゆかねばならぬ人間が、自己の存在の痕跡を残したいと痛切に思う気持ちが。」
中津は外に出て刀を捨て、失っては餓死してしまうかもしれない作物の植えられた畑の上でのたうち回り、号泣する。
それから月日が経ち、いよいよ夢の高圧架線を建設するために測量班がこの孤島に上陸したが、倒壊寸前の小屋の中で、半ばミイラ化した老人の死体が発見される。しかもその死体の腹部には刀剣が突き刺さっていた。
中津は自殺したのだ。
大家は中津と対決した後、総務部へ異動になり、用地買収とは関係ない立場になっていた。
「老人が何を考え、何を苦しんだとしても、それはもう大家には関係のないことであった。」
大家は冷徹にも会社の任務を忠実に実行しようとした。そこには相手の苦しみや悲しみを切り捨てる冷酷さが感じられる。
大家は、この老人の、死ぬまで自分の罪を悔い、懺悔したいとする生き方を奪った。
恐らく中津は自分の罪に気付き懺悔する機会も持たぬまま直ぐに死を選択したり、裁判で裁きを受けるという選択ではなく、誰とも交流を絶ち、過酷な自然環境の中で、死ぬまで命を落とした青年達の供養をしようと決心したに違いない。
大家は中津に命を助けられ、島で病気をしたときも介抱を受けた。
大家は命の恩人を、会社の命令に背いてまでもそっとしておいてあげようとしなかった。
中津はあの対決で特攻隊の生き残りの一人として大家に言われた一言で、自分の罪の深さに耐えられなくなり、自殺したのであろう。
大家のこの一言は、まだ将来のある若かった自分を「散華」という精神のもとに死に追いやろうとしたことに対する真実の怒りでもあり、会社のエリートとしての地位の保身のために出たものでもあるように思える。
この小説で高橋和巳が何を言いたかったのか、正直まだ分からない。
日本をかつてない悲劇に向かわせた思想、精神と、それを信じ、犠牲となった多くの若者たちの気持ちを表したかったとも受け止められるが、戦後日本が急速に回復し、高度経済成長へ突入し、物質的豊かさを求めて人々の精神が徐々に変遷、純粋さを失っていくことを暗示させているようにも感じられる。

高橋和巳は私の親と同世代。生きていれば80代半ばである。
第二次世界大戦の終戦の時は10代半ばであった。高橋和巳の父親は大阪釜ヶ崎に隣接した地域で町工場を経営していたが、第1回の大阪大空襲の際に家屋・工場が焼失。焼け跡を彷徨う(高橋和巳略年譜、編・太田代志朗を引用)。
この時の体験が元で、処女作「捨子物語」が書かれた。
釜ヶ崎と言えば、数年前に大阪へ小旅行をしたときに、何も知らなかった私は千円で泊まれる宿があるからと、旅費を浮かせるためにここに3泊したことがある。
この地域は日雇い労働者の町で、この宿は労働者がその日暮らしをするための簡易宿泊所であった。
朝から労働者が道端で酒を飲んでいるような町であったが、高橋和巳はこの貧民街の近隣で育ち、決して裕福ではなかった貧しい暮らしぶりが「捨子物語」から読み取ることができる。
「捨子物語」は全体に暗く、最終章の大空襲の様は物凄くリアルで悲しい。これを読んだ時、実際に体験した人でないと書けないと思った。
次に読んだ彼の代表作「悲の器」も暗く、しかも考え方が難解で、一気に読むことなど不可能であり、しばし読解を中断させられた。
今日紹介する「散華」という小説も暗く難解な小説である。
「捨子物語」や「悲の器」を読んだ後がそうであったように、この「散華」(さんげ)も何度も意味を考えさせられる内容であった。
第二次世界大戦での特攻隊の生き残りであった主人公の大家は、電力会社で用地買収の仕事をしていたが、四国と本州を結ぶ高圧海上架線を建設するために、瀬戸内海の小さな孤島を買収する仕事を命じられる。
この孤島には、かつて国家主義者として戦時中の青年達に「散華の精神」を説き、終戦と同時に世の中との関わりを一切拒絶し隠遁した、中津という名の老人が独り住んでいた。
「散華の精神」とは、個を自覚的に捨て、民族の運命に殉ずることを求め、特攻隊などによる死を美化、正当化する思想、論理のことである。
中津は国家主義者として多くの若者にこの精神を説きながらも、彼らとともに運命を共にしなかったことに責任を感じ、一切の社会的交流から隔絶する生き方を選んだ。
そして戦争に死んだ青年たちを祭る神棚に位牌を置き、自ら彫った仏像に読経することで、自分の罪を償う生活をしていた。
「しかし私は、自分の方から助けを求めたことはなかった。わたしはいつ死んでもよかったのだ。ただ自分で自分の命を絶つべき理由はみつからなかった。(中略)しかしわたしの苦痛は他者の同情によって癒えはしない。それがどんな苦痛であろうと、わたしの苦痛でありかぎり、わたしはそれを大事にするだろう。」
大家はこの老人を立ち退きさせるために何度かこの孤島を訪れるが、強固に拒否される。
しかしこの中津という老人と、食糧のための小蟹を取ったり、美しい自然に触れていくつれ、次第に中津に親近感を抱くようになる。
ある時大家は孤島の海岸で泳いでいるときに、潮の流れにさらわれ溺れてしまう。気が付いた時には、中津の家で介抱を受けていた。中津に命を救われたのである。
中津も大家に対し次第に心を開いていくが、大家はついに会社の命令のために中津に会いにきていることを切り出した。
大家の真意にこれまで気付かなかった中津は激怒し、なおも立ち退きのための交渉を進めようとする大家に対し、日本刀を抜き、振りかざした。しかし中津は本当に大家を斬るつもりはなかった。
大家はこの対決で、特攻隊の苦しみを吐露する。回天という人間魚雷の中でじっとうずくまって出撃を待っているときの気持ちを。
「おれはいまは一介の俗物にすぎない。しかし、それゆえに、一人高しとして孤独を守る人間を本質的に信じないんだ。あなたには解るか。やがて死んでゆかねばならぬ人間が、自己の存在の痕跡を残したいと痛切に思う気持ちが。」
中津は外に出て刀を捨て、失っては餓死してしまうかもしれない作物の植えられた畑の上でのたうち回り、号泣する。
それから月日が経ち、いよいよ夢の高圧架線を建設するために測量班がこの孤島に上陸したが、倒壊寸前の小屋の中で、半ばミイラ化した老人の死体が発見される。しかもその死体の腹部には刀剣が突き刺さっていた。
中津は自殺したのだ。
大家は中津と対決した後、総務部へ異動になり、用地買収とは関係ない立場になっていた。
「老人が何を考え、何を苦しんだとしても、それはもう大家には関係のないことであった。」
大家は冷徹にも会社の任務を忠実に実行しようとした。そこには相手の苦しみや悲しみを切り捨てる冷酷さが感じられる。
大家は、この老人の、死ぬまで自分の罪を悔い、懺悔したいとする生き方を奪った。
恐らく中津は自分の罪に気付き懺悔する機会も持たぬまま直ぐに死を選択したり、裁判で裁きを受けるという選択ではなく、誰とも交流を絶ち、過酷な自然環境の中で、死ぬまで命を落とした青年達の供養をしようと決心したに違いない。
大家は中津に命を助けられ、島で病気をしたときも介抱を受けた。
大家は命の恩人を、会社の命令に背いてまでもそっとしておいてあげようとしなかった。
中津はあの対決で特攻隊の生き残りの一人として大家に言われた一言で、自分の罪の深さに耐えられなくなり、自殺したのであろう。
大家のこの一言は、まだ将来のある若かった自分を「散華」という精神のもとに死に追いやろうとしたことに対する真実の怒りでもあり、会社のエリートとしての地位の保身のために出たものでもあるように思える。
この小説で高橋和巳が何を言いたかったのか、正直まだ分からない。
日本をかつてない悲劇に向かわせた思想、精神と、それを信じ、犠牲となった多くの若者たちの気持ちを表したかったとも受け止められるが、戦後日本が急速に回復し、高度経済成長へ突入し、物質的豊かさを求めて人々の精神が徐々に変遷、純粋さを失っていくことを暗示させているようにも感じられる。