コロナ感染が収まる気配が全然ないが、感染防止対策として政府や自治体が表明した5/6までの外出自粛期間内は要請どおり家にこもっていようかと思う。
(1日くらいは深夜の首都高ドライブにでもでかけるかな)
この外出自粛期間内はチャンスと言えばチャンスだ。
普段できないことができるからだ。
明後日から1週間は在宅&サテライト勤務なので通勤時間が大幅に短縮され、普段出来ないことに時間を当てることができる。
そこで明日から5/6までにやることを決めた。
1.勉強
①高梨健吉著「総解英文法」(美誠社、1970年初版)の学習
この学習参考書は、高校1年生の冬休みに入る直前に札幌の紀伊国屋で買ったものである。


嫌な高校にしか入れず、中学時代とは180度違うガリ勉にすっかり生まれ変わった私は、別人のように猛烈に勉強をするようになったが、中学時代の不勉強のせいで、しばらくは中学2年生程度のレベルしかなかった英語だったのだが、この本を読み始めて飛躍的に向上した。
この時の体験は強烈だった。
この本との出会いが無かったならば、卒業した大学に入れなかったと思う。
10年くらい前からこの本をもう一度、高校時代の頃を懐かしみながら勉強しようと思い立ったが、なかなか実現に至らなかったが、今回、これを機会に最初から再読することにした。
英語は一生役にたつものだと思う。
私の場合は、会話よりも英文学や英語雑誌を読んでみたい。
たしかイギリスだったかな、「ギター・レビュー」というクラシックギターの専門誌が出ているので、これを読んでみたいとも思っている。
②H.T.ジョンソン、R.S.キャプラン著、鳥居宏史訳「レレバンス・ロスト-管理会計の盛衰ー」(白桃書房、1992年初版)
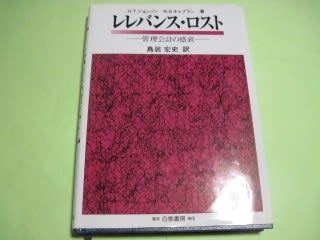
この本は昨年秋ごろから読み始めたが、年明けから中断していた。
自分の仕事に関連する内容であるが、学問の立場と実務の立場の違いを念頭に、この本の提示する論点や技法を検証してみたい。
感想も続きを継続して記事に取り上げていきたい。
③久野光朗著「アメリカ簿記史-アメリカ会計史序説-」(同文館、1985年初版)

この本を買ったのは、今から27、8年くらい前だったであろうか。
簿記学という学問は、財務会計のみならず原価計算や管理会計においても基礎となる学問であり、その歴史、生成過程を研究することは興味深いところである。
買ったけど一度も目を通さなかった本であり、これを機会に是非完読したい。
精読するという読み方ではなく、分からないところが出てきても、そのままかまわず読み進める読み方をしようと思う。
その為に用意したのが、赤と青の鉛筆と鉛筆削り。


重要だと感じた箇所には赤線を引き、分からない箇所、疑問に感じる箇所には青線を引くのである。
そして次に読み返す時には、この赤線を意識して読むようにし、青線部は他の書物などを探して参考にしながら解決するようにする。
こうすると勉強も楽しくなる。
ちなみに鉛筆削りは5年くらい前に札幌の大丸藤井で買ったものだ。
アルミ製。
中学時代に使っていたものよりか、いくぶん粗末なように感じるが、今ではなかなか手に入らない代物だ。
2.文学
原民喜全集、全3巻(青土社、1978年初版)


日本文学が好きだ。
これも7、8年前に買ったはいいけど、最初の数十ページ読んだきりで止めてしまったもの。
原民喜はあまり知られていない。確か、結城信一の著作を読んでいた時に、原民喜を評価する文面に出会い、彼の全集を買ったのだと思う。
東京、神保町の古書店(店の名前は忘れた)で購入。
3.ギター独奏
これは先日の記事でも触れたが、阿部保夫編集の「現代奏法によるカルカッシギター教則本」(全音出版社、初版年記載無)の第三部、50の漸進的練習曲を38年ぶりに再練習する。
50曲念入りにやっていたら時間が足りないので、初見能力向上を目的に、ざっと通すような進め方をしてみたい。
あと考えているのは、鈴木巌著「演奏家を志す人のための クラシック・ギター教本」第2巻、第3巻をじっくりやってみること。

この教則本は、カルカッシ、アグアド、ジュリアーニ、コスト、カルリなど、ギターの黄金時代と呼ばれた19世紀のギタリスト兼作曲家たちが教育目的に作曲した優れた練習曲を豊富に取り上げ、また詳細で丁寧な左手及び右手の運指を記載した非常に優れた教材である。
この教則本を今後、少しずつ、またじっくりとトライしていきたいと思っているのである。
いろいろやりたいことを挙げてみたが、欲張りすぎている感じがしないでもない。
欲張ると途中で挫折してしまう。
かなり強い意志が必要だが、漫然と目標もなくダラダラと過ごすよりかはいいと思う。
(1日くらいは深夜の首都高ドライブにでもでかけるかな)
この外出自粛期間内はチャンスと言えばチャンスだ。
普段できないことができるからだ。
明後日から1週間は在宅&サテライト勤務なので通勤時間が大幅に短縮され、普段出来ないことに時間を当てることができる。
そこで明日から5/6までにやることを決めた。
1.勉強
①高梨健吉著「総解英文法」(美誠社、1970年初版)の学習
この学習参考書は、高校1年生の冬休みに入る直前に札幌の紀伊国屋で買ったものである。


嫌な高校にしか入れず、中学時代とは180度違うガリ勉にすっかり生まれ変わった私は、別人のように猛烈に勉強をするようになったが、中学時代の不勉強のせいで、しばらくは中学2年生程度のレベルしかなかった英語だったのだが、この本を読み始めて飛躍的に向上した。
この時の体験は強烈だった。
この本との出会いが無かったならば、卒業した大学に入れなかったと思う。
10年くらい前からこの本をもう一度、高校時代の頃を懐かしみながら勉強しようと思い立ったが、なかなか実現に至らなかったが、今回、これを機会に最初から再読することにした。
英語は一生役にたつものだと思う。
私の場合は、会話よりも英文学や英語雑誌を読んでみたい。
たしかイギリスだったかな、「ギター・レビュー」というクラシックギターの専門誌が出ているので、これを読んでみたいとも思っている。
②H.T.ジョンソン、R.S.キャプラン著、鳥居宏史訳「レレバンス・ロスト-管理会計の盛衰ー」(白桃書房、1992年初版)
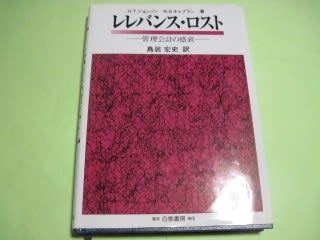
この本は昨年秋ごろから読み始めたが、年明けから中断していた。
自分の仕事に関連する内容であるが、学問の立場と実務の立場の違いを念頭に、この本の提示する論点や技法を検証してみたい。
感想も続きを継続して記事に取り上げていきたい。
③久野光朗著「アメリカ簿記史-アメリカ会計史序説-」(同文館、1985年初版)

この本を買ったのは、今から27、8年くらい前だったであろうか。
簿記学という学問は、財務会計のみならず原価計算や管理会計においても基礎となる学問であり、その歴史、生成過程を研究することは興味深いところである。
買ったけど一度も目を通さなかった本であり、これを機会に是非完読したい。
精読するという読み方ではなく、分からないところが出てきても、そのままかまわず読み進める読み方をしようと思う。
その為に用意したのが、赤と青の鉛筆と鉛筆削り。


重要だと感じた箇所には赤線を引き、分からない箇所、疑問に感じる箇所には青線を引くのである。
そして次に読み返す時には、この赤線を意識して読むようにし、青線部は他の書物などを探して参考にしながら解決するようにする。
こうすると勉強も楽しくなる。
ちなみに鉛筆削りは5年くらい前に札幌の大丸藤井で買ったものだ。
アルミ製。
中学時代に使っていたものよりか、いくぶん粗末なように感じるが、今ではなかなか手に入らない代物だ。
2.文学
原民喜全集、全3巻(青土社、1978年初版)


日本文学が好きだ。
これも7、8年前に買ったはいいけど、最初の数十ページ読んだきりで止めてしまったもの。
原民喜はあまり知られていない。確か、結城信一の著作を読んでいた時に、原民喜を評価する文面に出会い、彼の全集を買ったのだと思う。
東京、神保町の古書店(店の名前は忘れた)で購入。
3.ギター独奏
これは先日の記事でも触れたが、阿部保夫編集の「現代奏法によるカルカッシギター教則本」(全音出版社、初版年記載無)の第三部、50の漸進的練習曲を38年ぶりに再練習する。
50曲念入りにやっていたら時間が足りないので、初見能力向上を目的に、ざっと通すような進め方をしてみたい。
あと考えているのは、鈴木巌著「演奏家を志す人のための クラシック・ギター教本」第2巻、第3巻をじっくりやってみること。

この教則本は、カルカッシ、アグアド、ジュリアーニ、コスト、カルリなど、ギターの黄金時代と呼ばれた19世紀のギタリスト兼作曲家たちが教育目的に作曲した優れた練習曲を豊富に取り上げ、また詳細で丁寧な左手及び右手の運指を記載した非常に優れた教材である。
この教則本を今後、少しずつ、またじっくりとトライしていきたいと思っているのである。
いろいろやりたいことを挙げてみたが、欲張りすぎている感じがしないでもない。
欲張ると途中で挫折してしまう。
かなり強い意志が必要だが、漫然と目標もなくダラダラと過ごすよりかはいいと思う。
















