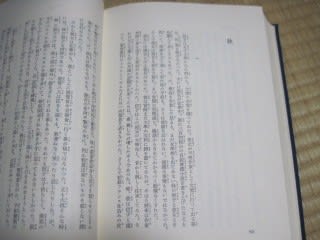この短いお盆休みの間、文学小説の1つでも読んでみたいと思っていたが、もう15年以上前に古本で買ったはいいがほとんど読んでいなかった志賀直哉全集が書棚で埃をかぶっているのを見て、短編でもいいからとにかく読んでみようと思い立った。
選んだのは全集第1巻の中に収録されていた初期作品「網走まで」という短編。
志賀直哉を初めて読んだのは高校入試の時ではなかっただろうか。
記憶が正しければ高校入試の国語に「城の崎にて」という短編を題材とした問題が出題されていたのを読んだのが最初であろう。
その後、文学に目覚めた私はこの志賀直哉や島崎藤村、芥川龍之介、菊池寛などといった文学小説を新潮文庫などの文庫本を買いあさって時間があれば読むという生活を送っていた。高校1年生のときだ。
しかし志賀直哉の小説は高校1年生のとき以来読むことはなくなった。
この時に読んだ小説で印象に残っているのは、代表作「城の崎にて」のほか、「小僧の神様」、「剃刀」、「好人物の夫婦」などだ。
今回読んだ「網走まで」という短編は志賀直哉が27歳の頃の作品。
主人公の青年(作者自身と思われる)が宇都宮で友人と会うために上野発青森行きの汽車で乗り合わせた若い母親とその子供たちとの会話などのやりとりを描いただけの短いストーリーではあるが、非常に鋭い人間心理に対する観察眼とこの時代の人々が自然に持ち合わせていたであろう人間的な暖かさや、(とりわけ男女間の)清廉な礼節さといったものを感じさせる、なかなか深みのある力を感じさせる名作の一つとして評価されるべき小説だと感じた。
主人公はこの列車に乗り合わせたこの女性が、結婚前は家柄の良い、裕福な家庭で礼儀正しく育てられたが、結婚後はそれに反して苦難の人生を強いられていることを直感で感じ取る。
しかしそれに反して、7歳ほどの息子は礼儀に欠け、愛情の乏しい家庭で育ったような粗野で生意気な性格を見せていた。
この女性は主人公にこの子が父親の性質を受け継いだ可能性のあることを示唆する。
「是は生れつきで御座いますの。お医者様は是の父が余り大酒するからだと仰いますが、鼻や耳は兎に角つむりの悪いのはそんなことではないかと存じます」
主人公はこの子供の父親が、人生の度々の失敗により次第に気難しく陰気になり、汚い家の中で弱い妻へ当たり散らして憂いを晴らすような人物に相違ないと想像する。
しかしこの母親はこの反抗的な子供に対し、終始丁寧な言葉使いで愛情を持って接していることが文脈から伝わってくる。
主人公の下車駅、宇都宮に着いたとき、子供を便所に行かせるために母親は赤子を急いで背負い始める。
「恐れ入りますが、どうかこの葉書を」こういって懐から出そうとするが、博多の帯が胸で十文字になって居るので、却々出せない。
「一寸待って........」女の人は顎を引いて、無理に胸をくつろげようとする。力を入れようとしたので耳の根が、紅くなった。其時、自分は襟首のハンケチが背負う拍子によれよれになって、一方の肩の所に挟まって居るのを見たから、つい、黙ってそれを直そうと其肩へ手を触れた。女の人は驚いて顔を挙げた。
「ハンケチが、よれていますから、.........」こう云いながら自分は顔を赤らめた。
「恐れ入ります」女の人は自分がそれを直す間、じっとして居た。
自分が黙って肩から手を引いた時に、女の人は「恐れ入ります」と繰り返した。
この女性は、わずかばかりの荷物でどのような理由で網走まで行かなければならなかったのか。
そして車内でなかなか筆が進まずに書き上げた2枚の葉書(宛先はそれぞれ男と女)の意味するところは。
作者はこの女性の現在置かれている境遇や、当時は最果ての極寒の地であったであろうと想像される北海道の網走まで1週間もかけて幼い子供連れで行く理由を読者の解釈、想像に委ねている。
私が思うには、この女性の夫は主人公が鋭い観察眼でもって想像するとおり、粗暴で家庭を顧みない人物であり、息子は礼儀正しく愛情のある母親ではなく父親の性質を引き継いでしまったのではないかと感じる。あるいは愛情を与えてくれるどころか私利私欲で生きている父親に対する憎悪が、無作法で反抗的な態度を生み出しているのかもしれない。
葉書の投函先の人物はこの女性の夫とその夫に関連する女か(宛先はいずれも東京である)。
網走という最果ての地まで行くのは、この葉書の宛先の人物との決別のためなのか。列車の中に夫がいない、荷物があまりにも簡素であることが気になる。夫が先に既に網走まで行っているとは思えない。
(夫が網走監獄に収監されている、と想像するのは行き過ぎだろう。この物語で重要な描写である葉書を出すこととの関連性が無くなる)
その答えをこの短い小説の中で書かれている内容で読み取ることは極めて困難である。
しかし、この短い小説の中には、当時の日本の女性たちの高貴な礼節さ、所作の美しさ、忍耐強さといった現代では見ることが皆無となったものを文中の描写により見出すことが出来る。
またたまたま列車で居合わせただけの他人に対する主人公の純粋な心のやさしさを思うと、当時の多くの日本人がまだ持っていたであろう、現代の日本人が見失い、消滅させてしまった何か尊いものをあらためて感じさせられたのである。
網走には学生時代に3度ほど訪れたことがある(マンドリンクラブと違う、所属していた別の団体の大会がそこで行われたため)。
行きは普通列車を乗り継ぎながらで北見を経由し、帰りは夜行急行「まりも」(?)で帰ってきた。
網走監獄にも見学で行ったことがある。

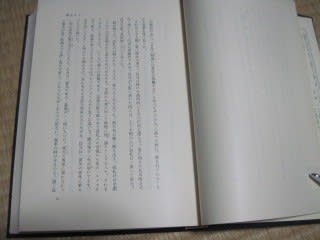
【追記】
網走から乗った夜行急行は「まりも」ではなく「大雪(たいせつ)」でした。
「まりも」(釧路・札幌間)も1度だけ乗ったことがあります。この時は帯広から乗りました。
選んだのは全集第1巻の中に収録されていた初期作品「網走まで」という短編。
志賀直哉を初めて読んだのは高校入試の時ではなかっただろうか。
記憶が正しければ高校入試の国語に「城の崎にて」という短編を題材とした問題が出題されていたのを読んだのが最初であろう。
その後、文学に目覚めた私はこの志賀直哉や島崎藤村、芥川龍之介、菊池寛などといった文学小説を新潮文庫などの文庫本を買いあさって時間があれば読むという生活を送っていた。高校1年生のときだ。
しかし志賀直哉の小説は高校1年生のとき以来読むことはなくなった。
この時に読んだ小説で印象に残っているのは、代表作「城の崎にて」のほか、「小僧の神様」、「剃刀」、「好人物の夫婦」などだ。
今回読んだ「網走まで」という短編は志賀直哉が27歳の頃の作品。
主人公の青年(作者自身と思われる)が宇都宮で友人と会うために上野発青森行きの汽車で乗り合わせた若い母親とその子供たちとの会話などのやりとりを描いただけの短いストーリーではあるが、非常に鋭い人間心理に対する観察眼とこの時代の人々が自然に持ち合わせていたであろう人間的な暖かさや、(とりわけ男女間の)清廉な礼節さといったものを感じさせる、なかなか深みのある力を感じさせる名作の一つとして評価されるべき小説だと感じた。
主人公はこの列車に乗り合わせたこの女性が、結婚前は家柄の良い、裕福な家庭で礼儀正しく育てられたが、結婚後はそれに反して苦難の人生を強いられていることを直感で感じ取る。
しかしそれに反して、7歳ほどの息子は礼儀に欠け、愛情の乏しい家庭で育ったような粗野で生意気な性格を見せていた。
この女性は主人公にこの子が父親の性質を受け継いだ可能性のあることを示唆する。
「是は生れつきで御座いますの。お医者様は是の父が余り大酒するからだと仰いますが、鼻や耳は兎に角つむりの悪いのはそんなことではないかと存じます」
主人公はこの子供の父親が、人生の度々の失敗により次第に気難しく陰気になり、汚い家の中で弱い妻へ当たり散らして憂いを晴らすような人物に相違ないと想像する。
しかしこの母親はこの反抗的な子供に対し、終始丁寧な言葉使いで愛情を持って接していることが文脈から伝わってくる。
主人公の下車駅、宇都宮に着いたとき、子供を便所に行かせるために母親は赤子を急いで背負い始める。
「恐れ入りますが、どうかこの葉書を」こういって懐から出そうとするが、博多の帯が胸で十文字になって居るので、却々出せない。
「一寸待って........」女の人は顎を引いて、無理に胸をくつろげようとする。力を入れようとしたので耳の根が、紅くなった。其時、自分は襟首のハンケチが背負う拍子によれよれになって、一方の肩の所に挟まって居るのを見たから、つい、黙ってそれを直そうと其肩へ手を触れた。女の人は驚いて顔を挙げた。
「ハンケチが、よれていますから、.........」こう云いながら自分は顔を赤らめた。
「恐れ入ります」女の人は自分がそれを直す間、じっとして居た。
自分が黙って肩から手を引いた時に、女の人は「恐れ入ります」と繰り返した。
この女性は、わずかばかりの荷物でどのような理由で網走まで行かなければならなかったのか。
そして車内でなかなか筆が進まずに書き上げた2枚の葉書(宛先はそれぞれ男と女)の意味するところは。
作者はこの女性の現在置かれている境遇や、当時は最果ての極寒の地であったであろうと想像される北海道の網走まで1週間もかけて幼い子供連れで行く理由を読者の解釈、想像に委ねている。
私が思うには、この女性の夫は主人公が鋭い観察眼でもって想像するとおり、粗暴で家庭を顧みない人物であり、息子は礼儀正しく愛情のある母親ではなく父親の性質を引き継いでしまったのではないかと感じる。あるいは愛情を与えてくれるどころか私利私欲で生きている父親に対する憎悪が、無作法で反抗的な態度を生み出しているのかもしれない。
葉書の投函先の人物はこの女性の夫とその夫に関連する女か(宛先はいずれも東京である)。
網走という最果ての地まで行くのは、この葉書の宛先の人物との決別のためなのか。列車の中に夫がいない、荷物があまりにも簡素であることが気になる。夫が先に既に網走まで行っているとは思えない。
(夫が網走監獄に収監されている、と想像するのは行き過ぎだろう。この物語で重要な描写である葉書を出すこととの関連性が無くなる)
その答えをこの短い小説の中で書かれている内容で読み取ることは極めて困難である。
しかし、この短い小説の中には、当時の日本の女性たちの高貴な礼節さ、所作の美しさ、忍耐強さといった現代では見ることが皆無となったものを文中の描写により見出すことが出来る。
またたまたま列車で居合わせただけの他人に対する主人公の純粋な心のやさしさを思うと、当時の多くの日本人がまだ持っていたであろう、現代の日本人が見失い、消滅させてしまった何か尊いものをあらためて感じさせられたのである。
網走には学生時代に3度ほど訪れたことがある(マンドリンクラブと違う、所属していた別の団体の大会がそこで行われたため)。
行きは普通列車を乗り継ぎながらで北見を経由し、帰りは夜行急行「まりも」(?)で帰ってきた。
網走監獄にも見学で行ったことがある。

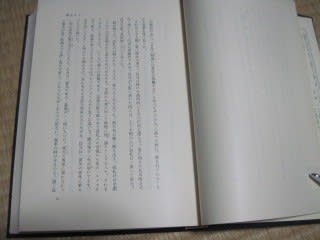
【追記】
網走から乗った夜行急行は「まりも」ではなく「大雪(たいせつ)」でした。
「まりも」(釧路・札幌間)も1度だけ乗ったことがあります。この時は帯広から乗りました。