こんにちは。
クラシックギター曲の中に武満徹がビートルズなどのポピュラー曲を編曲した「ギターのための12の歌」という曲があります。
先日、ウルグアイのギタリストでフランスで活躍したオスカー・カセレスが録音した武満徹編曲の12の歌を聴いていたのですが、最終曲が「インターナショナル」ではなく「ラスト・ワルツ」という曲だったのです。

そこでこの「ラスト・ワルツ」がなぜ12の歌になっているのか興味を覚え、色々調べていくうちに、作曲家の吉松隆氏が武満徹が亡くなったときに雑誌レコード芸術に寄せた追悼文に出会った。以下「11月のカナリアは歌を歌いたかったのか? -武満徹のポップ・ソングを聴く」と題する吉松氏の武満徹に対する追悼文を部分的であるが紹介する。
『武満さんの訃報を聞いた時、彼がしきりに「好きな作曲家はポール・マッカートニーだ」とか「ガーシュインみたいな作曲家になりたかった」とか言っていたということを思い出していた。
最後のCDが石川セリの歌うポップ・ソング風のアルバムだったのも象徴的だったが、二十世紀を代表する超一流の大作曲家「トオル・タケミツ」も残念ながらメロディ・メーカーとしては一流ではなかったことを最後に証明する結果になったのは少し悲しかった。
(中略)
なにしろ平気で無調の音楽を聴き続けられる「特殊な耳」を持っている現代音楽作曲家たちの中で、武満さんの耳は「普通の音楽」を聴く耳を持っていた。その証拠にデビュー作《弦楽レクイエム》では、その「歌」への指向がまだギリギリと軋みながらも残っている。彼は歌いたかったのだ。それなのに歌わなかった。歌わない時代が到来していたからだ。それが彼の生きた「前衛の時代」だった。
(中略)
それはちょっと考えれば誰でもすぐわかることだったのだ。もし「普通の音楽を聴く耳」を持っているのに現代音楽の作曲家などになってしまったら、「音楽が聞こえなくなる耳」を持ったベートーヴェンのように苦悩するに決まっているのだということは。
そもそも「音楽」は人間という生物の「音に反応する感覚」の上に成り立った行為なのだから、感性を切り離して知性で作る音たちは「音群」ではあっても「音楽」ではない。「音楽」の領域を極めるための実験として「音群」を知性で制御してみようと試みるのは勝手だが、それは「音への試み」ではあっても「音楽」ではないのだ。
ところが、この一般社会から遊離した実験行為がその「芸術性」を振りかざして逸脱し、大衆の支持を得られないのを逆手にとって一般の音楽を大衆音楽とか娯楽音楽と呼んで低いものと見なし始めると、この弱小集団は「現代音楽」という名のファッショのカルト教団化してゆく(この思考が生みだした最近のおぞましい例を私たちは知っている)。
武満さんが、現代音楽のこのファッショ・カルト化に反感を持ちながらも結局は終生「現代音楽教」の大幹部であり続けたのは、ソヴィエト政府に反感を持ちながらも結局は終生国家権力サイドの御用作曲家の地位にあり続けたショスタコーヴィチを思い起こさせて、作曲家もまた人間であるということを悲しく思い知らされる。
そのあたりのことについて、私はものわかりよさそうな顔をして理解したいとは思わない。いくら知性がたわごとを思い付いても感性はごまかせないはずだし、音については人一倍鋭敏で繊細な感性の持ち主だったはずだ。それなのに彼は「現代音楽」の一線で活躍し続け、ご丁寧にも海外の「現代音楽」を紹介する任まで買って出て、「先鋭的な音楽芸術を社会に認知させるべく働く知性的な文化人」を演じ続けた。その矛盾に耐えた偉大なる精神力には驚嘆するしかない。その苦悩は、たぶん耳が聞こえなくなったベートーヴェンの苦悩に匹敵するに違いない。私はそう思う。
(中略)
しかし60年代70年代と作曲家の一番脂の乗りきった時期にメロディを書かなかったツケは厳しい。甘いサウンドは書けるようになったが、その「核」となるメロディだけはどうしても書けなかったのだ(訃報を聞いて以後、彼の残した多くの作品を聴き直したうえでそう断定せざるを得ないことは、彼を敬愛し畏敬しながら作曲家を志した私にとっては悲しくつらい)。
(中略)
昔から口ずさんできたポップ・ソングをギターにアレンジした《12の歌》などはその前後の作だが、彼はどんな気持ちでこれらの楽譜を書いたのだろう。ジャズへの憧れ、ポップスの甘い響き、ノスタルジックに心を震わすメロディ。完ぺきなサウンド・コントロールによる見事な自己愛を聴かせる美しいアレンジだが、たったひとつ、「メロディ」だけが彼のものではないのだ。
武満さんの死後、FMの番組でその中のひとつの《オーヴァー・ザ・レインボウ》を若いギタリストが弾いたCDをかける機会があった。その時、その小さな一曲が武満さんの心を象徴しているような気がして、なぜか涙が出てきて仕方なかった。』
これはかなり強い批判的文章である。以前のブログに書いたが、吉松氏は現代音楽撲滅運動や世紀末抒情主義を提唱して現代音楽を徹底的に批判した。
その点、作曲家である原博氏も現代音楽に異を唱えたことは共通しており、その考えを「無視された聴衆」という本にまとめ出版したほどである。

吉松氏は人間の感性を切り離して知性で作る音群は「音楽」ではないと述べている。そして知性で作る音楽をたわごと扱いして蔑視している。かなり痛烈な批判だ。
また武満氏が普通の音楽を聴く耳を持ちながら現代音楽作曲家となったが故に、一流のメロディー・メーカーになれなかった、本当はメロディー・メーカーになりたかったが、前衛音楽の時代を生き、現代音楽作曲家でありつづけたがために自らの気持ちとの葛藤、矛盾を感じ苦悩したのではないか、その矛盾、葛藤する気持ちがギターのための12の歌を聴いて感じられたとまで言っている。
そもそも現代音楽は「人間の感性を切り離して知性で作られたもの」と決め付けられるものなのか。私は現代音楽の中には、人間の内面から湧き出るものを表現した曲が多いように感じる。現代音楽=「頭で計算した音楽」と杓子定規的にとらえるのは、現代音楽から聴こえてくる人間の心の影や闇を感じ取れていないからではないか。
現代音楽から感じ取れる心の感覚や人生経験がなければ、現代音楽=感性のない非音楽ととらえることもわからないではないが、音楽というテリトリーから撲滅すべきだと激しく排除する意図は理解しがたい面がある。
私は30歳代までは現代音楽に全く興味を示さなかったし、聴こうとも思わなかった。その最大の理由は、不気味で不快感を感じたからである。
その年代はロマンティックな曲ばかり聴いていた。ギターで言うとアグスティン・バリオスやマヌエル・ポンセなどである。
しかし40歳を過ぎ、東京国際ギターコンクールの本選課題曲で邦人作曲家の現代曲が採用され、実際に本選で聴くようになってから、現代音楽に興味をもつようになった。
今まで聴いた中で最も印象に残っているのは、野呂武男作曲「コンポジションⅠ」である。

この曲は1964年パリ放送局国際コンクールで第2位を受賞したほどの曲なのですが、難解でありながら私の心には非常に強く残るものが感じられた。特に最後のハーモニックスの部分は鮮明に覚えている。

この野呂武男の「コンポジションⅠ」の録音を探したが皆無である。野呂氏はギター曲はコンポジションⅣまで作曲しているが、出版されたのはコンポジションⅠとⅡ、ギター二重奏「MEET」とギターとバイオリンのための「IMPRONPTU」だけである。

しかしこのコンポジションⅠの演奏をまた聴きたいし、自分でもいつかは演奏したいと思っている。
また、毛利蔵人氏のアルバム「ディファレンス」も聴き応えがある。この毛利氏のアルバムを聴くと、吉松氏が言うような「知性で作られたたわごとのうような音群」とはとても感じられない。
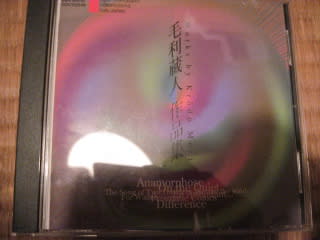
CDの解説文の中で毛利氏の妻である十紀子さんが次のように述べている。
「毛利が残した音楽は、頑固なまでに己の意志を貫き、自らの内側から聞こえてくる音を聞き取る作業を続けてきたのだと思います。音楽に対する一途な姿勢を持っていました。感性の奥深いところまで深く考え、それを聴衆と共に真に経ることで芸術は育まれていくのだと、世の変動が目まぐるしいなかで、価値判断が曖昧になる事も多く、また行く道を見失いがちになる時、これらのことを思い出すことで方向が見えてくるに違いありません。」
人間の感性は美しいものだけとは限らない。人間の心には影や闇が必ずあり、どんなに否定しても消し去ることはできない。現代音楽とは私は、そのような人間の負の部分を表現したものではないかと考えている。
多くの人が現代音楽を聴いて不快に感じるのは、自分が普段無意識的に抑圧して感じることを避けている負の感情に触れるからではないか。
心地よい音楽だけが音楽と言える、とは思えない。現代音楽は人間の負の部分を表現するために無調、不協和音などの手法を採用していると考えられないだろうか。それは音楽を作るうえで意図的なことではなく必然的なことである。
吉松氏が言う、現代音楽を「音楽の領域を極めるための実験を目的」としたとらえかたはあまりにも狭い見方なのではないだろうか。
このような一方的な決め付けで現代音楽を排除し、撲滅されたら、現代音楽を聴きたいと思っている人にとっては不愉快であろう。
正直に感じたことを言うと、吉松氏の音楽は聴きやすく、感覚的であり、哀愁漂う和声進行を特色とした曲が多いが、何度も繰り返し、また末永く聴きたいとは思わない。聴いて心に刻まれるものがない。
調性音楽だから聴きたいということはない。調性音楽だから大衆の支持を受けるとは限らない。全ては聴き手の心の感じ方、受け止め方である。
作曲家は聴き手を選べない。しかし大勢の聴き手を獲得しても1度しか聴いてもらえないよりは、ごく少数でも繰り返し、末永く聴いてくれる聴衆がいてくれるほうが作曲家としては幸せなのではないだろうか。
聴き手にとって、メロディーがあるかないか、メロディーが一流かどうかは関係ない。聴き手にとって重要なのは、その音楽が自分の心に何を与えてくれるか、ということに尽きる。
だから吉松氏が言う「人間の感性を切り離して知性で作る音群」に見えるような音楽であっても、聴き手の心に刻みこまれ、聴き手の心に共鳴するものであれば、それは立派な音楽であると言えるのである。
現代音楽は1980年代に入り作曲されることは少なくなった。しかし1つの音楽様式が末永く継続することはなく、それは現在までの音楽の変遷を見れば理解できる。
しかし現代音楽が消滅し、聴衆から見放されたとは思わない。武満徹の前衛時代の音楽は彼の死後も頻繁に演奏され、また聴き続けられている。それは多くの聴き手の心を刻むものがあったからではないだろうか。
作曲者と聴き手の音楽を通しての交流は、心の深いところでなされるものである。その深淵とも言うべき領域での交流において、現代音楽、調性音楽、大衆音楽の区別はない。
全て等しく、作曲者の心情と演奏者の心情と聴き手の心情が深く共鳴することができるものが音楽の原点と言えるのではないか。
(以下は吉松氏のCD)

【追記 2012/6/16】
雑誌「現代ギター」の古いバックナンバーを読んでいたら、作曲家の三善晃氏のインタビュー記事が載っていたが、その中で三善氏は野呂武男氏のギター曲を絶賛していました。
以下抜粋。
『芳志戸さんがいつかお弾きになった野呂武男さんの作品、あれは本当にすばらしいですね。楽譜を見るにつけても感心しました。あの方は亡くなられたんですね。(1978年1月号)』
ギタリストの故・芳志戸幹雄氏は1974年~1985年の長きにわたって、野呂武男氏の「コンポジション」をコンサートで演奏したことが記録で残っています。
野呂武男氏は42歳の若さで亡くなっています。自殺でした。
先の現代ギター誌に載っていた野呂氏の写真を見ましたが、とても温厚な顔でした。
少し後で1978年8月号の現代ギター誌に、野呂氏と同郷の作曲家である下山一二三氏のインタビューが掲載されていましたが、ここでも野呂氏の話題が出ていました。
下山氏によると野呂氏は弘前で焼き鳥屋をやっていたり、タンゴ・バンドを作って、自分でアレンジして、キャバレーで演奏していたことがあったりと、定まった職業というものを持たない人だったようです。しかしコンポジションⅠ・Ⅱの楽譜の略歴には私立東奥義塾高校の音楽の先生をしていたことが記されています。
下山氏も野呂氏のことを絶賛しています。以下抜粋。
『しかし、(野呂氏は)才能のある人でしたね。野呂さんとの出会いでギター曲を書くようになった。野呂のギター曲は、今でもちょっとしのぐ作品がないんじゃないですか。ギターというものをじつによく知って生かしていてね。』
下山氏は尊敬する先輩である野呂氏へのオマージュとして、ギターのための「N氏へのオマージュ、北緯41度」という曲を作曲しています。
野呂武男氏の情報は少なく、この作曲家のことをもっと知りたいという気持ちが強くなってきました。もしかすると弘前の先の高校や図書館に彼の資料があるかもしれません。
今度弘前に行くことがあったら、立ち寄ってみたい。
下の写真は、ギターのための「N氏へのオマージュ、北緯41度」が収められた下山一二三氏の作品集のCD。
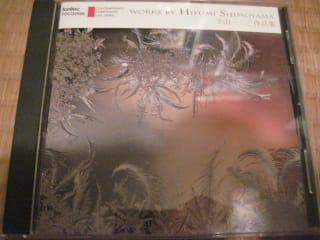
【追記(20130505)】
その後の調査でわかったことを下記に記しておきます。
・1964年のパリ放送局国際コンクールで第2位を受賞した曲は、ギターのためのコンポジションⅠ「永遠回帰」のみであること。
・遺作のOp.14、コンポジション KNOB (1966年)はギターの為の曲ではなく、バイオリンとピアノの為の曲であること。この曲の野呂氏自身の自筆譜は失われ、彼の師である阿保健の写譜のみが残されていること。
ギターのためのコンポジションⅡ「離と合」はコンポジションⅠ「永遠回帰」にも増して難解、複雑でありながら荒涼とした暗く深い闇の音楽です。この曲はクラシックギター曲の傑作であると確信しています。
クラシックギター曲の中に武満徹がビートルズなどのポピュラー曲を編曲した「ギターのための12の歌」という曲があります。
先日、ウルグアイのギタリストでフランスで活躍したオスカー・カセレスが録音した武満徹編曲の12の歌を聴いていたのですが、最終曲が「インターナショナル」ではなく「ラスト・ワルツ」という曲だったのです。

そこでこの「ラスト・ワルツ」がなぜ12の歌になっているのか興味を覚え、色々調べていくうちに、作曲家の吉松隆氏が武満徹が亡くなったときに雑誌レコード芸術に寄せた追悼文に出会った。以下「11月のカナリアは歌を歌いたかったのか? -武満徹のポップ・ソングを聴く」と題する吉松氏の武満徹に対する追悼文を部分的であるが紹介する。
『武満さんの訃報を聞いた時、彼がしきりに「好きな作曲家はポール・マッカートニーだ」とか「ガーシュインみたいな作曲家になりたかった」とか言っていたということを思い出していた。
最後のCDが石川セリの歌うポップ・ソング風のアルバムだったのも象徴的だったが、二十世紀を代表する超一流の大作曲家「トオル・タケミツ」も残念ながらメロディ・メーカーとしては一流ではなかったことを最後に証明する結果になったのは少し悲しかった。
(中略)
なにしろ平気で無調の音楽を聴き続けられる「特殊な耳」を持っている現代音楽作曲家たちの中で、武満さんの耳は「普通の音楽」を聴く耳を持っていた。その証拠にデビュー作《弦楽レクイエム》では、その「歌」への指向がまだギリギリと軋みながらも残っている。彼は歌いたかったのだ。それなのに歌わなかった。歌わない時代が到来していたからだ。それが彼の生きた「前衛の時代」だった。
(中略)
それはちょっと考えれば誰でもすぐわかることだったのだ。もし「普通の音楽を聴く耳」を持っているのに現代音楽の作曲家などになってしまったら、「音楽が聞こえなくなる耳」を持ったベートーヴェンのように苦悩するに決まっているのだということは。
そもそも「音楽」は人間という生物の「音に反応する感覚」の上に成り立った行為なのだから、感性を切り離して知性で作る音たちは「音群」ではあっても「音楽」ではない。「音楽」の領域を極めるための実験として「音群」を知性で制御してみようと試みるのは勝手だが、それは「音への試み」ではあっても「音楽」ではないのだ。
ところが、この一般社会から遊離した実験行為がその「芸術性」を振りかざして逸脱し、大衆の支持を得られないのを逆手にとって一般の音楽を大衆音楽とか娯楽音楽と呼んで低いものと見なし始めると、この弱小集団は「現代音楽」という名のファッショのカルト教団化してゆく(この思考が生みだした最近のおぞましい例を私たちは知っている)。
武満さんが、現代音楽のこのファッショ・カルト化に反感を持ちながらも結局は終生「現代音楽教」の大幹部であり続けたのは、ソヴィエト政府に反感を持ちながらも結局は終生国家権力サイドの御用作曲家の地位にあり続けたショスタコーヴィチを思い起こさせて、作曲家もまた人間であるということを悲しく思い知らされる。
そのあたりのことについて、私はものわかりよさそうな顔をして理解したいとは思わない。いくら知性がたわごとを思い付いても感性はごまかせないはずだし、音については人一倍鋭敏で繊細な感性の持ち主だったはずだ。それなのに彼は「現代音楽」の一線で活躍し続け、ご丁寧にも海外の「現代音楽」を紹介する任まで買って出て、「先鋭的な音楽芸術を社会に認知させるべく働く知性的な文化人」を演じ続けた。その矛盾に耐えた偉大なる精神力には驚嘆するしかない。その苦悩は、たぶん耳が聞こえなくなったベートーヴェンの苦悩に匹敵するに違いない。私はそう思う。
(中略)
しかし60年代70年代と作曲家の一番脂の乗りきった時期にメロディを書かなかったツケは厳しい。甘いサウンドは書けるようになったが、その「核」となるメロディだけはどうしても書けなかったのだ(訃報を聞いて以後、彼の残した多くの作品を聴き直したうえでそう断定せざるを得ないことは、彼を敬愛し畏敬しながら作曲家を志した私にとっては悲しくつらい)。
(中略)
昔から口ずさんできたポップ・ソングをギターにアレンジした《12の歌》などはその前後の作だが、彼はどんな気持ちでこれらの楽譜を書いたのだろう。ジャズへの憧れ、ポップスの甘い響き、ノスタルジックに心を震わすメロディ。完ぺきなサウンド・コントロールによる見事な自己愛を聴かせる美しいアレンジだが、たったひとつ、「メロディ」だけが彼のものではないのだ。
武満さんの死後、FMの番組でその中のひとつの《オーヴァー・ザ・レインボウ》を若いギタリストが弾いたCDをかける機会があった。その時、その小さな一曲が武満さんの心を象徴しているような気がして、なぜか涙が出てきて仕方なかった。』
これはかなり強い批判的文章である。以前のブログに書いたが、吉松氏は現代音楽撲滅運動や世紀末抒情主義を提唱して現代音楽を徹底的に批判した。
その点、作曲家である原博氏も現代音楽に異を唱えたことは共通しており、その考えを「無視された聴衆」という本にまとめ出版したほどである。

吉松氏は人間の感性を切り離して知性で作る音群は「音楽」ではないと述べている。そして知性で作る音楽をたわごと扱いして蔑視している。かなり痛烈な批判だ。
また武満氏が普通の音楽を聴く耳を持ちながら現代音楽作曲家となったが故に、一流のメロディー・メーカーになれなかった、本当はメロディー・メーカーになりたかったが、前衛音楽の時代を生き、現代音楽作曲家でありつづけたがために自らの気持ちとの葛藤、矛盾を感じ苦悩したのではないか、その矛盾、葛藤する気持ちがギターのための12の歌を聴いて感じられたとまで言っている。
そもそも現代音楽は「人間の感性を切り離して知性で作られたもの」と決め付けられるものなのか。私は現代音楽の中には、人間の内面から湧き出るものを表現した曲が多いように感じる。現代音楽=「頭で計算した音楽」と杓子定規的にとらえるのは、現代音楽から聴こえてくる人間の心の影や闇を感じ取れていないからではないか。
現代音楽から感じ取れる心の感覚や人生経験がなければ、現代音楽=感性のない非音楽ととらえることもわからないではないが、音楽というテリトリーから撲滅すべきだと激しく排除する意図は理解しがたい面がある。
私は30歳代までは現代音楽に全く興味を示さなかったし、聴こうとも思わなかった。その最大の理由は、不気味で不快感を感じたからである。
その年代はロマンティックな曲ばかり聴いていた。ギターで言うとアグスティン・バリオスやマヌエル・ポンセなどである。
しかし40歳を過ぎ、東京国際ギターコンクールの本選課題曲で邦人作曲家の現代曲が採用され、実際に本選で聴くようになってから、現代音楽に興味をもつようになった。
今まで聴いた中で最も印象に残っているのは、野呂武男作曲「コンポジションⅠ」である。

この曲は1964年パリ放送局国際コンクールで第2位を受賞したほどの曲なのですが、難解でありながら私の心には非常に強く残るものが感じられた。特に最後のハーモニックスの部分は鮮明に覚えている。

この野呂武男の「コンポジションⅠ」の録音を探したが皆無である。野呂氏はギター曲はコンポジションⅣまで作曲しているが、出版されたのはコンポジションⅠとⅡ、ギター二重奏「MEET」とギターとバイオリンのための「IMPRONPTU」だけである。

しかしこのコンポジションⅠの演奏をまた聴きたいし、自分でもいつかは演奏したいと思っている。
また、毛利蔵人氏のアルバム「ディファレンス」も聴き応えがある。この毛利氏のアルバムを聴くと、吉松氏が言うような「知性で作られたたわごとのうような音群」とはとても感じられない。
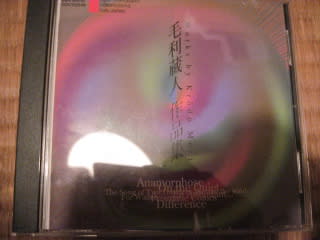
CDの解説文の中で毛利氏の妻である十紀子さんが次のように述べている。
「毛利が残した音楽は、頑固なまでに己の意志を貫き、自らの内側から聞こえてくる音を聞き取る作業を続けてきたのだと思います。音楽に対する一途な姿勢を持っていました。感性の奥深いところまで深く考え、それを聴衆と共に真に経ることで芸術は育まれていくのだと、世の変動が目まぐるしいなかで、価値判断が曖昧になる事も多く、また行く道を見失いがちになる時、これらのことを思い出すことで方向が見えてくるに違いありません。」
人間の感性は美しいものだけとは限らない。人間の心には影や闇が必ずあり、どんなに否定しても消し去ることはできない。現代音楽とは私は、そのような人間の負の部分を表現したものではないかと考えている。
多くの人が現代音楽を聴いて不快に感じるのは、自分が普段無意識的に抑圧して感じることを避けている負の感情に触れるからではないか。
心地よい音楽だけが音楽と言える、とは思えない。現代音楽は人間の負の部分を表現するために無調、不協和音などの手法を採用していると考えられないだろうか。それは音楽を作るうえで意図的なことではなく必然的なことである。
吉松氏が言う、現代音楽を「音楽の領域を極めるための実験を目的」としたとらえかたはあまりにも狭い見方なのではないだろうか。
このような一方的な決め付けで現代音楽を排除し、撲滅されたら、現代音楽を聴きたいと思っている人にとっては不愉快であろう。
正直に感じたことを言うと、吉松氏の音楽は聴きやすく、感覚的であり、哀愁漂う和声進行を特色とした曲が多いが、何度も繰り返し、また末永く聴きたいとは思わない。聴いて心に刻まれるものがない。
調性音楽だから聴きたいということはない。調性音楽だから大衆の支持を受けるとは限らない。全ては聴き手の心の感じ方、受け止め方である。
作曲家は聴き手を選べない。しかし大勢の聴き手を獲得しても1度しか聴いてもらえないよりは、ごく少数でも繰り返し、末永く聴いてくれる聴衆がいてくれるほうが作曲家としては幸せなのではないだろうか。
聴き手にとって、メロディーがあるかないか、メロディーが一流かどうかは関係ない。聴き手にとって重要なのは、その音楽が自分の心に何を与えてくれるか、ということに尽きる。
だから吉松氏が言う「人間の感性を切り離して知性で作る音群」に見えるような音楽であっても、聴き手の心に刻みこまれ、聴き手の心に共鳴するものであれば、それは立派な音楽であると言えるのである。
現代音楽は1980年代に入り作曲されることは少なくなった。しかし1つの音楽様式が末永く継続することはなく、それは現在までの音楽の変遷を見れば理解できる。
しかし現代音楽が消滅し、聴衆から見放されたとは思わない。武満徹の前衛時代の音楽は彼の死後も頻繁に演奏され、また聴き続けられている。それは多くの聴き手の心を刻むものがあったからではないだろうか。
作曲者と聴き手の音楽を通しての交流は、心の深いところでなされるものである。その深淵とも言うべき領域での交流において、現代音楽、調性音楽、大衆音楽の区別はない。
全て等しく、作曲者の心情と演奏者の心情と聴き手の心情が深く共鳴することができるものが音楽の原点と言えるのではないか。
(以下は吉松氏のCD)

【追記 2012/6/16】
雑誌「現代ギター」の古いバックナンバーを読んでいたら、作曲家の三善晃氏のインタビュー記事が載っていたが、その中で三善氏は野呂武男氏のギター曲を絶賛していました。
以下抜粋。
『芳志戸さんがいつかお弾きになった野呂武男さんの作品、あれは本当にすばらしいですね。楽譜を見るにつけても感心しました。あの方は亡くなられたんですね。(1978年1月号)』
ギタリストの故・芳志戸幹雄氏は1974年~1985年の長きにわたって、野呂武男氏の「コンポジション」をコンサートで演奏したことが記録で残っています。
野呂武男氏は42歳の若さで亡くなっています。自殺でした。
先の現代ギター誌に載っていた野呂氏の写真を見ましたが、とても温厚な顔でした。
少し後で1978年8月号の現代ギター誌に、野呂氏と同郷の作曲家である下山一二三氏のインタビューが掲載されていましたが、ここでも野呂氏の話題が出ていました。
下山氏によると野呂氏は弘前で焼き鳥屋をやっていたり、タンゴ・バンドを作って、自分でアレンジして、キャバレーで演奏していたことがあったりと、定まった職業というものを持たない人だったようです。しかしコンポジションⅠ・Ⅱの楽譜の略歴には私立東奥義塾高校の音楽の先生をしていたことが記されています。
下山氏も野呂氏のことを絶賛しています。以下抜粋。
『しかし、(野呂氏は)才能のある人でしたね。野呂さんとの出会いでギター曲を書くようになった。野呂のギター曲は、今でもちょっとしのぐ作品がないんじゃないですか。ギターというものをじつによく知って生かしていてね。』
下山氏は尊敬する先輩である野呂氏へのオマージュとして、ギターのための「N氏へのオマージュ、北緯41度」という曲を作曲しています。
野呂武男氏の情報は少なく、この作曲家のことをもっと知りたいという気持ちが強くなってきました。もしかすると弘前の先の高校や図書館に彼の資料があるかもしれません。
今度弘前に行くことがあったら、立ち寄ってみたい。
下の写真は、ギターのための「N氏へのオマージュ、北緯41度」が収められた下山一二三氏の作品集のCD。
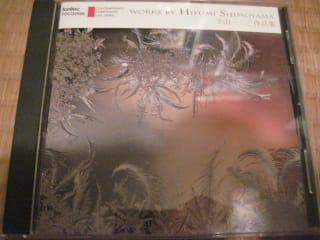
【追記(20130505)】
その後の調査でわかったことを下記に記しておきます。
・1964年のパリ放送局国際コンクールで第2位を受賞した曲は、ギターのためのコンポジションⅠ「永遠回帰」のみであること。
・遺作のOp.14、コンポジション KNOB (1966年)はギターの為の曲ではなく、バイオリンとピアノの為の曲であること。この曲の野呂氏自身の自筆譜は失われ、彼の師である阿保健の写譜のみが残されていること。
ギターのためのコンポジションⅡ「離と合」はコンポジションⅠ「永遠回帰」にも増して難解、複雑でありながら荒涼とした暗く深い闇の音楽です。この曲はクラシックギター曲の傑作であると確信しています。
















それが今は「撲滅なんてかわいそう」と言われるほどになったというのは、本当に時代の趨勢を感じます。
ただ、もう一度氏の文章を読み返していただければ、撲滅と言っている裏で、逆に深い「現代音楽への愛」を込めていることにお気づきになられると思います。
吉松氏の存在を始めて知ったのは1983年に、「現代ギター」誌に彼のギター小品集が掲載された時ですね。私が20代になったばかりの頃です。
1960~70年代は仰るように、クラシック界では現代音楽が最強で他音楽を寄せ付けない時代であったのかもしれません。ただ三善晃氏のようにこの時代に現代音楽を作曲する中、多数の美しい合唱曲も作曲し、「オデコのこいつ」のようなアフリカの社会問題を題材とした異色の曲も作曲しています。
伊福部昭氏や三木稔氏のように現代音楽には全く関心を示さず、自らの音楽を追求し続けた作曲家もいます。彼らにとって現代音楽は自分のものとは関係ない別次元の音楽であり、批判という気持ちそのものがなかったようにも思えます。
この時代は今から逆に考えると、音楽の創作がすごく活発な時代であったのでないでしょうか。少なくても今の時代よりも、多くの優れた音楽家を輩出し、曲もたくさん作曲された。クラシック界では現代音楽が主役といいつつ、その枠の外では多くの名曲が生まれていた。マンドリン・オーケストラが最も栄えたのもこの時代ですね。
吉松氏は現代音楽を自分の求める音楽と切り離して対象化できなかったのでしょうか。自分の求める音楽に真に集中するならば、現代音楽は自分の追及するものとは異次元のものとして放っておくことができるのではないかと思います。
現代音楽はまさに感性の音楽だと思うし、それを心の目で見ることの出来ない人たちが批判しているのだと思います。
僕も初めはメロディックな曲が好きでしたが、最近はポップスを聴くにしてもjames blakeやradioheadなどメロディーの枠を逸脱した曲を好んで聴いています。
僕はまだ15歳ですがこれからも現代音楽を聴いて、もっと理解が広まればいいなと思います。
素敵な記事をありがとうございました。
私もここに紹介した現代音楽に偶然出会うまでは調性音楽しか関心を持っておりませんでした。
現代音楽を聴くには、これまでの固着した先入観を一旦リセットして、まっさらな気持ちで聴く必要があります。
これ以上ないというくらい思いっきり暗く、荒涼としていて不気味で難解な音楽でも、物凄く心に響いてくる曲があります。
自分の凝り固まった主観で対象の範囲を狭めてしまうのは勿体ないですね。
エレクトロニカさんのように決めつけないで柔軟な心でもって感じてみる姿勢はとても大切ですね。
「現代音楽はまさに感性の音楽」。そのとおりです。
まだお若いのにここまで感じ取れる感受性をお持ちなので、これからどんどん楽しみが拡がっていくと思います。