日本の子守唄の中では、五木の子守唄、島原地方の子守唄、そして中国地方の子守唄の3曲が好きだ。
子守唄の魅力に気付いたのは30代半ばであろうか。
この五音音階陰旋法(ミ、ファ、ラ、シ、ド、ミ)による音楽は、日本独自のものであり、外国の音楽に聴くことは無い。
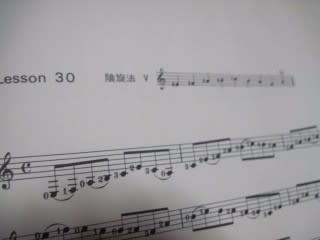
西洋の音楽にも短調の悲しい曲は沢山あるが、この日本独特の音階による音楽は、「悲しい」と同時に「抑圧的な暗さ」を感じる。
現代の平和で豊かな時代に育った世代からすると、少し「怖い」と感じるかもしれない。
何か安らぎ、平安、幸せ、穏やかさ、から生まれてくる音楽ではない。
寧ろ、不幸、淋しさ、不安、暗く辛い生活から聴こえてくるような音楽だ。
しかし同時に、純粋で素朴な美しさも感じる。
子守唄が何故こんなに暗く悲しいのか、昔から疑問に思っていた。
もしかすると、子供を寝かしつけるために歌ったのではなく、封建的で閉鎖的、男尊女卑の、貧しく自由が無かった時代の若い女性が、1日の終わりに、やるせない気持ちを解放するためにあったのではないか。
もちろん日本古来からある箏や三味線の音楽や、民謡にも陰旋法によるものが多く、子守唄だけがこの独自のものを持っていたわけではない。子守唄の中には明るいものもある。
しかし、それでもこの「中国地方の子守唄」ような音楽を聴くと、心にとても強く作用してくるのを感じる。
その作用とは、底に堆積している強い感情を意識下に引き出すものである。
この子守唄を自ら歌うことで、自らの表現出来なかった辛い感情を表出しているようにも思える。
言葉を未だ理解できない幼子を相手に、誰にも言えない気持ちを吐露してた、と感じるのは考えすぎかもしれないが、この曲を聴くとそのように思えてしまう。
この「中国地方の子守唄」は、岡山県西南部が発祥地とされ、この地の声楽家の上野耐之が師事していた山田耕作に聴かせ、山田耕作が歌曲に編曲したことで広まったと言われている。
ねんねこ しゃっしゃりませ
寝た子の かわいさ
起きて 泣く子の
ねんころろ つらにくさ
ねんころろん ねんころろん
ねんねこ しゃっしゃりませ
きょうは 二十五日さ
あすは この子の
ねんころろ 宮詣り
ねんころろん ねんころろん
宮へ 詣った時
なんと言うて 拝むさ
一生 この子の
ねんころろん まめなように
ねんころろん ねんころろん
Youtubeでいいと思った録音を下記に写しておいた。
(伴奏は絶対ピアノに限る。アカペラでは素人の、若い女性、できれば母親の歌ったものがいい)



【追記20170618】
人が、精神的に穏やかで安定した、前向きな気持ちで生活するには、表現されずに心の奥に堆積した感情を開放する必要はあると思う。
子守唄とは実はそのような意図があったのではないかと思う。
現代の世の中で、もはや殆ど聴こえてくることの無くなったこの子守唄のような音楽を聴くことで、普段、表出することのない感情を感じることは悪くない。
感情を持って生まれた人間の宿命とも言える。
子守唄の魅力に気付いたのは30代半ばであろうか。
この五音音階陰旋法(ミ、ファ、ラ、シ、ド、ミ)による音楽は、日本独自のものであり、外国の音楽に聴くことは無い。
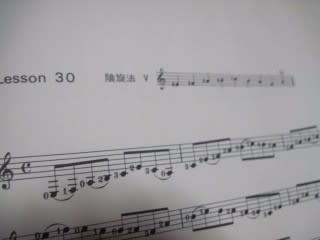
西洋の音楽にも短調の悲しい曲は沢山あるが、この日本独特の音階による音楽は、「悲しい」と同時に「抑圧的な暗さ」を感じる。
現代の平和で豊かな時代に育った世代からすると、少し「怖い」と感じるかもしれない。
何か安らぎ、平安、幸せ、穏やかさ、から生まれてくる音楽ではない。
寧ろ、不幸、淋しさ、不安、暗く辛い生活から聴こえてくるような音楽だ。
しかし同時に、純粋で素朴な美しさも感じる。
子守唄が何故こんなに暗く悲しいのか、昔から疑問に思っていた。
もしかすると、子供を寝かしつけるために歌ったのではなく、封建的で閉鎖的、男尊女卑の、貧しく自由が無かった時代の若い女性が、1日の終わりに、やるせない気持ちを解放するためにあったのではないか。
もちろん日本古来からある箏や三味線の音楽や、民謡にも陰旋法によるものが多く、子守唄だけがこの独自のものを持っていたわけではない。子守唄の中には明るいものもある。
しかし、それでもこの「中国地方の子守唄」ような音楽を聴くと、心にとても強く作用してくるのを感じる。
その作用とは、底に堆積している強い感情を意識下に引き出すものである。
この子守唄を自ら歌うことで、自らの表現出来なかった辛い感情を表出しているようにも思える。
言葉を未だ理解できない幼子を相手に、誰にも言えない気持ちを吐露してた、と感じるのは考えすぎかもしれないが、この曲を聴くとそのように思えてしまう。
この「中国地方の子守唄」は、岡山県西南部が発祥地とされ、この地の声楽家の上野耐之が師事していた山田耕作に聴かせ、山田耕作が歌曲に編曲したことで広まったと言われている。
ねんねこ しゃっしゃりませ
寝た子の かわいさ
起きて 泣く子の
ねんころろ つらにくさ
ねんころろん ねんころろん
ねんねこ しゃっしゃりませ
きょうは 二十五日さ
あすは この子の
ねんころろ 宮詣り
ねんころろん ねんころろん
宮へ 詣った時
なんと言うて 拝むさ
一生 この子の
ねんころろん まめなように
ねんころろん ねんころろん
Youtubeでいいと思った録音を下記に写しておいた。
(伴奏は絶対ピアノに限る。アカペラでは素人の、若い女性、できれば母親の歌ったものがいい)



【追記20170618】
人が、精神的に穏やかで安定した、前向きな気持ちで生活するには、表現されずに心の奥に堆積した感情を開放する必要はあると思う。
子守唄とは実はそのような意図があったのではないかと思う。
現代の世の中で、もはや殆ど聴こえてくることの無くなったこの子守唄のような音楽を聴くことで、普段、表出することのない感情を感じることは悪くない。
感情を持って生まれた人間の宿命とも言える。

















暑くなってきましたがお元気で過ごされておりますか。
子守歌と言えば、私は「お江戸の子守歌」が思い出されます。
ねんねんころりよ おころりよ
ぼうやは良い子だ ねんねしな
ぼうやのお守りは どこへ行った
あの山こえて 里へ行った
里のみやげに なにもろた
でんでん太鼓に 笙の笛
私の母は、34歳の時に脳梗塞になり入退院を繰り返していました。小学生低学年だった私は、専ら
父の祖母(おばあちゃん)に育てられたといっていいでしょう。
そのおばあちゃんが私を寝かしつけるとき必ず歌ってくれたのが「お江戸の子守歌」でした。
おばあちゃんは、身長も高く(160センチ)気の強い矍鑠とした女性でした。聴いた話では、加賀藩前田家の下級武士の子供で、おばあちゃんが子供のころ父親は槍を担いで出て行ったまま帰ってこなかったそうです。想像するに戊辰戦争に出兵して死んだのではないかと言っていました。
その後、主を失った家は没落し、村の何名かで、北海道の共和町、前田村に入植したようです。子供のころ岩内からおいしい魚をもって行商に来ていた人から魚を買ったそうです。そのせいか、おばあちゃんは魚が大好きでした。
年頃になり結婚したそうですが、入植者の生活は、それはそれは大変なものだったそうです。食べてゆくことが困難になり、旦那さんの叔父が樺太で書店を開き成功していると聞いて、叔父を頼り樺太に渡ったそうです。
商才のある旦那さんだったのでしょう、樺太では複数の書店を経営し羽振りが良かったようです。そうなると、昼間から遊びほうける毎日だったそうです。料亭に芸者さんをあげて毎日どんちゃん騒ぎを繰り返していたそうです。
主人のいない書店を切り盛りしていたのは、おばあちゃん・・・丁稚を何名も使い大変だったそうです。
旦那さんは遊びが過ぎて40代の前半で亡くなったそうです。そのため、店も傾き書店は人手に渡ってしまい、私の父も、おばあちゃんともども、叔父さんの書店に使ってもらい細々と生計を立てていたみたいですね。
その後は、緑陽さんもご存じのように太平洋戦争が終結して北海道に引き上げてきたのです。その間、私の父親は、就職し招集されて離れ離れになったようですが、戦後ラジオから流れてきた「尋ね人」を放送で聴いた父がおばあちゃんの引き上げ先を見つけ、再開したとのことです。
たとえ下級でも武士の子として育てられたおばあちゃんは教養も高く、本や新聞を読んでいた記憶があります。
何か、小説にでもできそうな生涯だったのですね。それから比べると、今の人たちは、私も含め「極楽とんぼ」ですね。
そんなおばあちゃんの口癖は「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、為さぬは人の為さぬなりけり」という上杉鷹山の言葉でした。この言葉を小学校の時に刷り込まれたのですね。
でも、私は、何も為すことはできなかったような気がします。
それではまた・・・。
fadoさんのおばあちゃんの出身地加賀藩は、能登半島、今の石川県でしょうか。昔、能登半島を旅したことがあります。
輪島の朝市とか輪島塗の漆器が記憶に残っていますね。
私の母方の祖母の親も新潟から北海道に入植したと子供の時に聞いたことがあります。
私が生まれてから唯一の祖母がこの母方の祖母でした。父の両親と母の父親は早くに亡くなったので、私の祖父母はこのおばあちゃんだけでした。
この明治生まれのおばあちゃんはよく私の家に泊りがけで遊びに来ましたが、昔は看護婦をしていたようです。早くに亡くなった夫は国鉄職員で蒸気機関車の機関士をしていたとか。
このおばあちゃんはとても厳しい人でした。
母がこの厳しいおばあちゃんの影響を受けたのが分かります。
私の両親は祖父母のことは殆ど話しませんでした。
fadoさんのおばあちゃんは魚好きだったのですね。
岩内といえば私の父の故郷です。
私の父は雷電海岸の近くで生まれ、泳ぎが達者でした。頑強で病気など滅多にしない人でした。
小学校の頃、墓参りで岩内に行き、岩内駅(今は廃止)近くの寿司屋に入り寿司を食べたら、おいしかったこと!。
みんなおいしい、おいしいと言って、お替りしようと言って、無駄遣いを一切しない両親がめずらしく奮発してたんさん食べた記憶が強く残っています。
樺太はその半分が日本領だったのですね。
1年くらい前だったか、テレビで樺太を訪れる番組を見ました。
父は若い頃、仕事で北方領土に行ったことがあると言っていたことがありました。
今はロシアの開発が進んでしまいましたが、昔は美しい島だったのでしょうね。私もいつか行ってみたいと時々思うことがあります。
北海道は今がいい季節なのでしょうね。
今月半ばにわずかな日数ですが、久しぶりに故郷に帰省します。