書評 「拝金社会主義中国」 遠藤誉 著 ちくま新書2010年刊
著者は1941年長春に生まれ、革命の動乱で共産党軍に降伏する形で命を永らえて53年に帰国、後筑波大学教授となって北京大学日本研究センター研究員など日中両国においてメジャーとなる地位を確立した上で改革開放後の中国社会を第三者的な目で観察している人です。
私はこの本に魅かれるのは、いくら現実主義の中国人と言ってもあれだけ共産主義革命のために資本主義を否定し、殆ど無実の同胞を見せしめのために何千万人も惨殺していながら、最も憎むべきアメリカ型資本主義をいとも簡単に取り入れて何も感じないものだろうか、ということを現地中国人の視点で書いていることです。
学生時代、私の世代は既にノンポリが主流でしたが、経済学部は依然マル経本流でしたし、一世代上の全共闘世代は「左翼にあらずんば人にあらず」と言われた時代で、ソ連中国北朝鮮は「正義」の代名詞として認識され、アメリカ寄りとか体制派というのは何か後ろめたい気持ちを背負わされたものでした。ソ連が崩壊し、北朝鮮は拉致を実行した悪者になり、中国はアメリカ以上の原始的資本主義国家になりましたが、当時ソ連中国北朝鮮を神聖視していた人達が何ら自己批判をすることなく市民運動家に鞍替えして相変わらず正義を名乗っているのはもともとその程度の偽善者達だったと考えれば良いとして、実際に日常生活で処刑や総括が行われ資本主義を一切否定していた中国で何の矛盾も感じないで資本主義化への頭の切り替えができるものなのかが不思議でした。
この本を読むと、「金儲けをしても良い」と初めて言われた中国の民衆が当初は全く信用せず、恐る恐る少しずつ資本主義的になってゆき、何より公共的な立場の人達が有利な地位を利用して金もうけを初めてあっという間に貧富の差ができてしまった経過。革命の主役であった農民が結局資本主義化から取り残されていった経過。一時は無理しても大学に行って高学歴を目指した方が良かったが、現在は大学卒でも解放軍の兵卒や地方の官吏になるのがやっとという実態。有能すぎる女性は却って幸せになれない、というどこかの国と似たような実態、などなど庶民の目から視た改革開放がどんなものであったかが良くわかりました。
そして「富二代、貧二代」と言われる貧富の差の世襲化、固定化、「未富先老・未富先懶」と言われる乗り遅れた者は頑張ってももう金持ちにはなれないという風潮は現在中国の火薬庫とも言える危険な状態と解説します。また激しい階級闘争を乗り越えてきた共産党老幹部はやはり現在の資本主義体制に批判的であるとも書かれていました。
著者は革命の成就と資本主義化の矛盾について中国人は勿論解ってはいるけれど、中国社会の今後を決定づけるのは結局毛沢東の用いた「誰が飯を与えるのか」という論理で決まるのではないかと結論付けています。つまり理屈先行の共産主義の概念では現在の状態は明らかに共産主義ではないし、単なる独裁政権下の原始的資本主義だけれども、衣食住を普く与えることができれば民衆はどのような政治経済形態であろうと受け入れるだろう、というものです。大事なことは衣食住が足りていることと、中国が外国の侵略を受けていないこと(もっと言うと中華として周辺国の中心であること)が示されていれば「特色ある社会主義」という詭弁だろうが共産党政府に付いて行くだろう、と結論付けているのです。
これはポイントを付いた指摘だと思いました。胡政権の諸政策も正にこれを狙っているように思います。本書は中国をことさら悪く書く事もなく、また美化することもなく民衆の視点で政府に気兼ねなく良い点悪い点を指摘して、現在の資本主義的中国のあるがままを描いている所が良書と思われました。
著者は1941年長春に生まれ、革命の動乱で共産党軍に降伏する形で命を永らえて53年に帰国、後筑波大学教授となって北京大学日本研究センター研究員など日中両国においてメジャーとなる地位を確立した上で改革開放後の中国社会を第三者的な目で観察している人です。
私はこの本に魅かれるのは、いくら現実主義の中国人と言ってもあれだけ共産主義革命のために資本主義を否定し、殆ど無実の同胞を見せしめのために何千万人も惨殺していながら、最も憎むべきアメリカ型資本主義をいとも簡単に取り入れて何も感じないものだろうか、ということを現地中国人の視点で書いていることです。
学生時代、私の世代は既にノンポリが主流でしたが、経済学部は依然マル経本流でしたし、一世代上の全共闘世代は「左翼にあらずんば人にあらず」と言われた時代で、ソ連中国北朝鮮は「正義」の代名詞として認識され、アメリカ寄りとか体制派というのは何か後ろめたい気持ちを背負わされたものでした。ソ連が崩壊し、北朝鮮は拉致を実行した悪者になり、中国はアメリカ以上の原始的資本主義国家になりましたが、当時ソ連中国北朝鮮を神聖視していた人達が何ら自己批判をすることなく市民運動家に鞍替えして相変わらず正義を名乗っているのはもともとその程度の偽善者達だったと考えれば良いとして、実際に日常生活で処刑や総括が行われ資本主義を一切否定していた中国で何の矛盾も感じないで資本主義化への頭の切り替えができるものなのかが不思議でした。
この本を読むと、「金儲けをしても良い」と初めて言われた中国の民衆が当初は全く信用せず、恐る恐る少しずつ資本主義的になってゆき、何より公共的な立場の人達が有利な地位を利用して金もうけを初めてあっという間に貧富の差ができてしまった経過。革命の主役であった農民が結局資本主義化から取り残されていった経過。一時は無理しても大学に行って高学歴を目指した方が良かったが、現在は大学卒でも解放軍の兵卒や地方の官吏になるのがやっとという実態。有能すぎる女性は却って幸せになれない、というどこかの国と似たような実態、などなど庶民の目から視た改革開放がどんなものであったかが良くわかりました。
そして「富二代、貧二代」と言われる貧富の差の世襲化、固定化、「未富先老・未富先懶」と言われる乗り遅れた者は頑張ってももう金持ちにはなれないという風潮は現在中国の火薬庫とも言える危険な状態と解説します。また激しい階級闘争を乗り越えてきた共産党老幹部はやはり現在の資本主義体制に批判的であるとも書かれていました。
著者は革命の成就と資本主義化の矛盾について中国人は勿論解ってはいるけれど、中国社会の今後を決定づけるのは結局毛沢東の用いた「誰が飯を与えるのか」という論理で決まるのではないかと結論付けています。つまり理屈先行の共産主義の概念では現在の状態は明らかに共産主義ではないし、単なる独裁政権下の原始的資本主義だけれども、衣食住を普く与えることができれば民衆はどのような政治経済形態であろうと受け入れるだろう、というものです。大事なことは衣食住が足りていることと、中国が外国の侵略を受けていないこと(もっと言うと中華として周辺国の中心であること)が示されていれば「特色ある社会主義」という詭弁だろうが共産党政府に付いて行くだろう、と結論付けているのです。
これはポイントを付いた指摘だと思いました。胡政権の諸政策も正にこれを狙っているように思います。本書は中国をことさら悪く書く事もなく、また美化することもなく民衆の視点で政府に気兼ねなく良い点悪い点を指摘して、現在の資本主義的中国のあるがままを描いている所が良書と思われました。










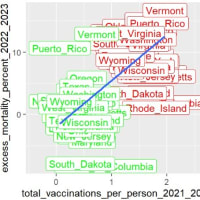



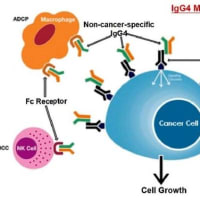











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます