2019年4月21日まで第107回日本泌尿器科学会総会が名古屋で開かれており参加してきました。その中で20日の学会長指定企画 鼎談「長寿社会の医療を考える」という一般市民参加もOKという企画がありました。名古屋にある大学の学長・理事長2名と中日新聞・東京新聞顧問で元新聞記者である小出宣昭氏が高齢者医療について医療者、市民の立場から語り合うという内容でした。現在厚労省が推進する「地域包括ケアシステム」において高齢者の医療介護を実践する上で病院と地域の在宅や介護の連携がスムーズでない現状について話す中で外国経験の長かった小出氏が英国の医療事情などを紹介する中で出てきた言葉が「日本の病院の英語訳はHospitalでなくSick Houseですね」という内容でした。
それは必ずしも皮肉めいた内容ではなくて、日欧の文化的背景の違いから来るものという話の流れで、Hospitalというのは教会に巡礼に来た参拝者達を「もてなす場所」hospitalityから来ているので、外国の病院はそこに病気の人が快癒を祈ってやってきたりした者を、医学的知識を持った尼僧や医師が介護や癒しを施したことが始まりだった。日本ではそれを介護院とか救護院でなく「病院」と訳してしまったから病気を治す事に特化した施設として進化してしまった、という説明でなるほどと思いました。
また「下の世話」を嫌がる雰囲気も「下半身」を忌むべきものとする風潮が日本の文化にあることも影響しているという話。外国では食事中「おなら」より「げっぷ」の方が無作法とされるし(イスラムはご馳走様の意味ですが)、手より足を優先するサッカーがあれだけ盛んなのも下半身への蔑視がない影響ともいえるという。まあオムツ替えについての抵抗感は心理的なものと体力的なものの両面あるので一概には言えませんが、市民の立場(かなりのインテリではありますが)の小出氏からこういった話が聞けたのはなかなか有益でした。また高齢者がいきいきと暮らすには「生きがい」特に「社会や人の役に立つ(つながりを持ち続ける)」事の重要性を3人とも強調していたのは共感できる内容でした。名古屋保健衛生大学では住宅都市整備公団と協力して古くなって高齢者が多くなった「団地」の4-5階を若い人向けに改装してもらい、学生寮として有料で使わせてもらい、同時に団地住民として高齢者たちと協力する場を持つ工夫をしているという試みを紹介、高齢者施設と幼児保育施設の併設による幼児教育への参加なども各地で試みられていますが、地域でのこのような取り組みが今後大事になってくると思いました。
日本人は宗教に無関心か?
上記の話と直接関連はありませんが、宗教が病気との向き合い方や人生観そのものまで影響しているかという点では日本人は無宗教と言えるかもしれませんが、全く宗教に関心がないかというとそうでもないという印象を学会に行く新幹線で感じました。たまたま横に座った60代の女性が「話しやすい」と感じたのか私にやたら話しかけてきまして。
「これから京都にさる寺々の桜見物に日帰りで行く・・」と。「・・の寺は・・天皇が建立されて云々」となかなか詳しい。私も暇でもあったので少し面白がって「本来皇室は神道のはずなのに、奈良時代に振興する目的があったとはいえ何故京都には寺ばかり多いのでしょう?」と水を向けてみました。「それは曽我氏と物部氏の抗争から始まって・・」と説明。おう、結構知識豊富だなあ・・。「でも今上天皇は最後に寺ではなくて伊勢に行きましたね。」「そりゃあなた、日本を始めたご先祖様だもの。」「日本を治める手段として利用するならば世界の本質は無であると説く純粋な仏教よりも儒教の方が支配者の道徳として使いやすかったのでは?」と意地悪な質問をぶつけてみたのですが、「儒教を中心にしたら中国や韓国のような社会になって嫌な世間になったでしょ。」と返されて「これは一本」と思いました。
小一時間こんなけっこう面白い会話をしながら過ごしたのですが、世の中、思考停止の人ばかりではないし、宗教についても種々の角度からいろいろ勉強している人も多いなと感心しました。だから高齢者医療について考えて行く上でも日本人的な宗教観や死生観に根差した無駄のない、また納得できる医療介護の在り方というのが模索できるのではないかと感じた次第です。











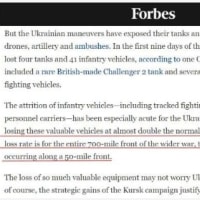














さすがに「養生所」では大岡越前ですし、「療養院」ではサナトリウム地味てます。(抗生物質が汎用される前の結核は死病ですから、イメージが悪いでしょう)
手の文化と足の文化の違いは歴然ですね。
例えば自転車です。我々はアメリカ式のハンドブレーキに慣れているので知らないけど、ヨーロッパはフットブレーキが中心です。ハンドル・レバーではなく、足のペダルを漕ぐ方向と反対に逆回転させるとブレーキがかかる。
先生は学生の頃に剣道をなさっておられたので御理解をいただけると思うのですが。剣道は高速フットワークですが、基本的には「摺り足」を基本にしますよね。
フェンシングのエペなどは最初から踵をあげて構えたり(ボクシングのように)します。おそらくは日本剣道は農耕民の鍬や鋤を持っ動作。フェンシングは平原で羊の群れを追いながら追った動作に由来するかと。
棒で突いて、羊と群れの向きを常に羊飼いが誘導する。
別に中東や西欧だけでなく、中国にしても彼らのカンフーは
初動で後足立が多い。対する日本の本土で進化した空手(琉球の唐手ではなく)は前屈立が主流です。踏み込む初動に
踵接地から動かないのが日本武道の特徴ですね。爪先から抜き足差し脚で動くのが多い。
大陸の歩法は第一歩を踵接地から踏み込む流派が多い。
それは平原が多くて平野が多い民族と、山岳や丘陵で分断された地形の民族の違いとも思います。
こうした身体感覚や環境の違いから、おのおのの医療感や美学や神に対する認識が違ってくるのではないでしょうか?
私がカトリックであったお話は何度もしましたが、クリスチャンであった時に、教会の説教より先生の記事の神道的な自然解釈の方がすんなり飲み込めたのですね(笑)
人は生まれ育った郷土や祖国の自然とは、やはり切り離せないものだと思います。そこを基盤に個々が考えるならば、
違いは出てくる訳ですね。
実感として良く解らないのですが、江戸時代くらいまでは歩くときに手足を同じ方を出していたという話がありますね。バランス的にどうだったか解らないのですが、武道では確かにすり足中心であるから手足がどうであろうと違和感はありませんね。
前回のP-47と零戦の格闘ですが、大戦後半では高高度での戦闘が多くなって、B−29なども7,000-8,000mの与圧が必要な高度から来るので、P-39とかP−47の様なターボチャージャーがないと追いつけない状況が多かったと思います。日本も紫電を改造した紫電改はターボを付けて高高度対応にしたけどなかなか上手く機能しなかったといった本を読んだ事があります。
良く出来たフライトシミュレーターでは5,000mを超える辺りから通常レシプロエンジンでは上昇速度が遅くなって、B-29などもやっと追いついても20mm機関砲などで一度追い払われて高度を失うと2度と追いつけなかったりして、きっと実戦もこんなだったのかなと思います。