今日は二冠対決の棋王戦第一局が行われましたが、大熱戦を羽生二冠が制したようです。
ということで、またしても羽生ネタです。
ssayさんの《モチベーション》という記事に触発されて書いてみます。
僕の「自分へのミッション」という記事に触発されて書いていただいたとのことですが、まず一部引用させてもらいます。
-------------------------------
将棋の羽生の場合、もちろん天賦の才能、並はずれた努力や根性も素晴らしいが、彼と他の超一流棋士達の何が決定的に違うのかと言えば、それはやはり「モチベーション」ではないだろうか。
--中略--
森内、佐藤にしても然りである。
森内が名人・竜王を含む三冠になった時、あるいは佐藤の5連続タイトル挑戦など、一時期羽生をも凌ぐ活躍を見せた事のある両名だが、長続きしなかった。何が羽生と違うのかと言えば、才能ではなく「モチベーション」である。
そもそも、羽生は勢いに任せて七冠を獲ったのではない。
七冠は棋士になった時からの目標だったと明言している。
このことは、自らの才能を過大評価しているのでも、他の棋士たちを見くびっていることを示しているのでもない。自分の才能に自惚れたり、他者を馬鹿にするような視野の狭い人間に、そんな大それたことなどできるはずがない。
おそらく羽生は、七冠王達成に対して「使命感」を持っていたのだろう。
それは、将棋界隆盛のため云々などという意味合いではない。そんな事を言うのは、国民のためと言ってその実訳の分からない使命感に燃えている政治家連中とあまり変わらない。
なぜ、七冠なのかと言えば、それは「そこに七冠があるから。」としか言いようがない。つまり、抽象的な漠然としたものでは、目標となりえない。羽生が棋士になった頃の将棋界は、それまでの先輩方の尽力により七つの公式タイトルを主催できるようになっていた。そういう環境を見て、羽生は七冠を目標に定めたのだろう。
ただし、目標にする事は誰でもできるが、本気で成し遂げようとするならば、これまでに述べた通り、才能+努力+体力+モチベーションが必要となる。
そして、羽生は自らに七冠制覇という「ミッション」を与えたのだ。
七冠達成以後の羽生の活躍も素晴らしいが、彼自身はその都度、その都度、自らのモチベーションの高さを維持するのに苦労したようだ。現在の羽生がどのようなモチベーションで臨んでいるのかは、現時点では分からない。
---------------------------------------
そこに七冠があるから、というのは蓋し名言だと思う。
7冠に向けての羽生のモチベーションは、マスコミも巻き込み、果ては世論までも巻き込んで、世論の強いモチベーションに昇華していった。
世間が7冠達成の瞬間を見たい、という大きな意思が、羽生を、そして、谷川を、そして、彼らの操る駒にまでも、ぐいぐいと染み込んでいった。
神戸大震災の被災というモチベーションで、谷川は一時凌いだものの、またそれはさらに拡大して、すべてのタイトルを防衛するという奇跡まで引き起こし、そのミッションは完璧に達成された。
その時点では、もう羽生のモチベーションと言うより、巨大に膨れ上がった世間のモチベーションとなっており、谷川は完全に飲み込まれていったのだと思う。
昨年暮れのプロフェッショナル仕事の流儀、心に響いた流儀特集の中で、今までで最も心に響いた流儀ということで、羽生二冠の言葉、『才能とは努力を継続できる力』が見事第一位に輝いた。
また、片上五段はこの記事の中で、
「また羽生二冠の言葉にも、いつもながら印象的な言葉がたくさんありました。本当に、どんどん一人で深い世界へ行っているような印象を受けます。」
と語っています。
羽生はこれからどこに向かって行くのだろうか。
どうせわからないのだから、あとは混沌の世界に身を任せ、混沌を楽しんで対局している。
当時と比べて、森内、佐藤、郷田、深浦、そして若き渡辺竜王などなど、全体的にもレベルは上がっているし、羽生もどんなにがんばったとしても、多分4冠、5冠が精一杯ではないかと思う。
それでも、頻繁にタイトル戦に登場し、7割を超える勝率を残し、そういう意味でも羽生時代はまだまだ続くのだと思う。
どんな戦型でも厭わず、付き合い、絶妙の大局観の中で最善手を指し続ける羽生。
要は、彼の景色の中に、どんな山が見えるのか、である。
谷川九段がこの本の中で言ってます。
棋士は3つの顔が必要。
それは、勝負師と研究家と芸術家。
特に前例のない局面では、芸術家の側面が大きくものを言う。
この3つの顔をバランスよく持つことが、トップ棋士の絶対条件ではないかと。
しかし、羽生は、もうこの領域は超えているような気もしている。
将棋のことばかりでなく、学者や評論家や各界の一流の人たちと、対等以上に渡り合える力。
人間的にも、明るく、謙虚で、気配りも忘れない、一流の力量を備えるに至っている。
7冠の次に、聳え立っている山、それは果たして何か。
こうやって考えると、新手一生、とか、棋界の発展とかではないだろうし、言葉では言いようのない何かを捉えているのではないだろうか。
多分一人だけ、指し手、とか、局面、とか、盤上、という狭いところにはいないのでは、と思います。
もはや棋界の人ではなくなっているのでは、ないだろうか、と。
ということで、またしても羽生ネタです。
ssayさんの《モチベーション》という記事に触発されて書いてみます。
僕の「自分へのミッション」という記事に触発されて書いていただいたとのことですが、まず一部引用させてもらいます。
-------------------------------
将棋の羽生の場合、もちろん天賦の才能、並はずれた努力や根性も素晴らしいが、彼と他の超一流棋士達の何が決定的に違うのかと言えば、それはやはり「モチベーション」ではないだろうか。
--中略--
森内、佐藤にしても然りである。
森内が名人・竜王を含む三冠になった時、あるいは佐藤の5連続タイトル挑戦など、一時期羽生をも凌ぐ活躍を見せた事のある両名だが、長続きしなかった。何が羽生と違うのかと言えば、才能ではなく「モチベーション」である。
そもそも、羽生は勢いに任せて七冠を獲ったのではない。
七冠は棋士になった時からの目標だったと明言している。
このことは、自らの才能を過大評価しているのでも、他の棋士たちを見くびっていることを示しているのでもない。自分の才能に自惚れたり、他者を馬鹿にするような視野の狭い人間に、そんな大それたことなどできるはずがない。
おそらく羽生は、七冠王達成に対して「使命感」を持っていたのだろう。
それは、将棋界隆盛のため云々などという意味合いではない。そんな事を言うのは、国民のためと言ってその実訳の分からない使命感に燃えている政治家連中とあまり変わらない。
なぜ、七冠なのかと言えば、それは「そこに七冠があるから。」としか言いようがない。つまり、抽象的な漠然としたものでは、目標となりえない。羽生が棋士になった頃の将棋界は、それまでの先輩方の尽力により七つの公式タイトルを主催できるようになっていた。そういう環境を見て、羽生は七冠を目標に定めたのだろう。
ただし、目標にする事は誰でもできるが、本気で成し遂げようとするならば、これまでに述べた通り、才能+努力+体力+モチベーションが必要となる。
そして、羽生は自らに七冠制覇という「ミッション」を与えたのだ。
七冠達成以後の羽生の活躍も素晴らしいが、彼自身はその都度、その都度、自らのモチベーションの高さを維持するのに苦労したようだ。現在の羽生がどのようなモチベーションで臨んでいるのかは、現時点では分からない。
---------------------------------------
そこに七冠があるから、というのは蓋し名言だと思う。
7冠に向けての羽生のモチベーションは、マスコミも巻き込み、果ては世論までも巻き込んで、世論の強いモチベーションに昇華していった。
世間が7冠達成の瞬間を見たい、という大きな意思が、羽生を、そして、谷川を、そして、彼らの操る駒にまでも、ぐいぐいと染み込んでいった。
神戸大震災の被災というモチベーションで、谷川は一時凌いだものの、またそれはさらに拡大して、すべてのタイトルを防衛するという奇跡まで引き起こし、そのミッションは完璧に達成された。
その時点では、もう羽生のモチベーションと言うより、巨大に膨れ上がった世間のモチベーションとなっており、谷川は完全に飲み込まれていったのだと思う。
昨年暮れのプロフェッショナル仕事の流儀、心に響いた流儀特集の中で、今までで最も心に響いた流儀ということで、羽生二冠の言葉、『才能とは努力を継続できる力』が見事第一位に輝いた。
また、片上五段はこの記事の中で、
「また羽生二冠の言葉にも、いつもながら印象的な言葉がたくさんありました。本当に、どんどん一人で深い世界へ行っているような印象を受けます。」
と語っています。
羽生はこれからどこに向かって行くのだろうか。
どうせわからないのだから、あとは混沌の世界に身を任せ、混沌を楽しんで対局している。
当時と比べて、森内、佐藤、郷田、深浦、そして若き渡辺竜王などなど、全体的にもレベルは上がっているし、羽生もどんなにがんばったとしても、多分4冠、5冠が精一杯ではないかと思う。
それでも、頻繁にタイトル戦に登場し、7割を超える勝率を残し、そういう意味でも羽生時代はまだまだ続くのだと思う。
どんな戦型でも厭わず、付き合い、絶妙の大局観の中で最善手を指し続ける羽生。
要は、彼の景色の中に、どんな山が見えるのか、である。
 | 構想力 (角川oneテーマ21 C 138)谷川 浩司角川書店このアイテムの詳細を見る |
谷川九段がこの本の中で言ってます。
棋士は3つの顔が必要。
それは、勝負師と研究家と芸術家。
特に前例のない局面では、芸術家の側面が大きくものを言う。
この3つの顔をバランスよく持つことが、トップ棋士の絶対条件ではないかと。
しかし、羽生は、もうこの領域は超えているような気もしている。
将棋のことばかりでなく、学者や評論家や各界の一流の人たちと、対等以上に渡り合える力。
人間的にも、明るく、謙虚で、気配りも忘れない、一流の力量を備えるに至っている。
7冠の次に、聳え立っている山、それは果たして何か。
こうやって考えると、新手一生、とか、棋界の発展とかではないだろうし、言葉では言いようのない何かを捉えているのではないだろうか。
多分一人だけ、指し手、とか、局面、とか、盤上、という狭いところにはいないのでは、と思います。
もはや棋界の人ではなくなっているのでは、ないだろうか、と。












 下記の図。
下記の図。 -----------------------+-------------------------
-----------------------+------------------------- 
 でも失敗の位置づけはそうではない。
でも失敗の位置づけはそうではない。 --------+---------+--------+---------+---------
--------+---------+--------+---------+---------

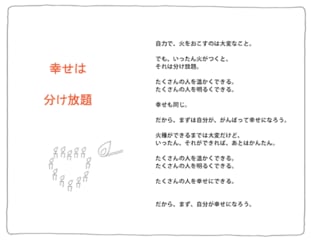
 新年です。寝不足だけど気持ちのいい年明け。今日は実家で、20人近く親戚が集まって大騒ぎでした。(1.1)
新年です。寝不足だけど気持ちのいい年明け。今日は実家で、20人近く親戚が集まって大騒ぎでした。(1.1) あっという間に6日間の休みが終わって明日から仕事です。ゆっくり本を読むとか、ハイビジョンで正月番組をゆっくり見る、とか、何もできないうちに過ぎてしまいました。(1.3)
あっという間に6日間の休みが終わって明日から仕事です。ゆっくり本を読むとか、ハイビジョンで正月番組をゆっくり見る、とか、何もできないうちに過ぎてしまいました。(1.3) 昨日は電車、すいてましたねえ。とりあえず、年賀状終わって、一息です。正月の録画、これから見ます。(1.5)
昨日は電車、すいてましたねえ。とりあえず、年賀状終わって、一息です。正月の録画、これから見ます。(1.5) 今日もいい天気。それにしても流通経済大柏、強いですね。大勝で決勝進出。そして、gooの木、あっという間に35000本、達成!(1.6)
今日もいい天気。それにしても流通経済大柏、強いですね。大勝で決勝進出。そして、gooの木、あっという間に35000本、達成!(1.6) 年明けから忙しいです。昨日も今日も一日中ハードで、昨夜は結構飲んでしまって。書きかけの記事、たくさんあって、どれからどう形にしようか、考えてはいるのだけど、落ち着いてまとめる時間がねえ・・・。(1.8)
年明けから忙しいです。昨日も今日も一日中ハードで、昨夜は結構飲んでしまって。書きかけの記事、たくさんあって、どれからどう形にしようか、考えてはいるのだけど、落ち着いてまとめる時間がねえ・・・。(1.8) 今夜はマーケティングコンサルタントのセミナーに行ってきました。ほんと、興味深い、頷ける話満載の二時間半。充実して少し興奮しちゃいました。(1.10)
今夜はマーケティングコンサルタントのセミナーに行ってきました。ほんと、興味深い、頷ける話満載の二時間半。充実して少し興奮しちゃいました。(1.10) 今日は仕事で会社。昨日とおとといは久々にカラダを動かして汗をかきました。あっ、gooの木、もうすぐ4万本ですよ。(1.14)
今日は仕事で会社。昨日とおとといは久々にカラダを動かして汗をかきました。あっ、gooの木、もうすぐ4万本ですよ。(1.14) gooの木、あっという間にすごいペースで4万本超えました。現在40.600本。3910ブログです。もうどうにも止まらない~
gooの木、あっという間にすごいペースで4万本超えました。現在40.600本。3910ブログです。もうどうにも止まらない~ (1.15)
(1.15) 寒い夜でした。飲んで帰ってきました。こんなに寒い日が続くと、温暖化は進んでないのかな、なんて、ふと安心したりもしますね。(1.16)
寒い夜でした。飲んで帰ってきました。こんなに寒い日が続くと、温暖化は進んでないのかな、なんて、ふと安心したりもしますね。(1.16) おととい、gooの木が4万本行きそう、って書いて、たった二日しかたってないのにもう42,000本です。いやあ、速い!(1.17)
おととい、gooの木が4万本行きそう、って書いて、たった二日しかたってないのにもう42,000本です。いやあ、速い!(1.17) 寒い毎日です。昨日の朝は少しだけど雪が積もってましたね。今日は寒気がして、早めに帰ってきました。しんどい一週間がやっと終わったけど、来週に持ち越しのこともたくさんです。(1.18)
寒い毎日です。昨日の朝は少しだけど雪が積もってましたね。今日は寒気がして、早めに帰ってきました。しんどい一週間がやっと終わったけど、来週に持ち越しのこともたくさんです。(1.18) 読みたい本が溜まってます。忙しくて読めてない現状、情けないです。今日は少し進みましたよ。(1.20)
読みたい本が溜まってます。忙しくて読めてない現状、情けないです。今日は少し進みましたよ。(1.20) 将棋の記事、書いてないです。もう少しお待ちくださいね。構想はいっぱい・・・。(1.21)
将棋の記事、書いてないです。もう少しお待ちくださいね。構想はいっぱい・・・。(1.21) 株価。
株価。 ガソリン。
ガソリン。 (1.22)
(1.22) gooの木、もうすぐ45,000本ですね。極寒でも、どんどん緑の木は育ってます。(1.25)
gooの木、もうすぐ45,000本ですね。極寒でも、どんどん緑の木は育ってます。(1.25) 今日はどこにも行かず、ずっと家にいました。いろいろやることあって、ブログは書いたけど、なかなか本が進みません。(1.27)
今日はどこにも行かず、ずっと家にいました。いろいろやることあって、ブログは書いたけど、なかなか本が進みません。(1.27) 明日は注目のハンドボール日韓戦。ルール、審判、判定、そして協会のやり方。いろいろ勉強になりますね。(1.28)
明日は注目のハンドボール日韓戦。ルール、審判、判定、そして協会のやり方。いろいろ勉強になりますね。(1.28) 冷たい雨の一日。たくさんコメントいただいてるのに、レスできてなくてすみません。草稿中の記事も溜まりに溜まってます。(1.29)
冷たい雨の一日。たくさんコメントいただいてるのに、レスできてなくてすみません。草稿中の記事も溜まりに溜まってます。(1.29)







