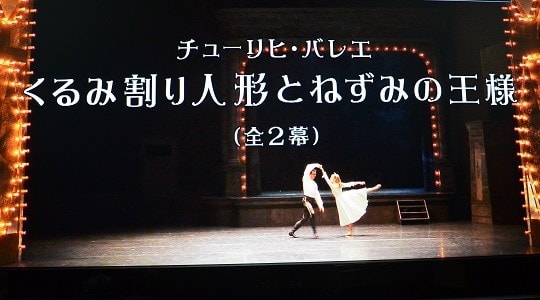5月5日
何とさわやかな日々が続くことだろう。
晴れ渡った青空の中に、いくつかの雲が浮かんでいる。
その空の下を、私は歩いて行く。
こうした時節だから、有名な山に行くわけにはいかない。
そこで、いつもの裏山をめぐる、2時間余りの山野歩きを楽しんできた。数日前のことだが。
それは、年寄りの私には、ひと汗かくぐらいのちょうどいい運動にもなったのだ。
もちろん、誰に会うこともない山道を、静かに歩いて行くことの愉しみもあるのだが、今の時季は、それ以上に様々な木々の芽吹きを眺められる喜びがある。
春の青空と新緑の組み合わせは、夏の雪渓と緑の山肌、さらには秋の紅葉に冬の雪景色などにも、勝るとも劣らない美しさがある。
振り返ってみれば、私の数十年にも及ぶ山旅は、そうした山々が季節とともに見せてくれる、その時だけの美しさに出会うためにあったのだと思う。
それは、研ぎ澄まされた芸術的な鑑賞眼からとかいうのではなく、自分の身の丈に合った世俗的な鑑賞眼から選んだ山々であって、卑近な例でいえば、下町の銭湯の壁に描かれた富士山の絵を美しいと思うような、言い換えればありふれた絵葉書写真のような、単純に私の目を引くだけの風景が組み込まれている山々たちだったのだ。
それだから、峩々(がが)たる山稜を連ねた北アルプスの剱岳(つるぎだけ)や穂高岳(ほたかだけ)の荘厳(そうごん)な姿だけでなく、たおやかにうねり続く草山や、木々に覆われた低い山々の、穏やかな姿にも目がいくようになったのだ。
さて、家を出て少し舗装道路を歩いて、その先で林道跡の山道に入って行く。
そこですぐに目につくのは、今の時期ならではの、樹々の中に見える紫色のフジの花だ。
人の手によって手入れされている植林地よりは、自然林の新緑の樹々の中で、その幹にまとわりついてツルを伸ばしていくフジ、今の時期には、その薄紫と木々の新緑の葉の色の対比がなんとも絶妙で、まるで一幅の絵として見事に収まっているように見える。(写真上)
確かに、人家の庭先などに、藤棚として育てられ枝を誘引されて張り巡らされた、フジの花は壮観だし、誰しも見とれるほどの美しさだが、私はこうした自然の山野で生きているフジの花の方に心惹(ひ)かれるのだ。
”やはり野に置け蓮華草(れんげそう)”というところか。
そこから続く林道跡の道は、深く切れ込んだ沢に下りて行くが、今年は雨の日が少なくて水量も少なく、簡単に対岸に渡り、見上げると、新緑の樹々が日の光を浴びて輝いている。(写真下)
木々の種類は、おおまかにいえば針葉樹と広葉樹という区切りで呼ばれるのだが、その中でも広葉樹は常緑広葉樹と落葉広葉樹に分けられていて、その常緑広葉樹の中で、照りのある厚い葉をもつ温帯樹林帯の樹々が、照葉樹と呼ばれていて、シイ・カシ類にクスノキやツバキなどがその主な木々である。
しかし、新緑のころになると、冬枯れの野山の樹々の先につぼみがふくらみ、モミジ、カエデ、コナラ、クリ、ヒメシャラ、ハゼノキなどもいっせいに明るく照り映える葉を開き出してきて、それを見ていると、むしろこの落葉広葉樹たちの新緑のころの姿こそ、照葉の樹だと言いたくなってしまう。
そして対岸の山腹を巻きながら登り返し、コナラの林を抜けると、まだ冬枯れのカヤが残る草原に出て、周囲の展望が広がる爽快な高原歩きになる。
この日は全九州的にも気温が高くなっていて、30℃近くまで上がった所もあったそうだが、ここでは山の高さもあってか、そう暑くは感じなかったが、夏が近づいてきていることを思わせる南風が吹きつけていた。
再び涼しい林の中に入り、この林の中でも芽吹き始めた樹々の葉が明るく透けて見えていて、そこに一本のヤシャブシの木があり、たくさんの黄色い花穂をぶら下げていた。(写真下)
ぐるっと回って来て、車道に出て人家の前を通った時、そこに派手な赤い小さな花が群がるように咲いているのを見つけた、花弁はあの黄色いマンサクの花の形に似ているが、今までに見たこともなく、何という木かは分からなかったので、写真に撮って家に戻ってパソコンで調べてみると、何とベニバナ(トキワ)マンサクという鑑賞用の木だということが分かった。
無理もない、いつもの時期ならもうとっくに北海道に行っていて、この道を今の時期に通ることなどなかったから気づかなかったのだ。
確かに、今、この世界中を覆う”コロナ禍”の問題は、現代の人間社会に大きな傷をつけ、過大な問題を残したのだが、悲観的な思いにふけっていても仕方がないし、一方では、悪いことばかりではなかったのだとも考えたい。
その一つの例が、”コロナ禍”によって、世界規模で現代の人間の経済活動が大きく抑えられた結果、問題になっていたCO2 (二酸化炭素)の排出量が大幅に抑えられることになったそうであり、自分の周りで患者が出ていないから、現実感が伴わずに傍観者の立場になってしまい、不謹慎な言い方になるのかもしれないが、こうした人間社会の”コロナ騒動”のてんまつを、地球上の他の動物や植物は、手をたたいて大喜びしているのかもしれない。
それは、形を変えて言えば、現代文明社会作り上げた人間たちへの、自然界から大きな警告の声だったのかもしれないのだが、果たして私たちはそれをどう受け止めればいいのだろうか。
そして言えば、この”コロナ禍”で一番危険な年寄りでもある、とうの私自身が、いつコロナウィルスによる病にかかるかもしれないのだが、それは、順送りの世の習いからすれば当然のことであり、私は従容(しょうよう)としてその運命を受け入れるつもりではあるのだが、何しろ、この一筋縄ではいかぬタヌキおやじ、死神におびえて、天上から下りてくる一本の”蜘蛛の糸”(芥川龍之介の短編小説)にしがみついて、最後まであさましき悪あがきをするのかもしれない。
すべては、”神のみぞ知る”ことなのだろうが。
前回も書いたように、相変わらず、日本文学の古典ばかりを読んでいる私であるが、こうした”コロナ禍”の大騒動をを見ていて思うことが多々あり、そこで、私の敬愛する二人の大先達(せんだつ)からの言葉を、自分のために言い聞かせるようにここに書いておきたいと思う。
まずは、ここでもたびたび取り上げてきた、兼好(けんこう)法師(1283~1350)による『徒然草(つれづれぐさ)』の第七十五段からの言葉であるが、彼は当時の都の神官の子でありながら、一時は北面の武士になり、その後出家して、京都郊外の山里に隠棲(いんせい)して、鎌倉時代末期から南北朝時代の混乱の世を、歌人としても生きた人である。
”つれづれわぶる人は、いかなる心ならん。まぎるる方なく、ただひとりあるのみこそよけれ。
・・・。
人に戯(たわむ)れ、物に争い、一度は恨み、一度は喜ぶ。そのこと定まれることなし。
・・・。
いまだ誠(まこと)の道を知らずとも、縁(えん)を離れて、身を閑(しずか)にし、ことにあずからずして、心を安くせんこそ、暫(しばら)く楽しぶとも言いつべけれ。”
(『日本古典文学全集』「徒然草」吉田兼好(兼好法師)永積安明校註・訳 小学館)
自分なりに訳すれば・・・。
”ひまになって、なすこともなく時を過ごして、困っている人は、どうしてそう思うようになったのだろうか。人や物とのかかわりがなくなって、のんびりと一人でいることが一番いいことなのに。”・・・。
”他の人たちと、楽しくたわむれ遊んでいる時はいいが、物をめぐって言い争うようになり、そのことで恨みに思ったりもするだろうし、また仲直りしてうまくいけばうれしくなる。そうしたふうに人と付き合えば、気持ちの浮き沈みがあって、いつも心が落ち着かなくなるものだ。”・・・。
”私はいまだに仏の道を悟ったとは言えないが、世の中の様々な因縁(いんねん)を離れて、静かな所に住んで、世俗のことにはかかわらず、心穏やかにして過ごすことで、それが、しばしの間でも、人生を楽しむことになっているとは言えないだろうか。”
もう一つは、これもここで度々あげてきた、良寛(りょうかん、1758~1831)の手紙の言葉である。
良寛は、江戸時代の末期に越後に生まれ、全国行脚の後に故郷の近くの国上山(くがみやま、313m)にある粗末な庵(いおり)に住んで、寺に入らず弟子も持たず、托鉢僧(たくはつそう)として清貧に甘んじて一人暮らしていたが、最期は近くの庇護者のもとに引き取られてそこで生涯を終えた。
その手紙は、江戸時代文政十一年(1828)、越後三条付近で起きた死者1600人倒壊家屋13000戸を出すほどの大地震が起きて、その時に良寛は歩いて現地まで行ってその惨状を目の当たりにしているが、近くに住む友人の一人であった山田杜皐(とこう)あてに書かれた見舞いの手紙の中にその有名な一節があり、(それは杜皐の災難をうまく逃れる方法はないものか、と尋ねられての返信であったともいわれているのだが)、そこで彼は以下のように書いている。
”しかし災難に逢(あう)時節には災難に逢がよく候(そうろう) 死ぬ時節には死ぬがよく候 是(これ)災難をのがるる妙法(みょうほう)にて候”
(『人と思想 良寛』山崎昇著 清水書院、『別冊太陽 良寛』平凡社)
受け取り方によっては、冷たく突き放した文言にも聞こえるかもしれないが、そこは歌会で顔を合わせるほどの間柄だから、おそらく杜皐は誤解することなく、この良寛の達観した思いを肝に銘じたことであろう。
私はと言えば、相変わらずのぐうたらな”デクノボー”(宮沢賢治の言葉)であり、コロナがさらに蔓延(まんえん)し地獄絵図の如くなれば、もしかしたら、われ先に”蜘蛛の糸”を目指す輩(やから)の一人になるかも知れないのだが、まあ、”明日は明日の風が吹く”し、やがては”散る桜 残る桜も 散る桜”なのだから(良寛の辞世の句ともいわれる)・・・。
それにしても、眼科での治療は完治までにさらに時間がかかるとのことであり、それでなくともコロナ緊急事態宣言は続いていて、今年は北海道には戻れないのかもしれない、となると、あのたださえヘビの多い家では(2019.6.10の項参照)、ヘビたちだけの"stay home "状態になっていて、お祭り状態の”ヘビ(蛇)ーメタル”の音楽祭が開かれているかも、それにしてもここでも何度も取り上げてきた、”ベビーメタル”の海外でのコンサート、いまだに一月に一度は”Youtube"で聴きたくなるのだが・・・元気になれる気がして。