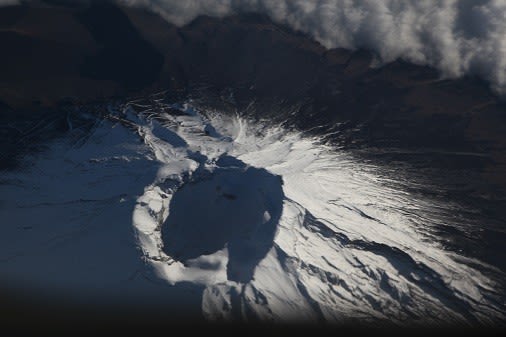11月26日
帰ってきた九州のわが家の庭には、落ち葉が降り積もっていた。(写真上)
それは、枯葉というよりは、まだその紅葉(黄葉)の色合いを十分に残している、落ちたばかりの葉だった。
モミジ、カエデ、ユリノキなどで、その下には、もう茶色になったサクラやウメの枯葉ものぞいていた。
いつもの年なら、この里山周辺では、まだ今頃までは十分に紅葉が楽しめるのだが、周りの人に聞いてみると、山々での紅葉が早かったように、平地の紅葉も早かったとのことだった。
わが家の庭の紅葉も、ほとんどが終わっていて、わずかに若いモミジの木に紅葉が残るだけで、あとは冬枯れの装いに変わっていた。
いつもは北海道との季節の差を見るかのように、まだまだこれからが九州の紅葉の盛りで、紅葉の景色を二度眺めることができたのだが。
もっとも、この秋は北海道のわが家での紅葉を、あれほどまでに、心ゆくまで楽しむことができたのだから(10月29日、11月5日の項参照)、さらに九州の紅葉までもというのは、いくら何でもムシが良すぎるだろう。
さて、こうした庭の落ち葉を掃き集めて、すでに一度目の”落ち葉焚(た)き”はすませたのだが、まだ他の枝葉などもあることだし、もう二三度はあちこち掃き集めて燃やさねばならないだろう。
ところが、この一週間は、庭仕事どころではなかった。
前回書いたように、風邪をひいてしまったからだ。
思えば、風邪薬を飲むほどの風邪をひいたのは、もう10年ぶりぐらいのことで、それまで軽い風邪気味の時は、前にもここで書いたこと月あるように、小さいカイロをタオルに包んで、頭なり首筋に巻いておけば、一日もたたずに治ったものだから、今回も甘く見ていたのだが。
しかし、今回の症状はそれらとはいささか違っていて、いつもの頭痛よりは、ともかく鼻水鼻づまりで体がだるく熱っぽいから、身動きするのもおっくうなくらいだった。
思えば、その前の日から鼻の奥が乾燥した感じで、それはいつもの鼻風邪の前兆に似ていたのだが、ともかく生垣の剪定(せんてい)をした後に、ぬれ落ち葉になる前に枯葉を掃き集めておこうと、庭仕事をしていて大汗かいたというのが良くなかったのだ。
ほぼ一週間たった今、大体治ったところだが、いやなセキが残っていて、人に会いに行く用事がいくつかあるのだが、マスクしてというのも変だし、人にうつさなくなるまでは、もう少しは家でおとなしくしているほうがいいだろう。
今まで、持って生まれた”おつむてんてん”脳天気な私だから、ここまで大きな病気ひとつしなくて、風邪などもめったにひくことがなく、若いころ会社で働いていた時に、風邪でたびたび休む人がいて、若い健康な体の私から見れば”ずる休み”ではないかと疑っていたものだが、今にして思えば当然のことだが、風邪をひきやすい体質の人もいるわけで、やむを得ない欠勤だったのだとわかるのだが。
そこで思ったのだが、昨日のテレビニュースの特集であげられていたことだが、今公開されているアメリカ映画『いろとりどりの親子』が評判になっているそうで、その女性監督の来日と併せて、その映画が取り上げられていたのだが、それは社会的マイノリティー(少数派)である、自閉症、ダウン症、低身長症などの障害を持つ子供と、それを見守る親たちのたちの日常を記録したドキュメンタリーということだった。
その中で、障がい者の子供と親たちは、様々な困難に立ち向かい、時には挫折し時には克服しては感動の涙を流すのだが、そこで語られていたのは、”幸せの形は無限にあり、幸せとはいろとりどりの形なのだ”ということだった。
低身長症の男が、まるでダルマさんのような格好で電動車いすに乗って街中を走っていた時、たまたま通り合わせた男から、”おれがそんな姿になったら、おれは自殺するね”と言われたそうだ。
そんな彼も、同じ病気の彼女とめぐり逢い、二人は結婚して、今その彼女のお腹には、二人の子供が宿っているという。
それを知った二人だけでなく、その両親たちも喜びにあふれて二人を抱きしめていた・・・二人だけの幸せのかたち。
さらにもう一つ思い出したのは、同じ日に放送されたいつもの「ポツンと一軒家」(テレビ朝日系列)の番組の中の一つの話だが、それは九州の山の中に造られた、大きなダム湖のさらに先にある一軒家の話だった。
55年前、大規模なダム建設で、その谷あいにあった300世帯もの人が住んでいた集落が、湖底に沈むことになって、多くの人は遠く離れた所へ引っ越して行ったが、そのうちのいくつかの世帯は、同じ谷の上に作られた代替地に住むことになって、そこで新しい集落を作ったが、そんな集落とは離れた、ダムの最奥地の所に水没を免れた一軒の家があって、そこには今も人が住んでいるという。
その家に一人で住んでいるという60代半ばになる彼は、人懐っこく取材陣を迎え入れてもてなし話をしてくれた。
もともと自分は、他の家の子供だったのだが、この家に養子にもらわれてきたのだという。
この家は水没から免れたものの、離れた一軒家になったために、元の持ち主は引っ越してしまい、空き家になっていたものを彼の養親が譲り受けて一部建て直し、以後ずっと数十年来住んでいるとのことだった。
その養父は20年前に亡くなり、養母も2年前に亡くなり、今ではこうして一人で暮らしているのだが、「養父からは、林業のことについていろいろと教えてもらい、養母からもよくしてもらって、今こうしてここにいられるのも二人のおかげであり、私は本当に幸せだと思う。」と明るい顔で話していた・・・彼の幸せのかたちがそこにはあったのだ。
2年前、あの神奈川県の知的障碍者施設「津久井やまゆり園」で起きた19人殺害の惨劇。
犯人の元施設従業員の若い彼の話によれば、社会に迷惑をかけるだけの障がい者たちだからという理由だけで・・・その彼が決めつけた幸せのかたちとは。
もともと、いわれなき差別化、迫害の歴史は、子供時代の”いじめ”から始まって、いつの時代にもあったことなのだが。
今、私には、自分の小さな安らぎの中にいることのできる、幸せがある。
こうして、年を取り、病気で横になっていた時を過ごしてから、余計に何ごともない時の、小さな幸せを思ってしまうのだ。
もう、一か月以上も山に登っていない、九重も地元の山も、ただ冬枯れの木立の中にあり、次に強い冬の寒気が押し寄せてきて冬景色に変わるまでは、あまり山に行きたいとは思わないのだ。
しかし、素晴らしい天気が続いたこの連休の間、ライブカメラで見る九重の牧ノ戸峠駐車場は、連日クルマでいっぱいだった。
考えてみれば、山に何らかのきらびやかな季節の衣装を求めて行く私と比べれば、ただ山の中を歩くことを目的とする彼らのほうが、より正しい山への接し方なのかもしれない。
話は変わるが、この23日は、満月だった。
それに合わせるかのように、その前後の日を含めて、夜の空は晴れ上がり、満月はひときわ大きく、照り輝いてた。
ちょうど1000年前のこの日、平安時代の藤原氏の絶頂の時代を築き上げた、あの摂政太政大臣(せっしょう、だじょうだいじん)の藤原道長(みちなが、966~1028)が宴のさ中に読んだとされる、あまりにも有名な歌・・・。
「この世をば わが世とぞ思う 望月(もちづき)の 欠けたることも なしと思えば」の一首が思い出されるが。
そこで思いつくのは、自分の栄耀栄華を満月になぞらえたとしても、思うに彼が見た満月は、雲の間にようやく見え隠れしていたものではなく、この数日私が見たような快晴の天気の日が続き、夜空はくまなく晴れ渡り、今日も昨日も、さらには明日にも見られるであろう満月の姿だったのだろうと思われるのだ。
さらにこの時の道長の年齢は52歳、昔の短命な時代の人のことを思えば、すでに高齢に近く、彼が亡くなったのはその10年後のことである。
つまり、若い時に権力の座にあった喜びとは違う、ある種の年寄りならではの感慨が含まれていて、兄弟との争いや天皇家との対立などを乗り越えて、やっとここまできたという思いがあったからだと思う。
若い時の喜びは、短急に絶頂に駆け上がった喜びであるが、年を経て経験を積んで勝ち得た喜びは、それまでの自分の足跡をも振り返り見ることのできる、感慨深い喜びになるのだ。
その後、彼は三人の娘を天皇家に嫁がせ、長男頼通(よりみち)に自分の職位を譲った後、剃髪(ていはつ)して仏門に入るが、ほどなく病に倒れ62歳で亡くなっている。(以上Wikipediaより)
さて、こちらに戻ってきた時に、家の庭でいまだに残っていたモミジの木は、まだ盛りの華やかさだったのだが、朝夕の冷え込みで少しずつ枯れ落ちていって、もうわずかな枚数を残すだけになってしまった。(写真下)
”散るもみじ 残る紅葉(もみじ)も 散るもみじ”
(元の句は、良寛辞世の句とされる「散る桜 残る桜も 散る桜」より)