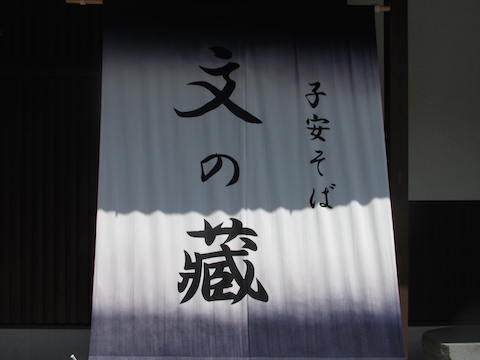開基は15世紀前半。臨済宗の寺である。

それ程、歴史のある庭ではないようだが、境内に足を踏み入れれば苔や新緑の姿が素晴らしい。
そういうものを大事にされるお寺のありがたさ。

度々の火災で多くの建物が焼失した中で、最も歴史があるのはこの山門である。

山門の右脇、翠豊かな池庭が設営されている。
大多数の仏教寺院では本堂の北側に、山からの流れを受け止める庭が設けられるのだが、こちらは山門の脇、誰でも気軽に行ける場所に池庭が設営されている。

ダイナミックな展開を狙ったためか、本堂の南面に石庭が展開されている。

実に味わい深い石が設置されたものである。
ここまで運び入れる苦労は並大抵のものではなかったのだろうと思う。

中央にあるのは坐禅石なのだろうか。南面の庭にあるので、月見にも適しているように見受けられる。


本堂の北面には裏山からのの流れが水を落とし、この辺りの名産である味噌を育てる木桶が洗われて干されていた。

魚沼の自然の中で、深い文化を伝えるお寺、境内にいれば本当に心地よく、実に存在が貴重なお寺であった。

それ程、歴史のある庭ではないようだが、境内に足を踏み入れれば苔や新緑の姿が素晴らしい。
そういうものを大事にされるお寺のありがたさ。

度々の火災で多くの建物が焼失した中で、最も歴史があるのはこの山門である。

山門の右脇、翠豊かな池庭が設営されている。
大多数の仏教寺院では本堂の北側に、山からの流れを受け止める庭が設けられるのだが、こちらは山門の脇、誰でも気軽に行ける場所に池庭が設営されている。

ダイナミックな展開を狙ったためか、本堂の南面に石庭が展開されている。

実に味わい深い石が設置されたものである。
ここまで運び入れる苦労は並大抵のものではなかったのだろうと思う。

中央にあるのは坐禅石なのだろうか。南面の庭にあるので、月見にも適しているように見受けられる。


本堂の北面には裏山からのの流れが水を落とし、この辺りの名産である味噌を育てる木桶が洗われて干されていた。

魚沼の自然の中で、深い文化を伝えるお寺、境内にいれば本当に心地よく、実に存在が貴重なお寺であった。