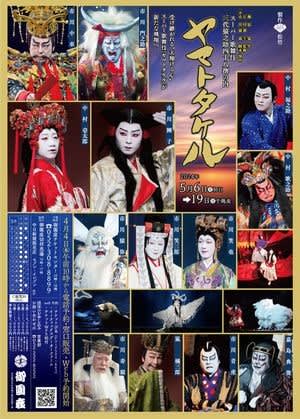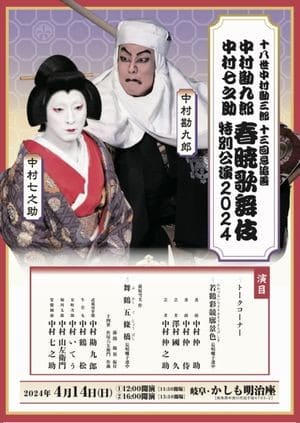「伝統芸能の今 -夢幻-」(8月17日・名古屋能楽堂)
酷暑の下、名古屋城三の丸にある「名古屋能楽堂」へ。今回の催しは「伝統芸能の今 -夢幻-」と題した舞踊を中心とした舞台。歌舞伎役者のみならず、囃子方、落語家、はたまたダンス・グループの若い子も出演するという変わった趣向。当初は児太郎が父、福助と共演ということで期待していたが不祥事で休演。廣松が代役で出ることになった。当日はもう暑いのなんの、37℃を超える酷暑。日差しも強烈で、自分は浅間町駅方面から歩いたので能楽堂に着いた頃には汗びっしょり。




名古屋能楽堂は以前にも見学に入ったことがある素晴らしい施設だが、予想した通り客入りは今ひとつ。自分の見た回は5列目程までしか観客が座っていなかった。キャパは630席とのことだからちょっと寂しい。他の会場がどうだったか知らないが、事前に公演情報もあまり目にしなかったものなァ。自分の座った席は中正面。正面に目付柱がくるのでちょうど役者の顔が隠れてしまう…。演目によるだろうが、ちょっとフラストレーションの溜まる席だった(こんなに空いているのでどこかに移れば良かったか)。
囃子方が配置に付き、開演。西本茉生がどんな活動をしている子かよく知らないが、観客には若い女性もちらほら居たのでファンが来ているのかな。落語家の桂空治の配役の意図は知らないが、なかなか達者。さすが噺家、台詞もはっきりと聞き易い。古い舞踊劇と現代語劇の融合した演目なのでしっくりこない部分もあったが面白い趣向だった。どの舞台でも廣松が大活躍。歌舞伎役者の代役はよくあることだが、急に任されてよく舞台を務められるものだ。右團次が出てくるとさすがに迫力が違う。舞台が近いので眼力が凄い。こういう舞台だから囃子方や「地謡(じうたい)」がとても重要で、実際素晴らしかったのだが、チラシやネットには全く名前が出ていない。プログラムの方には小さく「杵屋五吉郎社中」「田中傳次郎社中」とあったのがそれだろうが、いかにも扱いが小さいような。せめて各人の名前ぐらい載せて欲しいと思うのだが、伝統的にそういうことはしないものなんだろうな。
最後にアマテラス役で出演した福助。2013年に女形の大名跡、歌右衛門襲名発表直後に病に倒れ、襲名は延期されたまま。様子からするとなかなか右半身が思うようにならないようだが、すっくと立って観客を見回し、左手指先を差し伸べる姿と表情はさすが。短い出番だったが感動的だった。

演目
一、新作舞踊『幻お七』
出演:大谷廣松、西本茉生
二、朗読舞踊劇『井筒』
出演:市川右團次、大谷廣松、桂空治
三、新作舞踊『天乃岩戸』
出演:中村福助(アマテラス)、市川右團次(タジカラ)、市川右近(舞人)
大谷廣松(ウズメ)、西本茉生(アメノコヤネ)、桂空治(スサノオノミコト)
↓ gooブログの終了予告に伴って、記事をHatena Blogにも掲載しています