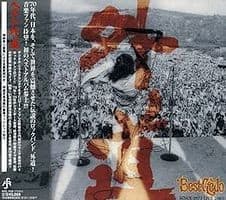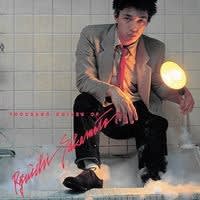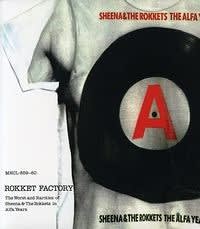Baby a Go Go / RCサクセション (1990)
1990年に発表されたRCサクセションのラスト・アルバム。ずっと好きだったRCだしライヴも何度も行ったが、このアルバムは持っていなかった。当時、清志郎(に似た人・笑)がタイマーズ(The Timers)の活動を経て、「COVERS」、ライヴ・アルバム「コブラの悩み」を出した頃までは追っかけていたのだけれど、だんだんとバンド内のゴタゴタが伝わってきていた。当時はまだインターネットが無かったので雑誌とかだったと思うが。そして先行シングルの牧歌的な「I Like You」を聴いて「あの過激さはどこに!?…」となって興味を失ってしまったのだったと思う。
メンバーが清志郎、チャボ、リンコの3人+春日博文になってしまったRC。アルバムは件の01から始まる。もろにバーズ(The Byrds)のようなサウンド。後から知ったことだが、録音は70年代のアナログなやり方に拘ったものだったらしい。タイマーズやらカバーズ、それに当時の空気感のことをいったん置いておけば、これらの楽曲はとても充実していて完成度も高い。清志郎ならではの比喩やダブル・ミーニングはあまり露出させず、素直に言葉を連ねている感じ。でも自分が当時、このアルバムを全部しっかりと聴いていたとしても、やっぱり好きにはならなかったろうなァ…。なにせ東京のアパートの一室で、野音で録音された「コブラの悩み」冒頭の、
♪頭の悪い奴らが 圧力をかけてくる
呆れてものも言えねえ
またしてもものが言えない
権力を振り回す奴らが またわがままを言う
俺を黙らせようとしたが
かえって宣伝になってしまったとさ♪
にビリビリと痺れてしまった身だもの…。
中古店にて購入(¥330)
- Label : EMIミュージック・ジャパン
- ASIN : B000064U0Y
- Disc : 1