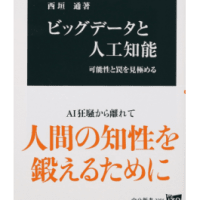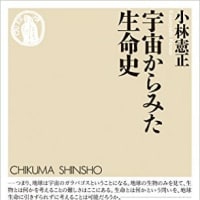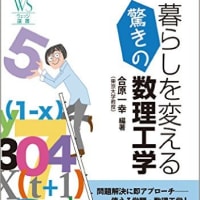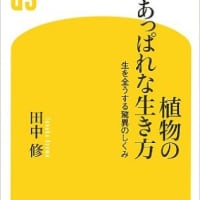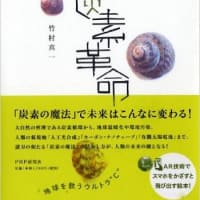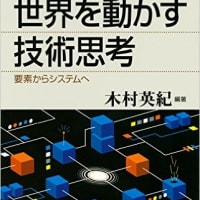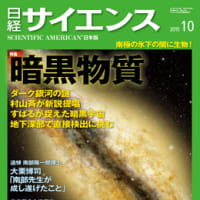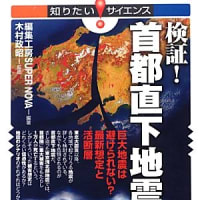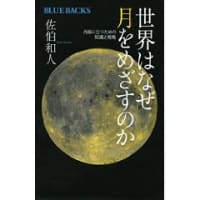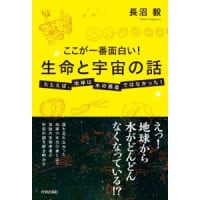産業技術総合研究所(産総研)電子光基礎技術研究部門 超伝導エレクトロニクスグループ 伊豫 彰 上級主任研究員、荻野 拓 主任研究員、石田 茂之 主任研究員、永崎 洋 研究グループ長は、金属ナトリウム(Na)がグラファイト層間化合物(Graphite Intercalation Compound, GIC)の生成に有効な触媒として働くことを発見した。
これをもとに、高速かつ簡便にGICの大量合成を可能にする新しい手法(Na触媒法)を開発した。
このNa触媒法によるGIC製造方法は、GICの応用開拓および産業利用に向けた開発に貢献することが期待できる。
炭素(C)には、グラファイト、ダイヤモンド、フラーレン、グラフェン、カーボンナノチューブといった同素体が存在する。これらは全く異なる機能性を有しており、幅広い分野での研究や応用がなされている。例えば、グラフェンは2004年に発見されたCの新しい同素体であり、非常に高い電気・熱伝導度などの特異な性質を持っている。グラフェンが弱く積層した物質がグラファイト。グラファイトは鉛筆の芯などにも用いられるありふれた材料。グラファイトはこのグラフェン層の間にさまざまな原子や分子を挿入(インターカレート)することができる。インターカレートで生じた物質をグラファイト層間化合物(GIC)という。
層間に入る原子の種類により多種のGICが存在し、それぞれが高導電性やガス吸蔵性、超伝導性など、多様な機能を有している。
グラファイトへのインターカレーション現象は、リチウムイオン二次電池の電極でも利用されている。最近では、GICを原料にしたグラフェン合成技術も開発され、今後もさまざまな応用が期待される。
しかし、気相法や溶融塩法などの従来のGIC合成手法は、合成プロセスが複雑で、合成に数日〜数週間を要し、ステージ構造の制御が容易ではなく、高価な高配向性グラファイト原料が必要など、高品質試料の大量合成には不向きであった。
そのため、GICの実用化に向けて、革新的なGIC合成法の開発が望まれていた。
産総研では、省エネ社会と革新的な量子コンピューティングの実現を目指して、次世代超伝導材料の探索を行っている。その過程で、従来では合成が困難であったGICの一種であるCaC6が、金属ナトリウム(Na)の存在下では容易に生成できることに気づいた。
さらに、このNaの効果は、LiやKなどのアルカリ金属(AM)やSrやBaなどのアルカリ土類金属(AE)のGIC(AM-GIC, AE-GIC)の生成にも有効であることを見いだした。この偶然の発見をもとに、AM-GICやAE-GICを簡便に合成できる技術の研究に取り組んだ。
今回開発したNa触媒法では、従来法に比べ格段に低温・短時間で高品質なAM-GICおよびAE-GICの合成が可能。また、この方法では、安価な粉末グラファイトを原料として使用可能であり、かつ設備やプロセスも従来法に比べ各段に簡便になっている。
しかし、Na触媒法によるGIC合成の研究は端緒についたばかり。今後、GICの大量合成と応用展開の検討、AEやAM以外の元素や分子のグラファイトへのインターカレーションに対する有効性の検証、Naの触媒作用によるGIC生成の微視的メカニズムの解明などの研究を行う予定。また、GICやインターカレーション現象を利用している二次電池の電極などへのNa触媒法の適用可能性を追求する。<産業技術総合研究所(産総研)>
これをもとに、高速かつ簡便にGICの大量合成を可能にする新しい手法(Na触媒法)を開発した。
このNa触媒法によるGIC製造方法は、GICの応用開拓および産業利用に向けた開発に貢献することが期待できる。
炭素(C)には、グラファイト、ダイヤモンド、フラーレン、グラフェン、カーボンナノチューブといった同素体が存在する。これらは全く異なる機能性を有しており、幅広い分野での研究や応用がなされている。例えば、グラフェンは2004年に発見されたCの新しい同素体であり、非常に高い電気・熱伝導度などの特異な性質を持っている。グラフェンが弱く積層した物質がグラファイト。グラファイトは鉛筆の芯などにも用いられるありふれた材料。グラファイトはこのグラフェン層の間にさまざまな原子や分子を挿入(インターカレート)することができる。インターカレートで生じた物質をグラファイト層間化合物(GIC)という。
層間に入る原子の種類により多種のGICが存在し、それぞれが高導電性やガス吸蔵性、超伝導性など、多様な機能を有している。
グラファイトへのインターカレーション現象は、リチウムイオン二次電池の電極でも利用されている。最近では、GICを原料にしたグラフェン合成技術も開発され、今後もさまざまな応用が期待される。
しかし、気相法や溶融塩法などの従来のGIC合成手法は、合成プロセスが複雑で、合成に数日〜数週間を要し、ステージ構造の制御が容易ではなく、高価な高配向性グラファイト原料が必要など、高品質試料の大量合成には不向きであった。
そのため、GICの実用化に向けて、革新的なGIC合成法の開発が望まれていた。
産総研では、省エネ社会と革新的な量子コンピューティングの実現を目指して、次世代超伝導材料の探索を行っている。その過程で、従来では合成が困難であったGICの一種であるCaC6が、金属ナトリウム(Na)の存在下では容易に生成できることに気づいた。
さらに、このNaの効果は、LiやKなどのアルカリ金属(AM)やSrやBaなどのアルカリ土類金属(AE)のGIC(AM-GIC, AE-GIC)の生成にも有効であることを見いだした。この偶然の発見をもとに、AM-GICやAE-GICを簡便に合成できる技術の研究に取り組んだ。
今回開発したNa触媒法では、従来法に比べ格段に低温・短時間で高品質なAM-GICおよびAE-GICの合成が可能。また、この方法では、安価な粉末グラファイトを原料として使用可能であり、かつ設備やプロセスも従来法に比べ各段に簡便になっている。
しかし、Na触媒法によるGIC合成の研究は端緒についたばかり。今後、GICの大量合成と応用展開の検討、AEやAM以外の元素や分子のグラファイトへのインターカレーションに対する有効性の検証、Naの触媒作用によるGIC生成の微視的メカニズムの解明などの研究を行う予定。また、GICやインターカレーション現象を利用している二次電池の電極などへのNa触媒法の適用可能性を追求する。<産業技術総合研究所(産総研)>