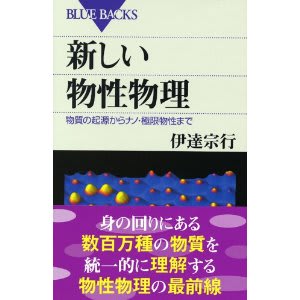書名:特集:素粒子の世界<月刊Newton(ニュートン)2012年7月号>
監修:村山 斉
発行所:ニュートン プレス
発行日:2012年6月7日
目次:プロローグ 素粒子とは何か
身のまありのあらゆる物質は、結局、素粒子の集まりでしかない。素粒子を知ることは、
自然界を知ることなのだ
PART1“物質の素粒子”の仲間
電子、クォーク、ニュートリノなど、物質を形づくる素粒子の仲間たちを紹介
PART2“力の素粒子”の仲間
“物質の素粒子”という役者だけでは自然界という劇は成立しない。役者どうしがおよぼ
しあう「力」を知る必要がある
PART3 素粒子物理学最前線
万物に質量をあたえる「ヒッグス粒子」とは?宇宙を支配する「ダークマター」の正体は
未発見の素粒子?
PART4 最前線特別レポート
現在、世界で最も注目をあびている研究機関「CERN(セルン)」。ヒッグス粒子探しの
最前線をレポート
2012年7月4日、欧州合同原子核研究機関(CERN<セルン>)は、「ヒッグス粒子」とみられる新しい粒子を99.9999%以上の確率で発見したと発表した。これは、2つの国際チームによる大型加速器を使った探索実験によるもので、年内にもヒッグス粒子と最終的に確認される公算が大きく、ノーベル賞級の大発見となるものとみられる。ヒッグス粒子は、宇宙や物質の成り立ちを説明する素粒子物理学の基礎である「標準理論」の中で、これまで唯一見つかってなかった素粒子。CERNでは、東京大学などの研究者が参加する「アトラスと欧米の研究者が参加する「CMS」の2つのチームに分かれ実験を行ってきたが、両チームとも2012年6月までの実験で、ヒッグス粒子とみられる新粒子の存在確率が99.9999%以上になったことを確認したもの。
「ヒッグス粒子発見」のニュースは、新聞・テレビで大々的に報道されたので、素粒子に対する国民的関心が一挙に高まったと言えよう。我々の身の回りにある、ありとあらゆる物質は、「電子」と2種類のクォーク、すなわち「アップクォーク」と「ダウンクォーク」でできているが、これらの素粒子を研究する国際的な巨大実験施設として、スイス、ジュネーブの郊外に大型ハドロン衝突型加速器「LHC」が設置されており、今回のヒッグス粒子の発見も、このLHCがなくては到底不可能であった。LHCの建設費用は約9000億円で、東京のJR山手線の長さに匹敵する1周27㎞もあり、世界各国から1万人を上回る研究者が関わっている。LHCは、正に人類を挙げての一大実験施設なのである。
現在の素粒子物理学の基礎となっている理論は「標準モデル(標準理論、標準模型)」であり、現在、この標準モデルを実証しようと世界の素粒子物理学者たちが、日夜奮闘しているわけで、今回のヒッグス粒子の発見は、この標準モデルが大きく一歩前進したことを意味する。標準モデルは、自然界にある4つの力(電磁気力、弱い力、強い力、重力)の統一にある。既に電磁気力と弱い力は、電弱統一理論により、統一的に理解することに成功している。現在、次の目標として、これに弱い力を加えた力の統一理論が研究されているのである。最終的には、さらに重力も加えて、全ての力を統一的に理解されることを目指している。何故、力の統一を目指すのかというと、「さまざまのものを少ない要素で美しく説明したいから」(村山 斉氏)である。
このように、現在の素粒子理論は大きな飛躍を見せているわけであるが、素粒子理論の専門書はいずれも難しく、一般の人が理解するのは困難だ。しかし、ここまで大きなニュースになって、人々の関心を集めている素粒子について最低限の知識だけは持っておきたい、という熱いニーズに応えているのが「月刊Newton(ニュートン)」の2012年7月号の特集:素粒子の世界である。カラーのグラフィックスをふんだんに使い、初心者でも理解できるよう配慮されているのが嬉しい。極端な話、素粒子を全く知らないない者でも、丁寧にこの特集を読み終えれば、現在の世界の素粒子研究の最先端を理解することも不可能でない。東京大学カリブ数理連携宇宙研究機構の機構長である村山 斉が監修者となり、協力者に世界の第一線で活躍している人たちが参画しているので、内容的にも安心して読み通せる。(STR:勝 未来)