■ レターヘッド(Letterhead)
日本企業も最近は使うことがある社外向けの会社の「便箋」だが、日本で言うところの「会社の便箋」とは重みが違う。レターヘッドを使った手紙は、「その組織が正式に出した文書」ということになる。だから組織に属している人間がその組織から手紙を出す場合でも、個人として手紙を書く場合は、レターヘッドを使ってはいけない。ゆえにレターヘッド使用に対する管理は、厳しくしなければいけないらしい。
以下は、
「英文ビジネスレター作成のためのガイドライン」より引用である。
レターヘッドとは文字どおりレター用紙の頭の部分という意味であり、企業・団体のシンボルマーク、社名、アドレス、電話番号などが印刷された、レター用紙上部のスペースを指す。一般には、そのようなデータが印刷された正式なレター用紙そのものをレターヘッドと呼んでいる。
http://someya1.hp.infoseek.co.jp/chap-2(1).html
ある米系証券会社では、ヴァイス・プレジデント以上の地位になると、企業のロゴとヘディング(=Heading)に加えて、自分の名前と肩書きがあらかじめ印刷されたレターヘッドを作ることになっていた。証券会社なので「ヴァイス・プレジデント」(=vice president、直訳すると「副社長」)とはいっても地位はそれほど高くなく、実際は「部長」程度の地位だった。米系の金融サービス業では、しばしば「オフィスで石を投げれば、ヴァイス・プレジデントに当たる」といわれるぐらい、ヴァイス・プレジデントがわんさといたりするのだ。従業員が5名のある部署では、全員がヴァイス・プレジデントだった。もちろん全員がエネルギッシュにバリバリと働いていた。
ここで、国際展開をしている
BSI Groupという企業体の
レターヘッドの見本(
http://www.bsi-global.com/Brand+Identity/Stationery/uk_strap_2.pdf)を見てみよう。(要Acrobat Reader)
用紙のどの位置に、どの大きさで、どんな色を使って何を印刷すべきかがきちんと決められている。そこで再び
「英文ビジネスレター作成のためのガイドライン」より引用する。
欧米にはレターヘッドのデザインを専門とするレターヘッドデザイナーがおり、またレターヘッドデザインを含めたトータルなCI戦略を専門とするコンサルティング企業も多い。欧米企業では、ビジネス用のレターヘッドや封筒、名刺などの、いわゆるビジネス・ステーショナリー (business stationery) はこうした専門家の手によって、それぞれの企業のイメージを伝える総合的なCI (corporate identity) 戦略の一環として制作されるのが普通である。
http://someya1.hp.infoseek.co.jp/chap-2(1).html#2.4
レターヘッドとはそういうものなである。
ところで、以前勤めていた英国企業の日本法人では、社外向けの会社の便箋として
コンケラー(Conqueror) の透かし入りの紙を使ったレターヘッドを使っていた。このレターヘッドは英国本社のレターヘッドにならい、デザインを英国本社のレターヘッドを、日本法人の情報に日本語で差し替えたものだった。
わたしが「おや?」と思ったのは紙の質についてだった。社長に尋ねると、やはり英国で印刷されたものだった。「さすが英国企業だ。コンケラーを使っている。」日本法人はえらくケチな企業だったが、このレターヘッドの用紙には大いに感銘を受けたものだ。
しかし、このレターヘッドはわたしが予想しなかったところで問題になった。ある日、50代の男性従業員が思いつめた顔でやってきた。
男性従業員「ふくしまさん。このレターヘッドは、絶対にまずいと思いませんか?」
わたし「え?????」
男性従業員「当社の名前と住所が、お客様の住所と会社名より上に置かれるというのは、ものすごく失礼ですよ。」
わたし「でもレターヘッドって、こういうもなのですが…」
男性従業員「外国ではそうかもしれませんが、ここは日本です。日本では絶対にだめですよ。」
確かに、彼の説明にも一理あった。日本では手紙文で「私は」とか「私議」と言う言葉を行の一番下配置するべきとしているぐらい、文字の位置関係にこだわって、自分を低くして相手をたてるものだ。本社のレターヘッドのデザインに合わせた日本人のレターヘッドは、そんな日本人の手紙のマナーににじみ出る美徳を、見方によっては「踏みにじる」ものだった。さらには、こう言ってきた男性従業員が、米国系メーカーに長年勤務していた人間だったこともあった。「外資系企業に勤めてきた人間ですらこう感じるのならば、日系企業の人間は、このレターヘッドに対して、もっと無礼だと感じるに違いない。」
そこでわたしは、レターヘッドの上部にある日本法人の会社名や住所などの情報を、すべて英語表記に直し、用紙の下余白辺りに日本語で企業名、住所、電話番号等を入れて、英国の本社に発注した。いわゆるバイリンガル表記である。
用紙の上部の文字を英語表記にしたのは、英国本社の仕様から外れて、グループ企業としての統一感がなくなることを嫌ったのが第一の理由だ。それに「英語で書かれているものなら、日本人は『文字』というよりも『デザインの一部』という感覚で見てくれるだろう」とも考えた。さらには「英語なのだから、用紙の上部に差出人情報が置かれているのも当然だろう感じてくれる率が高い」とも。そして、
わざわざ英国に発注したのは、当時日本では入手経路が非常に限られていたコンケラーを使ってくれるはずだからであった。
ところが到着したレターヘッドは、デザインは指示通りになっていたものの、なぜか紙の質が大幅にグレードダウンしていた。まるで厚手のコピー用紙のような質で、もちろん透かしはない。ヌォォォォ! レターヘッドは企業の顔だろ。CI戦略のひとつだろ。これが以前には研修所としてお城を所有していた、格式ありげな企業のやることかぁぁぁ。
このとき、わたしはこの英国本社は近い将来、つぶれるか、別の企業に買い取られるだろうと予測した。そしてわたしが会社を去った後で、この予測は当たった。
ちなみに、全くの一個人でも、カッコいいレイアウトのレターヘッドで手紙を書く人が多くなった。タイプライターで手紙を打っていた昔にはできなかった芸当だが、現在はコンピュータを使用するため、手紙のレイアウトが自由になるからだ。
例えば、→
これ←をみて欲しい。(リンク先は、
Distinctiveweb.comのカバーレターのサンプルの1つである。)
差出人氏名が一番上にバーンと印刷されている。この人は使っていないが、人によっては企業よろしく、個人でもロゴマークが使う人もいる。
実はわたしも、Microsoft Publisherで作った個人のレターヘッドを、誤解を受けないときに限り使用している。(さすがにロゴマークはない。)その誤解とは「なんだぁ? こいつ、自分を手紙の一番上にでかでかと載せやがって。失礼な女だ。」というものである。
■ コンティニュエーション・ペーパー(Continuation Paper)
さて、レターヘッドを使って手紙を書く場合、手紙の2枚目以降にはどのような紙を使うべきだろうか。
レターヘッドには差出人情報がすべて含まれているが、この用紙を2枚目以降に使うと、差出人情報全部がいちいち入ってしまって余計だし、スペースをとってうるさい。
ここで2枚目以降用として、コンティニュエーション・ペーパー(continuation paper)とかコンティニュエーション・シート(continuation sheet)と呼ばれている用紙の出番である。
コンティニュエーション・ペーパーは、デザインとしては、レターヘッドで使ったタイプのロゴや会社名を小さめのサイズにしたものを、紙の上部のどこかに配しておいたものが多い。大体はレターヘッドの位置にあわせて、用紙の右肩か左肩が多い。紙の質は、もちろんレターヘッドと同じものを使用する。住所や電話番号等の情報はなしだ。
日本の企業では、レターヘッドは用意していても、コンティニュエーション・ペーパーは作っていないところが多い。かつて秘書として派遣に行った先などで、2枚以上にわたる長文の英文の手紙の原稿がきても、コンティニュエーション・ペーパーがない企業が結構あった。こんなときは、「2枚目の紙はどうするんだぁ!」と、心の中で叫んだものである。もちろん会社にケチをつける生意気な派遣だと思われると嫌なので、「コンティニュエーション・ペーパーを作るべき」などという提案は、よほどのことがない限りしなかったが。
その代わり周りを見渡して、他の秘書の方がやっている方法にならうことにしていた。レターヘッドを2枚目にも使うか、無地の用紙を使うかのどちらかだった。後者の方法を採る企業の中には、2枚目用としてレターヘッドの紙と質が同じの無地の紙を用意しているところもあった。
ちなみに先ほどレターヘッドの見本を示したBSI Groupの、コンティニュエーション・ペーパーの見本は以下のURLにある。
http://www.bsi-global.com/Brand+Identity/Stationery/cont+a4.pdf
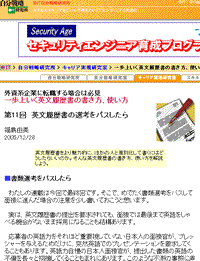 @IT自分戦略研究所の「一歩上いく英文履歴書の書き方、使い方」の連載が無事終了。
@IT自分戦略研究所の「一歩上いく英文履歴書の書き方、使い方」の連載が無事終了。








