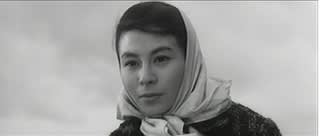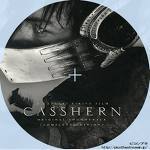前日に引き続いて、石井裕也監督作品のレビューです。
ハ)『ガール・スパークス』
石井裕也監督による長編映画の第3作(2007年制作)(注1)。

映画の冒頭では、主人公の女子高生が、交通量の多い道路脇に現れて空を見上げると、それと判別できるロケットが右から左から飛んでいて、中には空中で衝突するものもあります。
これはSF映画かなと身構えると、それ以降は極めて現実的なストーリーが面白おかしく描き出されます(話の合間には、空にロケットが飛ぶものの!)。
有体にいえば、田舎の高校に通うこの女子高生に接近してくるする男性は、皆が皆ダメ人間で(「男って、チョーダサイ!」)、彼女は「ロケットにも、親父にも、学校にも、工場にも、チョーむかつく」と叫び出さざるを得なくなってしまうのです。
なにしろ、父親はネジを製造する零細企業の社長ながら、母親のいない彼女のためを思って、割烹着を着たり、果ては化粧までしてしまいます。また、彼女に気のある男子生徒は、彼女へのプレゼントを、ほかの生徒を脅して調達したりします。学校の担任は、性教育の授業中に、わざわざ彼女に教科書を読み上げさせようとします、などなど。
それで、彼女は、ここを離れればもっと世の中のことが分かり、この世を変えられるかもしれないと、東京に出て下宿生活をしますが、5kg太っただけで何も分からずに1か月で舞い戻る羽目に。
そうこうするうちに、父親の会社の経営状況が思わしくないことがわかり、そんなことならと今度はネジ製造の仕事に一生懸命になります。
ところが、空にロケットが飛ばなくなると、そのロケットにこの工場のネジが使われていたこともあって、父親の会社は倒産してしまいます。
ロケットの意味するところを別にすれば、この映画は他の石井作品と比べても、かなり分かりやすく出来上がっているなと思いました。男性陣は皆ダメ人間ばかりで、彼らに「チョーむかつ」いている女子高生が、最後には頑張ってしまうというストーリーがくっきりと描かれています〔最後の最後では、その頑張りも無意味になってしまいますが〕。
さて、そのロケットですが、もちろん各人各様に受け止めればいいと思います(注2)。たとえば、日本経済の中核(大企業とか大銀行など)と考えてみてはどうでしょうか?地方の零細企業ならば、直接に関係しないものの、その中心部分が失速してしまうと、早速倒産という影響をもろに受けてしまうのです。
となれば、このロケットこそがモウ一方の主役なのではないでしょうか?そして、一時代前の無様な形で今にも墜落しそうに空を飛んでいる姿からすると、日本社会に対する石井監督の見方もそんなところなのかなとも思えてしまいます。

(注1)「Intro」掲載の「インタビュー」によれば、この映画は50万円で制作されたとのこと。
(注2)「映画芸術DIARY」に掲載された「インタビュー」では、石井裕也監督は、「不誠実や悪が現実に存在してるのに、それがわからないように隠蔽されている。そういうことのシンボルって言うか、具現的な表現があのロケットなんです。意味わかんないけど、でも現に飛んでるっていう」と語っています。
ニ)『ばけもの模様』
2007年制作の本作品は、専業主婦の順子が主人公。海で一人息子の清が溺死するという事故に遭ってから、精神に幾分変調をきたし、夫の喜一との関係もギクシャクしています。

ある日、順子は、パチンコ店の駐車場を走る車にもう少しのところで轢かれそうになります。その若い運転手は、石井監督の映画によく出てくる“ダメ人間”というか、大変気の小さな人間。近くのスーパーの入り口で、叔母さんと一緒にメロンパンを車を使って販売しています。
他方で、順子との生活に疲れた夫の喜一は、会社の女子事務員と不倫旅行に出掛けてしまいます。順子の方も、自分を轢きそうになった運転手とばったり会ったのをいいことに、彼を強迫してメロンパン販売用のバンに乗って、当て所もない旅に出ます。
ここらあたりまでは、まあ普通の物語の進み具合といえるでしょう。
ところが、全然別口で出発したにもかかわらず、二人は、息子を亡くした海辺で巡り会ってしまうのです。それで戻って再び一緒の生活を始めるのですが、スッキリしない順子は、衝動的に夫をバットで殴りつけてしまいます。その上、順子はあの運転手を家に連れてきて、瀕死の重傷を負ったはずの夫の介抱に当たらせるのです。
ただ、暫くすると、夫は何事もなかったように起き上がり、最後はメロンパンの販売に携わるようになっています。
順子の方は、再び海の方に出て空を見上げると、重い便秘が治ってしまい、死んだはずの息子が現れて、その後片づけをするところでジ・エンド。
前半は、子どもを事故で亡くした夫婦の重苦しい関係が中心的ですが、順子が夫をバットで殴りつけた辺りから物語は酷くオカシナ様相を呈してきて、結局、順子はズット苦しめられてきた便秘も治り、また死んだ息子との関係も折り合いが付いた感じになるのです。
もしかしたら、『反逆次郎の恋』の主人公のように、バットで重圧をはね除けろ、そうすれば局面が打開されるかもしれない、と映画は言っているのでしょうか?といっても、メロンパンの販売に携わる夫にしても、便秘が治った順子にしても、アカルイミライが待ち構えているとはトテモ思えないのですが。
ところで、この映画のラストの方では、主役の順子(元宝塚劇団華組トップスターの大鳥れいが扮しています)が、海岸で“野糞”をする場面があるところ、上記の『ガール・スパークス』でも、父親の大きな便が浴室にあったと女子高生が騒ぐ場面があります。『川の底からこんにちは』では、木村佐和子(満島ひかり)が糞尿を川岸に撒く姿が何度も描かれています。
石井監督の糞便に対する拘りの表れなのでしょうが、決して糞便を汚いマイナスのものとして扱っていない点が面白いなと思いました。
ハ)『ガール・スパークス』
石井裕也監督による長編映画の第3作(2007年制作)(注1)。

映画の冒頭では、主人公の女子高生が、交通量の多い道路脇に現れて空を見上げると、それと判別できるロケットが右から左から飛んでいて、中には空中で衝突するものもあります。
これはSF映画かなと身構えると、それ以降は極めて現実的なストーリーが面白おかしく描き出されます(話の合間には、空にロケットが飛ぶものの!)。
有体にいえば、田舎の高校に通うこの女子高生に接近してくるする男性は、皆が皆ダメ人間で(「男って、チョーダサイ!」)、彼女は「ロケットにも、親父にも、学校にも、工場にも、チョーむかつく」と叫び出さざるを得なくなってしまうのです。
なにしろ、父親はネジを製造する零細企業の社長ながら、母親のいない彼女のためを思って、割烹着を着たり、果ては化粧までしてしまいます。また、彼女に気のある男子生徒は、彼女へのプレゼントを、ほかの生徒を脅して調達したりします。学校の担任は、性教育の授業中に、わざわざ彼女に教科書を読み上げさせようとします、などなど。
それで、彼女は、ここを離れればもっと世の中のことが分かり、この世を変えられるかもしれないと、東京に出て下宿生活をしますが、5kg太っただけで何も分からずに1か月で舞い戻る羽目に。
そうこうするうちに、父親の会社の経営状況が思わしくないことがわかり、そんなことならと今度はネジ製造の仕事に一生懸命になります。
ところが、空にロケットが飛ばなくなると、そのロケットにこの工場のネジが使われていたこともあって、父親の会社は倒産してしまいます。
ロケットの意味するところを別にすれば、この映画は他の石井作品と比べても、かなり分かりやすく出来上がっているなと思いました。男性陣は皆ダメ人間ばかりで、彼らに「チョーむかつ」いている女子高生が、最後には頑張ってしまうというストーリーがくっきりと描かれています〔最後の最後では、その頑張りも無意味になってしまいますが〕。
さて、そのロケットですが、もちろん各人各様に受け止めればいいと思います(注2)。たとえば、日本経済の中核(大企業とか大銀行など)と考えてみてはどうでしょうか?地方の零細企業ならば、直接に関係しないものの、その中心部分が失速してしまうと、早速倒産という影響をもろに受けてしまうのです。
となれば、このロケットこそがモウ一方の主役なのではないでしょうか?そして、一時代前の無様な形で今にも墜落しそうに空を飛んでいる姿からすると、日本社会に対する石井監督の見方もそんなところなのかなとも思えてしまいます。

(注1)「Intro」掲載の「インタビュー」によれば、この映画は50万円で制作されたとのこと。
(注2)「映画芸術DIARY」に掲載された「インタビュー」では、石井裕也監督は、「不誠実や悪が現実に存在してるのに、それがわからないように隠蔽されている。そういうことのシンボルって言うか、具現的な表現があのロケットなんです。意味わかんないけど、でも現に飛んでるっていう」と語っています。
ニ)『ばけもの模様』
2007年制作の本作品は、専業主婦の順子が主人公。海で一人息子の清が溺死するという事故に遭ってから、精神に幾分変調をきたし、夫の喜一との関係もギクシャクしています。

ある日、順子は、パチンコ店の駐車場を走る車にもう少しのところで轢かれそうになります。その若い運転手は、石井監督の映画によく出てくる“ダメ人間”というか、大変気の小さな人間。近くのスーパーの入り口で、叔母さんと一緒にメロンパンを車を使って販売しています。
他方で、順子との生活に疲れた夫の喜一は、会社の女子事務員と不倫旅行に出掛けてしまいます。順子の方も、自分を轢きそうになった運転手とばったり会ったのをいいことに、彼を強迫してメロンパン販売用のバンに乗って、当て所もない旅に出ます。
ここらあたりまでは、まあ普通の物語の進み具合といえるでしょう。
ところが、全然別口で出発したにもかかわらず、二人は、息子を亡くした海辺で巡り会ってしまうのです。それで戻って再び一緒の生活を始めるのですが、スッキリしない順子は、衝動的に夫をバットで殴りつけてしまいます。その上、順子はあの運転手を家に連れてきて、瀕死の重傷を負ったはずの夫の介抱に当たらせるのです。
ただ、暫くすると、夫は何事もなかったように起き上がり、最後はメロンパンの販売に携わるようになっています。
順子の方は、再び海の方に出て空を見上げると、重い便秘が治ってしまい、死んだはずの息子が現れて、その後片づけをするところでジ・エンド。
前半は、子どもを事故で亡くした夫婦の重苦しい関係が中心的ですが、順子が夫をバットで殴りつけた辺りから物語は酷くオカシナ様相を呈してきて、結局、順子はズット苦しめられてきた便秘も治り、また死んだ息子との関係も折り合いが付いた感じになるのです。
もしかしたら、『反逆次郎の恋』の主人公のように、バットで重圧をはね除けろ、そうすれば局面が打開されるかもしれない、と映画は言っているのでしょうか?といっても、メロンパンの販売に携わる夫にしても、便秘が治った順子にしても、アカルイミライが待ち構えているとはトテモ思えないのですが。
ところで、この映画のラストの方では、主役の順子(元宝塚劇団華組トップスターの大鳥れいが扮しています)が、海岸で“野糞”をする場面があるところ、上記の『ガール・スパークス』でも、父親の大きな便が浴室にあったと女子高生が騒ぐ場面があります。『川の底からこんにちは』では、木村佐和子(満島ひかり)が糞尿を川岸に撒く姿が何度も描かれています。
石井監督の糞便に対する拘りの表れなのでしょうが、決して糞便を汚いマイナスのものとして扱っていない点が面白いなと思いました。