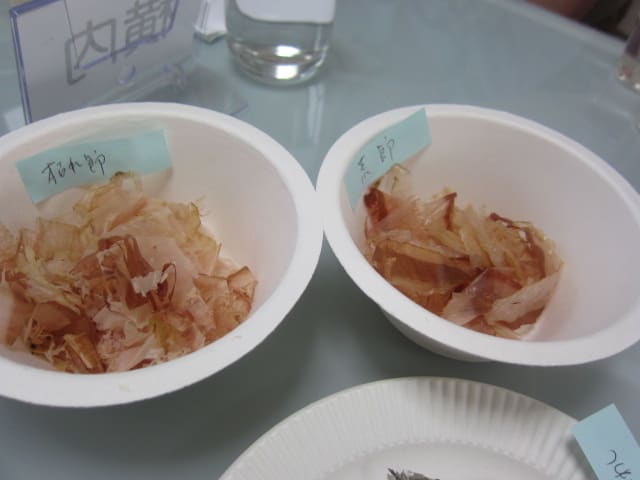袋井市健康づくり食生活推進協議会の
リーダー研修が行われ、
「お盆のいわれと行事食」について勉強しました。
講師は、大角恵子先生。
静岡市では、お盆は割と簡略化して行われるので、
遠州地方で丁寧に行われ、
主婦の皆さんがそのしきたりにお詳しいのには、
驚くばかりです。
実習したお料理は、
霊供膳(りょうくぜん)にお供えするものと迎え団子です。
・ぼたもち
・ゆうごう汁風
・煮豆
・きゅうりとわかめの酢の物
・にんじんとこんにゃくの白和え
・白玉団子(迎え団子)
ゆうごう汁の「ゆうごう」とは夕顔のことです。
かんぴょうを作る夕顔は「実夕顔」。
それに対して、未熟な実を食べる「葉夕顔」があります。
この場合は、「葉夕顔」を使いますが、
手に入らなかったので、冬瓜で代用しました。
お盆の行事は、
606年 推古天皇の時代に始まったと言われています。
冷蔵庫もなかった時代だからこそ、
その時期に採れるものだけを使って
先祖の霊を供養したのでしょう。
その食事が、物が豊富になった現代でも
受け継がれています。
その行事のいわれを学ぶと同時に
旬を大切にしてきた先人たちの知恵を見直す
大切な時間となりました。
ありがとうございました。