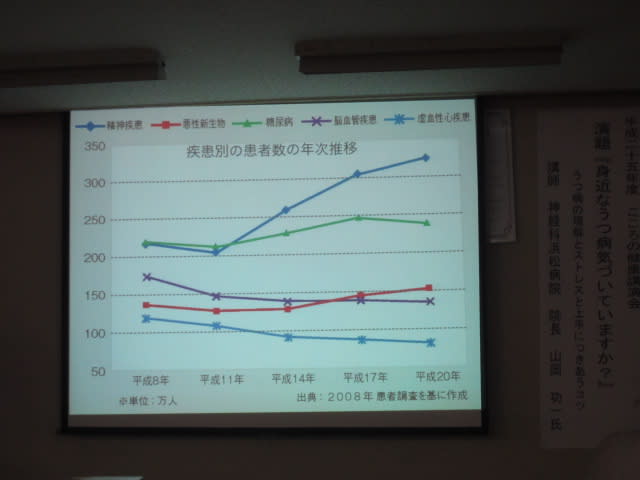浜松で中部原子力懇談会 講演会
「一緒に学びませんか? 食品と放射線のこと」
が開催されました。
講師は、東京都市大学 原子力研究所 准教授の
岡田往子先生。
震災後、食品と放射線に関する講演は、ずいぶん聴いてきました。
しかし、最後に聞いたのは去年の4月。
食品中の放射性セシウムの新基準が適用された直後で、
県内でも、学校給食の放射線量を測定する地域が
増えてきた時期でした。
その後、基準値を超えた農作物についての報道はだんだん減り、
学校給食での取り組みが、どうなったのかも知りません。
この講演会のために、過去の新聞記事を読み返してみると、
忘れてしまっていることの多さに気づかされました。
岡田先生のお話は、とてもわかりやすく
すうっと入ってきました。
というのも、先生は小学生対象に放射線の授業をされており、
その資料をもとに解説してくださったから・・・。
私のような科学オンチでも、ついていくことができました。
内部被爆の量を計算
食物に含まれる自然放射性物質の量をもとに、
私たちが1日に、どのくらい内部被爆をしているのか
1回の食事メニュー(主食、主菜、副菜、飲み物)から
計算をしてみました。
霧箱の中で、放射線を可視化して見せていただきました。
放射線という言葉は、
原発事故後、突然降ってきた「恐怖の大魔王」のように
思っている人が多かったけれど、
放射性物質は地球の誕生以来、存在し続けています。
その事実をしっかり理解して、むやみに恐がらなくなり、
今に至っているというのなら良いのですが、
時間が経って、食品と放射線のことなど
考えなくなってしまったというのなら、
改めてお話を聴いてみるのもいいかもしれません。
今年度、岡田先生の講演は静岡県内で
あと2回開催されます。(内容は、同じです)
●平成26年1月21日(火) 13:00~15:00
会場:クーポール会館静岡
●平成26年3月5日(水) 13:00~15:00
会場:掛川グランドホテル
※お問い合わせは、中部原子力懇談会 静岡支部
TEL 054-253-4140
(9:00~17:00 土日祝日を除く)
岡田先生、そして関係者様
ありがとうございました。