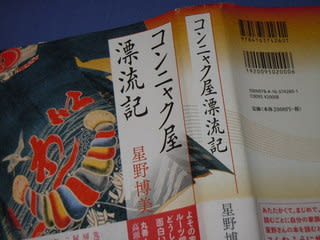塩尻市の下小曽部大日の双体道祖神
■ 鬼は節分の豆まきに欠かせないキャラクタ―ですが、この鬼って、厄神を具体的なものとして可視化したものなんですよね。目に見えないものを可視化することで、みんなで共通なものとして認識することができるわけで、これってすごく意味のあることのように思います。仏の姿を具体的な形で表現した仏像の場合もそうです。
*****
厄神というのは空間の境目、時間の境目から侵入してくると考えられているということで、道祖神は集落の入り口やはずれ、つまり空間の境目に祀られていることが多いですし、豆まきは節分、つまり時間の境目に行われます。道祖神のことを塞(さえ、さい)の神ということも頷けます。塞は塞ぐという意味ですから、空間の隙間を塞ぎ厄神の侵入を防ぐ神様と理解することができるというわけです。
この道祖神は抱肩握手像です。男神と女神がお互い相手の肩に手をかけ、握手をしています。道祖神によくみられるポーズです。裏面に下小曽部村中と彫ってありますが、他の文字は見当たらず、建立年も分かりません。像の摩耗の状態などから古いものだろうと思います。
道祖神にはこのように仲のいい神様が彫られていますが、これは熱々のところには厄神は寄りつこうとはしないと考えられていたからだとか。
**道祖の神々に官能的な姿態をとらせ、生命力の旺盛さを強調し、それによって悪霊などの外敵の侵入を防ごうとした人たちの心根は微笑ましい。**『道祖神』降旗勝次編/鹿島出版会に収録されている加藤氏の「三国街道の道祖神」より引用(182頁)
道祖神巡り まだまだ続けます。