■『紫式部考』柴井博四郎(信濃毎日新聞社2016年)との出合いは『源氏物語』を読んだことに対するご褒美だと思った。
あとがきに次のような一文がある。**私は科学者として、自然が隠した神秘を探り当てることを仕事としてきた。が、紫式部が隠した秘密を探りあてる作業も、実にエキサイティングで楽しいことであった。**(415頁)
そう、柴井さんは自然科学が研究対象に対して採る一般的なアプローチ方法を『源氏物語』にも適用して全体構造(構成より構造ということばの方が的確だ)を把握し、紫式部が世に伝えようとしたメッセージを解き明かしている。『源氏物語』の構造の「相似性」と「繰り返し」、「そっぽ」に注目して、紫式部が巧妙に仕組んだ物語の真意を読み解いている。
柴井さんはあとがきに次のようにも書いている。**紫式部の観察と考察の対象は、彼女がどっぷり浸かっている宮廷貴族社会である。彼女の執筆意図が対象相手に直接分かってしまうのであれば、自分たちの生態をさらけ出される宮廷貴族に受け入れられるはずはない。皮相的にしか理解できなかった宮廷貴族たちの俗っぽさに受け入れられたことで、書きたいことを存分に1000年後まで残してくれたのが「源氏物語」なのである。**(405頁)
皮相的、そう表面的にしか理解できていないのは当時の貴族たちだけではなく、現代人でも同じことではないか。ぼくもその一人。だがしかし、『源氏物語』は通俗的な恋愛小説ではないということが本書の論考で示される。
1000年もこの小説が人々を惹きつけ続けているのはなぜか? 柴井さんは書く、**彼女の紡ぐ物語の中にこそ人間と社会の真実があり、(後略)**(405頁)と。100年経とうが、1000年経とうがその本質は変わらない。
本書の副題は「雲隠の深い意味」。「雲隠」は本文が何もない帖だが、柴井さんは「相似性」と「繰り返し」という『源氏物語』の構造からその内容を解き明かしている。ここにはその内容を具体的に書くことは控え、**源氏と浮舟は表裏一体の主人公といえよう。**(195頁)という引用に留めたい。説得力のある論考ということも付記しておく。
*****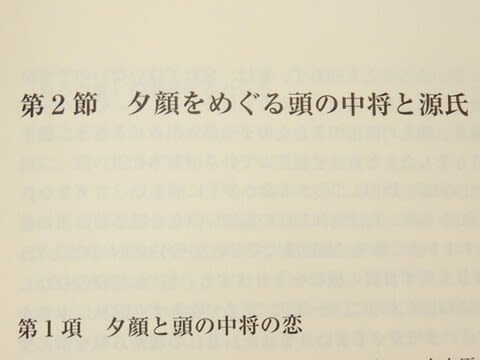 320
320
第1章 まえがき
第2章 紫式部の執筆動機
第3章 発端としての<桐壺>
第4章 空蝉と藤壷の相似性
第5章 雲隠
第6章 浮舟の死と再生
第7章 桐壷帝と朱雀帝の相似性
第8章 協奏曲「源氏物語」のフィナーレ
本書はこのように章立てされ、各章とも原則として「節」「項」まで構成されていて、論旨が分かりやすい。
本を読んで感動し、興奮するという経験はずいぶん久しぶりのことだった。









