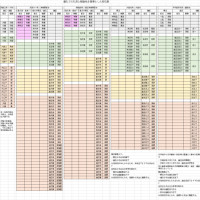『遊仙窟』原文並びに訓読 <訓読篇 前篇>
PDFのリンク先;
https://drive.google.com/file/d/1nwgzhiKEyWTctYjXbfxRHv62Pr7njL1I/view?usp=sharing
はじめに
ブログの文字数制限のために、<原文篇>と<訓読篇 前篇>・<訓読篇 後篇>の三篇で掲載しています。必要に応じて、それぞれを参照下さい。
注意事項:-
紹介する『遊仙窟』<原文篇>は、漢文入力の労を省くためインターネット上に公表されている『遊仙窟(維基文庫、自由的図書館;中華人民共和国)』を使い、日本漢字体への変換と中国現代文解釈されたものを本来のものへとすべく次の資料を用いて個人の作業の下に校訂を行っています。なお、相互に異同が認められる場合は醍醐寺本影寫を個人の判断で判定した表記を用いています。また、一部の文字にはフォントの都合で当て字を用いているものがあり、下線にてそれを示しています。
『遊仙窟(張文成作、漆山又四郎訳註;岩波書店)1996年第2刷』
『遊仙窟(張文成作、今村与志雄訳;岩波書店)1990年第1刷』収醍醐寺蔵古鈔本影印
『遊仙窟』漢籍電子文献資料庫、中央研究院歴史語言研究所;中華民国
ただし、正規の教育を受けていない個人の作業であるために掲げる原文は校本となるような学問ではありません。従いまして、ここでのものを使用されます場合は皆様の趣味の範囲での参照にのみ薦めますし、その場合でも適切な原文との対照をお願い致します。
また、『遊仙窟』<訓読篇>に示す訓読文もまた正規の教育を受けていない個人の作業です。従いまして、原文読解における趣味の範囲内での笑文以外のものにはならないものと理解して下さい。そのため、それ以外での訓読み引用には推薦しません。あくまでも本格的な引用への予備資料として下さい。
追記参考として、歴史に于いて『遊仙窟』は中国では早い時期に失せた書物で、日本にのみ現在までに伝えられた唐初時代に成立した中国伝奇小説です。その日本においても奈良時代初期に伝えられたとされる『遊仙窟』は、室町時代の南北朝時代の鈔本と思われる醍醐の三寶院の鈔本(醍醐寺本)、室町時代の鈔本と思われる成簣堂蔵本、江戸時代の慶安以前に刊行された刊本(慶安以前刊本)と元禄時代に刊行された繪入りの半紙本の四系統があるのみとされ、奈良時代から平安時代のものは現存していません。ここでの校訂の作業で資料として使用した『遊仙窟(漆山又四郎訳註)』は江戸時代の刊本(慶安以前刊本)を基として最古の伝本である醍醐寺本の影寫本を参照して譯註に使用したと記述していますが、調べでは完全には校訂されたものではありません。そのため、紹介しましたように、ここでは異同校訂には醍醐寺本を優先しています。なお、醍醐寺本の影寫本は『遊仙窟(今村与志雄訳)』中で容易に知ることが出来ます。
<訓読>
遊仙窟
寧州襄楽縣尉張文成の作
若(けだ)し夫れ積石山は、金城の西南に在りて、河の經る所なり。書に云ふに「河の積石より導き、龍門に至る」と。 即ち此の山是なり。
僕、汧隴に従ひて、河源に使ひを奉(たま)はる。運命の邅たるを嗟(なげ)き、鄉関の渺邈たるを歎く。張騫の古跡は十萬里の波濤にして、伯禹の遺跡は二千年の阪磴なり。深谷は地を帶(た)らし、崖岸の形を鑿穿(さいうつ)し、高き嶺は天に(よこた)はり、崗巒の勢ひは刀削たり。煙霞子細(こまやか)にして、泉石分明(あきらか)なり、實に天上の霊奇にして、乃ち人間(じんかん)の妙(みょう)絶(たへ)たり。目にも見ざる所、耳にも聞かざる所なり。日は晩れ途(みち)遙かにして、馬疲れ人乏(たゆ)みぬ。行きて一(ある)所(ところ)に至る。險峻たるは常(つね)に非(あら)ずして、上を向けば則ち青壁は萬尋に有りて、直下には則ち碧潭は千仞に有る。
古老の相ひ傳へて云ふに「此れは是れ神仙の窟(いはや)なり。人跡の及ぶこと罕(まれ)にして、鳥の路纔(わず)かに通ふ。毎(つね)に香しき菓(くだもの)や瓊(たま)の枝が有り、天衣錫鉢、自然(おのづ)と浮かび出で、何(いづ)れより至れるかを知らず」と云へり。
余、乃(すなわ)ち端(つつし)み仰ぎて心を一にして、潔齋すること三日。細き葛に縁(よ)り、輕舟にて溯(さかのぼ)る。身體(からだ)は飛ぶが若(ごと)く、精霊(こころ)は夢みるに似る。須臾(しまし)の間、忽ち松柏の巌・桃華の澗(たに)に至る。香風は地を觸(めぐ)り、光彩は天(そら)に遍(あまね)く。
一(ある)女子(おなご)の水の側(かたはら)に向かひて衣を浣(あら)ふを見、余、乃(すなわ)ち問ふて曰く「承(うけたま)はり聞く、此の處に神仙の窟宅(いほり)有りと。故に来りて伺候(うかが)へり。山川阻隔たりて、疲れ頓(う)むこと常に異(こと)なり、娘子に投(や)りて、片時(かたとき)に停まり歇(やす)まんことを欲(ねが)ふ。交情を惠み賜はり、幸ひに聽き許すを垂れよ」と云へり。
女子の答へて曰はく「兒(われ)の家、堂舍は賤陋(せんおく)にして、供給(もてなし)は単疏(おろそか)なり、また、堪(た)へざらんを恐(おそ)る。吝惜(おしむ)に無(な)かざらむ」と云へり。
余の答へて曰はく「下官、是れ客なれば、事に觸(よ)りて卑微(いやし)きものにして、ただ風塵を避けなば、則ち幸甚と為さむ」と云へり。
遂に余を門の側(かたは)らの草亭(そうてい)の中に止め、良久(やくやく)にして乃ち出でり。
余の問ふて曰はく「此れは誰か家舍ならむか」と。
女子の答へて曰はく「此れは是れ崔女郎の舍なり」と。
余の問ふて曰はく「崔女郎とは何人(なにひと)なりや」と。
女子の答へて曰はく「博陵王の苗裔にして、清河公の舊族なり。容貌は舅に似、潘安仁の外甥なり。気調は兄の如く、崔季珪の小妹なり。華容は婀娜(たおや)か、天上に儔(たぐ)ひ無く、玉體は逶迤(なおや)かにして、人の間に疋(なら)び少なし。輝輝(かがや)ける面子(かんばせ)は荏苒(じんぜん)として穿(うが)かば弾(はじ)かむを畏れしめ、細細(こまや)かなる腰支は参差(しんし)として勒(いだ)かば断えなむと疑はる。韓娥や宋玉も見(なが)めれば則ち愁ひを生じ、絳樹や青琴も之に對(たい)すれば羞じて死なむ。千嬌百媚、造次にも比方すべきは無し。弱躰輕身、之を談ずるも備(つまび)らかに盡すは能はず」と云へり。
須臾(しまし)の間、忽ちに内裏に箏を調へる聲を聞く。
僕、因りて詠ひて曰はく「自(おのず)から姿則の多(すぐれ)れたるを隱し、他を欺きて獨り自(みずか)ら眠(ひそ)む。故故に纖(かよわ)き手を將(も)ちて、時時に小弦を弄(もてあそ)ぶ。耳に聞くに猶さら気を絶ち、眼に見るに若(いかば)りか憐れみを為さむ。従(よし)や、渠(きみ)、痛(はなは)だ肯(う)べなく、人をして更に就天を別(いと)はむや」と云へり。
片時にして、婢の桂心を遣はして、傳へ語たるに余の詩に報(こた)へて曰はく「面(かんばせ)は他舍の面に非ず、心は是れ自(おのず)から家の心、何處(なんぞ)、天事に関(かか)はりて、辛苦を漫(みだ)りに追尋せむ」と。
余、詩を讀み訖(お)りて、頭を門中に舉げ、忽ちに十娘の半面(よこがお)を見たり。
余、則ち詠ひて曰はく「斂(ほほ)は笑(え)みて残の靨を偷(かく)し、羞(はじら)ひを含みて半ば唇(くちびる)を露はし、一眉は猶ほ耐へ難たく、雙眼は定めて人を傷(いた)めむ」と。
又、婢の桂心を遣はして、余の詩に報へて曰はく「好みは是れ他家の好み、人は人の意を著くるに非ず、何を須(す)てか漫りに相ひ弄びて、幾許(いくばく)か精神(おもひ)を費せる」と。
その時、夜は久しく更に深け、沈吟して睡(ねむ)らず、彷徨徙倚するに便(すべ)無く、披陳するに彼の誠は既に来意有り、此の間何ぞ能く答へざらんむと。
遂に懷抱(おもひ)を申(の)べ、因りて以ちて書を贈りて曰はく「余、以(おもむみ)れば少(おさな)くして聲色を娯(たのし)み、早く佳き期(ちぎり)を慕ひ、歴(ことごと)く風流を訪ねて、遍く天下に遊ぶ。蜀郡に鶴琴を弾きて、飽くまで文君と見(まみ)へ、秦樓に鳳管を吹きて、熟(みつ)るまで弄玉と看(まみ)へむ。雖、複た蘭を贈りて珮(おび)を解くとも、未だ甚(はなは)だ懷ひに関はらずして、合巹陳、何曾(なにそ)意に愜(かな)はむ。昔日の雙(ふたり)して眠(ねむ)しは、恆(ひさし)く夜の短きを嫌ひ、今宵の獨(ひとり)して臥するは、實に更(よる)の長きを怨む。一種(あるしゅ)の天公、両般の時節なり。遙かに香気を聞き、獨り韓壽の心を傷み、近きに琴聲を聽き、文君の面(かんばせ)に對(むか)ふるに似たり。向来(さきより)、桂心の談り説くを見るに、十娘は天上に雙(ふたつ)は無く、人の間に一つ有るのみ。依依たる弱(わおや)き柳、束ねて腰支を作(な)し、焰焰として(よこた)はれる波、翻りて眼尾(めじり)を成せり。纔(わずか)かに両頰を舒(の)ぶれば、熟(つらつ)ら地上に華無きを疑ひ、乍(さら)に雙眉を出ださば、漸(やくや)く天邊に月を失うと覚える。能く西施をして面(かんばせ)を掩(おほ)ひせしめて百遍の粧(よそおひ)を焼(ほろぼ)し、南國をして心を傷(いた)せしめて千廻(ちた)び鏡を撲(なげ)む。洛川の廻雪も、只だ堪だ衣裳を疊(たた)ませしめ、巫峽の仙雲も、未だ敢へて鞾履を撃(ささげ)るを為さしめむ。忿(いか)りて秋胡の眼拙して、枉(ま)げて黄金を費し、念ひて交甫の心狂して、虚しく白玉に當(あ)へる。下官、偶(たまたま)勝境に遊び、閑亭に旅泊して、忽ちに神仙に遇(あ)ひ、迷亂に勝(あ)へず。芙蓉は澗底に生じて、蓮子は實に深く、木栖は山頭に出でて、相思は日に遠し。未だ曾つて炭を飲まざれど、腹(はらわた)の熱きこと焼くが如く、刃を吞むこと憶へざらむを、腸(はらわた)を穿(うが)ちたること割くに似たり。無情の明月、故故に窗に臨み、多事たる春風、時時に帳(とばり)を動かす。愁人此に對(むか)ひて何を將(もち)てか自(みずか)ら堪へむ。空しく断えなんとする腸を懸げて、終ひに臨まむとする命を救はむを請ふ。元来(もとより)、見(あ)はざれば他も自も尋常(つね)にして事無きしを、相ひ逢うて卻(かへ)つて交(たが)ひに煩ひ悩む。敢へて心素(おもひ)を陳べ、幸ひに照(あきら)かに知るを願ふ。若し其の光儀(すがた)を見ることを得るは、豈、敢へて其の萬が一を論ぜむや」と云へり。
書の達するの後、十娘色を斂(ひそ)め、桂心に謂ひて曰はく「向来(さきより)、劇(はなはだ)しく戲れ相ひ弄(もてあそぶ)こと、真に人に逼(せま)らむと欲せりを成さむ」と。
余、更にまた詩一首を贈り、其の詞に曰はく「今朝忽ちに渠(きみ)の姿首に見(まみ)へ、覚へずして慇懃に心は口に著く。人をして頻りに作許の叮嚀あらしめ、渠の家は太劇を求守するは難し。端坐して心驚は剩(ただなら)ずして、愁へ来りて益(さら)らに平(たい)らかならず。看(まみ)へる時に未だ必ずしも死を相ひ看(み)むとはおもわず、難き時は那許(いかばかり)か太(はなはだ)だ生き難し。沈吟して幽室に處(こも)り、相ひ思ふて轉(かへ)つて疾(やまひ)を成す。自ら往還の疎を恨み、誰か交遊の密を肯(う)べみて、夜夜空しく心の眼を失ふを知り、朝朝膠漆に投ずる便(すべ)無きを。園裹に華は開きて人を避けず、閨中に面子(かんばせ)の出でむことを羞(はじら)ふを翻かえす。如今(ただいま)、寸歩は天津を阻て、伊(いず)れの處にか情(おもひ)を留めて更に新しきを覚(さと)らむ。言ふこと莫かれ長(ひさ)しく千金の面に有りて、終ひに歸へり變じて一抄の灰塵と作(な)らむ。生前に但だ樂みを為すべき日は有りて、死後に更(なおさら)に人の看るべき春は無からむ。祗に一生の意を倡佯すべく、何を須てか百年の身を負持べけむや」と云へり。
少時坐睡し、則(たちま)ちに十娘に見(まみ)へむ夢を見む。驚き覚めて之を攬るに、忽然として手は空(むな)し。心中悵怏たるに、複た何をか論ずべき。
余、因りて乃ち詠ひて曰はく「夢中に是れ實(まこと)かと疑ひ、覚めし後に忽ちに真に非ず。誠に腸(はらわた)の断てむと欲せりを知り、窮鬼は故に人を調ふ」と。
十娘の詩を見、また讀み肯(う)べむとして、即ち焼き卻てむを欲す。
僕、即ち詠ひて曰はく「未だ必ずしも詩に由りて得むにはあらず、將に詩に故りて憐みを表はむ。渠(きみ)が火に擲げ入らるるを聞き、定めて是れ相ひ燃さむと欲すならむ」と。
十娘の詩を讀み、悚息として起(た)つ。匣中より鏡を取り、箱の裏に衣を拈く。袨服靚粧し、階(きざし)に當りて履を正しくす。
僕、また詩を為して曰はく「香四面に合ふて、光色は両邊に披く。錦障は劃然と卷きて、羅帷は半ばに垂れて欹(かたむ)けり。紅顏は緑黛と雜はり、處として相ひ宜(よ)からざるは無し。艶色に粧粉を浮かべ、含香は口脂を亂せり。鬢は蟬鬢の鬢を成せるに非ざるを欺き、眉は蛾眉の是れ眉ならざるを笑ふ。見るに實に娉婷を許し、何れの處にか輕盈たらざらむ。憐むべし嬌裏の面(かんばせ)、愛すべし語中の聲。婀娜たる腰支は細細たるを許し、兼占(れんせん)たる眼子(まなじり)は長長に馨(かおる)。巧に兒の舊来(もとより)鐫(え)るとも未だ得らざり、畫匠は迎へ生すの成らざるを摸(な)ぞる。相ひ著(し)るに未だ相ひ識(し)らず、傾城は複た傾國なり。風を迎えては帔子に鬱金の香り、日に照らして裙裾に石榴の色あり。口上の珊瑚は拾ひ取るに耐え、頰裏の芙蓉は摘み得るに堪える。名を聞くに腹肚(はらのうち)に已(おのず)に猖狂し、面を見るに精神(こころ)は更に迷ひ惑ふ。心肝恰(あたか)も摧けむと欲し、踴躍して裁つは能はず。徐かに行くに歩歩に香風を散らし、語らむと欲して時時に媚子を開く。靨(えくぼ)は織女の星を留めて去くかと疑ひ、眉は恒娥(じょうが)の月を送り来たるに似る。嬌を含みて窈窕して前(すす)み出でて迎へ、笑(え)みを忍びて嫈冥(えいめい)の卻(しりぞ)きて廻して返す」と云へり。
余、遂に之を止めて曰はく「既に好意有らば、何ぞ須らく卻きて入れむ」と。
然る後、十娘逶迤(きい)として面を廻らし、亜余(あた)として向ひ前(すす)む。手を斂め再拜して下官に向かひ、下官も亦た低頭し禮を盡して言ふて曰はく「向見して稱揚せられて謂へらく言ふこと虚假なりと、誰か知らむ面に對(むか)ひて、恰も是れ神仙なるを。此れは是れ神仙の窟なり」と。
十娘の曰はく「向見して詩篇、謂へらく言ふこと凡俗なりと、今、玉貌に逢ひて、更に文章に勝れり。此れは是れ文章の窟なり」と。
僕、因りて問ふて曰はく「主人の姓望は何れの處ぞ、夫主は何くに在らむ」と。
十娘の答へて曰はく「兒(わらは)は是れ清河の崔公の末孫にして、弘農の楊府君が長子に適(かな)ふ。孰(つい)に大禮を成し、父に隨ひて河西に住む。蜀生狡猾にして、屢邊境を侵す。兄及び夫主は筆を弃て戎に従ひ、身は寇場に死して気魂は返すこと莫し。兒は年十七にして、死すとも一夫を守り、嫂は年十九にて、再醮(さいしょう)せざるを誓う。兄は即ち清河の崔公の第五の息にして、嫂は即ち太原公の第三の女なり。別(こと)に此に宅(す)み、積りて歳年有り。室宇は荒涼にして、家途は翦弊たり。知らず上客は何くより至れる」と云へり。
僕、容を斂(あらた)めて答へて曰はく「下官は南陽に望屬せられて、西鄂に住居す。黄石の霊術を得て、白水の餘波を控く。漢に在りては則ち七葉の貂蟬、韓に居みては則ち五重の卿相たり。鍾を鳴らして鼎食し、代を積みては衣纓せり。戟の長にして高門を高くし、禮樂に因り循ふ。下官、堂構は紹かず、家業淪滑たり。青州の刺史博望侯が孫、廣武將軍鉅鹿侯の子なり。俗を免るること能はずして、跡を下寮に沈める。隱るるに非ず遁れるに非ずて、逍遙して鵬鴳の間、吏に非ず俗に非ずて、是非の境に出入す。暫く駆使せらるるに因りて、此の間に至れり。卒爾に幹煩たり、實に傾仰を為す」と。
十娘の問ふて曰はく「上客は何の官に任(ま)けられや」。
下官の答へて曰はく「幸ひに太平に屬(よ)り、貧賤に居ることを恥ず。前に賓貢を被り、已は甲科に入り、後に搜揚に屬(つ)き、また高第を蒙れり。敕を奉じて関内道の小縣の尉を授け、河源道の行軍総管の記室に宛てられむ。頻りに上命を繁して、徒らに報恩を想ふ。下寮に馳驟して、寧處に遑(いとま)あらず」と。
十娘の曰はく「少府、行使あるに因らずんば、豈、相ひ過らむは肯(う)べならむや」と。
下官の答へて曰はく「頃(このころ)、相ひ知らずして、参展(つかまつ)り為すを闕(か)く。今日より後、敢へて差し違(たが)はざらむ」と。
十娘の遂に頭(こうべ)を廻らし、桂心を喚びて曰はく「中堂を料理し、將に少府を安らかに置かむ」と。
下官、逡巡して謝して曰はく「遠客は卑微にして、此の間は幸甚なり。才は賈誼に非ざれば、豈、敢へて堂に昇らむや」と。
十娘の答へて曰はく「向(さき)に承はり聞くは、謂ふに言へるは凡客、拙く禮貺を為すは、深く面を覚みて兒の意を慚じ、事に相ひ當りて須く引接せむ。此の間は疏陋にして、未だ風塵を免れず。室に入るは推辭(いなむ)に合はずして、堂に昇るに何ぞ須く進退(あとずさり)せむ」と。
遂に中堂に引き入れたり。時に金台銀闕、日を蔽ひ雲を干(おか)す。或は銅雀の新たに開けたるに似、乍ちに霊光の且(あした)に敞(ほがらか)かなるが如し。梅の梁桂の棟、澗(たに)の長虹を飲むかと疑ひ、反(そ)れる宇(のき)雕れる甍(いらか)、天の嬌鳳を排するが若し。水精の浮柱、的皪として星を含み、雲母の飾窗、玲瓏として日を映す。長き廊(わたどの)は四に注(そそ)ぎ、争ふて玳冐(たいまい)の椽(たるき)を施し、高閣は三重にして、悉く瑠璃の瓦を用ふ。白銀を壁と為し、魚鱗のごとく照り曜やき、碧玉は陛(きざはし)を縁り、鴈歯を参差たらしむ。穹崇たる室宇に入らば、歩歩に心は驚き、黨閬(とうろう)たる門庭を見れば、看看として眼は参(かがや)けり。遂に少府を引きて階を昇る。
下官の答へて曰はく「客主の間、豈、先後無からむや」と。
十娘の曰はく「男女の禮、自から尊卑有り」と。
下官、遷延とし退きて曰はく「向来(さきより)、罪過有りて、忘れて五嫂に通ぜざりき」と。
十娘の曰はく「五嫂、亦た、自から来るべし、少府、遣通(いま)せ、亦た、是れ周り匝(めぐ)らむ」と。
則ち桂心を遣はして通はせ、暫く五嫂の参屈す。十娘、少府と語話(かたらひ)するに、須臾の間、五嫂の則ち至る。羅綺繽紛として、丹青暐曄たり。金釵銅鐶、裙の前には麝を散じ、髻(もとどり)の後には龍が盤(わだか)まる。珠繩は翠衫に絡ひ、金薄を丹履に塗りぬ。
余乃ち詠ひて曰はく「奇異きまでの妍雅、貌は特に驚くまでに新たなり。眉間に月は出でて夜を争うを疑ひ、頰上に華は開きて春を闘ふに似る。細腰は偏(ひとへ)に愛ずべき轉り、笑臉は特に顰むに宜し。真に物外の奇しき稀なる物に成るは、實に是れ人の間の断絶の人なり。自然から能く舉を止み、念ふべし比方すべき無しを。能く公子をして百廻生しめ、巧みに王孫をして千遍死なしむ。雲は両鬢を裁ち、白雪は雙歯を分つ。綿袖には織り成す騏の兒、裙腰には刺繡せりし鸚鵡の子。處に觸れて盡く懷ひの関(ことのおこ)りて、何ぞ曾て佳からざらことか有らむ、機関太だ雅妙にして、行歩絶へて娃屏(みやびか)なり。傍人は一一の丹羅の襪(くつたび)、侍婢だも三三の緑線の鞋。黄龍を透(ちりば)めて黄金の釧(うでわ)に入れ、白燕は白玉の釵に飛来せり」と。
相ひ見みること既に畢はりて、五嫂の曰はく「少府、山川を跋渉し、深く道路に疲れるも、行途此に屆まれり、神を傷むるに及ばず」と。
下官の答へて曰はく「王事に黽勉(びんべん)し、豈、敢へて勞りを辭せんや」と。
五嫂の頭を廻らし、笑みて十娘に向きて曰はく「今朝、鳥鵲の語ひを聞き、真に好き客の来たるは成る」と。
下官の曰はく「昨夜、眼皮(まぶた)は閏(またた)き、今朝、好き人を見(まみ)えむ」と。
即ち相ひ隨ひて堂に上る。珠玉は心を驚かし、金銀は眼を曜かす。五彩龍鬢の席、錦繡縁邊の氈、八尺の象牙の牀、緋綾帖薦の褥。車渠・馬瑙・真珠等の寶、俱に優曇の花に映じ、並びに頗梨の線(いとすじ)に貫けり。文柏の榻子、俱に豹頭を寫し、蘭草の燈芯、並びて魚腦を焼けり。管弦は寥亮にして、北戸の間に分張し、杯盞の交(こもごも)は横はりて、南窗の下に列なり坐れり。各自(おのおの)相ひ讓りて、俱に先じて坐することを肯へてせず。
僕の曰はく「十娘は主人なり、下官は是れ客。請ふ主人、先ず坐することを」。
五嫂、人と為りて饒(おほ)いに劇(たわむ)れ、口を掩ひて笑(え)みて曰はく「娘子は既に是れ主人の母、少府は須らく主人公と作るべし」と。
下官の曰はく「僕、是れ何人なれば、敢へて此の事に當らむや」。
十娘の曰はく「五嫂、向(さき)に来りて戲れ語る、少府、何ぞ須らくも漫(みだ)りに怕れるや」。
下官の答へて曰はく「必ず其れ免れずんば、只、身を須(まか)せて當らむ」。
五嫂の笑みて曰はく「只、恐るる張郎、此の事を禁(いな)むること能はざるを」。
眾人皆大ひに笑む。一時に俱に坐せり。即ち香兒を喚びて酒を取らせむ。俄爾(しばらく)の中間(あひだ)に、三升可かりを受くる一大鉢を撃(ささ)げて已に来れり。金釵銅鐶、金盞銀杯、江螺海蚌、竹根細眼、樹癭蠍唇、九曲の酒池、十盛の飲器。觴は則ち兕觥犀角ありて、尫尫然として座中に置き、杓は則ち鵝項と鴨頭ありて、汛汛焉として酒上に浮べり。小婢細辛を遣はして酒を酌ましめ、並びに先じて提げるは肯(う)べざらむ。
五嫂の曰はく「張郎は門下の賤客なり、必ず先じて提ることは肯(う)べざらむ。娘子徑(ただ)ちに須らく把り取るべし」と。
十娘の則ち斜眼みて佯り嗔りて曰はく「少府は初めて此間に到れり、五嫂の會(あしら)ひ些(いか)ん。頻頻(しばしば)相ひ弄ぶ」。
五嫂の曰はく「娘子は酒を把りて嗔ること莫れ、新婦は更に亦た敢へてせず」と。
酒巡りて下官に到るも、飲みて乃ち盡さず。
五嫂の曰はく「何為ぞ盡くさざる」と。
下官の答へて曰はく「性れつき飲むこと多からず、恐らくは顚沛を為さむ」と。
五嫂の罵りて曰はく「何に由りては耐へ難からむ。女婿は是れ婦家の狗なり、打殺するも尤(あやまち)ち無からむ。終(つひ)に須らく傾け盡くし、漫りに眾諸に造ること莫らしむ」と。
十娘の五嫂に謂ふて曰はく「向来(さきより)、正首(まさ)に病の發(おこ)れるや」と。
五嫂の起ちて謝して曰はく「新婦の錯(あやまち)、大ひに罪過あり」と。
因つて頭を廻らし下官を熟視して曰はく「新婦、細(つらつ)ら人を見ること多く、少府公に如(し)く者は無し。少府公乃ち是れ仙才なり、本より凡俗に非ず」と。
下官の起ちて謝して曰はく「昔の卓王の女、琴を聞いて相如の器量を識り、山濤の妻、壁を鑿ちて阮籍の賢人を知る。誠に言ふ所の如きは、敢へてを望(のぞ)まず」と。
十娘の曰はく「緑竹を遣はして琵琶を取り弾かさしめ、兒(わらは)は少府公と酒を送らむ」と。
琵琶を手に入れるも未だ弾ざる中間(あいだ)に、僕、乃ち詠ひて曰はく「心は虚にして測るべからず、眼は細にして強ちに情に関はる。身を廻らして已の抱(ふところ)に入れ、見へざるも嬌聲は有り」と。
十娘の聲に應へて即ち詠ひて曰はく「憐むらく腸を忽ち断たむと欲するを、眼の已の先に開くを憶ふ。渠(きみ)、未だ相ひ撩撥せずて、嬌は何處よりか来たらむか」と。
下官、當に此の詩を見、心膽は俱に碎けむ。床に下りて起ちて謝して曰はく「向来(さきより)、唯、十娘の面を覩、如今(ただいま)乃ち始めて十娘の心を見む、班婕をして輪を扶け、曹大家をして筆を閣かしむに足り、豈、年を同じうして語り、代を共にして論ずべけむや。請ふらくは筆と硯を索(もと)め、抄寫して懷袖に置かむ」と。
詩を抄(うつ)し訖りて、十娘の弄びて曰はく「少府公、但だ詞句の断絶するに非ずして、亦た自から書を能す。筆は青鷥に似、人は白鶴に同じ」と。
下官の曰はく「十娘、直(すなお)な才は情(なさけ)に非ずて、實に能く吟詠す。誰か玉貌を知り、恰も金聲は有らむ」と。
十娘の曰はく「兒は近来(ここのところ)、嗽(せき)を患へて、聲音は徹(とお)らず」と。
下官の答へて曰はく「僕、近来、手を患へて、筆墨は未だ調はず」と。
五嫂の笑みて曰はく「娘子は是(よ)からず故に誇り、張郎の複た能く應答せり」と。
十娘の五嫂に語りて曰はく「向来(さきより)、純(もつはら)當(まさ)に漫語、元来、次第の無し、請ふ五嫂の酒章を作り為すべし」と。
五嫂の答へて曰はく「命を奉ずることは敢へてせず、則ち娘子に従りて賦するに是らず、古詩に云はく『章を断ち意を取り、唯だ須らく情を得るべし、若し愜當(あきたら)ずんば、罪として科罰は有らむ』」と。
十娘の即ち命を遵びて曰はく「関関たる雎鳩、河の洲に在り。窈窕たる淑女、君子の好き仇なり」。
次に、下官の曰はく「南に樛木有り、休息すべからず。漢に遊女有り、求むべからず」と。
五嫂の曰はく「薪を折ること之れ、何の如く、斧に匪(あら)ざれば剋(あた)はず。妻を娶りて之れ、何の如く、媒に匪ざれば得ず」と。
又た次に、五嫂の曰はく「複た関(ことのおこり)を見ずは、泣涕は漣漣たり。既に複た関(ことのおこり)を見れば、載(すなわ)ち笑(え)み載ち言(かたら)ふ」と。
次に、十娘の曰はく「女は爽(たが)はず、士は其の行ひを二つにす。士は極まり罔き、其のを二つ三つにす」と。
次に、下官の曰はく「穀(い)けるには則ち室を異にするも、死なば則ち穴を同じくせむ。余を信あらずと謂ふも、日(あかきひ)の如く有り」と。
五嫂の笑みて曰はく「張郎、心は專(いちず)なり、詩を賦すること太だ道理有り。俗の諺に曰はく『心を專ならむと欲せば、石を鑿るとも穿ちなむ。誠に能く之を思はば、何の遠きこと之れ有らむ』」と。
其の時、緑竹の箏を弾く。
五嫂の箏を詠ひて曰はく「天は素(しろ)き面(かんばせ)を生じて能く客を留め、意を發つし情に関はること併に渠(きみ)は在り。怪むこと莫れ、向(さき)には頻りに聲は戰(ふる)へ、良く伴を得るに由り乍に心の虚なるを」と。
十娘の曰はく「五嫂は箏を詠ひ、兒は尺八を詠ふ。『眼多くして本より自ら渠を愛せしめ、口少くして由来は毎に侵を被むり、事無くして風聲は他の耳に徹り、教人をして気満たらしめば自ら心に填なむ』」と。
下官の又た謝して曰はく「善を盡し美を盡し、處として佳からざる無し。此は是れ下愚にして、預め高唱を聞くなり」と。
少時にして、桂心、將に酒物(さけさかな)を下げて来り、東海の鯔條、西山の鳳脯、鹿尾に鹿舌、乾魚と炙魚、鴈醢荇菹、鶉韯桂糝、熊掌に兎髀、雉臎と豺唇、百味五辛、之を談るも盡くすこと能はずて、之を説くとも窮むるは能はず。
十娘の曰はく「少府、亦た、太だ飢えたるなるべし」と。
桂心を喚びて飯を盛らしむ。
下官の曰はく「向来、眼は飽きたりて、身は飢えを覚えざり」と。
十娘の笑みて曰はく「相ひ弄ること莫れ、且た雙六局を取りて来たれ、共に少府公と酒を賭けむ」と。
僕の答へて曰はく「下官は酒を賭けること能はず、娘子と宿を賭けむ」と。
十娘の問ふて曰はく「若為(いかにして)てか宿を賭けむ」と。
余の答へて曰はく「十娘、籌(かず)を輸(ま)けなば、則ち下官と一宿を臥せ、下官、籌を輸けなば、則ち共十娘と一宿を臥せむ」と。
十娘の笑みて曰はく「漢の驢に騎らば則ち胡は歩より行き、胡の歩より行かば則ち漢は驢に騎らむ、総べて悉く他に輸(いた)さなば便ち點頭(うなづ)かむ。兒、遞ひに換り作すなり、少府公、太だ能く生れり」と。
五嫂の曰はく「新婦、娘子に報ず、須らく賭け来り賭け去るべからず、今夜定めて知る娘子の免れざらむを」。
十娘の曰はく「五嫂、時時、漫語なり、浪りに少府の消息を作らむ」と。
下官の起ちて謝して曰はく「元来(もとより)、劇(たわむ)れごとなるを知れり、未だ敢へて承望せず」と。
局(すごろく)の至るや、十娘、手を引きて前に向かひ、眼子は盱婁(くろう)にして、手子は膃腯たり。一雙の臂腕は我が肝腸を切り、十個の指頭は人の心髓を刺す。
下官の因りて局を詠じて曰はく「眼は星の初めて轉るに似、眉は月の消えむと欲するが如く、先づ須らく後脚を捺で、然して始めて前腰を勒(おさ)むべし」と。
十娘の則ち詠ひて曰はく「腰を勒めなば須らく巧く快かるべし、脚を捺でなば更に風流、但だ細き眼を合わせしめば、人も自も籌(かず)を輸(ま)けること分たむ」と。
須臾の間、一婢有り、名は琴心、亦た姿首(よきかほ)有り、下官の處に到るを、時に複た偷(ぬす)み眼を看む、十娘、欲(おもひ)は快(よ)からざるが如し。
五嫂の大語(おほごえ)に嗔(いか)りて曰はく「足ることを知れば辱められじ、人の生に限り有り。娘子眉を皺(ひそ)めむと欲するが似(ごと)し、張郎、須らく斜眼(ながしめ)をせざれ」と。
十娘の佯(いつわ)りて色を捉(とりおさ)め嗔りて曰はく「少府、兒に何事か関(ことをおこ)さむ、五嫂、頻頻(しばしば)相ひ悩ます」と。
五嫂の曰はく「娘子は少来頗(しき)りに少府を盼(かへり)み、若し情に想ふに非ずんば、交り通ふ所は有らむや、何に因りてか眼眽(むすみめ)し、朝来(けさより)頓に引かれんや」と。
十娘の曰はく「五嫂、自ら心の偏れるを隱せり、兒、複た何ぞ曾て眼を引かれんや」と。
五嫂の曰はく「娘子能からずんば、新婦、自ら取らむ」と。
十娘の答へて曰はく「自ら少府に問へ、兒、亦た知らず」と。
五嫂の遂に詠ひて曰はく「新華は両樹に發(ひら)き、香を分かちて一林に遍(あまね)し。風を迎へて細影を轉し、日に向ひて輕陰を動す。戲蜂は時に隱見し、飛蝶は遠く追尋す。聞くならく採摘せむと欲すと、若箇(いかばか)りか君の心を動かせる」と。
下官の曰はく「性と為り多く貪り、両華、俱に采らむと欲す」と。
五嫂の答へて曰はく「暫く雙樹の下に遊び、遙かに両枝の芳きを見、日に向ひて俱に影を翻し、風を迎えては並びて香を散ず。戲蝶は丹萼に扶(あつ)まり、遊蜂は紫房に入る」と。
下官の曰はく「人、今総べて摘み取らば、各(おのおの)一邊の廂に著かむ」と。
五嫂の曰はく「張郎太だ貪生なり、一箭に両の垜を射むとす」と。
十娘の則ち謂いて曰はく「三を遮らば一をも得ず、両を覚(もと)めなば都盧(すべて)を失はむ」と。
五嫂の曰はむ「娘子、分疎(いいわけ)すること莫れ、兎の狗突裏に入らば、自らは飲食に来(いた)れり、知る複た何如(なにを)かを欲するを」と。
下官の即ち起ちて謝して曰はく「漿を乞ふて酒を得、舊来(きゅうらい)神口(かみがかり)、兎を打ちて麞を得るは、意の望む所に非ず」と。
十娘の曰はく「五嫂、如許(いかばかり)かの大人なれば、專ら此の事を調へ合せむと擬(はか)る。少府の謂ふて言はく『兒、是れ九泉下の人、明日には外に在りて談り導(い)はれむ、兒は一錢にも値ひせず』」と。
下官の答へて曰はく「向来(さきより)、顏色を承(うけたま)はるに、神気は頓に盡きたり、また清談を見るに、心膽は俱に碎けたり。豈、敢へて外に在りて談り説きて、妄りに加諸(わずらは)しさを事とせむや、忝く人流に預け、寧ぞ此(か)くの如きを容(ゆる)されむや。伏して願はくは歡樂して情を盡くさば、死すとも恨むる所無からむ」と。
少時にして、飲食俱に到り。香は室に満ち、赤白前に兼はり、海陸の珍羞を窮め、川原の菓菜を備へ、宍は則ち龍肝鳳髓、酒は則ち玉醴瓊漿。城南雀噪の禾、江上蟬鳴の稻。雞の韯雉の臛、鱉の醢鶉の羹、椹下の肥豚、荷間の細鯉。鵝子鴨卵、銀盤に照曜し、麟脯豹胎、玉疊に紛綸たり。熊の腥は純白にして、蟹の漿は純黄なり、鮮き膾は紅の縷と輝きを争ひ、冷なる肝は青き絲と色を亂る。蒲桃甘蔗、栭棗石榴、河東の紫鹽、嶺南の丹橘。敦煌の八子の柰、青門の五色の瓜。太谷張公の梨、房陵朱仲の李。東王公の仙桂、西王母の神桃、南燕牛乳の椒、北趙雞心の棗。千名萬種にして俱かに論ずべからず。
下官の起ちて謝して曰はく「予、夫人・娘子と本より相ひ識らず、暫く公の使ひに縁りて邂逅(たまさか)に相ひ遇へり。玉饌珍奇、常に非ざる厚重(もてなし)なり、身を粉にし骨を灰にすとも、酬謝すること能はず」と。
五嫂の曰はく「親には則ち謝せず、謝するとき則ち親しからず。幸ひに願ふところ張郎形跡(よそよそ)しく為すこと莫れ」と。
下官の曰はく「既に恩命を奉ぜり、敢へて辭遜せず」と。
此の時に當りて、気は便ち絶えむと欲し、覚えず眼を轉らして、偷(ぬす)むて十娘を看む。
十娘の曰はく「少府、兒を看ること莫かれ」と。
五嫂の曰はく「還た相ひ弄(もてあそ)ぶ」と。
下官の詠ひて曰はく「忽然として心裏に愛しみ、覚えず眼中の憐み。未だ雙眼は曲に関わらずて、直だ是れ寸心偏(かたむ)くなり」と。
十娘の詠ひて曰はく「眼と心は一つ處に非ず、心と眼は舊より分ち離る。直ちに渠が眼をして見せしめば、誰か報心をして知らしめむ」と。
下官の詠ひて曰はく「舊来、心は眼を使はしめ、心の思ふときは眼剰(あまつさ)へ傳ふ。心の眼を使ふに由つて見るや、眼も亦た心と共に憐む」と。
十娘の詠ひて曰はく「眼と心と俱に憶ひ念ふや、心と眼と共に追ひ尋ねむ。誰家(だれ)か事を解する眼ぞ、副(そ)ひ著(な)せる可憐なる心」と。
その時に五嫂、遂ひに菓子の上に向ひ、機警を作して曰はく「但だ問ふ意は如何、相ひ知る棗に在らざるか」と。(棗と早は同音で、言葉遊びがあります)
十娘の曰はく「兒、今、正に意は密なり、忍ばずて即ち梨を分かたむ」と。(梨と離は同音です)
下官の曰はく「忽ち深恩に遇ふて、一生は杏に有り」と。(杏と幸は同音です)
五嫂の曰はく「此の時に當りて、誰か能く柰(りんご)を忍ばむ」と。(柰と耐は同音です)
十娘の曰はく「暫く少府の刀子を借りて梨を割らむ」と。
下官の刀子を詠ひて曰はく「自ら憐む膠漆の重んずべきを、相ひ思ひて意は窮まらず。惜むべし尖(さき)き頭の物、終日(ひねもす)皮中に在るを」と。
十娘の鞘を詠ひて曰はく「數(まね)して皮を捺でなば應に緩にして、頻ぶるに磨すれば快は轉る多からむ。渠(きみ)今拔き出して後、空しき鞘を如何にか欲さむ」と。
五嫂の曰はく「向来(さきより)、漸漸に入ること深し」と。
即ち碁局を索め、少府と酒を賭けむ。下官、勝ちを得たり。
五嫂の曰はく「圍碁は智慧より出で、張郎亦た複た太だ能くす」と。
下官の曰はく「智者は千慮も必ず一を失ふは有り、愚者も千慮すれば亦た一を得るは有り。且く休卻(やすま)む」。
五嫂の曰はく「何為ぞ即ち休む」と。
僕、詠ひて曰はく「向来、道徑を知り、生平(つね)に欺くに忍びず。但だ行跡を守らしむるのみ、何を用つてか數(まね)く圍碁をせむ」と。
五嫂の詠ひて曰はく「娘子、性は圍碁を好むに為り、人に逢ひて剩へ戲れて尋思せず、気は断絶せむと欲するに先づ眼に挑み、既に連なるを得、即ち須遲を罷れざらむ」と。
十娘、五嫂の頻りに弄ぶを見、佯(いつわ)り嗔(いか)りて笑まず。
余、詠ひて曰はく「千金此處に有りて、一笑は渠(きみ)が為すことを待つ。望まず全く歯を露はすことを、請ふ暫く眉を顰むるを為すを」と。
十娘の詠ひて曰はく「雙眉は客の膽を碎き、両眼は君の心を判つ。誰か能く一笑を用ひ、賤價をして千金を買(あがな)はむ」と。
時に當り、一つの破れたる銅の熨斗有りて、床の側に在り、十娘の忽ち詠ひて曰はく「舊来、心肚は熱せり、端無く強ひて他に熨さる。即ち今形勢は冷えて、誰か肯へて重なりて相ひ磨かむ」と。
僕、詠ひて曰はく「若し冷なる頭の面に在ありて、生平(つね)に空を熨さず、即ち今冷惡なりと雖も、人も自も残銅を覚(もと)めむ」と。(銅と洞は同音)
眾人皆笑む。
PDFのリンク先;
https://drive.google.com/file/d/1nwgzhiKEyWTctYjXbfxRHv62Pr7njL1I/view?usp=sharing
はじめに
ブログの文字数制限のために、<原文篇>と<訓読篇 前篇>・<訓読篇 後篇>の三篇で掲載しています。必要に応じて、それぞれを参照下さい。
注意事項:-
紹介する『遊仙窟』<原文篇>は、漢文入力の労を省くためインターネット上に公表されている『遊仙窟(維基文庫、自由的図書館;中華人民共和国)』を使い、日本漢字体への変換と中国現代文解釈されたものを本来のものへとすべく次の資料を用いて個人の作業の下に校訂を行っています。なお、相互に異同が認められる場合は醍醐寺本影寫を個人の判断で判定した表記を用いています。また、一部の文字にはフォントの都合で当て字を用いているものがあり、下線にてそれを示しています。
『遊仙窟(張文成作、漆山又四郎訳註;岩波書店)1996年第2刷』
『遊仙窟(張文成作、今村与志雄訳;岩波書店)1990年第1刷』収醍醐寺蔵古鈔本影印
『遊仙窟』漢籍電子文献資料庫、中央研究院歴史語言研究所;中華民国
ただし、正規の教育を受けていない個人の作業であるために掲げる原文は校本となるような学問ではありません。従いまして、ここでのものを使用されます場合は皆様の趣味の範囲での参照にのみ薦めますし、その場合でも適切な原文との対照をお願い致します。
また、『遊仙窟』<訓読篇>に示す訓読文もまた正規の教育を受けていない個人の作業です。従いまして、原文読解における趣味の範囲内での笑文以外のものにはならないものと理解して下さい。そのため、それ以外での訓読み引用には推薦しません。あくまでも本格的な引用への予備資料として下さい。
追記参考として、歴史に于いて『遊仙窟』は中国では早い時期に失せた書物で、日本にのみ現在までに伝えられた唐初時代に成立した中国伝奇小説です。その日本においても奈良時代初期に伝えられたとされる『遊仙窟』は、室町時代の南北朝時代の鈔本と思われる醍醐の三寶院の鈔本(醍醐寺本)、室町時代の鈔本と思われる成簣堂蔵本、江戸時代の慶安以前に刊行された刊本(慶安以前刊本)と元禄時代に刊行された繪入りの半紙本の四系統があるのみとされ、奈良時代から平安時代のものは現存していません。ここでの校訂の作業で資料として使用した『遊仙窟(漆山又四郎訳註)』は江戸時代の刊本(慶安以前刊本)を基として最古の伝本である醍醐寺本の影寫本を参照して譯註に使用したと記述していますが、調べでは完全には校訂されたものではありません。そのため、紹介しましたように、ここでは異同校訂には醍醐寺本を優先しています。なお、醍醐寺本の影寫本は『遊仙窟(今村与志雄訳)』中で容易に知ることが出来ます。
<訓読>
遊仙窟
寧州襄楽縣尉張文成の作
若(けだ)し夫れ積石山は、金城の西南に在りて、河の經る所なり。書に云ふに「河の積石より導き、龍門に至る」と。 即ち此の山是なり。
僕、汧隴に従ひて、河源に使ひを奉(たま)はる。運命の邅たるを嗟(なげ)き、鄉関の渺邈たるを歎く。張騫の古跡は十萬里の波濤にして、伯禹の遺跡は二千年の阪磴なり。深谷は地を帶(た)らし、崖岸の形を鑿穿(さいうつ)し、高き嶺は天に(よこた)はり、崗巒の勢ひは刀削たり。煙霞子細(こまやか)にして、泉石分明(あきらか)なり、實に天上の霊奇にして、乃ち人間(じんかん)の妙(みょう)絶(たへ)たり。目にも見ざる所、耳にも聞かざる所なり。日は晩れ途(みち)遙かにして、馬疲れ人乏(たゆ)みぬ。行きて一(ある)所(ところ)に至る。險峻たるは常(つね)に非(あら)ずして、上を向けば則ち青壁は萬尋に有りて、直下には則ち碧潭は千仞に有る。
古老の相ひ傳へて云ふに「此れは是れ神仙の窟(いはや)なり。人跡の及ぶこと罕(まれ)にして、鳥の路纔(わず)かに通ふ。毎(つね)に香しき菓(くだもの)や瓊(たま)の枝が有り、天衣錫鉢、自然(おのづ)と浮かび出で、何(いづ)れより至れるかを知らず」と云へり。
余、乃(すなわ)ち端(つつし)み仰ぎて心を一にして、潔齋すること三日。細き葛に縁(よ)り、輕舟にて溯(さかのぼ)る。身體(からだ)は飛ぶが若(ごと)く、精霊(こころ)は夢みるに似る。須臾(しまし)の間、忽ち松柏の巌・桃華の澗(たに)に至る。香風は地を觸(めぐ)り、光彩は天(そら)に遍(あまね)く。
一(ある)女子(おなご)の水の側(かたはら)に向かひて衣を浣(あら)ふを見、余、乃(すなわ)ち問ふて曰く「承(うけたま)はり聞く、此の處に神仙の窟宅(いほり)有りと。故に来りて伺候(うかが)へり。山川阻隔たりて、疲れ頓(う)むこと常に異(こと)なり、娘子に投(や)りて、片時(かたとき)に停まり歇(やす)まんことを欲(ねが)ふ。交情を惠み賜はり、幸ひに聽き許すを垂れよ」と云へり。
女子の答へて曰はく「兒(われ)の家、堂舍は賤陋(せんおく)にして、供給(もてなし)は単疏(おろそか)なり、また、堪(た)へざらんを恐(おそ)る。吝惜(おしむ)に無(な)かざらむ」と云へり。
余の答へて曰はく「下官、是れ客なれば、事に觸(よ)りて卑微(いやし)きものにして、ただ風塵を避けなば、則ち幸甚と為さむ」と云へり。
遂に余を門の側(かたは)らの草亭(そうてい)の中に止め、良久(やくやく)にして乃ち出でり。
余の問ふて曰はく「此れは誰か家舍ならむか」と。
女子の答へて曰はく「此れは是れ崔女郎の舍なり」と。
余の問ふて曰はく「崔女郎とは何人(なにひと)なりや」と。
女子の答へて曰はく「博陵王の苗裔にして、清河公の舊族なり。容貌は舅に似、潘安仁の外甥なり。気調は兄の如く、崔季珪の小妹なり。華容は婀娜(たおや)か、天上に儔(たぐ)ひ無く、玉體は逶迤(なおや)かにして、人の間に疋(なら)び少なし。輝輝(かがや)ける面子(かんばせ)は荏苒(じんぜん)として穿(うが)かば弾(はじ)かむを畏れしめ、細細(こまや)かなる腰支は参差(しんし)として勒(いだ)かば断えなむと疑はる。韓娥や宋玉も見(なが)めれば則ち愁ひを生じ、絳樹や青琴も之に對(たい)すれば羞じて死なむ。千嬌百媚、造次にも比方すべきは無し。弱躰輕身、之を談ずるも備(つまび)らかに盡すは能はず」と云へり。
須臾(しまし)の間、忽ちに内裏に箏を調へる聲を聞く。
僕、因りて詠ひて曰はく「自(おのず)から姿則の多(すぐれ)れたるを隱し、他を欺きて獨り自(みずか)ら眠(ひそ)む。故故に纖(かよわ)き手を將(も)ちて、時時に小弦を弄(もてあそ)ぶ。耳に聞くに猶さら気を絶ち、眼に見るに若(いかば)りか憐れみを為さむ。従(よし)や、渠(きみ)、痛(はなは)だ肯(う)べなく、人をして更に就天を別(いと)はむや」と云へり。
片時にして、婢の桂心を遣はして、傳へ語たるに余の詩に報(こた)へて曰はく「面(かんばせ)は他舍の面に非ず、心は是れ自(おのず)から家の心、何處(なんぞ)、天事に関(かか)はりて、辛苦を漫(みだ)りに追尋せむ」と。
余、詩を讀み訖(お)りて、頭を門中に舉げ、忽ちに十娘の半面(よこがお)を見たり。
余、則ち詠ひて曰はく「斂(ほほ)は笑(え)みて残の靨を偷(かく)し、羞(はじら)ひを含みて半ば唇(くちびる)を露はし、一眉は猶ほ耐へ難たく、雙眼は定めて人を傷(いた)めむ」と。
又、婢の桂心を遣はして、余の詩に報へて曰はく「好みは是れ他家の好み、人は人の意を著くるに非ず、何を須(す)てか漫りに相ひ弄びて、幾許(いくばく)か精神(おもひ)を費せる」と。
その時、夜は久しく更に深け、沈吟して睡(ねむ)らず、彷徨徙倚するに便(すべ)無く、披陳するに彼の誠は既に来意有り、此の間何ぞ能く答へざらんむと。
遂に懷抱(おもひ)を申(の)べ、因りて以ちて書を贈りて曰はく「余、以(おもむみ)れば少(おさな)くして聲色を娯(たのし)み、早く佳き期(ちぎり)を慕ひ、歴(ことごと)く風流を訪ねて、遍く天下に遊ぶ。蜀郡に鶴琴を弾きて、飽くまで文君と見(まみ)へ、秦樓に鳳管を吹きて、熟(みつ)るまで弄玉と看(まみ)へむ。雖、複た蘭を贈りて珮(おび)を解くとも、未だ甚(はなは)だ懷ひに関はらずして、合巹陳、何曾(なにそ)意に愜(かな)はむ。昔日の雙(ふたり)して眠(ねむ)しは、恆(ひさし)く夜の短きを嫌ひ、今宵の獨(ひとり)して臥するは、實に更(よる)の長きを怨む。一種(あるしゅ)の天公、両般の時節なり。遙かに香気を聞き、獨り韓壽の心を傷み、近きに琴聲を聽き、文君の面(かんばせ)に對(むか)ふるに似たり。向来(さきより)、桂心の談り説くを見るに、十娘は天上に雙(ふたつ)は無く、人の間に一つ有るのみ。依依たる弱(わおや)き柳、束ねて腰支を作(な)し、焰焰として(よこた)はれる波、翻りて眼尾(めじり)を成せり。纔(わずか)かに両頰を舒(の)ぶれば、熟(つらつ)ら地上に華無きを疑ひ、乍(さら)に雙眉を出ださば、漸(やくや)く天邊に月を失うと覚える。能く西施をして面(かんばせ)を掩(おほ)ひせしめて百遍の粧(よそおひ)を焼(ほろぼ)し、南國をして心を傷(いた)せしめて千廻(ちた)び鏡を撲(なげ)む。洛川の廻雪も、只だ堪だ衣裳を疊(たた)ませしめ、巫峽の仙雲も、未だ敢へて鞾履を撃(ささげ)るを為さしめむ。忿(いか)りて秋胡の眼拙して、枉(ま)げて黄金を費し、念ひて交甫の心狂して、虚しく白玉に當(あ)へる。下官、偶(たまたま)勝境に遊び、閑亭に旅泊して、忽ちに神仙に遇(あ)ひ、迷亂に勝(あ)へず。芙蓉は澗底に生じて、蓮子は實に深く、木栖は山頭に出でて、相思は日に遠し。未だ曾つて炭を飲まざれど、腹(はらわた)の熱きこと焼くが如く、刃を吞むこと憶へざらむを、腸(はらわた)を穿(うが)ちたること割くに似たり。無情の明月、故故に窗に臨み、多事たる春風、時時に帳(とばり)を動かす。愁人此に對(むか)ひて何を將(もち)てか自(みずか)ら堪へむ。空しく断えなんとする腸を懸げて、終ひに臨まむとする命を救はむを請ふ。元来(もとより)、見(あ)はざれば他も自も尋常(つね)にして事無きしを、相ひ逢うて卻(かへ)つて交(たが)ひに煩ひ悩む。敢へて心素(おもひ)を陳べ、幸ひに照(あきら)かに知るを願ふ。若し其の光儀(すがた)を見ることを得るは、豈、敢へて其の萬が一を論ぜむや」と云へり。
書の達するの後、十娘色を斂(ひそ)め、桂心に謂ひて曰はく「向来(さきより)、劇(はなはだ)しく戲れ相ひ弄(もてあそぶ)こと、真に人に逼(せま)らむと欲せりを成さむ」と。
余、更にまた詩一首を贈り、其の詞に曰はく「今朝忽ちに渠(きみ)の姿首に見(まみ)へ、覚へずして慇懃に心は口に著く。人をして頻りに作許の叮嚀あらしめ、渠の家は太劇を求守するは難し。端坐して心驚は剩(ただなら)ずして、愁へ来りて益(さら)らに平(たい)らかならず。看(まみ)へる時に未だ必ずしも死を相ひ看(み)むとはおもわず、難き時は那許(いかばかり)か太(はなはだ)だ生き難し。沈吟して幽室に處(こも)り、相ひ思ふて轉(かへ)つて疾(やまひ)を成す。自ら往還の疎を恨み、誰か交遊の密を肯(う)べみて、夜夜空しく心の眼を失ふを知り、朝朝膠漆に投ずる便(すべ)無きを。園裹に華は開きて人を避けず、閨中に面子(かんばせ)の出でむことを羞(はじら)ふを翻かえす。如今(ただいま)、寸歩は天津を阻て、伊(いず)れの處にか情(おもひ)を留めて更に新しきを覚(さと)らむ。言ふこと莫かれ長(ひさ)しく千金の面に有りて、終ひに歸へり變じて一抄の灰塵と作(な)らむ。生前に但だ樂みを為すべき日は有りて、死後に更(なおさら)に人の看るべき春は無からむ。祗に一生の意を倡佯すべく、何を須てか百年の身を負持べけむや」と云へり。
少時坐睡し、則(たちま)ちに十娘に見(まみ)へむ夢を見む。驚き覚めて之を攬るに、忽然として手は空(むな)し。心中悵怏たるに、複た何をか論ずべき。
余、因りて乃ち詠ひて曰はく「夢中に是れ實(まこと)かと疑ひ、覚めし後に忽ちに真に非ず。誠に腸(はらわた)の断てむと欲せりを知り、窮鬼は故に人を調ふ」と。
十娘の詩を見、また讀み肯(う)べむとして、即ち焼き卻てむを欲す。
僕、即ち詠ひて曰はく「未だ必ずしも詩に由りて得むにはあらず、將に詩に故りて憐みを表はむ。渠(きみ)が火に擲げ入らるるを聞き、定めて是れ相ひ燃さむと欲すならむ」と。
十娘の詩を讀み、悚息として起(た)つ。匣中より鏡を取り、箱の裏に衣を拈く。袨服靚粧し、階(きざし)に當りて履を正しくす。
僕、また詩を為して曰はく「香四面に合ふて、光色は両邊に披く。錦障は劃然と卷きて、羅帷は半ばに垂れて欹(かたむ)けり。紅顏は緑黛と雜はり、處として相ひ宜(よ)からざるは無し。艶色に粧粉を浮かべ、含香は口脂を亂せり。鬢は蟬鬢の鬢を成せるに非ざるを欺き、眉は蛾眉の是れ眉ならざるを笑ふ。見るに實に娉婷を許し、何れの處にか輕盈たらざらむ。憐むべし嬌裏の面(かんばせ)、愛すべし語中の聲。婀娜たる腰支は細細たるを許し、兼占(れんせん)たる眼子(まなじり)は長長に馨(かおる)。巧に兒の舊来(もとより)鐫(え)るとも未だ得らざり、畫匠は迎へ生すの成らざるを摸(な)ぞる。相ひ著(し)るに未だ相ひ識(し)らず、傾城は複た傾國なり。風を迎えては帔子に鬱金の香り、日に照らして裙裾に石榴の色あり。口上の珊瑚は拾ひ取るに耐え、頰裏の芙蓉は摘み得るに堪える。名を聞くに腹肚(はらのうち)に已(おのず)に猖狂し、面を見るに精神(こころ)は更に迷ひ惑ふ。心肝恰(あたか)も摧けむと欲し、踴躍して裁つは能はず。徐かに行くに歩歩に香風を散らし、語らむと欲して時時に媚子を開く。靨(えくぼ)は織女の星を留めて去くかと疑ひ、眉は恒娥(じょうが)の月を送り来たるに似る。嬌を含みて窈窕して前(すす)み出でて迎へ、笑(え)みを忍びて嫈冥(えいめい)の卻(しりぞ)きて廻して返す」と云へり。
余、遂に之を止めて曰はく「既に好意有らば、何ぞ須らく卻きて入れむ」と。
然る後、十娘逶迤(きい)として面を廻らし、亜余(あた)として向ひ前(すす)む。手を斂め再拜して下官に向かひ、下官も亦た低頭し禮を盡して言ふて曰はく「向見して稱揚せられて謂へらく言ふこと虚假なりと、誰か知らむ面に對(むか)ひて、恰も是れ神仙なるを。此れは是れ神仙の窟なり」と。
十娘の曰はく「向見して詩篇、謂へらく言ふこと凡俗なりと、今、玉貌に逢ひて、更に文章に勝れり。此れは是れ文章の窟なり」と。
僕、因りて問ふて曰はく「主人の姓望は何れの處ぞ、夫主は何くに在らむ」と。
十娘の答へて曰はく「兒(わらは)は是れ清河の崔公の末孫にして、弘農の楊府君が長子に適(かな)ふ。孰(つい)に大禮を成し、父に隨ひて河西に住む。蜀生狡猾にして、屢邊境を侵す。兄及び夫主は筆を弃て戎に従ひ、身は寇場に死して気魂は返すこと莫し。兒は年十七にして、死すとも一夫を守り、嫂は年十九にて、再醮(さいしょう)せざるを誓う。兄は即ち清河の崔公の第五の息にして、嫂は即ち太原公の第三の女なり。別(こと)に此に宅(す)み、積りて歳年有り。室宇は荒涼にして、家途は翦弊たり。知らず上客は何くより至れる」と云へり。
僕、容を斂(あらた)めて答へて曰はく「下官は南陽に望屬せられて、西鄂に住居す。黄石の霊術を得て、白水の餘波を控く。漢に在りては則ち七葉の貂蟬、韓に居みては則ち五重の卿相たり。鍾を鳴らして鼎食し、代を積みては衣纓せり。戟の長にして高門を高くし、禮樂に因り循ふ。下官、堂構は紹かず、家業淪滑たり。青州の刺史博望侯が孫、廣武將軍鉅鹿侯の子なり。俗を免るること能はずして、跡を下寮に沈める。隱るるに非ず遁れるに非ずて、逍遙して鵬鴳の間、吏に非ず俗に非ずて、是非の境に出入す。暫く駆使せらるるに因りて、此の間に至れり。卒爾に幹煩たり、實に傾仰を為す」と。
十娘の問ふて曰はく「上客は何の官に任(ま)けられや」。
下官の答へて曰はく「幸ひに太平に屬(よ)り、貧賤に居ることを恥ず。前に賓貢を被り、已は甲科に入り、後に搜揚に屬(つ)き、また高第を蒙れり。敕を奉じて関内道の小縣の尉を授け、河源道の行軍総管の記室に宛てられむ。頻りに上命を繁して、徒らに報恩を想ふ。下寮に馳驟して、寧處に遑(いとま)あらず」と。
十娘の曰はく「少府、行使あるに因らずんば、豈、相ひ過らむは肯(う)べならむや」と。
下官の答へて曰はく「頃(このころ)、相ひ知らずして、参展(つかまつ)り為すを闕(か)く。今日より後、敢へて差し違(たが)はざらむ」と。
十娘の遂に頭(こうべ)を廻らし、桂心を喚びて曰はく「中堂を料理し、將に少府を安らかに置かむ」と。
下官、逡巡して謝して曰はく「遠客は卑微にして、此の間は幸甚なり。才は賈誼に非ざれば、豈、敢へて堂に昇らむや」と。
十娘の答へて曰はく「向(さき)に承はり聞くは、謂ふに言へるは凡客、拙く禮貺を為すは、深く面を覚みて兒の意を慚じ、事に相ひ當りて須く引接せむ。此の間は疏陋にして、未だ風塵を免れず。室に入るは推辭(いなむ)に合はずして、堂に昇るに何ぞ須く進退(あとずさり)せむ」と。
遂に中堂に引き入れたり。時に金台銀闕、日を蔽ひ雲を干(おか)す。或は銅雀の新たに開けたるに似、乍ちに霊光の且(あした)に敞(ほがらか)かなるが如し。梅の梁桂の棟、澗(たに)の長虹を飲むかと疑ひ、反(そ)れる宇(のき)雕れる甍(いらか)、天の嬌鳳を排するが若し。水精の浮柱、的皪として星を含み、雲母の飾窗、玲瓏として日を映す。長き廊(わたどの)は四に注(そそ)ぎ、争ふて玳冐(たいまい)の椽(たるき)を施し、高閣は三重にして、悉く瑠璃の瓦を用ふ。白銀を壁と為し、魚鱗のごとく照り曜やき、碧玉は陛(きざはし)を縁り、鴈歯を参差たらしむ。穹崇たる室宇に入らば、歩歩に心は驚き、黨閬(とうろう)たる門庭を見れば、看看として眼は参(かがや)けり。遂に少府を引きて階を昇る。
下官の答へて曰はく「客主の間、豈、先後無からむや」と。
十娘の曰はく「男女の禮、自から尊卑有り」と。
下官、遷延とし退きて曰はく「向来(さきより)、罪過有りて、忘れて五嫂に通ぜざりき」と。
十娘の曰はく「五嫂、亦た、自から来るべし、少府、遣通(いま)せ、亦た、是れ周り匝(めぐ)らむ」と。
則ち桂心を遣はして通はせ、暫く五嫂の参屈す。十娘、少府と語話(かたらひ)するに、須臾の間、五嫂の則ち至る。羅綺繽紛として、丹青暐曄たり。金釵銅鐶、裙の前には麝を散じ、髻(もとどり)の後には龍が盤(わだか)まる。珠繩は翠衫に絡ひ、金薄を丹履に塗りぬ。
余乃ち詠ひて曰はく「奇異きまでの妍雅、貌は特に驚くまでに新たなり。眉間に月は出でて夜を争うを疑ひ、頰上に華は開きて春を闘ふに似る。細腰は偏(ひとへ)に愛ずべき轉り、笑臉は特に顰むに宜し。真に物外の奇しき稀なる物に成るは、實に是れ人の間の断絶の人なり。自然から能く舉を止み、念ふべし比方すべき無しを。能く公子をして百廻生しめ、巧みに王孫をして千遍死なしむ。雲は両鬢を裁ち、白雪は雙歯を分つ。綿袖には織り成す騏の兒、裙腰には刺繡せりし鸚鵡の子。處に觸れて盡く懷ひの関(ことのおこ)りて、何ぞ曾て佳からざらことか有らむ、機関太だ雅妙にして、行歩絶へて娃屏(みやびか)なり。傍人は一一の丹羅の襪(くつたび)、侍婢だも三三の緑線の鞋。黄龍を透(ちりば)めて黄金の釧(うでわ)に入れ、白燕は白玉の釵に飛来せり」と。
相ひ見みること既に畢はりて、五嫂の曰はく「少府、山川を跋渉し、深く道路に疲れるも、行途此に屆まれり、神を傷むるに及ばず」と。
下官の答へて曰はく「王事に黽勉(びんべん)し、豈、敢へて勞りを辭せんや」と。
五嫂の頭を廻らし、笑みて十娘に向きて曰はく「今朝、鳥鵲の語ひを聞き、真に好き客の来たるは成る」と。
下官の曰はく「昨夜、眼皮(まぶた)は閏(またた)き、今朝、好き人を見(まみ)えむ」と。
即ち相ひ隨ひて堂に上る。珠玉は心を驚かし、金銀は眼を曜かす。五彩龍鬢の席、錦繡縁邊の氈、八尺の象牙の牀、緋綾帖薦の褥。車渠・馬瑙・真珠等の寶、俱に優曇の花に映じ、並びに頗梨の線(いとすじ)に貫けり。文柏の榻子、俱に豹頭を寫し、蘭草の燈芯、並びて魚腦を焼けり。管弦は寥亮にして、北戸の間に分張し、杯盞の交(こもごも)は横はりて、南窗の下に列なり坐れり。各自(おのおの)相ひ讓りて、俱に先じて坐することを肯へてせず。
僕の曰はく「十娘は主人なり、下官は是れ客。請ふ主人、先ず坐することを」。
五嫂、人と為りて饒(おほ)いに劇(たわむ)れ、口を掩ひて笑(え)みて曰はく「娘子は既に是れ主人の母、少府は須らく主人公と作るべし」と。
下官の曰はく「僕、是れ何人なれば、敢へて此の事に當らむや」。
十娘の曰はく「五嫂、向(さき)に来りて戲れ語る、少府、何ぞ須らくも漫(みだ)りに怕れるや」。
下官の答へて曰はく「必ず其れ免れずんば、只、身を須(まか)せて當らむ」。
五嫂の笑みて曰はく「只、恐るる張郎、此の事を禁(いな)むること能はざるを」。
眾人皆大ひに笑む。一時に俱に坐せり。即ち香兒を喚びて酒を取らせむ。俄爾(しばらく)の中間(あひだ)に、三升可かりを受くる一大鉢を撃(ささ)げて已に来れり。金釵銅鐶、金盞銀杯、江螺海蚌、竹根細眼、樹癭蠍唇、九曲の酒池、十盛の飲器。觴は則ち兕觥犀角ありて、尫尫然として座中に置き、杓は則ち鵝項と鴨頭ありて、汛汛焉として酒上に浮べり。小婢細辛を遣はして酒を酌ましめ、並びに先じて提げるは肯(う)べざらむ。
五嫂の曰はく「張郎は門下の賤客なり、必ず先じて提ることは肯(う)べざらむ。娘子徑(ただ)ちに須らく把り取るべし」と。
十娘の則ち斜眼みて佯り嗔りて曰はく「少府は初めて此間に到れり、五嫂の會(あしら)ひ些(いか)ん。頻頻(しばしば)相ひ弄ぶ」。
五嫂の曰はく「娘子は酒を把りて嗔ること莫れ、新婦は更に亦た敢へてせず」と。
酒巡りて下官に到るも、飲みて乃ち盡さず。
五嫂の曰はく「何為ぞ盡くさざる」と。
下官の答へて曰はく「性れつき飲むこと多からず、恐らくは顚沛を為さむ」と。
五嫂の罵りて曰はく「何に由りては耐へ難からむ。女婿は是れ婦家の狗なり、打殺するも尤(あやまち)ち無からむ。終(つひ)に須らく傾け盡くし、漫りに眾諸に造ること莫らしむ」と。
十娘の五嫂に謂ふて曰はく「向来(さきより)、正首(まさ)に病の發(おこ)れるや」と。
五嫂の起ちて謝して曰はく「新婦の錯(あやまち)、大ひに罪過あり」と。
因つて頭を廻らし下官を熟視して曰はく「新婦、細(つらつ)ら人を見ること多く、少府公に如(し)く者は無し。少府公乃ち是れ仙才なり、本より凡俗に非ず」と。
下官の起ちて謝して曰はく「昔の卓王の女、琴を聞いて相如の器量を識り、山濤の妻、壁を鑿ちて阮籍の賢人を知る。誠に言ふ所の如きは、敢へてを望(のぞ)まず」と。
十娘の曰はく「緑竹を遣はして琵琶を取り弾かさしめ、兒(わらは)は少府公と酒を送らむ」と。
琵琶を手に入れるも未だ弾ざる中間(あいだ)に、僕、乃ち詠ひて曰はく「心は虚にして測るべからず、眼は細にして強ちに情に関はる。身を廻らして已の抱(ふところ)に入れ、見へざるも嬌聲は有り」と。
十娘の聲に應へて即ち詠ひて曰はく「憐むらく腸を忽ち断たむと欲するを、眼の已の先に開くを憶ふ。渠(きみ)、未だ相ひ撩撥せずて、嬌は何處よりか来たらむか」と。
下官、當に此の詩を見、心膽は俱に碎けむ。床に下りて起ちて謝して曰はく「向来(さきより)、唯、十娘の面を覩、如今(ただいま)乃ち始めて十娘の心を見む、班婕をして輪を扶け、曹大家をして筆を閣かしむに足り、豈、年を同じうして語り、代を共にして論ずべけむや。請ふらくは筆と硯を索(もと)め、抄寫して懷袖に置かむ」と。
詩を抄(うつ)し訖りて、十娘の弄びて曰はく「少府公、但だ詞句の断絶するに非ずして、亦た自から書を能す。筆は青鷥に似、人は白鶴に同じ」と。
下官の曰はく「十娘、直(すなお)な才は情(なさけ)に非ずて、實に能く吟詠す。誰か玉貌を知り、恰も金聲は有らむ」と。
十娘の曰はく「兒は近来(ここのところ)、嗽(せき)を患へて、聲音は徹(とお)らず」と。
下官の答へて曰はく「僕、近来、手を患へて、筆墨は未だ調はず」と。
五嫂の笑みて曰はく「娘子は是(よ)からず故に誇り、張郎の複た能く應答せり」と。
十娘の五嫂に語りて曰はく「向来(さきより)、純(もつはら)當(まさ)に漫語、元来、次第の無し、請ふ五嫂の酒章を作り為すべし」と。
五嫂の答へて曰はく「命を奉ずることは敢へてせず、則ち娘子に従りて賦するに是らず、古詩に云はく『章を断ち意を取り、唯だ須らく情を得るべし、若し愜當(あきたら)ずんば、罪として科罰は有らむ』」と。
十娘の即ち命を遵びて曰はく「関関たる雎鳩、河の洲に在り。窈窕たる淑女、君子の好き仇なり」。
次に、下官の曰はく「南に樛木有り、休息すべからず。漢に遊女有り、求むべからず」と。
五嫂の曰はく「薪を折ること之れ、何の如く、斧に匪(あら)ざれば剋(あた)はず。妻を娶りて之れ、何の如く、媒に匪ざれば得ず」と。
又た次に、五嫂の曰はく「複た関(ことのおこり)を見ずは、泣涕は漣漣たり。既に複た関(ことのおこり)を見れば、載(すなわ)ち笑(え)み載ち言(かたら)ふ」と。
次に、十娘の曰はく「女は爽(たが)はず、士は其の行ひを二つにす。士は極まり罔き、其のを二つ三つにす」と。
次に、下官の曰はく「穀(い)けるには則ち室を異にするも、死なば則ち穴を同じくせむ。余を信あらずと謂ふも、日(あかきひ)の如く有り」と。
五嫂の笑みて曰はく「張郎、心は專(いちず)なり、詩を賦すること太だ道理有り。俗の諺に曰はく『心を專ならむと欲せば、石を鑿るとも穿ちなむ。誠に能く之を思はば、何の遠きこと之れ有らむ』」と。
其の時、緑竹の箏を弾く。
五嫂の箏を詠ひて曰はく「天は素(しろ)き面(かんばせ)を生じて能く客を留め、意を發つし情に関はること併に渠(きみ)は在り。怪むこと莫れ、向(さき)には頻りに聲は戰(ふる)へ、良く伴を得るに由り乍に心の虚なるを」と。
十娘の曰はく「五嫂は箏を詠ひ、兒は尺八を詠ふ。『眼多くして本より自ら渠を愛せしめ、口少くして由来は毎に侵を被むり、事無くして風聲は他の耳に徹り、教人をして気満たらしめば自ら心に填なむ』」と。
下官の又た謝して曰はく「善を盡し美を盡し、處として佳からざる無し。此は是れ下愚にして、預め高唱を聞くなり」と。
少時にして、桂心、將に酒物(さけさかな)を下げて来り、東海の鯔條、西山の鳳脯、鹿尾に鹿舌、乾魚と炙魚、鴈醢荇菹、鶉韯桂糝、熊掌に兎髀、雉臎と豺唇、百味五辛、之を談るも盡くすこと能はずて、之を説くとも窮むるは能はず。
十娘の曰はく「少府、亦た、太だ飢えたるなるべし」と。
桂心を喚びて飯を盛らしむ。
下官の曰はく「向来、眼は飽きたりて、身は飢えを覚えざり」と。
十娘の笑みて曰はく「相ひ弄ること莫れ、且た雙六局を取りて来たれ、共に少府公と酒を賭けむ」と。
僕の答へて曰はく「下官は酒を賭けること能はず、娘子と宿を賭けむ」と。
十娘の問ふて曰はく「若為(いかにして)てか宿を賭けむ」と。
余の答へて曰はく「十娘、籌(かず)を輸(ま)けなば、則ち下官と一宿を臥せ、下官、籌を輸けなば、則ち共十娘と一宿を臥せむ」と。
十娘の笑みて曰はく「漢の驢に騎らば則ち胡は歩より行き、胡の歩より行かば則ち漢は驢に騎らむ、総べて悉く他に輸(いた)さなば便ち點頭(うなづ)かむ。兒、遞ひに換り作すなり、少府公、太だ能く生れり」と。
五嫂の曰はく「新婦、娘子に報ず、須らく賭け来り賭け去るべからず、今夜定めて知る娘子の免れざらむを」。
十娘の曰はく「五嫂、時時、漫語なり、浪りに少府の消息を作らむ」と。
下官の起ちて謝して曰はく「元来(もとより)、劇(たわむ)れごとなるを知れり、未だ敢へて承望せず」と。
局(すごろく)の至るや、十娘、手を引きて前に向かひ、眼子は盱婁(くろう)にして、手子は膃腯たり。一雙の臂腕は我が肝腸を切り、十個の指頭は人の心髓を刺す。
下官の因りて局を詠じて曰はく「眼は星の初めて轉るに似、眉は月の消えむと欲するが如く、先づ須らく後脚を捺で、然して始めて前腰を勒(おさ)むべし」と。
十娘の則ち詠ひて曰はく「腰を勒めなば須らく巧く快かるべし、脚を捺でなば更に風流、但だ細き眼を合わせしめば、人も自も籌(かず)を輸(ま)けること分たむ」と。
須臾の間、一婢有り、名は琴心、亦た姿首(よきかほ)有り、下官の處に到るを、時に複た偷(ぬす)み眼を看む、十娘、欲(おもひ)は快(よ)からざるが如し。
五嫂の大語(おほごえ)に嗔(いか)りて曰はく「足ることを知れば辱められじ、人の生に限り有り。娘子眉を皺(ひそ)めむと欲するが似(ごと)し、張郎、須らく斜眼(ながしめ)をせざれ」と。
十娘の佯(いつわ)りて色を捉(とりおさ)め嗔りて曰はく「少府、兒に何事か関(ことをおこ)さむ、五嫂、頻頻(しばしば)相ひ悩ます」と。
五嫂の曰はく「娘子は少来頗(しき)りに少府を盼(かへり)み、若し情に想ふに非ずんば、交り通ふ所は有らむや、何に因りてか眼眽(むすみめ)し、朝来(けさより)頓に引かれんや」と。
十娘の曰はく「五嫂、自ら心の偏れるを隱せり、兒、複た何ぞ曾て眼を引かれんや」と。
五嫂の曰はく「娘子能からずんば、新婦、自ら取らむ」と。
十娘の答へて曰はく「自ら少府に問へ、兒、亦た知らず」と。
五嫂の遂に詠ひて曰はく「新華は両樹に發(ひら)き、香を分かちて一林に遍(あまね)し。風を迎へて細影を轉し、日に向ひて輕陰を動す。戲蜂は時に隱見し、飛蝶は遠く追尋す。聞くならく採摘せむと欲すと、若箇(いかばか)りか君の心を動かせる」と。
下官の曰はく「性と為り多く貪り、両華、俱に采らむと欲す」と。
五嫂の答へて曰はく「暫く雙樹の下に遊び、遙かに両枝の芳きを見、日に向ひて俱に影を翻し、風を迎えては並びて香を散ず。戲蝶は丹萼に扶(あつ)まり、遊蜂は紫房に入る」と。
下官の曰はく「人、今総べて摘み取らば、各(おのおの)一邊の廂に著かむ」と。
五嫂の曰はく「張郎太だ貪生なり、一箭に両の垜を射むとす」と。
十娘の則ち謂いて曰はく「三を遮らば一をも得ず、両を覚(もと)めなば都盧(すべて)を失はむ」と。
五嫂の曰はむ「娘子、分疎(いいわけ)すること莫れ、兎の狗突裏に入らば、自らは飲食に来(いた)れり、知る複た何如(なにを)かを欲するを」と。
下官の即ち起ちて謝して曰はく「漿を乞ふて酒を得、舊来(きゅうらい)神口(かみがかり)、兎を打ちて麞を得るは、意の望む所に非ず」と。
十娘の曰はく「五嫂、如許(いかばかり)かの大人なれば、專ら此の事を調へ合せむと擬(はか)る。少府の謂ふて言はく『兒、是れ九泉下の人、明日には外に在りて談り導(い)はれむ、兒は一錢にも値ひせず』」と。
下官の答へて曰はく「向来(さきより)、顏色を承(うけたま)はるに、神気は頓に盡きたり、また清談を見るに、心膽は俱に碎けたり。豈、敢へて外に在りて談り説きて、妄りに加諸(わずらは)しさを事とせむや、忝く人流に預け、寧ぞ此(か)くの如きを容(ゆる)されむや。伏して願はくは歡樂して情を盡くさば、死すとも恨むる所無からむ」と。
少時にして、飲食俱に到り。香は室に満ち、赤白前に兼はり、海陸の珍羞を窮め、川原の菓菜を備へ、宍は則ち龍肝鳳髓、酒は則ち玉醴瓊漿。城南雀噪の禾、江上蟬鳴の稻。雞の韯雉の臛、鱉の醢鶉の羹、椹下の肥豚、荷間の細鯉。鵝子鴨卵、銀盤に照曜し、麟脯豹胎、玉疊に紛綸たり。熊の腥は純白にして、蟹の漿は純黄なり、鮮き膾は紅の縷と輝きを争ひ、冷なる肝は青き絲と色を亂る。蒲桃甘蔗、栭棗石榴、河東の紫鹽、嶺南の丹橘。敦煌の八子の柰、青門の五色の瓜。太谷張公の梨、房陵朱仲の李。東王公の仙桂、西王母の神桃、南燕牛乳の椒、北趙雞心の棗。千名萬種にして俱かに論ずべからず。
下官の起ちて謝して曰はく「予、夫人・娘子と本より相ひ識らず、暫く公の使ひに縁りて邂逅(たまさか)に相ひ遇へり。玉饌珍奇、常に非ざる厚重(もてなし)なり、身を粉にし骨を灰にすとも、酬謝すること能はず」と。
五嫂の曰はく「親には則ち謝せず、謝するとき則ち親しからず。幸ひに願ふところ張郎形跡(よそよそ)しく為すこと莫れ」と。
下官の曰はく「既に恩命を奉ぜり、敢へて辭遜せず」と。
此の時に當りて、気は便ち絶えむと欲し、覚えず眼を轉らして、偷(ぬす)むて十娘を看む。
十娘の曰はく「少府、兒を看ること莫かれ」と。
五嫂の曰はく「還た相ひ弄(もてあそ)ぶ」と。
下官の詠ひて曰はく「忽然として心裏に愛しみ、覚えず眼中の憐み。未だ雙眼は曲に関わらずて、直だ是れ寸心偏(かたむ)くなり」と。
十娘の詠ひて曰はく「眼と心は一つ處に非ず、心と眼は舊より分ち離る。直ちに渠が眼をして見せしめば、誰か報心をして知らしめむ」と。
下官の詠ひて曰はく「舊来、心は眼を使はしめ、心の思ふときは眼剰(あまつさ)へ傳ふ。心の眼を使ふに由つて見るや、眼も亦た心と共に憐む」と。
十娘の詠ひて曰はく「眼と心と俱に憶ひ念ふや、心と眼と共に追ひ尋ねむ。誰家(だれ)か事を解する眼ぞ、副(そ)ひ著(な)せる可憐なる心」と。
その時に五嫂、遂ひに菓子の上に向ひ、機警を作して曰はく「但だ問ふ意は如何、相ひ知る棗に在らざるか」と。(棗と早は同音で、言葉遊びがあります)
十娘の曰はく「兒、今、正に意は密なり、忍ばずて即ち梨を分かたむ」と。(梨と離は同音です)
下官の曰はく「忽ち深恩に遇ふて、一生は杏に有り」と。(杏と幸は同音です)
五嫂の曰はく「此の時に當りて、誰か能く柰(りんご)を忍ばむ」と。(柰と耐は同音です)
十娘の曰はく「暫く少府の刀子を借りて梨を割らむ」と。
下官の刀子を詠ひて曰はく「自ら憐む膠漆の重んずべきを、相ひ思ひて意は窮まらず。惜むべし尖(さき)き頭の物、終日(ひねもす)皮中に在るを」と。
十娘の鞘を詠ひて曰はく「數(まね)して皮を捺でなば應に緩にして、頻ぶるに磨すれば快は轉る多からむ。渠(きみ)今拔き出して後、空しき鞘を如何にか欲さむ」と。
五嫂の曰はく「向来(さきより)、漸漸に入ること深し」と。
即ち碁局を索め、少府と酒を賭けむ。下官、勝ちを得たり。
五嫂の曰はく「圍碁は智慧より出で、張郎亦た複た太だ能くす」と。
下官の曰はく「智者は千慮も必ず一を失ふは有り、愚者も千慮すれば亦た一を得るは有り。且く休卻(やすま)む」。
五嫂の曰はく「何為ぞ即ち休む」と。
僕、詠ひて曰はく「向来、道徑を知り、生平(つね)に欺くに忍びず。但だ行跡を守らしむるのみ、何を用つてか數(まね)く圍碁をせむ」と。
五嫂の詠ひて曰はく「娘子、性は圍碁を好むに為り、人に逢ひて剩へ戲れて尋思せず、気は断絶せむと欲するに先づ眼に挑み、既に連なるを得、即ち須遲を罷れざらむ」と。
十娘、五嫂の頻りに弄ぶを見、佯(いつわ)り嗔(いか)りて笑まず。
余、詠ひて曰はく「千金此處に有りて、一笑は渠(きみ)が為すことを待つ。望まず全く歯を露はすことを、請ふ暫く眉を顰むるを為すを」と。
十娘の詠ひて曰はく「雙眉は客の膽を碎き、両眼は君の心を判つ。誰か能く一笑を用ひ、賤價をして千金を買(あがな)はむ」と。
時に當り、一つの破れたる銅の熨斗有りて、床の側に在り、十娘の忽ち詠ひて曰はく「舊来、心肚は熱せり、端無く強ひて他に熨さる。即ち今形勢は冷えて、誰か肯へて重なりて相ひ磨かむ」と。
僕、詠ひて曰はく「若し冷なる頭の面に在ありて、生平(つね)に空を熨さず、即ち今冷惡なりと雖も、人も自も残銅を覚(もと)めむ」と。(銅と洞は同音)
眾人皆笑む。