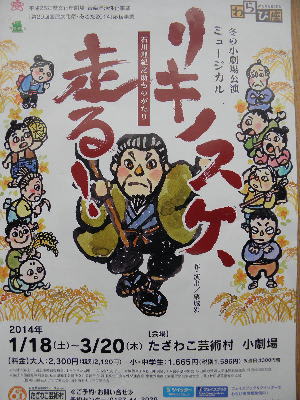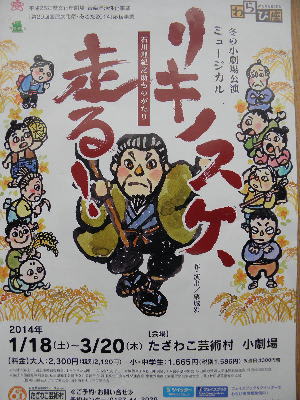
お休み初日の15日、私には珍しくお芝居を観てきました。劇団わらび座小劇場で上演中の「リキノスケ、走る!」。秋田県金足村(現秋田市)に生まれた石川理紀之助は、独自の哲学で貧しい農村を立て直し、「農聖」と謳われた人物です。昨秋仙北市を会場に開催された「県種苗交換会」の創始者としても有名なんですね。農業従事者でもない私がなぜこのお芝居を観ることになったのか、そこにはひとりの女性の熱い思いがありました。
2月5日のブログにご登場の女性が、その三日後に再度お訪ねくださいました。ご自分用と共に三人の知人へプレゼントとしてお選びくださったのですが、その三人というのがこのお芝居に登場する役者さんだったんですね。女性も劇団わらび座に勤務するスタッフさんのお一人で、主に広い庭を管理する園芸部に所属していました。
ではなぜ同じ会社の、いわばお仲間に草履のプレゼントを思い立ったのか。それはこのお芝居のストーリーにありました。
石川理紀之助が立て直しを図っていた農村で、ある年大水害に見舞われます。村の半分に達する田畑が氾濫した川の水に流され、農民は地主へ納めるコメさえなくしました。途方に暮れる農民たちを励ましながら、理紀之助は地主に対し、その年だけ納めるコメの量を半分にしてほしいと交渉します。その代り翌年には倍にして返すと…。
理紀之助はかねてから、農村の貧困脱出に農作物だけではない収入源を考えていました。そのひとつが「ワラジ」です。丈夫なワラジは当時鉱山で高く売れ、暇を見つけてはワラジを編むことを農民に奨励したんですね。
しかし地主は理紀之助の懇願を拒否します。そんなに上手く農民が働くわけはないと思ったのでしょう。何度頼んでも拒否される押し問答の最中、舞台に登場するのはそれまでに農民たちがひたすら編み続けた無数のワラジなんですね。その数を見た地主が、理紀之助をはじめとする村人の願いを聞き入れるというくだりがあるわけです。
舞台に登場したワラジは、役者さんも含めたわらび座スタッフさんたちで作り上げたんだそうです。その姿を見ていた先の女性が、三人の役者さんに対して私の草履をプレゼントしたいと思ってくれたんですね。
そしてお買い上げの際、私に観劇チケットを二枚プレゼントしてくれました。その日帰宅しカミさんと娘たちに話すと、娘二人も観たいと言います。そこで15日にお伺いする旨、いただいていた名刺からメールを送りました。
お芝居は素晴らしかったです。理紀之助の偉業を80分のドラマで観せてくれました。歴史に名を遺す人は、同時に言葉も遺します。
『寝ていて人を起こすことなかれ』。自らが寝ている状態で人に起きろと言っても、それは聞く耳を持ってくれないでしょう。一日の労働時間を少しでも長くとるため、理紀之助は朝三時に版木を叩いて村人を起こして歩きました。
2007年1月15日のブログに、「早起きは三文の得」を書いています。理紀之助の考えはまさにこれだったんですね。
そしてラストのカーテンコール。三人の役者さんが並び観客から拍手喝采を浴びる最中、その間隙に先の女性が角館草履を三つ携え、理紀之助役の役者さんへ手渡しました。意外な品物に『おっ!』と驚いた表情を見せる役者さん。これまで九年の草履職人生活で、私の草履がプレゼントされるシーンを目の当たりにする機会は少なかったです。しかも興奮冷めやらぬこの場面ですから、私の感激も並々ならぬものでしたよ。
幕が下りたあと、女性が私を見つけ駆け寄ってくれました。草履お買い上げのお礼と、チケットプレゼントのお礼と、そして感激のお礼を込めて熱く握手しました。50歳最後の一日は、なかなか出来ない感動の記念日だったと思います。