5年前までは合唱曲を聴くことはなかった。
昔から歌謡曲にも関心が無かったし、フォークソングやロックなど思春期にちょっとかじったけどすぐに冷めてしまった。
歌を伴う音楽を聴くのは30代になって子守唄に関心を持ったくらいか。
子供の時から歌を歌うのが大嫌いだったせいなのか。
中学校時代に合唱大会というものが確かあったが、歌った曲も場面も殆ど記憶が無い。
しかしそれでも強烈に記憶に残っている出来事があった。
それは中学3年生の時に地区の学校の合唱大会で、「木琴」という歌を歌ったことであった。
このことは今まで何度か記事にしたので繰り返しになるが、歌の大嫌いな私が、心底歌うことに熱中した生涯唯一の出来事であった。
もちろん一緒に歌ったクラスの連中がとても仲が良く、結束が高かったこともあるが、この「木琴」という曲の悲しい旋律が、思春期真っ盛りだった当時の私の心に強く刻みこまれたからであろう。
中学を卒業し、高校時代、大学時代、就職してからも合唱曲とは一切無縁であったが、何故かこの曲の旋律が忘れられなかった。
何かふとしたことで、この旋律が心に流れてくることがあった。
そしてこの曲をもう一度聴きたいと思ったが、この曲の題名は既に忘れてしまっていた。
曲の出だしの歌詞が、「妹よ」で始まるので、「妹よ」という曲だと思い込んでいた。
何度か探したが見つけることは出来なかった。
しかし今から5年度ほど前に、Youtubeでやっとこの曲を見つけた。
それは実に32年ぶりの再会であった。
この曲は、まさに、中学3年生の時に歌った、あの思い出の曲であった。
この時に感じた強烈な感動は今でも忘れられない。
その時この曲が「木琴」という名前の曲であることに今さらのように気が付いた。
この出会いの後にこのYoutubeの演奏を何度も何度も聴いた。
砂漠でのどが渇いて水を飲みなくなってどうにもならなくなった人間が、オアシスに出会って水をむさぼるように飲み続けるようなものだった。
この出会いと「木琴」を2か月くらい毎日飽きずに聴き続けたことで、何か心の重しが軽くなると同時に、もっと合唱曲を聴きたいという気持ちに目覚めた。
これがこの時を境に合唱曲にのめり込んだきっかけだ。
つい先日、合唱曲人気ランキングなるものをたまたまインターネットで見つけたら、お勧めの曲として、「木琴」と同じ作曲者の「十字架(クルス)の島」(山本和夫作詞、岩河三郎作曲)という曲が紹介されていた。
早速Youtubeで探してみたら、見つかった。
曲想は「木琴」と同じような構成を取るが、「木琴」が暗く悲しく曲を終えるのに対し、この「十字架(クルス)の島」は明るく希望を感じさせるような終わりかたをしていた。
この曲は、かつて江戸時代に幕府から弾圧を受けて悲惨な最後を遂げた隠れキリシタンの無念の悲しみを歌ったものだ。
中間部の讃美歌と終結部を除き、曲は暗く、重く、悲痛だ。ところどころ「木琴」を彷彿させる。
Youtubeで記載されている歌詞を読みながら曲を聴くと一層、悲痛さを増すが、残酷な歴史の暗部をただ単に訴えるのではなく、ひとりひとりの人間の命の尊さと、どんなに障害がたちはだかっても、正しいことを信じ続けることの大切さ、人間の精神の強さのようなものが伝わってくる。
この曲が名曲であり、人気曲である所以であろう。
昭和の時代の曲であるが、世界情勢が悪くなりつつ現在において、この曲の価値はますます高まっていくと思う。
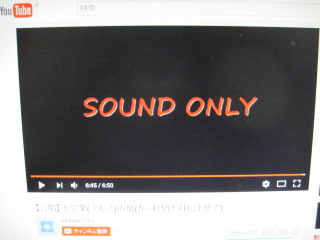
昔から歌謡曲にも関心が無かったし、フォークソングやロックなど思春期にちょっとかじったけどすぐに冷めてしまった。
歌を伴う音楽を聴くのは30代になって子守唄に関心を持ったくらいか。
子供の時から歌を歌うのが大嫌いだったせいなのか。
中学校時代に合唱大会というものが確かあったが、歌った曲も場面も殆ど記憶が無い。
しかしそれでも強烈に記憶に残っている出来事があった。
それは中学3年生の時に地区の学校の合唱大会で、「木琴」という歌を歌ったことであった。
このことは今まで何度か記事にしたので繰り返しになるが、歌の大嫌いな私が、心底歌うことに熱中した生涯唯一の出来事であった。
もちろん一緒に歌ったクラスの連中がとても仲が良く、結束が高かったこともあるが、この「木琴」という曲の悲しい旋律が、思春期真っ盛りだった当時の私の心に強く刻みこまれたからであろう。
中学を卒業し、高校時代、大学時代、就職してからも合唱曲とは一切無縁であったが、何故かこの曲の旋律が忘れられなかった。
何かふとしたことで、この旋律が心に流れてくることがあった。
そしてこの曲をもう一度聴きたいと思ったが、この曲の題名は既に忘れてしまっていた。
曲の出だしの歌詞が、「妹よ」で始まるので、「妹よ」という曲だと思い込んでいた。
何度か探したが見つけることは出来なかった。
しかし今から5年度ほど前に、Youtubeでやっとこの曲を見つけた。
それは実に32年ぶりの再会であった。
この曲は、まさに、中学3年生の時に歌った、あの思い出の曲であった。
この時に感じた強烈な感動は今でも忘れられない。
その時この曲が「木琴」という名前の曲であることに今さらのように気が付いた。
この出会いの後にこのYoutubeの演奏を何度も何度も聴いた。
砂漠でのどが渇いて水を飲みなくなってどうにもならなくなった人間が、オアシスに出会って水をむさぼるように飲み続けるようなものだった。
この出会いと「木琴」を2か月くらい毎日飽きずに聴き続けたことで、何か心の重しが軽くなると同時に、もっと合唱曲を聴きたいという気持ちに目覚めた。
これがこの時を境に合唱曲にのめり込んだきっかけだ。
つい先日、合唱曲人気ランキングなるものをたまたまインターネットで見つけたら、お勧めの曲として、「木琴」と同じ作曲者の「十字架(クルス)の島」(山本和夫作詞、岩河三郎作曲)という曲が紹介されていた。
早速Youtubeで探してみたら、見つかった。
曲想は「木琴」と同じような構成を取るが、「木琴」が暗く悲しく曲を終えるのに対し、この「十字架(クルス)の島」は明るく希望を感じさせるような終わりかたをしていた。
この曲は、かつて江戸時代に幕府から弾圧を受けて悲惨な最後を遂げた隠れキリシタンの無念の悲しみを歌ったものだ。
中間部の讃美歌と終結部を除き、曲は暗く、重く、悲痛だ。ところどころ「木琴」を彷彿させる。
Youtubeで記載されている歌詞を読みながら曲を聴くと一層、悲痛さを増すが、残酷な歴史の暗部をただ単に訴えるのではなく、ひとりひとりの人間の命の尊さと、どんなに障害がたちはだかっても、正しいことを信じ続けることの大切さ、人間の精神の強さのようなものが伝わってくる。
この曲が名曲であり、人気曲である所以であろう。
昭和の時代の曲であるが、世界情勢が悪くなりつつ現在において、この曲の価値はますます高まっていくと思う。
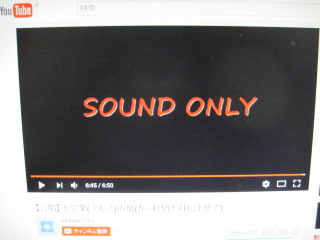

















未だに人前では歌う事はないですね。
ご紹介いただきました木琴と十字架の島を聴きました
有り難うございます。
https://www.youtube.com/watch?v=1fTTzAlfNF8
https://www.youtube.com/watch?v=-VgrbF1rmLI
紹介した合唱曲、お聴き下さりありがとうございました。
Tommyさんも私と同じだったのですね。
人前で歌ったことで、どんなに恥ずかしい思いをしたかわかりません。
社会人になって飲み会などで無理やり歌わさせられるのが苦痛でした。
今は音楽を聴いたり楽器を演奏する、それだけで十分満足です。