
晴れの国・岡山も田植えもほぼ終わりホッとしたところです。
京都のdogdaliさんのブログでは、田植えを終えると昔は柏餅をいただいたのだとか・・・。
ようちゃんのブログでも紹介されていたように、当地では田植えが終わることを<代みて>と言われています。
そして、その代みてのおやつといえば<けんびき焼き>です。
実家では、子どもの頃この時季になると母がミョウガの葉で包んだけんびき焼きを作ったものでした。
なつかしいこの季節のおやつを真似て作ってみますが、材料も作り方も分からずネット検索を頼っています。母も亡くなりすでに30年。聞きたいときに親は無し・・・です。
夫に聞けば我が家でもけんびき焼きは作っていたとか・・・。
同居家族が多く大人・子ども合わせて10人分を作り、祖母がほうろく鍋で香ばしく焼いていたんだとか。昔々の家族模様が見えてきます。
やはり我が家でも姑も見送り、けんびき焼きの作り方を知る者はいません。
農作業の疲れを癒す<けんびき焼き>の素朴な初夏の味を伝えていきたいと、今年もああでもない、こうでもないと試行錯誤でございます。
< 腰を伸し 初夏の香りに 母しのぶ >
京都のdogdaliさんのブログでは、田植えを終えると昔は柏餅をいただいたのだとか・・・。
ようちゃんのブログでも紹介されていたように、当地では田植えが終わることを<代みて>と言われています。
そして、その代みてのおやつといえば<けんびき焼き>です。
実家では、子どもの頃この時季になると母がミョウガの葉で包んだけんびき焼きを作ったものでした。
なつかしいこの季節のおやつを真似て作ってみますが、材料も作り方も分からずネット検索を頼っています。母も亡くなりすでに30年。聞きたいときに親は無し・・・です。
夫に聞けば我が家でもけんびき焼きは作っていたとか・・・。
同居家族が多く大人・子ども合わせて10人分を作り、祖母がほうろく鍋で香ばしく焼いていたんだとか。昔々の家族模様が見えてきます。
やはり我が家でも姑も見送り、けんびき焼きの作り方を知る者はいません。
農作業の疲れを癒す<けんびき焼き>の素朴な初夏の味を伝えていきたいと、今年もああでもない、こうでもないと試行錯誤でございます。

< 腰を伸し 初夏の香りに 母しのぶ >















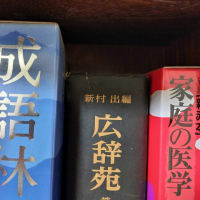




言われるのですね。 いい響きです。
田植えも一段落して ホッと一息 このけんびき焼きを
作って皆で楽しんだわけですね。
ほうろくで香ばしく焼かれ ミョウガが香ってくるようです。
これは、珍しい
実は、田舎で「けんびき」と言えば、病気のことです
具体的にどのような病をいうのかは、知りませんが
祖母などは、「けんびき」て言葉を使っていました
田植えの疲れで調子の悪い身体を労わる為のおやつなのでしょうね
茗荷の葉は、食べるのですか?
香りを楽しむだけですか?
田舎では、特別なものは、ありませんでしたが
「鱧のお吸い物」が、度々食卓にのった記憶が
懐かしい。
エンドウ豆のあんこを作って わたしも ちょっと変わり種のみょうが餅を焼いてみました。
でも やはり こちらのような 昔ながらのなじみがあるのが いいです。
肩引きとも書いて、肩凝りや疲労などの病気を表す言葉だそうですね。
農作業が続いた後の、一斉休みの日に、甘いものと、
血流を良くするといわれる茗荷の組み合わせを食べるのは、理にかなっていると思います。
先人の知恵は、本当にすごいですね。
ところで、しまそだちさんも記していましたが、
茗荷の葉ごと食べるのでしょうか?
ちーちゃんが、機会があれば作ってみたいといってネットを調べていましたが、食べ方までは載っていなかったので
ぜひ、教えてください。
当地では柏モチです。
今は和菓子屋さんで買ってきます。
季節が来ると食べたくなるあんこの入ったモチを柏の葉でつつみます。
明日紹介のため、買ってきてアップしておきますね。
所変われば食べるものも変わる。面白いですね。
みょうがの葉でつつんでおられるのですね。
今は柏の葉がなくてしません。野茨の葉でつつんだりもしていましたよ。次世代にも伝えていきたいですね。
年間通して晴れの日が多い岡山県です。
災害も少なく、温暖で過ごしやすいので東日本から移住される方もいらっしゃるようです。
穏やかで危機感がないのがちょっと心配です。
ミョウガのいい香りを昔ほど感じないのは大人になったからでしょうか・・・。
海の幸・鱧というところがしまそだちさんですね。
わが家では鱧は度々とは・・・(-.-)
けんびきは確か肩引きだと思います。田植えで疲れた肩を癒す意味があると聞きます。
茗荷の香りは子どもの頃は苦手でした。葉っぱの付かないのが欲しい・・・と思うのはやはり味わいの分からない子どもですね。
茗荷の葉は焼くと薄くなってきますが食べるには・・・ちょっとね。
作りましたか・・・エンドウ豆の餡はいかがでしたか?
実家ではミョウガ焼きといってました。岡山の郷土食ではけんびき焼きといいますね。
母の作るミョウガ焼きは米粉だったのかなーと食感から想像します。よく作り方を聞いておくべきでしたね。
県北の道の駅では地元主婦の手作りのけんびき焼きを売ってました。
けんびきは肩こりを表す言葉なんでしょうね。
岡山の郷土料理も豊富ですが、素朴な田舎のおやつですね。
茗荷は子どもには好まれない香でしたが、季節を感じさせる香は大人にはとても味わい深いです。蕗や山椒もそうですね。
茗荷の葉は、桜餅の葉のようにはないですね。剥がしても幾らかはり付いていて、そのまんま・・・いただくことになります。
ちーちゃんにぜひ一度お願いしましょう。(^_^.)
郷土料理はだんだん薄らいできますね。
こうして残しておきたいものがたくさんあります。岡山ならではのものがね。
柏餅はやはり柏の葉がなくて、山帰来の葉で包んでいます。
上新粉を使うと食感がいいですね。サクッとして良い味わいです。