

昨年のNHK古典芸能鑑賞会での「土蜘」のTVオンエアは録画しつつのチラ見だけ。ついつい舞踊だからと後回しになっていてしっかり観ていなかった。能仕立ての松羽目物の舞踊劇ということで、菊之助が演舞場の「船弁慶」の静御前と同じ衣裳を着ているなぁ、千筋の蜘蛛の糸を初めて観ておお綺麗だなぁということくらいしか覚えていなかった。今回はイヤホンガイドも聞きながら真面目に観た。

【新古演劇十種の内 土蜘(つちぐも)】
九代目團十郎の「歌舞伎十八番」の向こうをはって、五代目菊五郎が「新古演劇十種」と銘打った作品のひとつとして初演。
あらすじは公式サイトよりほぼ引用。
「病いの床に伏す源頼光は、家来の平井保昌の見舞いや侍女の胡蝶のあでやかな舞いに、しばし心癒されています。そこへ何処からか、比叡山の智籌(ちちゅう=くもの音読みからとイヤホンガイド)と名乗る僧が現れ、病平癒の祈祷を申し出ます。太刀持の音若が様子を怪しみ忠告すると、智籌は蜘蛛の本性を顕し、姿を消します。
頼光館では、番卒の太郎、次郎、藤内が土蜘退治を祈願して、巫子の榊に諫めの舞いを舞わせます。一方、土蜘を追って荒れ塚に行き着いた保昌と頼光の四天王の前に、ついに鬼神の姿をした土蜘の精が現れ、壮絶な闘いが繰り広げられます。」
今回の配役は以下の通り。
僧智籌実は土蜘の精:菊五郎 源頼光:富十郎
太刀持音若:鷹之資 侍女胡蝶:菊之助
巫子榊:芝雀 石神:玉太郎
平井保昌:左團次 渡辺源氏綱:権十郎
坂田公時:亀蔵 ト部季武:市蔵
碓井貞光:亀三郎 番卒太郎:仁左衛門
番卒次郎:梅玉 番卒藤内:東蔵

いつも元気いっぱいイメージの富十郎が病鉢巻をつけた源頼光というギャップがちょっと面白いというと不遜だろうか。息子の鷹之資を太刀持で身近につけているのも「閻魔と政頼」の閻魔と後見の時よりもしっかりしてきている。
菊之助の侍女胡蝶は昨年の静御前の時よりも顔のメイクが格段にうまくなっていると思えた。壺折の衣裳での舞も美しくて惚れ惚れする。

夜中に頼光の部屋に訪れた智籌と名乗る僧形の者。菊五郎の斜めに睨む目が効いて妖しさたっぷりの前半の姿にぴったりだ。私はどうもこういう目に弱いようで買った舞台写真は全てこの目線の表情ばかり(^^ゞ太刀持音若に影の形の怪しさを指摘されて土蛛の本性を現して手に持つ数珠で割けた口の形を表して台の上に上がるなどの前半の見せ所もいい。鷹之資の台詞がやっぱり子ども子どもしているが、少しずつしっかりしてきているのだなぁとも思えて可愛さも感じるようになった。
四天王たちが刀を頭上に基本は横にかざしての立ち回り。これも能の立ち回りのお約束なのだという。前半でも蜘蛛の糸の繰り出しがあってお弟子さんたちが上手く巻き取るのに感心。一太刀浴びた土蛛は姿を消す。

間狂言部分の番卒は、仁左衛門・梅玉・東蔵という大ご馳走の配役!東蔵の馬子の玉太郎が石神さまで出ていて、親子や爺孫での共演が何組あるのだろうという感じ。玉太郎も台詞はホント下手くそだが、舞台での集中力はついてきたのがよくわかった。巫子の榊が頭に狂言の女性役がつける美男鬘のアレンジのような布をつけているのは、まさに狂言風だ。こんな拵えで芝雀の巫女が面をとった石神さんをおんぶしていくのは微笑ましかった。番卒の退場時も先頭の仁左衛門が足先まで神経を行き届かせたステップだったのを見てまた惚れてしまった(^^ゞ

後半の舞台。能のツクリ物(「紅天女」で観ている)のような塚が舞台中央に出てくる。四天王たちが刀傷の血汐の後を追って塚の唸り声にたどりつき、塚をくずすと後シテの土蛛が姿を現す。ツクリ物の布が取り払われて細い柱に張られた紙テープの蜘蛛の巣状のものが目を引いていい(毎回お弟子さんたちがつくるのだそうだ)。
それを破って妖怪の隈取をした菊五郎が出てくるが、もう本当に立派。気力が漲る土蛛だ。派手に蜘蛛の糸を投げかけるので菊十郎ともうひとりの後見が絶妙のタイミングで菊五郎の掌から糸のついた端の紙?を受け取ってくるくると巻き取っていくのを嬉しく見てしまう。
四天王たちが通力を持った刀で追い詰め、ついに土蛛の首をかき切った。と思いきや、最後は座頭役者として赤い台の上に登り、左右に居並ぶ頼光、四天王や捕り方たちに糸がかかって迫力の絵面!引っ張りの見得となって幕となるという、贅沢な舞台だった。



これは土蛛をつとめる座頭と周囲の息が合わないとここまで盛り上がれないのではないだろうかと思えた。初めての「土蛛」を堪能した。長唄も名曲ということだが、予習をサボったツケがきてちょっと残念。次回観るまでには長唄も調べて、どこかにあるはずの録画を探してもう一度じっくり聞き取れるように準備したいものだと思った(忘れることも多いのだけれど(^^ゞ)。
ちょっと追記:ネット検索して見つけた「土蜘」の詞章のサイト(能の方かもしれないが(^^ゞ)

ここでちょっと脱線だが、源頼光と四天王たちの名前がズラズラ出てくると劇団☆新感線の「朧の森に棲む鬼」を連想(笑)源頼光といえば大江山の酒呑童子退治でも有名(それも「朧~」の主要人物で出てきた)。さて「蜘蛛」というのも大江山の鬼と同様に大和政権にまつろわぬ民扱いされた集団として史実に残っているということだった。だから源頼光に退治させる話として一貫性があるのだろうなぁと、そちらにも興味が湧いてきた。
写真は「顔見世」と「千穐楽」の2枚の幕がかかった歌舞伎座正面。六条亭さん撮影分の掲載の快諾をいただきましたm(_ _)m
11/18昼の部①「種蒔三番叟」「素襖落」
11/18昼の部②初めて泣けた「吃又」
11/18昼の部③仁左衛門の「御所五郎蔵」
11/25千穐楽夜の部①「宮島のだんまり」「三人吉三巴白浪」
11/25千穐楽夜の部②「山科閑居」













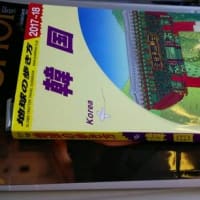
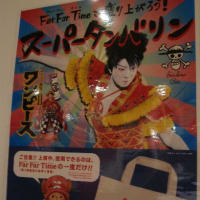

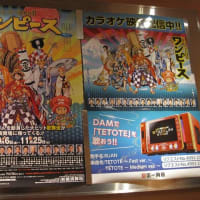
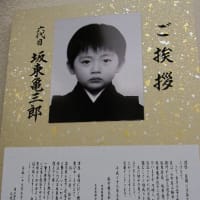
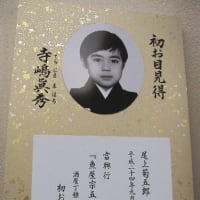

「土蜘」はお能でも歌舞伎でも人気曲なのに見たのは初めてでした(苦笑)
以前、中学生が仕舞で蜘蛛の糸を撒いていたのは見ましたが・・(わたしもやってみたい・・・笑)
菊五郎さんもすばらしく、堪能できました。
こちらにはTB届いていませんでしたので、再度よろしくおねがいいたします。
それとTBの件です。TB承認制をとられている方のところにする場合は、できたかどうかすぐにわからないので念のために名前欄のURL欄に該当記事のURLを入れるようにはしています。とりあえず名前欄でご確認お願いします。少し間をあけてまたTBにトライしてみま~す(^O^)/
長唄の土蜘蛛、テープダビングしましょうか?
私的眼目は、クルクルクルっクルリンパっ。と糸を巻き取るエキスパートな後見!!だからいつも本編はあんまり気にしてません(おいおい)
でも、妖怪&バケモノ好きでもあるので、幸せなひとときでした♪
昨日は十二月大歌舞伎の初日観劇のため、コメントが遅くなりました。また写真の件、わざわざ記事中にふれていただき、ありがとうございました。
菊五郎家の『土蜘』も、かなり能を意識しているようですが、そこは歌舞伎、かなり歌舞伎としての見せ場がたっぷりあって堪能できました。
『信濃路紅葉鬼揃』は、衣裳も玉三郎さんの洗練された美意識で統一された素晴らしいものでしたよ。
TBをうちました。
やはり顔見世での「土蜘蛛」ということで、本当に豪華な顔ぶれで「土蜘蛛」デビューさせてもらって幸運だったと思います。
>最初の花道の出、低音のセリフ、これでゾクゾク......私も最近になって菊五郎さんの低音の魅力がわかってきました。若い頃はこんなお声じゃなかったですよねぇ。昨日の大宮ミニオフ会で辰之助が亡くなって菊五郎劇団の中で辰之助がやっていたような立役がどんどん回ってきたというお話はなるほど~と思いました。そういった中で兼ねる役者として大成してしまったということですね。長唄の土蜘蛛、お借りできると有難いですm(_ _)m
★かしまし娘さま
妖怪変化物ってやっぱり楽しいですよね。
>糸を巻き取るエキスパートな後見!!......菊十郎さん、私も大好きです。毎回あのツクリ物の蜘蛛の巣も菊十郎さんたちが作っているのだと知り、歌舞伎のベテランのお弟子さんたち無しにはやはり歌舞伎公演は成り立たないのだと痛感しました。
(注)かしまし娘さんの記事は名前をクリックすると読んでいただけますのでご紹介m(_ _)m
★六条亭さま
お能は「紅天女」しか観ていないのですが、ツクリ物とかも見ているのでなかなか面白いと思って見ました。歌舞伎の「土蜘」を観たのだから、能の「土蜘蛛」も観るといいかもしれないと思えてきました。まぁあせらずゆっくりいきますが(^^ゞ
12月歌舞伎座初日の綺麗な写真も見せていただきました。朝日が当たった初日の幕が綺麗でした。昼の部は今度の日曜日9日に拝見します。玉三郎丈の能取り物の「信濃路紅葉鬼揃」も楽しみがいよいよ増してきました(^O^)/