BS朝日サタデーシアターの12/4のオンエアを録画しておいた映画「おろしや国酔夢譚」を何回かに分けて鑑賞。実話にもとづいた井上靖原作の小説が映画化され、封切られた頃から1回観てみたいと思っていた作品。
Amazonの「おろしや国酔夢譚 特別版」のDVDの情報はこちら
以下、上記よりあらすじをほぼ引用。
1782年、船で遭難した大黒屋光太夫(緒形拳)らはおよそ9ヶ月の漂流の末にカムチャッカ半島に漂着。光太夫ら生き残った6人の日本人たちは日本へ帰る日を夢見ながら極寒のロシア・シベリア地方を転々としていく。やがて光太夫は学者キリル・ラックスマン(オレグ・ヤンコフスキー)と友人になり、彼らの協力で女王エカテリーナ二世(マリナ・ブラディ)との面会が可能となるが……。
BS朝日「サタデーシアター」の項はこちら
Wikipediaの「おろしや国酔夢譚」の項もこちら

1992年制作だから20年も前の作品で、出演者がみんな若い。一緒に観ていた娘も驚いた。緒形拳にはカッコいいと感嘆。西田敏行も、劇団☆新感線の「SHIROH」の松平伊豆守でお気に入りの江守徹も痩せていてこんなにイケメンだったのと聞いてくる。沖田浩之もこの頃は頑張っていたのになぁ。
漂流民が日本に戻れた例はないという現実に立ち向かい、あきらめずに道を求める光太夫の姿が周囲の人々を動かしていく。光太夫に会った何人もの知識人が彼の生きざまに心を動かされて著作の中で言及するくらいになっていた。友となったラックスマンがコーダユ=光太夫ほどの人間が船頭をやっているような日本は素晴らしい国に違いない。だからこそ対等に交易を結ぶべきと主張してくれたことに胸を打たれた。緒方拳がそれだけの人物像を存在感をもって抑えた演技でくっきり浮かび上がらせているのががよい。
ドラマチックな歴史的な実話を実に淡々と描き出しているのがまたよい。漂流した17人が漂流の中で、異国の地で一人二人と死んでいく。庄蔵(西田敏行)は凍傷で片足を切断し生きる希望を失ってロシア正教のキリストに生きる支えを求め、それまでの漂流民と同様に日本語教師となった。若い新蔵(沖田浩之)は現地のロシア人女性とともに生きることにしてイルクーツクにとどまった。
日本に帰る望みを抱き続ける3人がペテルブルクまで行き、光太夫がラックスマンの助力を得てエカテリーナ女帝の謁見をようやく実現する。夏の宮殿に逗留中の女帝は、話題の人物コーダユに会ってもよいという気になったのだ。漂流して多くの仲間を失ったことに同情し、光太夫に何か歌えと命じる。

ここで緒方拳の光太夫が人形ぶりで浄瑠璃で「俊寛」を語り出したのに驚いた。確かに当時の日本で広く楽しまれたのは人形浄瑠璃だろう。流刑にあった俊寛が恩赦のかなった丹波少将成経たちが乗る赦免船が遠ざかっていくくだりだ。日本語のわからない女帝は途中でやめさせて退席しようとするのに追いすがって必死の嘆願。女帝は心を動かされたというよりも、大の男が涙を流して訴える姿に気まぐれのように帰国を許す。
女帝の親書を届ける船に乗せられて蝦夷地まできたものの、鎖国中の幕府はすぐに受け入れてくれない。碇を下した船の中で命を落とす小市(川谷拓三)が哀れ。
ついに若い磯吉(米山望文)と二人だけで日本の地を踏めた光太夫だが、罪人護送用の駕籠で江戸へ運ばれる。休息で駕籠から出された海辺で海の向こうに別れてきた仲間たちを思って再び「俊寛」を語る。再会は「未来で」というくだりにまた胸を打たれる。帰りたかったろうに時代が状況がゆるさなかった仲間たち・・・・・。

20年前に映画を観ていたら、この「俊寛」の場面の素晴らしさが理解できなかったろうと思う。当時、あまり評価が高くなかったように記憶しているが、これは作品を味わうには少し修行がいるだろうなぁと納得した次第。

Amazonの「おろしや国酔夢譚 特別版」のDVDの情報はこちら
以下、上記よりあらすじをほぼ引用。
1782年、船で遭難した大黒屋光太夫(緒形拳)らはおよそ9ヶ月の漂流の末にカムチャッカ半島に漂着。光太夫ら生き残った6人の日本人たちは日本へ帰る日を夢見ながら極寒のロシア・シベリア地方を転々としていく。やがて光太夫は学者キリル・ラックスマン(オレグ・ヤンコフスキー)と友人になり、彼らの協力で女王エカテリーナ二世(マリナ・ブラディ)との面会が可能となるが……。
BS朝日「サタデーシアター」の項はこちら
Wikipediaの「おろしや国酔夢譚」の項もこちら

1992年制作だから20年も前の作品で、出演者がみんな若い。一緒に観ていた娘も驚いた。緒形拳にはカッコいいと感嘆。西田敏行も、劇団☆新感線の「SHIROH」の松平伊豆守でお気に入りの江守徹も痩せていてこんなにイケメンだったのと聞いてくる。沖田浩之もこの頃は頑張っていたのになぁ。
漂流民が日本に戻れた例はないという現実に立ち向かい、あきらめずに道を求める光太夫の姿が周囲の人々を動かしていく。光太夫に会った何人もの知識人が彼の生きざまに心を動かされて著作の中で言及するくらいになっていた。友となったラックスマンがコーダユ=光太夫ほどの人間が船頭をやっているような日本は素晴らしい国に違いない。だからこそ対等に交易を結ぶべきと主張してくれたことに胸を打たれた。緒方拳がそれだけの人物像を存在感をもって抑えた演技でくっきり浮かび上がらせているのががよい。
ドラマチックな歴史的な実話を実に淡々と描き出しているのがまたよい。漂流した17人が漂流の中で、異国の地で一人二人と死んでいく。庄蔵(西田敏行)は凍傷で片足を切断し生きる希望を失ってロシア正教のキリストに生きる支えを求め、それまでの漂流民と同様に日本語教師となった。若い新蔵(沖田浩之)は現地のロシア人女性とともに生きることにしてイルクーツクにとどまった。
日本に帰る望みを抱き続ける3人がペテルブルクまで行き、光太夫がラックスマンの助力を得てエカテリーナ女帝の謁見をようやく実現する。夏の宮殿に逗留中の女帝は、話題の人物コーダユに会ってもよいという気になったのだ。漂流して多くの仲間を失ったことに同情し、光太夫に何か歌えと命じる。

ここで緒方拳の光太夫が人形ぶりで浄瑠璃で「俊寛」を語り出したのに驚いた。確かに当時の日本で広く楽しまれたのは人形浄瑠璃だろう。流刑にあった俊寛が恩赦のかなった丹波少将成経たちが乗る赦免船が遠ざかっていくくだりだ。日本語のわからない女帝は途中でやめさせて退席しようとするのに追いすがって必死の嘆願。女帝は心を動かされたというよりも、大の男が涙を流して訴える姿に気まぐれのように帰国を許す。
女帝の親書を届ける船に乗せられて蝦夷地まできたものの、鎖国中の幕府はすぐに受け入れてくれない。碇を下した船の中で命を落とす小市(川谷拓三)が哀れ。
ついに若い磯吉(米山望文)と二人だけで日本の地を踏めた光太夫だが、罪人護送用の駕籠で江戸へ運ばれる。休息で駕籠から出された海辺で海の向こうに別れてきた仲間たちを思って再び「俊寛」を語る。再会は「未来で」というくだりにまた胸を打たれる。帰りたかったろうに時代が状況がゆるさなかった仲間たち・・・・・。

20年前に映画を観ていたら、この「俊寛」の場面の素晴らしさが理解できなかったろうと思う。当時、あまり評価が高くなかったように記憶しているが、これは作品を味わうには少し修行がいるだろうなぁと納得した次第。














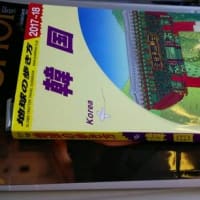
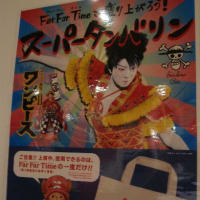

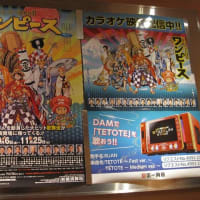
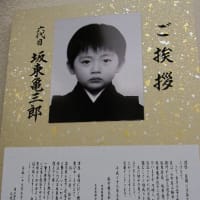
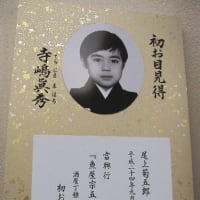

ほれぼれした映画でした!!大好きな一本です!!
ぴかちゅうさんがご覧になってUPされてて
びっくり!・・・とともに嬉しいです!
今度お会いした時は、『黄金の日々』に続く第二弾・・
として、盛り上がれること間違いなしですねっ!(笑)
さて・・・私はといえば・・
まだまだ何もしらない(今も知らないけど・・)頃、見たので
『俊寛』を語られるシーンは記憶にありません(泣)!
でも、宮殿の豪華さは覚えてる・・(笑)
また、もう一度是非観てみたいです!!
宮殿の豪華さは映画の封切り当時の宣伝画像でも力が入っていた記憶があります。そのくらい気になった映画ですが、観ることかなわずでした。
最近、地デジ放送で観たいものがない時はBSの民放の映画などを観ることが増えて、これも前の週の映画を観て、次週の予告で観なくてはならないと録画予約をその場で入れたのがよかったのです。
「俊寛」を語る場面が2回です!かなり力が入った扱いなんですよね。女帝に何か歌えと言われ、とっさに義太夫を語り、それが自分の想いを代弁するような俊寛僧都の最後のクライマックスの場面が身体も動いて語ってしまったことで、追いすがった時の滂沱の涙となったのかぁ、なるほど感情の流れが自然で素晴らしいと感心しきりでした。
何かの機会でまた観ることができたら、最後をしっかりと堪能してくださいませ!!