31歳で作家デビューを果たした吉村昭。
歴史小説で有名だが、初期は短編小説が多い。また、生涯を通じて書き続けた。
昭和48年(1973)、46歳で発表した「蛍」(中公文庫)は、いわゆる吉村小説の傾向である「死」が全編のテーマの短編集。戦争と病気をテーマに心情描写と視覚描写が交錯する吉村ワールドを展開する。
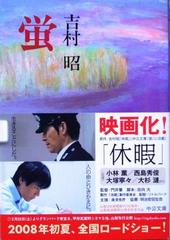
また、昭和53年(1978)に発表した「帽子」(中公文庫)は、9つの短編からなる。夫婦を機軸に、男女の機微を描いた。
その瞬間の妙がたまらなく身に迫る。

昭和57年(1982)には10の短編からなる「遅れた時計」(中公文庫)。男女が基調ではあるが、男女の情念や人の生を描く短編小説集である。
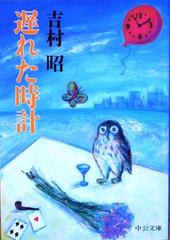
吉村は「短編が好きで小説家になったようなもの」「短編は書くこと、そこに私の生きる意味がある」とまで言う。
あの数々の歴史長編に携わりながら、300を超える短編を書き続けた。
史実に基づき淡々と描く歴史物から生活の香りのするエッセイ、はたまた、さまざまな場面を通し男と女の生を語る短編小説まで。
このギャップがたまらない。
歴史小説で有名だが、初期は短編小説が多い。また、生涯を通じて書き続けた。
昭和48年(1973)、46歳で発表した「蛍」(中公文庫)は、いわゆる吉村小説の傾向である「死」が全編のテーマの短編集。戦争と病気をテーマに心情描写と視覚描写が交錯する吉村ワールドを展開する。
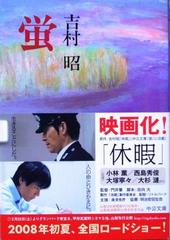
また、昭和53年(1978)に発表した「帽子」(中公文庫)は、9つの短編からなる。夫婦を機軸に、男女の機微を描いた。
その瞬間の妙がたまらなく身に迫る。

昭和57年(1982)には10の短編からなる「遅れた時計」(中公文庫)。男女が基調ではあるが、男女の情念や人の生を描く短編小説集である。
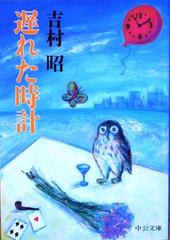
吉村は「短編が好きで小説家になったようなもの」「短編は書くこと、そこに私の生きる意味がある」とまで言う。
あの数々の歴史長編に携わりながら、300を超える短編を書き続けた。
史実に基づき淡々と描く歴史物から生活の香りのするエッセイ、はたまた、さまざまな場面を通し男と女の生を語る短編小説まで。
このギャップがたまらない。



















