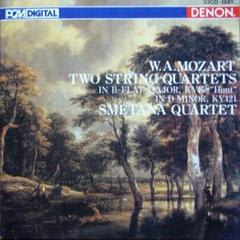鶏料理です。脂身の皮のカリカリ感、ほっこりした繊維、そして、たんぱくな味。そして、簡単で安価な一品。
くわ焼きは、昔、畑の合間に、鍬で野鳥などを焼いたのが始まりとか。
材料です。
鶏もも肉 1枚300㌘
ホウレンソウ 2分の1束
片栗粉 適量
粉サンショウ 適量
塩 適量
サラダ油
漬け汁(酒大さじ2、しょうゆ大さじ2、みりん大さじ3)
鶏肉はひと口大に切ります。パットなどに薄く塩をして並べ、上からも薄く塩をふります。そのまま5分おきます。
ホウレンソウは塩を加えた湯でゆで、冷水にとります。葉の向きをそろえて水気を絞り、食べやすい長さに切っておきます。
ボウルに漬け汁の調味料を合わせて、鶏肉を入れ、10分漬けます。
鶏肉をザルにあけます。5分から6分おいて、汁気をきるか、急ぐ特はペーパータオルなどでふき取ります。漬け汁は取っておきます。
鶏肉の前面に片栗粉をまぶしつけます。余分な粉も、はたかずに残します。
フライパンにサラダ油を温め、鶏肉を並べ入れます。中火でしっかり焼き色をつけ、肉の側面を見て、下から3分の1ほど白くなったら上下を返して同様に加熱します。片栗粉をよく焼くことで香ばしさが加わります。
漬け汁を回しかける。はしで鶏肉の上下を何度か返しながら、汁気がほとんどなくなるまでからめます。
器に鶏肉を盛ってホウレンソウを添え、粉サンショウをふります。
塩で肉の汁気を出し、そこにみりんが入った甘辛の漬け汁が染み入ります。10分ほどでちょうどよく染み込むとか。その風味を逃がさないように片栗粉で密封。その片栗粉が、焼けてカリカリ感が包み込みます。そのためにも加熱する前に汁気をきっておきましょう。
添えの野菜は口直しなので、味付けはしない。その代わり粉サンショウで味が引き締まります。
ホウレンソウのほかに、青菜や、ゆでたレタス、炒めたタマネギなど、たっぷりとどうぞ。
くわ焼きは、昔、畑の合間に、鍬で野鳥などを焼いたのが始まりとか。
材料です。
鶏もも肉 1枚300㌘
ホウレンソウ 2分の1束
片栗粉 適量
粉サンショウ 適量
塩 適量
サラダ油
漬け汁(酒大さじ2、しょうゆ大さじ2、みりん大さじ3)
鶏肉はひと口大に切ります。パットなどに薄く塩をして並べ、上からも薄く塩をふります。そのまま5分おきます。
ホウレンソウは塩を加えた湯でゆで、冷水にとります。葉の向きをそろえて水気を絞り、食べやすい長さに切っておきます。
ボウルに漬け汁の調味料を合わせて、鶏肉を入れ、10分漬けます。
鶏肉をザルにあけます。5分から6分おいて、汁気をきるか、急ぐ特はペーパータオルなどでふき取ります。漬け汁は取っておきます。
鶏肉の前面に片栗粉をまぶしつけます。余分な粉も、はたかずに残します。
フライパンにサラダ油を温め、鶏肉を並べ入れます。中火でしっかり焼き色をつけ、肉の側面を見て、下から3分の1ほど白くなったら上下を返して同様に加熱します。片栗粉をよく焼くことで香ばしさが加わります。
漬け汁を回しかける。はしで鶏肉の上下を何度か返しながら、汁気がほとんどなくなるまでからめます。
器に鶏肉を盛ってホウレンソウを添え、粉サンショウをふります。
塩で肉の汁気を出し、そこにみりんが入った甘辛の漬け汁が染み入ります。10分ほどでちょうどよく染み込むとか。その風味を逃がさないように片栗粉で密封。その片栗粉が、焼けてカリカリ感が包み込みます。そのためにも加熱する前に汁気をきっておきましょう。
添えの野菜は口直しなので、味付けはしない。その代わり粉サンショウで味が引き締まります。
ホウレンソウのほかに、青菜や、ゆでたレタス、炒めたタマネギなど、たっぷりとどうぞ。