
たて続けに2つの「野火」の映画を観た。
「野火」(のび)は、1951年に発表された大岡昇平の小説で、1959年に市川崑、そして2015年に塚本晋也による監督で映画化されたものである。
内容は、第2次世界大戦末期のフィリピン、レイテ島を舞台に、敗走する日本兵の飢えや人肉食いを、著者、大岡昇平の体験をもとに描いたものである。
市川崑監督の作品時代の1959年当時は、まだ先の戦争の実体験がわが国の社会全体に残っていた時代である。「ビルマの竪琴」(監督:市川崑)や「人間の条件」(監督:小林正樹)などに見られるように、戦争の記憶の残照が生々しくあったはずだ。
日本は満州(中国東北部)を支配下に置いたあと、1941年太平洋戦争がはじまると“大東亜共栄圏”の旗印のもと南方に攻め入ったが、戦争末期には敗走を重ねた。戦後、その戦争の実態はどうだったのかが、体験をもとに小説や映画で描かれていった。
映画「野火」は、主演の船越英二が熱演している。また、当時人気のロカビリアンだったミッキー・カーチスが好演している。
そして、半世紀が過ぎた。
東京・第25回多摩映画祭TAMA CINEMA FORUM(11月21日―29日開催)で、塚本晋也監督の映画「野火」が11月21日に上映された。
現在の2015年、なぜ「野火」という戦争を扱った映画なのか。
塚本監督は、多摩映画祭での上映のあとの今日マチ子(漫画家)、荻上チキ(評論家)とのトークで次のように語った。
「構想は20年前からあって、いつかはと思っていたが、きな臭い時代になって、今この映画を作らなければもう作れないのではないかと思った」
この映画で、塚本晋也は監督・脚本・製作などに加え、主演も兼ねていることからみても、その意気込みが伝わってくる。
時代的にモノクロの市川作品に対して、塚本作品は原色の南国の森林を著す濃緑が生々しい。その濃緑に血の赤が混じりこむ。画面から、戦争がもたらす残酷さと狂気がにじみ出る。
今日、世界中がきな臭い時代である。そして、70年前、日本は戦争をしていた。
今、戦争というものを考えるきっかけになる映画であろう。
「野火」(のび)は、1951年に発表された大岡昇平の小説で、1959年に市川崑、そして2015年に塚本晋也による監督で映画化されたものである。
内容は、第2次世界大戦末期のフィリピン、レイテ島を舞台に、敗走する日本兵の飢えや人肉食いを、著者、大岡昇平の体験をもとに描いたものである。
市川崑監督の作品時代の1959年当時は、まだ先の戦争の実体験がわが国の社会全体に残っていた時代である。「ビルマの竪琴」(監督:市川崑)や「人間の条件」(監督:小林正樹)などに見られるように、戦争の記憶の残照が生々しくあったはずだ。
日本は満州(中国東北部)を支配下に置いたあと、1941年太平洋戦争がはじまると“大東亜共栄圏”の旗印のもと南方に攻め入ったが、戦争末期には敗走を重ねた。戦後、その戦争の実態はどうだったのかが、体験をもとに小説や映画で描かれていった。
映画「野火」は、主演の船越英二が熱演している。また、当時人気のロカビリアンだったミッキー・カーチスが好演している。
そして、半世紀が過ぎた。
東京・第25回多摩映画祭TAMA CINEMA FORUM(11月21日―29日開催)で、塚本晋也監督の映画「野火」が11月21日に上映された。
現在の2015年、なぜ「野火」という戦争を扱った映画なのか。
塚本監督は、多摩映画祭での上映のあとの今日マチ子(漫画家)、荻上チキ(評論家)とのトークで次のように語った。
「構想は20年前からあって、いつかはと思っていたが、きな臭い時代になって、今この映画を作らなければもう作れないのではないかと思った」
この映画で、塚本晋也は監督・脚本・製作などに加え、主演も兼ねていることからみても、その意気込みが伝わってくる。
時代的にモノクロの市川作品に対して、塚本作品は原色の南国の森林を著す濃緑が生々しい。その濃緑に血の赤が混じりこむ。画面から、戦争がもたらす残酷さと狂気がにじみ出る。
今日、世界中がきな臭い時代である。そして、70年前、日本は戦争をしていた。
今、戦争というものを考えるきっかけになる映画であろう。












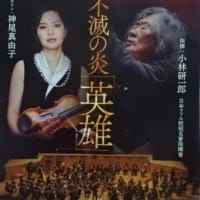

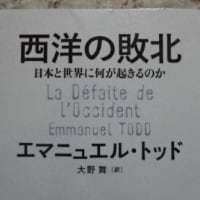










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます