
足音だけがついてくるのよヨコハマ……
横浜に馬車道があるのは有名だが、汽車道があるのはうかつにも最近知った。
「馬車道」は文字通り馬車が通った道で、江戸幕末に日米修好通商条約により開港させられ外国人居留地であった関内から港に到る道である。現在、JRの桜木町駅と関内駅の北側に、その名のみなとみらい線馬車道駅がある。
馬車道は、最初の関門である吉田橋から北へ進み、地下に潜っている馬車道駅がある本町通りに到る。まっすぐ本町通りを超えると万国橋に出て、その先は新港埠頭である。
では、汽車が通った廃線跡の「汽車道」とはどこか?
馬車道駅のある本町通りから続くみなとみらい大通りのすぐのところから、入江を縦断するように新港埠頭に細く延びた道が汽車道である。
地図を見ると、馬車道も汽車道も新港埠頭、つまり港に向かって延びている。
港の埠頭には、かつて貨物運送が主だった鉄道が通っていたのだ。しかも、ごく最近まで山下公園の脇を鉄道が走っていたのだ。
*電車道のこと
私が育った九州・佐賀の炭鉱町(杵島炭鉱)の大町には「電車道」があった。鉄道は電車でなく汽車(蒸気機関車)が通っていた時代である。
電車道とは、炭鉱夫の移動(通勤)にも使われていた石炭を運ぶトロッコ電車の線路道で、大町町から隣の江北町まで繋がっていた。佐賀県で電車が走っているのは、ここ大町だけだと自慢げに話す人もいたが、東京などの都会で走っている電車を雑誌などで見ていた私は、そのあまり評価されない自慢を含んだ話に、これも電車と言うのかなあと疑心を抱いていた。
子どもの頃は、好奇心いっぱいだ。私たちは、学校帰りに友だちと連れ立って、遠回りだというのに訳もなく電車道を歩いたのだった。
ときに悪ガキたちは、走ってきた電車の最後部にカエルのように跳び付いて、しばらくぶら下がった状態で乗っていて、得意げに跳び下りたりした。だから、教師はしばしば朝礼などで、電車に跳び乗りしないようにという忠告を発しなければならなかった。冒険に危険はつきものだ。
炭鉱が閉山になり、電車も通らなくなりレールもなくなった後も、その道は電車道と呼ばれている。
*汽車が運んだ日本の成長の道
日本最初の鉄道は、1872(明治5)年開業の、新橋駅(後の汐留貨物駅、現廃止)~横浜駅(現・桜木町駅)間である。つまり、横浜は鉄道発祥の地ともいえる。
その後、鉄道は京阪神の方へ路線を延ばし続け、1889(明治22)年に新橋駅~神戸駅間の全線が開業して現在の東海道線の元ができた。
同じ年の1889(明治22)年に、甲武鉄道により新宿~立川-八王子間が開業した。その後1895(明治28)年、新宿~牛込-飯田町(現・飯田橋)が開通し、1904(明治37)年に御茶ノ水まで延長、後のJR中央線の元となった。
鉄道は日本の産業の発展とともに、動脈から毛細血管が広がるように全国に延びていく。
*汽車道を歩く
横浜の港である埠頭に鉄道が敷かれたのはいつであろう。
「日本鉄道旅行地図帳」を見ると、1911(明治44)年に横浜鉄道により貨物線の東神奈川~海神奈川(神奈川沖)間が開通している。これが、横浜港における最初の貨物線である。
同年、横浜(現・桜木町)から横浜埠頭の横浜港荷扱所間が開通している。この臨港線は通称税関線と呼ばれていた。この路線の跡が現在の汽車道となるのだが、なぜかこの路線は「日本鉄道旅行地図帳」には記載されていない。
このあと、1917(大正6)年に鶴見~高島間、そして東神奈川~東高島(最初は高島)間が開通し、臨海への貨物線の拠点となった高島駅から次々と支線が敷かれ、1965(昭和40)年には山下埠頭まで延びた。
しかし、一方で戦後は、次第に陸上輸送がトラックへの移転や横浜線の貨物輸送の減少などに伴い、臨海の駅の統合や支線の廃止が相次いだ。
山下ふ頭まで延びた路線も、1986(昭和61)年に廃止となった。その路線は、今は赤レンガ倉庫の南あたりから象の鼻パークを経て山下公園入口まで「山下臨海プロムナード」という遊歩道になっている。
上に記した新港埠頭に残った廃線跡を、1997(平成9)年に整備したのが「汽車道」である。
新港埠頭にある「海上保安資料館」を出たあと、汽車道を歩いた。道には、2本のレールが綺麗に並んでいる。過疎化した地方で残る、ひなびた廃線跡には決して見えない。都会の、観光地の真ん中の廃線跡が、横浜の汽車道だ。
汽車道は、入江に3つの橋梁で繋いだ2つの人工島によって新港埠頭地区まで繋げた細長い道である。かつてのレールがそのまま埋まっているが、ウッドデッキを設えてあるので歩くのは心地いい。
その横浜の歴史の足跡を歩くと、(少し無理がある表現だが)足音だけがついてくる。
見上げると、空にはボックスが流れるように飛んでいる。いつの間に、横浜はこんな風景になったのだろう。
ともあれ、空の道に行ってみよう。
(写真は汽車道の上を飛ぶエア・キャビン)
*
2月1日、このブログ「ブルーライト・ヨコハマ②」が、「 Yahoo 」 に登場した。
Yahooに取り上げられたのは初めてのことである。
横浜に馬車道があるのは有名だが、汽車道があるのはうかつにも最近知った。
「馬車道」は文字通り馬車が通った道で、江戸幕末に日米修好通商条約により開港させられ外国人居留地であった関内から港に到る道である。現在、JRの桜木町駅と関内駅の北側に、その名のみなとみらい線馬車道駅がある。
馬車道は、最初の関門である吉田橋から北へ進み、地下に潜っている馬車道駅がある本町通りに到る。まっすぐ本町通りを超えると万国橋に出て、その先は新港埠頭である。
では、汽車が通った廃線跡の「汽車道」とはどこか?
馬車道駅のある本町通りから続くみなとみらい大通りのすぐのところから、入江を縦断するように新港埠頭に細く延びた道が汽車道である。
地図を見ると、馬車道も汽車道も新港埠頭、つまり港に向かって延びている。
港の埠頭には、かつて貨物運送が主だった鉄道が通っていたのだ。しかも、ごく最近まで山下公園の脇を鉄道が走っていたのだ。
*電車道のこと
私が育った九州・佐賀の炭鉱町(杵島炭鉱)の大町には「電車道」があった。鉄道は電車でなく汽車(蒸気機関車)が通っていた時代である。
電車道とは、炭鉱夫の移動(通勤)にも使われていた石炭を運ぶトロッコ電車の線路道で、大町町から隣の江北町まで繋がっていた。佐賀県で電車が走っているのは、ここ大町だけだと自慢げに話す人もいたが、東京などの都会で走っている電車を雑誌などで見ていた私は、そのあまり評価されない自慢を含んだ話に、これも電車と言うのかなあと疑心を抱いていた。
子どもの頃は、好奇心いっぱいだ。私たちは、学校帰りに友だちと連れ立って、遠回りだというのに訳もなく電車道を歩いたのだった。
ときに悪ガキたちは、走ってきた電車の最後部にカエルのように跳び付いて、しばらくぶら下がった状態で乗っていて、得意げに跳び下りたりした。だから、教師はしばしば朝礼などで、電車に跳び乗りしないようにという忠告を発しなければならなかった。冒険に危険はつきものだ。
炭鉱が閉山になり、電車も通らなくなりレールもなくなった後も、その道は電車道と呼ばれている。
*汽車が運んだ日本の成長の道
日本最初の鉄道は、1872(明治5)年開業の、新橋駅(後の汐留貨物駅、現廃止)~横浜駅(現・桜木町駅)間である。つまり、横浜は鉄道発祥の地ともいえる。
その後、鉄道は京阪神の方へ路線を延ばし続け、1889(明治22)年に新橋駅~神戸駅間の全線が開業して現在の東海道線の元ができた。
同じ年の1889(明治22)年に、甲武鉄道により新宿~立川-八王子間が開業した。その後1895(明治28)年、新宿~牛込-飯田町(現・飯田橋)が開通し、1904(明治37)年に御茶ノ水まで延長、後のJR中央線の元となった。
鉄道は日本の産業の発展とともに、動脈から毛細血管が広がるように全国に延びていく。
*汽車道を歩く
横浜の港である埠頭に鉄道が敷かれたのはいつであろう。
「日本鉄道旅行地図帳」を見ると、1911(明治44)年に横浜鉄道により貨物線の東神奈川~海神奈川(神奈川沖)間が開通している。これが、横浜港における最初の貨物線である。
同年、横浜(現・桜木町)から横浜埠頭の横浜港荷扱所間が開通している。この臨港線は通称税関線と呼ばれていた。この路線の跡が現在の汽車道となるのだが、なぜかこの路線は「日本鉄道旅行地図帳」には記載されていない。
このあと、1917(大正6)年に鶴見~高島間、そして東神奈川~東高島(最初は高島)間が開通し、臨海への貨物線の拠点となった高島駅から次々と支線が敷かれ、1965(昭和40)年には山下埠頭まで延びた。
しかし、一方で戦後は、次第に陸上輸送がトラックへの移転や横浜線の貨物輸送の減少などに伴い、臨海の駅の統合や支線の廃止が相次いだ。
山下ふ頭まで延びた路線も、1986(昭和61)年に廃止となった。その路線は、今は赤レンガ倉庫の南あたりから象の鼻パークを経て山下公園入口まで「山下臨海プロムナード」という遊歩道になっている。
上に記した新港埠頭に残った廃線跡を、1997(平成9)年に整備したのが「汽車道」である。
新港埠頭にある「海上保安資料館」を出たあと、汽車道を歩いた。道には、2本のレールが綺麗に並んでいる。過疎化した地方で残る、ひなびた廃線跡には決して見えない。都会の、観光地の真ん中の廃線跡が、横浜の汽車道だ。
汽車道は、入江に3つの橋梁で繋いだ2つの人工島によって新港埠頭地区まで繋げた細長い道である。かつてのレールがそのまま埋まっているが、ウッドデッキを設えてあるので歩くのは心地いい。
その横浜の歴史の足跡を歩くと、(少し無理がある表現だが)足音だけがついてくる。
見上げると、空にはボックスが流れるように飛んでいる。いつの間に、横浜はこんな風景になったのだろう。
ともあれ、空の道に行ってみよう。
(写真は汽車道の上を飛ぶエア・キャビン)
*
2月1日、このブログ「ブルーライト・ヨコハマ②」が、「 Yahoo 」 に登場した。
Yahooに取り上げられたのは初めてのことである。











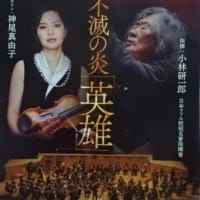

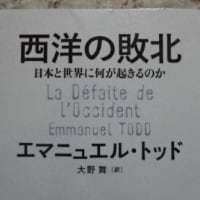











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます