
流れてきたのか 流されたのか
どこへ行こうか気の向くままに メリケン波止場が見える丘
ここは横浜 日ノ出 野毛坂 桜木町
*野毛坂から野毛山公園へ
伊勢山皇大神宮から成田山横浜別院をあとにして、野毛坂へやってきた。
野毛坂の交差点から「野毛坂」を登ったところに緑の小高い丘がある。ここが動物園もある「野毛山公園」である。
「野毛山」は、明治のころは横浜の豪商たちの邸宅や別荘地帯であった。ところが関東大震災によって崩壊し、その後、公園として整備された。
1887(明治20)年、野毛山にイギリス人のヘンリー・スペンサー・パーマーによって横浜水道の配水池が設置され、日本初の近代水道が始まった。
野毛坂を登りはじめたところに、黒い鉄の筒のようなものが飾られてある。古い大砲の筒かと思った。
・「日本近代水道・最古の水道管」
これは、明治の日本政府に依頼されたヘンリー・スペンサー・パーマーの指導によって作られた水道管の一部の筒だった。
野毛坂からすぐのところで公園のなかに入っていくと、石碑があった。
・「中村汀女句碑」(野毛山公園内)
中村汀女は、明治生まれの昭和の代表的な俳人である。
熊本生まれで、官僚だった夫の転勤とともに東京、横浜、仙台、名古屋など転々とし、後に東京に定住した。どうしてここに碑があるのだろうと思った。
横浜にも一時住んでここで俳句を作ったというのであれば、ちょっと弱い理由ではなかろうか。弘法大師とは違うのだから。
さらに公園の奥に入っていくと、また幕末の知識人の碑がある。
・「佐久間象山顕彰碑」(野毛山公園内)
佐久間象山は、江戸時代後期の信濃松代藩士の思想家で、朱子学、洋学、蘭学、砲術などあらゆるジャンルに長けた知識人であった。吉田松陰、勝海舟らに強い影響を与えた。開国佐幕のために奔走したが、京都で攘夷派により暗殺された。
横浜開港を強く唱えたということで、ここに顕彰碑が建てられた。
この近くに常夜燈のようなものが建っている。
昭和初期、ラジオが普及し始めたころ、全国に建てたラジオの発信塔だという。このような塔は、初めて目にした。
・「ラジオ塔」(野毛山公園内)
説明板には以下の文が記してある。
「このラジオ塔はラジオの聴取契約者が百万人を越えた記念に、日本放送協会が昭和七年に全国の著名な公園や広場に建てる計画が進められ、昭和七年度から昭和八年度中に四十一ヵ所が完成して、その中に野毛山公園も選ばれ建塔されたものです。
正式名/公衆用聴取施設 全高/三メートル 建塔/昭和七年十一月十九日」
※説明文には読点(、)がなかったので筆者が付した。
この区域を離れ「野毛山動物園」のところへ移ったが、動物園には入らなかった。ちなみに、動物園は入場無料となっている。
*野毛山公園展望台の丘へ
動物園地区から道路上に架かっている吊り橋を渡って、南の展望台のある区域に入った。
しばらく歩くと、外国人の胸像があった。
㉚「ヘンリー・スペンサー・パーマー胸像」(野毛山公園内)
1887(明治20)年、横浜に日本最初の近代水道が創設された。この場所は野毛山貯水場の跡であり、「近代水道発祥の地」となっている。
野毛山公園に入ったすぐのところに、「日本近代水道・最古の水道管の筒」があった。イギリス人のヘンリー・スペンサー・パーマーはその生みの父である。
当時、海辺を埋め立てて造られた横浜は、いい水ではなかった。パーマーの設計・監督により、相模川と道志川の合流点(現・津久井町)に求めた水源から44Km離れた野毛山の貯水場に運ばれた水は、浄水され市内に給水された。
パーマーは、横浜のほかにも大阪、神戸、函館、東京などの水道計画にも貢献したとある。
さてとこの一帯を見まわすと、中央部分に何やらモニュメントのようなものが建っている。
・「オリンピック記念碑」(野毛山公園内)
1964(昭和39)年開催された東京オリンピックの記念碑である。
この記念碑には3面に競技のレリーフが飾られている。まず目に入ってくるのは、記念の題字とともにバレーボールをしている女子選手の像である。そして、サッカー、バスケットボールをしている選手像がある。
女子バレーボールは、当時、“東洋の魔女”と呼ばれて日本中を熱狂させ、金メダルを獲得したのだから、正面に飾られて当然だろう。
面白いのは、躍動している選手像の右上に競技名が、例えば「バレーボール」、「バスケットボール」と描かれているのだが、ボールを蹴(け)っているサッカーのところは「蹴球」となっているのである。
つまり、フットボールであるが、まだサッカーが日本では定着していなかったためか漢字になっている。これではラグビーと区別がつかない。ちなみに、日本のプロサッカーリーグ(Jリーグ)が開始・開催されたのは1993(平成5)年である。
ところで、なぜ東京の代々木競技場でなく、ここに東京オリンピックの記念碑があるのかと思っていたら、バレーボール、サッカー、バスケットボール(予選)の3種目が横浜市で行われたとのこと。これを記念して、1966(昭和41)年に設立されたものである。
その先に、3階建てのコンクリート枠組みの建築物がある。
・「野毛山公園展望台」
野毛山公園自体が高い丘になっているので、さらにその上の見晴らし台からは、少し殺風景な建物ではあるが、見晴らしがよさそうである。
1階にトイレがあり、上に行くには階段だけでなくエレベーターも備えてある。が、ここは歩いていく。
上からは、四方の横浜の街並みが見えた。
みなとみらいのランドタワーも観覧車も見える。
横浜港の方からぐっと右(南東)の方に、街並みの彼方に、何やら並んだ3つの塔が見える。
うん? 異様だ。いや、威容だ。街並みから、あの塔だけが浮いている。いや、家やビルの乱立する街並みから置き去りにされている。
あれは見たことがある、と思いだした。横浜港の南、確か根岸方面だ。よく見れば、塔の周りは緑に囲まれている。だとすると、根岸公園の旧競馬場の廃墟に違いない。
あたかも、森(ジャングル)の繁みのなかにポツンとあるマヤ文明の遺跡のようだ。
(写真)
※「日本発祥の地を求めて、横浜⑦ 根岸の旧競馬場の廃墟」(2023-09-18)
https://blog.goo.ne.jp/ocadeau3/e/4336444ad59110b65ff8f20735a84a15?fm=entry_awc
野毛山公園を出て、「横浜迎賓館」を見ながら、日ノ出町の駅に向かった。
そこから、細い急な下り階段である「天神坂」を下りて、「日ノ出町」駅に出た。
日ノ出町駅から桜木町の駅に向かった。
野毛大通りより大岡川寄りの脇の通りを歩き、もうすっかり日が落ちて、灯りがともる「野毛小路」の飲み屋が連なる通りを歩いた。
*
桜木町から石川町までJRの電車で移動し、中華街の満州(中国東北)料理店に向かった。
ビールのあと紹興酒を飲みながら、この日の料理は以下の通り。
まず、「羊肉」「手羽先」「豚マメ」3種の串焼き。
「パクチー、ネギ、青唐辛子の東北和え」
「きのこと牛肉のオイスターソース炒め」
「ラム肉、カキ、漬け白菜の酸味土鍋」
最後に、「焼きビーフン」
今回、野菜類を一つと思って、「パクチー、ネギ、青唐辛子の東北和え」をとった。生の野菜を良い加減の味に和えてあったのだが、何せ青唐辛子がその美味しさを失わせるほど辛い。
しばらく顔をしかめて食べたあと、青唐辛子を除いて(あるいは微量に残して)食べればいい感じの柔らかい味になるとわかった。そして、残った青唐辛子は味の薄いビーフンなどに付け交ぜれば、これまたいい味に変容するとわかった。
それと、タイ料理ではないカメムシ臭いのパクチーの味も収穫だった。これから、自分で家で作る料理にも使おうと思った。
どこへ行こうか気の向くままに メリケン波止場が見える丘
ここは横浜 日ノ出 野毛坂 桜木町
*野毛坂から野毛山公園へ
伊勢山皇大神宮から成田山横浜別院をあとにして、野毛坂へやってきた。
野毛坂の交差点から「野毛坂」を登ったところに緑の小高い丘がある。ここが動物園もある「野毛山公園」である。
「野毛山」は、明治のころは横浜の豪商たちの邸宅や別荘地帯であった。ところが関東大震災によって崩壊し、その後、公園として整備された。
1887(明治20)年、野毛山にイギリス人のヘンリー・スペンサー・パーマーによって横浜水道の配水池が設置され、日本初の近代水道が始まった。
野毛坂を登りはじめたところに、黒い鉄の筒のようなものが飾られてある。古い大砲の筒かと思った。
・「日本近代水道・最古の水道管」
これは、明治の日本政府に依頼されたヘンリー・スペンサー・パーマーの指導によって作られた水道管の一部の筒だった。
野毛坂からすぐのところで公園のなかに入っていくと、石碑があった。
・「中村汀女句碑」(野毛山公園内)
中村汀女は、明治生まれの昭和の代表的な俳人である。
熊本生まれで、官僚だった夫の転勤とともに東京、横浜、仙台、名古屋など転々とし、後に東京に定住した。どうしてここに碑があるのだろうと思った。
横浜にも一時住んでここで俳句を作ったというのであれば、ちょっと弱い理由ではなかろうか。弘法大師とは違うのだから。
さらに公園の奥に入っていくと、また幕末の知識人の碑がある。
・「佐久間象山顕彰碑」(野毛山公園内)
佐久間象山は、江戸時代後期の信濃松代藩士の思想家で、朱子学、洋学、蘭学、砲術などあらゆるジャンルに長けた知識人であった。吉田松陰、勝海舟らに強い影響を与えた。開国佐幕のために奔走したが、京都で攘夷派により暗殺された。
横浜開港を強く唱えたということで、ここに顕彰碑が建てられた。
この近くに常夜燈のようなものが建っている。
昭和初期、ラジオが普及し始めたころ、全国に建てたラジオの発信塔だという。このような塔は、初めて目にした。
・「ラジオ塔」(野毛山公園内)
説明板には以下の文が記してある。
「このラジオ塔はラジオの聴取契約者が百万人を越えた記念に、日本放送協会が昭和七年に全国の著名な公園や広場に建てる計画が進められ、昭和七年度から昭和八年度中に四十一ヵ所が完成して、その中に野毛山公園も選ばれ建塔されたものです。
正式名/公衆用聴取施設 全高/三メートル 建塔/昭和七年十一月十九日」
※説明文には読点(、)がなかったので筆者が付した。
この区域を離れ「野毛山動物園」のところへ移ったが、動物園には入らなかった。ちなみに、動物園は入場無料となっている。
*野毛山公園展望台の丘へ
動物園地区から道路上に架かっている吊り橋を渡って、南の展望台のある区域に入った。
しばらく歩くと、外国人の胸像があった。
㉚「ヘンリー・スペンサー・パーマー胸像」(野毛山公園内)
1887(明治20)年、横浜に日本最初の近代水道が創設された。この場所は野毛山貯水場の跡であり、「近代水道発祥の地」となっている。
野毛山公園に入ったすぐのところに、「日本近代水道・最古の水道管の筒」があった。イギリス人のヘンリー・スペンサー・パーマーはその生みの父である。
当時、海辺を埋め立てて造られた横浜は、いい水ではなかった。パーマーの設計・監督により、相模川と道志川の合流点(現・津久井町)に求めた水源から44Km離れた野毛山の貯水場に運ばれた水は、浄水され市内に給水された。
パーマーは、横浜のほかにも大阪、神戸、函館、東京などの水道計画にも貢献したとある。
さてとこの一帯を見まわすと、中央部分に何やらモニュメントのようなものが建っている。
・「オリンピック記念碑」(野毛山公園内)
1964(昭和39)年開催された東京オリンピックの記念碑である。
この記念碑には3面に競技のレリーフが飾られている。まず目に入ってくるのは、記念の題字とともにバレーボールをしている女子選手の像である。そして、サッカー、バスケットボールをしている選手像がある。
女子バレーボールは、当時、“東洋の魔女”と呼ばれて日本中を熱狂させ、金メダルを獲得したのだから、正面に飾られて当然だろう。
面白いのは、躍動している選手像の右上に競技名が、例えば「バレーボール」、「バスケットボール」と描かれているのだが、ボールを蹴(け)っているサッカーのところは「蹴球」となっているのである。
つまり、フットボールであるが、まだサッカーが日本では定着していなかったためか漢字になっている。これではラグビーと区別がつかない。ちなみに、日本のプロサッカーリーグ(Jリーグ)が開始・開催されたのは1993(平成5)年である。
ところで、なぜ東京の代々木競技場でなく、ここに東京オリンピックの記念碑があるのかと思っていたら、バレーボール、サッカー、バスケットボール(予選)の3種目が横浜市で行われたとのこと。これを記念して、1966(昭和41)年に設立されたものである。
その先に、3階建てのコンクリート枠組みの建築物がある。
・「野毛山公園展望台」
野毛山公園自体が高い丘になっているので、さらにその上の見晴らし台からは、少し殺風景な建物ではあるが、見晴らしがよさそうである。
1階にトイレがあり、上に行くには階段だけでなくエレベーターも備えてある。が、ここは歩いていく。
上からは、四方の横浜の街並みが見えた。
みなとみらいのランドタワーも観覧車も見える。
横浜港の方からぐっと右(南東)の方に、街並みの彼方に、何やら並んだ3つの塔が見える。
うん? 異様だ。いや、威容だ。街並みから、あの塔だけが浮いている。いや、家やビルの乱立する街並みから置き去りにされている。
あれは見たことがある、と思いだした。横浜港の南、確か根岸方面だ。よく見れば、塔の周りは緑に囲まれている。だとすると、根岸公園の旧競馬場の廃墟に違いない。
あたかも、森(ジャングル)の繁みのなかにポツンとあるマヤ文明の遺跡のようだ。
(写真)
※「日本発祥の地を求めて、横浜⑦ 根岸の旧競馬場の廃墟」(2023-09-18)
https://blog.goo.ne.jp/ocadeau3/e/4336444ad59110b65ff8f20735a84a15?fm=entry_awc
野毛山公園を出て、「横浜迎賓館」を見ながら、日ノ出町の駅に向かった。
そこから、細い急な下り階段である「天神坂」を下りて、「日ノ出町」駅に出た。
日ノ出町駅から桜木町の駅に向かった。
野毛大通りより大岡川寄りの脇の通りを歩き、もうすっかり日が落ちて、灯りがともる「野毛小路」の飲み屋が連なる通りを歩いた。
*
桜木町から石川町までJRの電車で移動し、中華街の満州(中国東北)料理店に向かった。
ビールのあと紹興酒を飲みながら、この日の料理は以下の通り。
まず、「羊肉」「手羽先」「豚マメ」3種の串焼き。
「パクチー、ネギ、青唐辛子の東北和え」
「きのこと牛肉のオイスターソース炒め」
「ラム肉、カキ、漬け白菜の酸味土鍋」
最後に、「焼きビーフン」
今回、野菜類を一つと思って、「パクチー、ネギ、青唐辛子の東北和え」をとった。生の野菜を良い加減の味に和えてあったのだが、何せ青唐辛子がその美味しさを失わせるほど辛い。
しばらく顔をしかめて食べたあと、青唐辛子を除いて(あるいは微量に残して)食べればいい感じの柔らかい味になるとわかった。そして、残った青唐辛子は味の薄いビーフンなどに付け交ぜれば、これまたいい味に変容するとわかった。
それと、タイ料理ではないカメムシ臭いのパクチーの味も収穫だった。これから、自分で家で作る料理にも使おうと思った。












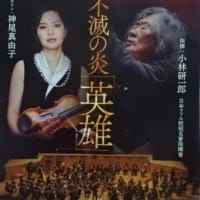

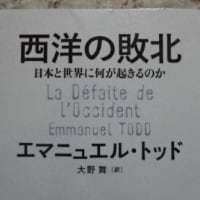










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます