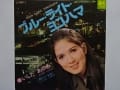ことの始まりは、こうだった。
去年の末、横浜の港を散策した。山下公園から埠頭の赤レンガ倉庫、汽車道、エア・キャビンに乗るなど港の周辺を歩いた。そのことは、当ブログ「ブルーライト・ヨコハマ」①~④に書いた。
そのとき、みなとみらい線、元町・中華街駅を出発してホテルニューグランドに向かおうとした矢先に、通りの脇に「日本洋裁業発祥記念碑」を見つけた。こんなところに、日本洋裁の発祥の地があったのかと、思いもよらない発見に嬉しくなった。
横浜には、日本発祥とされるものや出来事が多いようだ。
それをきっかけに、湘南の士が調べてくれた横浜発祥地の跡地・記念碑を巡り、4月28日に横浜を歩いた。
記念碑の多くには、それについての解説文が付いている。発祥地の散策に基づく案内とともに、その解説文をもとに概略を記した。
*「日本洋裁業発祥記念碑」から、「電信創業の地」まで
13時30分、みなとみらい線「元町・中華街駅」を出発する。
➀「日本洋裁業発祥記念碑」(メトロタワー山下町前)
元町・中華街駅の山下公園寄りの出口を出たら、すぐにある。ビルの前に植えられた木に紛れて婦人の銅像と記念の小塔が立っている。これが日本洋裁業発祥の記念碑である。(写真)
碑文によると、「1863年 (文久3年) 英国人ミセス・ピアソンが 横浜居留地97番にドレス ・メーカーを開店したのが横浜の洋裁業の始まりである」とある。
明治の西洋開花ブームになっても、日本では和服の慣習が長く続いた。洋裁業の普及とあいまって、一般大衆に洋服が急速に普及したのは戦後のことである。戦後、ミシンの普及とともに女性のファッションは花開く。
ここから「ホテルニューグランド」に出る。古い建物が残る横浜だが、このホテルは威厳がある。
「スパゲッティ・ナポリタンの発祥」とされるホテルで、予約が取れなかったが寄ってみる。やはり1階カフェの前では並んで待っている人がいるので、この日もナポリタンを食するのは諦める。いずれ、一度は食しないといけない。
ホテルニューグランドを出ると、前はもう「山下公園」である。
山下公園には、横浜市と姉妹都市であるアメリカ・サンディエゴ市から贈られた「水の守護神像」、北原白秋詩の童謡で有名な「赤い靴はいてた女の子像」、在日インド人協会から寄贈された「インド水塔」など、多くの記念碑や建造物がある。
②「西洋理髪発祥の地」(山下公園)
山下公園のなかに、白い円形の像がある。よく見ると、髪を真ん中から分けた男の頭で、これが「西洋理髪発祥の地」の記念碑である。
日本の明治政府によって、一般に言われる「断髪令」である「散髪脱刀令」が発せられたのは1871(明治4)年。これによりちょん髷(まげ)からザンギリ頭の西洋開花へ加速度が増すことになる。
それより先駆けること2年前の1869(明治2)年、横浜にわが国初の「西洋理髪店」が開業した。しかし、この山下公園の地で開業されたということではなく、ここに記念碑が建てられたということである。
*2022(令和4)年2月21日、「西洋理髪発祥の地」を伝えるモニュメントの除幕式が、横浜市の横浜中華街で行われた。この地で、明治初期に日本人が経営する初めての西洋理髪店が開業したことを記念して、中華街大通りの中ほどに新たに碑が建てられた。
山下公園を出てすぐのシルクセンターの前に、石碑と柵の奥に女性の裸像がある。
〇「英一番館跡碑」(山下町)
幕末、横浜が開港した時に、来日したイギリス人のウイリアム・ケズウィックが居留地一番館で貿易を始めた。当時、そこに建てられた英一番館と呼ばれた建物の碑で、碑には、当時の建物の様子も描かれている。
明治の中頃、東京・丸の内にできた「三菱一号館」を始めとした赤煉瓦のオフィス街の「一丁倫敦(ロンドン)」は、ここ横浜の英一番館を意識して創られたのかもしれない。
すぐ近くの横浜開港資料館に隣接して、開港広場公園がある。
〇「日米和親条約調印の地」(開港広場内)
開港広場公園に、1854(安政元)年の「日米和親条約」を締結(調印)した記念の碑がある。
よく見ると、記念碑は二つある。見過ごしそうな細い立柱には「日米和親条約締結の地」とあり、目立つ丸い球の碑には「日米和親条約調印の地」と記されている。
この先の日本大通りに、パンの写真の付いた碑がある。
③「近代のパン発祥の地」(日本大通)
幕末、横浜開港とともに外国との貿易が増大するに伴い、幕府はこの地に日用食品街を設けた。1860(万延元)年、その一角でフランス人にパンの製法を習った内海兵吉がパン屋を始めたのが近代のパンの発祥とされ、パンの元祖「富田屋」として知られた。
日本大通り交差点近くの、駐車場前の道路に沿って、何気なく建てられたような碑がある。
④「消防救急発祥之地」(日本大通)
この地に、1968(明治初)年から旧外国人居留地の消防隊が置かれていた。この「消防救急発祥之地」の碑の奥には、「旧居留地消防隊地下貯水槽」の遺構が公開されている。そこで、ガラス越しに地下水槽を覗くことができる。
この碑の前で、6、7人の若者の集団がいた。彼らも何やらリストの用紙を見つめ、写真を撮っている。訊くと、横浜市内の高校生で、やはり横浜発祥地を巡っているとのことだった。
この日は、周った碑のあちこちで、何度かこのような中学生、高校生の調査グループに出くわした。ゴールデンウイークに向けて、学校で課題としてレポート提出でも課されているのだろうか。でも、誰もが修学旅行のノリだ。
この碑の近くに、日本新聞博物館が入る「横浜情報文化センター」がある。
このビルの前に、「新聞少年の像」がある。
日本大通りに面した、横浜地方検察庁の前に碑がある。
⑤「電信創業の地」(日本大通)
1869(明治2)年に、この場所での横浜電信局と東京電信局間の、初めての電報による通信が始まった。
東京側にも、同名の碑が東京都中央区明石町に建っている。
さて次は、日本大通りから馬車道の方に向かってみよう。
去年の末、横浜の港を散策した。山下公園から埠頭の赤レンガ倉庫、汽車道、エア・キャビンに乗るなど港の周辺を歩いた。そのことは、当ブログ「ブルーライト・ヨコハマ」①~④に書いた。
そのとき、みなとみらい線、元町・中華街駅を出発してホテルニューグランドに向かおうとした矢先に、通りの脇に「日本洋裁業発祥記念碑」を見つけた。こんなところに、日本洋裁の発祥の地があったのかと、思いもよらない発見に嬉しくなった。
横浜には、日本発祥とされるものや出来事が多いようだ。
それをきっかけに、湘南の士が調べてくれた横浜発祥地の跡地・記念碑を巡り、4月28日に横浜を歩いた。
記念碑の多くには、それについての解説文が付いている。発祥地の散策に基づく案内とともに、その解説文をもとに概略を記した。
*「日本洋裁業発祥記念碑」から、「電信創業の地」まで
13時30分、みなとみらい線「元町・中華街駅」を出発する。
➀「日本洋裁業発祥記念碑」(メトロタワー山下町前)
元町・中華街駅の山下公園寄りの出口を出たら、すぐにある。ビルの前に植えられた木に紛れて婦人の銅像と記念の小塔が立っている。これが日本洋裁業発祥の記念碑である。(写真)
碑文によると、「1863年 (文久3年) 英国人ミセス・ピアソンが 横浜居留地97番にドレス ・メーカーを開店したのが横浜の洋裁業の始まりである」とある。
明治の西洋開花ブームになっても、日本では和服の慣習が長く続いた。洋裁業の普及とあいまって、一般大衆に洋服が急速に普及したのは戦後のことである。戦後、ミシンの普及とともに女性のファッションは花開く。
ここから「ホテルニューグランド」に出る。古い建物が残る横浜だが、このホテルは威厳がある。
「スパゲッティ・ナポリタンの発祥」とされるホテルで、予約が取れなかったが寄ってみる。やはり1階カフェの前では並んで待っている人がいるので、この日もナポリタンを食するのは諦める。いずれ、一度は食しないといけない。
ホテルニューグランドを出ると、前はもう「山下公園」である。
山下公園には、横浜市と姉妹都市であるアメリカ・サンディエゴ市から贈られた「水の守護神像」、北原白秋詩の童謡で有名な「赤い靴はいてた女の子像」、在日インド人協会から寄贈された「インド水塔」など、多くの記念碑や建造物がある。
②「西洋理髪発祥の地」(山下公園)
山下公園のなかに、白い円形の像がある。よく見ると、髪を真ん中から分けた男の頭で、これが「西洋理髪発祥の地」の記念碑である。
日本の明治政府によって、一般に言われる「断髪令」である「散髪脱刀令」が発せられたのは1871(明治4)年。これによりちょん髷(まげ)からザンギリ頭の西洋開花へ加速度が増すことになる。
それより先駆けること2年前の1869(明治2)年、横浜にわが国初の「西洋理髪店」が開業した。しかし、この山下公園の地で開業されたということではなく、ここに記念碑が建てられたということである。
*2022(令和4)年2月21日、「西洋理髪発祥の地」を伝えるモニュメントの除幕式が、横浜市の横浜中華街で行われた。この地で、明治初期に日本人が経営する初めての西洋理髪店が開業したことを記念して、中華街大通りの中ほどに新たに碑が建てられた。
山下公園を出てすぐのシルクセンターの前に、石碑と柵の奥に女性の裸像がある。
〇「英一番館跡碑」(山下町)
幕末、横浜が開港した時に、来日したイギリス人のウイリアム・ケズウィックが居留地一番館で貿易を始めた。当時、そこに建てられた英一番館と呼ばれた建物の碑で、碑には、当時の建物の様子も描かれている。
明治の中頃、東京・丸の内にできた「三菱一号館」を始めとした赤煉瓦のオフィス街の「一丁倫敦(ロンドン)」は、ここ横浜の英一番館を意識して創られたのかもしれない。
すぐ近くの横浜開港資料館に隣接して、開港広場公園がある。
〇「日米和親条約調印の地」(開港広場内)
開港広場公園に、1854(安政元)年の「日米和親条約」を締結(調印)した記念の碑がある。
よく見ると、記念碑は二つある。見過ごしそうな細い立柱には「日米和親条約締結の地」とあり、目立つ丸い球の碑には「日米和親条約調印の地」と記されている。
この先の日本大通りに、パンの写真の付いた碑がある。
③「近代のパン発祥の地」(日本大通)
幕末、横浜開港とともに外国との貿易が増大するに伴い、幕府はこの地に日用食品街を設けた。1860(万延元)年、その一角でフランス人にパンの製法を習った内海兵吉がパン屋を始めたのが近代のパンの発祥とされ、パンの元祖「富田屋」として知られた。
日本大通り交差点近くの、駐車場前の道路に沿って、何気なく建てられたような碑がある。
④「消防救急発祥之地」(日本大通)
この地に、1968(明治初)年から旧外国人居留地の消防隊が置かれていた。この「消防救急発祥之地」の碑の奥には、「旧居留地消防隊地下貯水槽」の遺構が公開されている。そこで、ガラス越しに地下水槽を覗くことができる。
この碑の前で、6、7人の若者の集団がいた。彼らも何やらリストの用紙を見つめ、写真を撮っている。訊くと、横浜市内の高校生で、やはり横浜発祥地を巡っているとのことだった。
この日は、周った碑のあちこちで、何度かこのような中学生、高校生の調査グループに出くわした。ゴールデンウイークに向けて、学校で課題としてレポート提出でも課されているのだろうか。でも、誰もが修学旅行のノリだ。
この碑の近くに、日本新聞博物館が入る「横浜情報文化センター」がある。
このビルの前に、「新聞少年の像」がある。
日本大通りに面した、横浜地方検察庁の前に碑がある。
⑤「電信創業の地」(日本大通)
1869(明治2)年に、この場所での横浜電信局と東京電信局間の、初めての電報による通信が始まった。
東京側にも、同名の碑が東京都中央区明石町に建っている。
さて次は、日本大通りから馬車道の方に向かってみよう。