
先日「ガレタッソ」のカウンターでボンソワ・ミカちゃんと話をしていた時、何故か色彩の話となり、そういえば昔イギリスで友達と色の種類を日本語と英語とで互いに言いあった際にこちらのストックがあまりに少なく完敗したことを思い出してしまった。
ただその時はたまたま青色限定だったけれど、こちらが青、水色、群青色、紫、薄紫、藍色、紺色といった具合にひいひい言いながら思い出したのに対して相手のほうは、コバルトブルーとかターコイズブルー、マリンブルー、スカイブルーと、何にでもブルーを付けて、そりゃないやろ的展開だっだのだけど、ともあれ自分の知識の浅薄さ加減にうんざりさせられたものでありました。
そしてそんな話から話題はさらに突き進み、やがて表意文字である漢字を言語に持つ日本語ならではの、生活の中に息づく特有の色彩感覚溢れる美しい色の表現がそれこそ無数にあるよねえということとなり、それを知るきっかけが大日本インキ化学工業株式会社(DIC)発行の「日本の伝統色」という色見本( color guide )だったんだと、みかリンと期せずして一致したのでした。

思えば昔々、雑誌の編集や様々な印刷物の制作に携わっていた頃、DICの色見本は本当に良く使ったものでした。
ただ、そんな中でも使う色というのは大体パターンが決まっていて、その特定の色(例えば『銀鼠』とかね)以外の色のことを改めてあれこれ考えることは少なかったような気がする。
そして人生の半分を大きく過ぎた今、こうした日本の伝統の色の名前を単に眺めるだけで、ひとつの物語を観るようで思わずうっとりしてしまう自分がいたりするのであります。
ほえ~

ちなみに例えば『利休鼠(りきゅうねずみ)』という色には「千利休が好んだ色といわれ、利休は葉茶の緑みを形容したもので、緑みがかった灰色を指し、日本のように湿気の多い気候のところでは霧や靄(もや)がたちこめ、草木の緑も遠くからはこのような色に見えることがある」といった背景を知ったりすると、くーっ! やはり堪りませんのじゃ。
ということで参考までに青色系の色をほんの一部だけあげてみると
錆浅葱(さびあさぎ) 瓶覗(かめのぞき) 浅葱色(あさぎいろ) 新橋色(しんばしいろ) 錆御納戸(さびおなんど) 藍鼠(あいねずみ) 御納戸色(おなんどいろ) 花浅葱(はなあさぎ) 千草色(ちぐさいろ) 舛花色(ますはないろ) 縹(はなだ) 熨斗目花色(のしめはないろ) 御召御納戸(おめしおなんど)…
かくも素晴らしい言葉の数々に何だか感謝したくなる今日この頃なのであります。

今日の1曲 “ 風をあつめて ” : はっぴいえんど
~ 人気のない
朝の珈琲屋で 暇をつぶしてたら
ひび割れた 玻璃ごしに
摩天楼の衣擦れが
舗道をひたすのを 見たんです ♪
松本隆もこんな歌詞を書いていたことがあったんだなあとつい思ってしまうはっぴいえんどの2枚目のアルバム「風街ろまん」(1971年)に収録されている名曲であります。














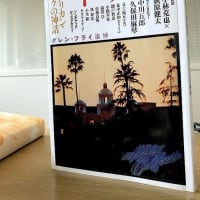





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます