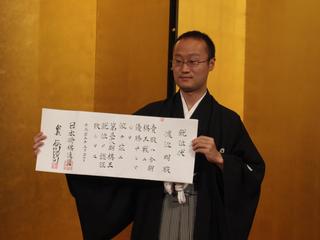昨日の第四局も一時は森下九段が指せそうなところまでは頑張ったのですけど、第三局の豊島七段のように序中盤のうちに明確な差がつけられるようにできないと結局かなわないという図式ができつつあるようです。
(それにしてもあのトイレの位置っていうのは何なんだ?!和服着てる棋士に対するいじめみたいに見える。大雨とかだったらどうなってたの?試合放棄もんじゃない?そして外に出て階段下りてトイレに行く様を中継してるってどうなの??)
さて、電王戦の仕掛け人の記事がありました。
 「将棋、そして囲碁」電脳に負ける人類を待つもの (川上量生)
「将棋、そして囲碁」電脳に負ける人類を待つもの (川上量生) <一部引用させてもらいます。>======================
身の回りの強い人から挑んでいって負けていく。だんだん勝てるひとが少なくなって、そして、最終的にはプロが人間を代表して戦う。そういう構図です。素人から徐々に勝てなくなっていく様子をリアルタイムで歴史に残していける、というのが、囲碁電王戦の役割だと思っています。
そこから人々は何を学ぶことができるのか。それは、コンピューターとのつきあい方でしょう。人間よりも優秀になってくコンピュータに対して、正々堂々と一騎打ちを挑む道もあれば、戦いを避けることもできる。また、利用するという生き方もある。
だれもコンピューターに負けたくないわけですよ、人間は。でも現実はいつかは負ける。コンピューターが進化したらどうなるかというと、徐々に人間の頭脳は必要とされなくなっていくのです。
この問題に対して向き合うというのが、これから21世紀を生きる我々にとって重要だと思っています。コンピューターの頭脳が人間を追い越したときのひとつの回答として、人間には共存を選ぶという道がある。将棋電王戦ではそれを試しました。
<中略>
そういう意味では、将棋電王戦はAIの進化に少なからず影響を与えるとは思います。でも、将棋電王戦をやったところで、AIの進化の速度はさほど変わらない。コンピューターは知らないうちに賢くなるし、知らないうちに人間に勝つ。
ただ、将棋や囲碁というのは、人間がやってきたことにコンピューターが挑戦してくるわけで、分かりやすくその進化が可視化される。つまり、人間が知らないうちに追い抜かれるのではなくて、ちゃんとわかる形で追い抜かれるんです。
そのとき、人間はどう対応していくかのモデルケースが電王戦です。進化していくコンピューター、人工知能にどう対応すればいいのかを人間側に考えさせる極めていいモデルケース、というのが、電王戦の意義だと思っています。そこに、社会的な意味がある。
少なくとも5年10年は電王戦を盛り上げたいと思っています。人間がどこまでやれるか、見守る。それが僕らの義務だと思っているので。
==========================
僕はプログラマーとか科学者じゃないのでわからないけど、なんだかずいぶんと不遜な言い方に聞こえるし、上から目線も感じるし、正しいことを言ってるのかもしれないけど、どうにも友達にはなりたくない人っていう印象が残る。
いや、言ってるように電王戦の意味とか役割っていうのは理屈としてはよくわかるのだけど。。
『コンピューターは知らないうちに賢くなるし、知らないうちに人間に勝つ。』って、誰かが一生懸命そういう研究開発をしてるからそうなるんですよね?
もちろんメーカーや国も加担してるということだろうけど、なんだか人の手を離れて、人間の意志とは別のところで勝手にそうなってるわけではないですよね?
ITとか科学技術の研究開発はすごいスピードで進んでいるし、もうどうにも止まらない状況なのかもしれないけど、それってどうなのだろうか。
もちろん人類の発展や進化や幸せに結びつくことは計り知れない価値があるのだと思う。
でも負の部分だってたくさんある。
結局は人間が主導的に自分の幸せ、地球全体の幸せとは何かをきちんと考えて取捨選択したり判断したりしていかないと歯止めがきかなくなる。
環境問題、地球温暖化の問題、核や原発の問題、市場経済・金融経済の問題などなど科学技術の進化は巨大な文明や経済発展をもたらし、限りなく地球や人間を変えていってる。
人間はそれでいいのか。
将棋はそれでいいのか。
ずいぶん前の<成長し続けること>という記事の中でも書いているけど、近代化、文明化、経済発展のこの流れは我々にとって本当にいいのだろうか、という懸念です。
経済発展による恩恵は十分受けているし感謝もしているけど、
いささか調子に乗りすぎなんじゃないの?
少し立ち止まって反省したり振り返ったりする時期なんじゃないの?
3年前の東日本大震災を機に皆がそういう気持ちになったのではないの?
と冷静に、客観的にそう思うのです。
ips細胞やSTAP細胞ができて、病気が治って、若返って、すべての人が120歳まで生きられることが本当に幸せなのかどうか。
そのことで社会全体のデメリットはないのか。
戻りたくても後戻りできなくなることはないのか。
いろんな画期的なものができてしまったときにそれをきちんと運用できるだけの信頼感がコントロールする人間に対して持てるのかどうか。
などと、話は将棋と関係なくどんどん大げさな展開になっていって収拾つかなくなっていってるけど、こんな記事も見つけました。
 電王戦は,21世紀を生きる人類を映し出す鏡なのかも――将棋棋士・谷川浩司氏がゲストの「ゲーマーはもっと経営者を目指すべき!」第16回
電王戦は,21世紀を生きる人類を映し出す鏡なのかも――将棋棋士・谷川浩司氏がゲストの「ゲーマーはもっと経営者を目指すべき!」第16回 山崎バニラが語る今回の将棋電王戦について思うこと
山崎バニラが語る今回の将棋電王戦について思うこと 羽生善治三冠と川上量生ドワンゴ会長のスペシャル対談
羽生善治三冠と川上量生ドワンゴ会長のスペシャル対談また電王戦に話をもどしてこのシリーズ続けますね。










 <九鬼さん>もう1つの問題点、「強い将棋ソフトを作るのは何のためなのか?」に対して、私は直接回答できませんが、こう言わせてください。将棋自体はゲームにすぎません。将棋のプロ棋戦が成り立たなくなっても、将棋はなくならないでしょう。じゃあ、将棋のプロ棋戦は何のためにあるのでしょうか? 将棋文化は? そんなに社会の役に立っていますでしょうか?
<九鬼さん>もう1つの問題点、「強い将棋ソフトを作るのは何のためなのか?」に対して、私は直接回答できませんが、こう言わせてください。将棋自体はゲームにすぎません。将棋のプロ棋戦が成り立たなくなっても、将棋はなくならないでしょう。じゃあ、将棋のプロ棋戦は何のためにあるのでしょうか? 将棋文化は? そんなに社会の役に立っていますでしょうか? かなり奥深いところに行ってしまいそうなテーマです。
かなり奥深いところに行ってしまいそうなテーマです。


 関連記事:
関連記事:







 20代の反乱
20代の反乱