住友金属鉱山別子事業所の四坂島(愛媛県今治市宮窪町)の精錬所の大煙突が一昨日解体を完了した。解体の理由は老朽化による為で、大煙突建設は、大正13年(1924)に建設され、鉄筋コンクリート製、高さ64,2m亜鉛ガス排出のためであった。
元禄4(1691)年に開かれた住友家の別子銅山は、明治に入り、機械設備の導入、索道、鉄道の敷設などによって出鉱量の拡大が図られ、これに対応する製錬能力を確保するため、別子山中にあった製錬所は新居浜の沿岸部に移設された。
考えてなかった亜硫酸ガスによる煙害が発生、住友総理事伊庭貞剛は、製錬所を無人島の四阪島へ移転するという決断を下した。
四阪島は新居浜から約20キロ離れた無人島で、ここに製錬所を移転すれば、亜硫酸ガスは瀬戸内海上で拡散され、煙害が発生することはないと考えた。
明治38年に製錬所を四阪島に移転、大煙突は、大正13年に完成した。しかし、瀬戸内海上で拡散されると考えた亜硫酸ガスが風に乗って、そのまま四国本土にまで流れ、予想に反して煙害を愛媛県の東予地方全体にまで拡大させることとなり、農民達は、煙害の根絶と損害賠償を求めて激しい運動を繰り広げた。
その後煙害の除去、軽減のため、いくつもの試験研究を実施、これらの対策により、四阪製錬所から排出される硫黄量は、大正8年には半分にまで減少した。
製錬所造成時に家ノ島と美濃島は埋め立てられ陸続きとなり、家ノ島に精錬所、美濃島には社宅・学校・病院等が設置された。大正4年のピーク時の人口5500人が居住した。
現在、四坂島では(株)四阪島製錬所が、製錬技術を活かし、製鋼煙灰に含まれる亜鉛を回収するリサイクル事業を行っている。従業員は新居浜市から定期船で通勤している。

四阪島製錬所の大煙突で、平成22年4月11日船上見学時に撮影。

四阪島製錬所の大煙突。

四阪島製錬所では現在も操業している。従業員は新居浜から定期船で通勤。

四坂島は正確には、家ノ島、美濃島、明神島、鼠島、梶島の5つの島で構成されるが、一般に「四阪島」と呼称される。製錬所造成時には、家ノ島と美濃島は埋め立てられ陸続きとなり、家ノ島に精錬所、美濃島には社宅等が設置された。画像、手前が家ノ島の精錬所大煙突、左奥が美濃島。

画像は、今日(7月4日)付けの愛媛新聞に掲載された解体され無くなった大煙突跡の精錬所。愛媛新聞画像引用。

美濃島には社宅等がまだ現存されている。
最盛期は、私立の住友四阪島尋常小学校が明治34年に設置され、大正9年には生徒数1,000人を数えた。私の知人もこの学校を卒業して現在松山市に在住。住友は、優秀な先生を招き優秀な生徒が沢山卒業して社会に貢献された。

美濃島には社宅等がまだ現存されている。居住者はいない。
家ノ島の精錬所とは埋め立てられ陸続き。

東京の皇居にある楠木正成の騎馬像で、この騎馬像は明治30年1月、別子銅山で精錬された青銅で住友氏が建立奉納された。平成19年12月12日撮影。

楠木正成の騎馬像の台座に埋め込まれている名板。

楠木正成の騎馬像の反対側台座には、騎馬像作成に携わった人達の名前が刻印されている。
元禄4(1691)年に開かれた住友家の別子銅山は、明治に入り、機械設備の導入、索道、鉄道の敷設などによって出鉱量の拡大が図られ、これに対応する製錬能力を確保するため、別子山中にあった製錬所は新居浜の沿岸部に移設された。
考えてなかった亜硫酸ガスによる煙害が発生、住友総理事伊庭貞剛は、製錬所を無人島の四阪島へ移転するという決断を下した。
四阪島は新居浜から約20キロ離れた無人島で、ここに製錬所を移転すれば、亜硫酸ガスは瀬戸内海上で拡散され、煙害が発生することはないと考えた。
明治38年に製錬所を四阪島に移転、大煙突は、大正13年に完成した。しかし、瀬戸内海上で拡散されると考えた亜硫酸ガスが風に乗って、そのまま四国本土にまで流れ、予想に反して煙害を愛媛県の東予地方全体にまで拡大させることとなり、農民達は、煙害の根絶と損害賠償を求めて激しい運動を繰り広げた。
その後煙害の除去、軽減のため、いくつもの試験研究を実施、これらの対策により、四阪製錬所から排出される硫黄量は、大正8年には半分にまで減少した。
製錬所造成時に家ノ島と美濃島は埋め立てられ陸続きとなり、家ノ島に精錬所、美濃島には社宅・学校・病院等が設置された。大正4年のピーク時の人口5500人が居住した。
現在、四坂島では(株)四阪島製錬所が、製錬技術を活かし、製鋼煙灰に含まれる亜鉛を回収するリサイクル事業を行っている。従業員は新居浜市から定期船で通勤している。

四阪島製錬所の大煙突で、平成22年4月11日船上見学時に撮影。

四阪島製錬所の大煙突。

四阪島製錬所では現在も操業している。従業員は新居浜から定期船で通勤。

四坂島は正確には、家ノ島、美濃島、明神島、鼠島、梶島の5つの島で構成されるが、一般に「四阪島」と呼称される。製錬所造成時には、家ノ島と美濃島は埋め立てられ陸続きとなり、家ノ島に精錬所、美濃島には社宅等が設置された。画像、手前が家ノ島の精錬所大煙突、左奥が美濃島。

画像は、今日(7月4日)付けの愛媛新聞に掲載された解体され無くなった大煙突跡の精錬所。愛媛新聞画像引用。

美濃島には社宅等がまだ現存されている。
最盛期は、私立の住友四阪島尋常小学校が明治34年に設置され、大正9年には生徒数1,000人を数えた。私の知人もこの学校を卒業して現在松山市に在住。住友は、優秀な先生を招き優秀な生徒が沢山卒業して社会に貢献された。

美濃島には社宅等がまだ現存されている。居住者はいない。
家ノ島の精錬所とは埋め立てられ陸続き。

東京の皇居にある楠木正成の騎馬像で、この騎馬像は明治30年1月、別子銅山で精錬された青銅で住友氏が建立奉納された。平成19年12月12日撮影。

楠木正成の騎馬像の台座に埋め込まれている名板。

楠木正成の騎馬像の反対側台座には、騎馬像作成に携わった人達の名前が刻印されている。










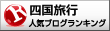

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます