松山市下難波(旧北条市)にある、腰折山(標高214m)に自生する「国指定天然記念物・エヒメアヤメ、自生南限地帯・」の観察と、明治31年4月17日に、松山市の梅村甚太郎が発見し、理学博士、牧野富太郎が命名した「イヨスミレ」の観察を終え、瀬戸内海国立公園内にある「鹿島」の散策をした。
鹿島は、周囲1,5km、標高114mの小さな島で、昭和31年国立公園となり「伊予の江ノ島」とも呼ばれている。
中世時代は、島全体が伊予国守護河野氏の家臣として活躍した来島村上水軍の海域で鹿島城があった。頂上には、城跡の形跡が残っている。また神宮皇后の伝説の場所がある。それは、西征の途中軍船を風早郷の鹿島に止め、軍備・旅装を整えられると巌に立って弓に矢をつがえ沖に放たれて戦勝を祈願し、勇躍大津地の湊を出発されたと伝えられている。
また、島には鹿島神社がありこの神のお仕えの鹿と言い伝えがある鹿60頭が生息している。
島には沢山の記念の石碑が建立されていて、句碑が一番多い。
島の南西方向沖合い100m位に位置する所に3個の岩がありこの岩に大注連縄を張られ伊予の二見と呼ばれている名勝巌もある。
午後1時30分鹿島散策を終え、東雲大学「学び舎えひめ悠々大学・社会人講座・自然観察第1回目の学習は終了し大学に帰った。次回は5月21日1,000m級の四国山地「皿ヶ峰」の自然観察である。

学習地である「腰折山」から見た「鹿島」で、下山して渡船で島に行き昼食を取ってから、鹿島散策をした。
18年振りの鹿島は随分と綺麗に清掃、整備されていた。腰折山の隣に恵良山標高302mがる。太古の時代恵良山が激怒して、腰折山を蹴飛ばし、山頂が飛び海に落ち島になった。その島が鹿島と言われる伝説がある。

移動は、松山東雲大学のマイクロバスで移動し渡船で鹿島に渡る。
時間は5分、往復100円であった。

周囲1,5km、標高114mの小さな島で、昭和31年国立公園となり「伊予の江ノ島」とも呼ばれている。

鹿島の船着場には画像のような、伊予の方言「ようおいでたなもし」と書かれたお出迎えの掲示板があった。

鹿島の案内図。

お立ち台の巌(山頂にある)
神宮皇后の伝説の場所で、それは、西征の途中軍船を風早郷の鹿島に止め、軍備・旅装を整えられると巌に立って弓に矢をつがえ沖に放たれて戦勝を祈願し、勇躍大津地の湊を出発されたと伝えられている岩場。

伊予の二見と言われる、夫婦岩で、玉理(ぎょくり)島、寒戸(かんど)島で春の北条鹿島祭りのときに大注連縄(おおしめなわ)が張り替えられる。
張替えの前なのか大注連縄ははずされていた。

大注連縄は画像のように張られる。

日清、日露戦役に北条地区から出征した人達の記念碑が建立してあった。
揮毫は、陸軍大将乃木希典、裏面には、大正6年5月建之 北条町兵事支會と刻印されていた。

伊予国守護河野氏の家臣として活躍した来島村上水軍の来島通総時代の城跡図で、来島通総は豊臣秀吉の文禄、慶長の役には、加藤嘉明の配下として船団を率い兵を朝鮮に送り込んだ一人である。

鹿島神社の神の使者であったと言い伝えのあえる鹿で、県指定・天然記念物「鹿島のシカ」、この島は安山岩で構成されていて植物はあまり育たなく、島の面積も小さく鹿の食料となる植物が育たない。60頭の鹿が生きていくには大変である。

この花は、浦島草で、本種は日本の本州、四国を中心に、北海道と九州の一部に分布する宿根性の多年草、沢山自生しているが、毒性の植物で鹿は食べられない。

鹿島には楠木が沢山あるが、表皮は画像のように無くなっている。これは鹿が食べた後だそうです。鹿が食べられる高さの位置。下には植物があるが毒性のもので鹿は食べられない。餌を与えてやればいいのに餌を与えてないとの事。・・何故か??食料難で時々鹿が餓死するそうだ。・・可哀想に、地上には植物は生えていない・・それは鹿が食べつくすから。シダ類は生息しているが鹿は食べないそうだ。
鹿島は、周囲1,5km、標高114mの小さな島で、昭和31年国立公園となり「伊予の江ノ島」とも呼ばれている。
中世時代は、島全体が伊予国守護河野氏の家臣として活躍した来島村上水軍の海域で鹿島城があった。頂上には、城跡の形跡が残っている。また神宮皇后の伝説の場所がある。それは、西征の途中軍船を風早郷の鹿島に止め、軍備・旅装を整えられると巌に立って弓に矢をつがえ沖に放たれて戦勝を祈願し、勇躍大津地の湊を出発されたと伝えられている。
また、島には鹿島神社がありこの神のお仕えの鹿と言い伝えがある鹿60頭が生息している。
島には沢山の記念の石碑が建立されていて、句碑が一番多い。
島の南西方向沖合い100m位に位置する所に3個の岩がありこの岩に大注連縄を張られ伊予の二見と呼ばれている名勝巌もある。
午後1時30分鹿島散策を終え、東雲大学「学び舎えひめ悠々大学・社会人講座・自然観察第1回目の学習は終了し大学に帰った。次回は5月21日1,000m級の四国山地「皿ヶ峰」の自然観察である。

学習地である「腰折山」から見た「鹿島」で、下山して渡船で島に行き昼食を取ってから、鹿島散策をした。
18年振りの鹿島は随分と綺麗に清掃、整備されていた。腰折山の隣に恵良山標高302mがる。太古の時代恵良山が激怒して、腰折山を蹴飛ばし、山頂が飛び海に落ち島になった。その島が鹿島と言われる伝説がある。

移動は、松山東雲大学のマイクロバスで移動し渡船で鹿島に渡る。
時間は5分、往復100円であった。

周囲1,5km、標高114mの小さな島で、昭和31年国立公園となり「伊予の江ノ島」とも呼ばれている。

鹿島の船着場には画像のような、伊予の方言「ようおいでたなもし」と書かれたお出迎えの掲示板があった。

鹿島の案内図。

お立ち台の巌(山頂にある)
神宮皇后の伝説の場所で、それは、西征の途中軍船を風早郷の鹿島に止め、軍備・旅装を整えられると巌に立って弓に矢をつがえ沖に放たれて戦勝を祈願し、勇躍大津地の湊を出発されたと伝えられている岩場。

伊予の二見と言われる、夫婦岩で、玉理(ぎょくり)島、寒戸(かんど)島で春の北条鹿島祭りのときに大注連縄(おおしめなわ)が張り替えられる。
張替えの前なのか大注連縄ははずされていた。

大注連縄は画像のように張られる。

日清、日露戦役に北条地区から出征した人達の記念碑が建立してあった。
揮毫は、陸軍大将乃木希典、裏面には、大正6年5月建之 北条町兵事支會と刻印されていた。

伊予国守護河野氏の家臣として活躍した来島村上水軍の来島通総時代の城跡図で、来島通総は豊臣秀吉の文禄、慶長の役には、加藤嘉明の配下として船団を率い兵を朝鮮に送り込んだ一人である。

鹿島神社の神の使者であったと言い伝えのあえる鹿で、県指定・天然記念物「鹿島のシカ」、この島は安山岩で構成されていて植物はあまり育たなく、島の面積も小さく鹿の食料となる植物が育たない。60頭の鹿が生きていくには大変である。

この花は、浦島草で、本種は日本の本州、四国を中心に、北海道と九州の一部に分布する宿根性の多年草、沢山自生しているが、毒性の植物で鹿は食べられない。

鹿島には楠木が沢山あるが、表皮は画像のように無くなっている。これは鹿が食べた後だそうです。鹿が食べられる高さの位置。下には植物があるが毒性のもので鹿は食べられない。餌を与えてやればいいのに餌を与えてないとの事。・・何故か??食料難で時々鹿が餓死するそうだ。・・可哀想に、地上には植物は生えていない・・それは鹿が食べつくすから。シダ類は生息しているが鹿は食べないそうだ。










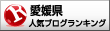



















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます