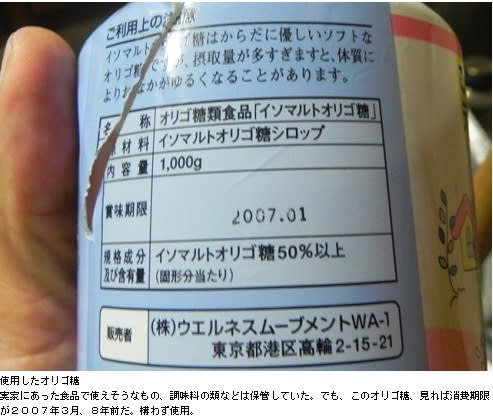うっちん茶については既に2013年2月12日に、『飲み物も自給を目指し』とサブタイトルを付けて紹介し、その記事の中で「お茶も買っているが、これも今月から自作している」、「(お茶の自作は)生活費を削減しなければならない、という貧乏からくる考えの一つ」などと書いているが、それから今日までの2年半、うっちん茶を自作したのはその時以来無い。老化した脳味噌はそのことをすっかり忘れていた。
2年半も経ってうっちん茶作りを再開したのは「飲み物も自給しなきゃ」と思い出したからではない。ウコンは畑の果樹園の一角にあり、先日、果樹園を除草、整地している時に邪魔になっているウコンを4株ほど掘り採って、「これどうする?」と考えて、「そうだ、お茶にしよう」と閃いたから。家に帰ってパソコン作業(ガジ丸記事書きなど)している時、「うっちん茶、前に紹介したかも」と思い出して調べたら、紹介していた。
前に紹介した「うっちん茶」の文の中に「根茎を薄くスライス、または刻み、それをそのまま煎じて飲むか、スライス、または刻んだものを乾燥させ、それを煎じて飲む」と書いてあって、その時は「刻んだものを乾燥させ」て作っている。なので、今回は「根茎を薄くスライス、または刻み、それをそのまま煎じて」みようと思い立った。
前回の記事には自作うっちん茶を飲んだ感想が書かれていない。今、思い返してもどんな味だったか思い出せない。特に感想もなく、思い出せもしないということは、おそらく自作うっちん茶、市販のうっちん茶とほとんど変わらなかったものと思われる。
今回はちゃんと感想を書こう。今回の「そのまま煎じ」たうっちん茶、煎じたものそのままは市販のものと比べて色が濃い。飲むと味も匂いも濃い。元々漢方薬のような「いかにも薬」みたいな味と匂いなので少々飲み辛い。それを水で薄めて飲んだらいくらか飲みやすくなって、市販のものと味も匂いもそう変わらないようになった。
ウコンの味と匂いは独特で、私としてはちょっと苦手な部類に入る。これを日常の飲物にするについてはちょっと抵抗があるのだが、緑茶にしたって独特の味と匂いだ、うっちん茶も慣れてしまえば普通に飲めるようになるかもしれない。取り敢えず、当分の間は水をたっぷり加えて、ごく薄いうっちん茶にして利用しようと考えている。
ちなみに、ウッチンはウコンの沖縄語読み。




記:2015.10.5 ガジ丸 →沖縄の飲食目次