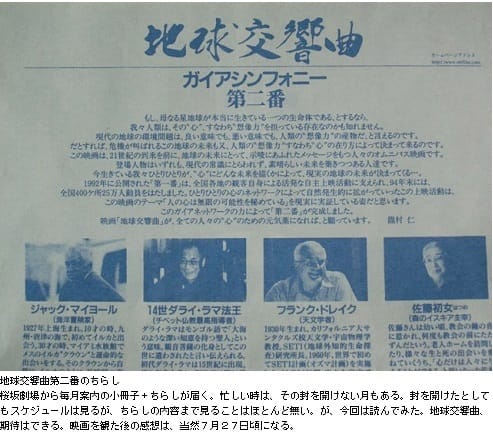最近マナに元気が無いと思っていたら、恋煩いだと言う。ケダマンがそう言うのだが、そう言われてみれば確かにそのような雰囲気ではある。今までに比べるとちょっと優しい感じだし、全体にしっとりとしている。相手はジラースーだと言う。ケダマンがそう言うのだが、相手がジラースーかどうかについては、マナは白状しない。まあ、しかし、他には見当つかないし、どうやらそれも当たっているようである。
恋煩いはしていてもさすがに経験豊富なプロの女である。ユクレー屋で我々の飲み相手をしている間は、ちゃんとその仕事をこなす。今宵の肴は、畑から採ったばかりのシマラッキョウ。シマラッキョウを細かく刻んで、挽肉と一緒に味噌で炒め、それを大葉に包んだもの。マナの創作料理らしい。それとは別に、シマラッキョウのヒラヤーチーを、別のテーブルにいた村人たちへ出していた。これも好評であった。
一時期は、料理や酒を出すことはしたが、あとはカウンターの中でボーっとしていることの多かったマナであるが、その夜の彼女は、一時期に比べると幾分かは元気を取り戻して いるみたいであった。我々の話に加わる時間も多くなった。


「ねぇ、そう言えばさあ、ウルトラの米が炊けるっていうジャーはどうなったの?」
「あー、あれは今、博士が頑張って製作中だと思うよ。」(私)
「ん!、そうだ、マナ、良いアイデアが浮かんだ。ウルトラの星から米粒仕入れて、世界中に売ってやろうぜ、そしたら博士のジャーも売れるぜ。儲かるぜ。」(ケダ)
「儲かるって話をしてるんじゃないよ。ユーナも言ってたじゃない。世界中の飢えに苦しんでいる人々の助けにならないかって話よ。」
その時、カランコロンカランと音がしてドアが開き、ガジ丸が入ってきた。
「おっ、ガジ丸、ちょうどいいところに来た。今、ウルトラの米を輸入して一儲けしようという話をしていたところだ。博士のジャーも一緒に売れるぜ。」(ケダ)
「だから、儲けようって話じゃないんだってば!」(マナ)
「儲ける?ウルトラの米?博士のジャー?・・・ってそうか、博士が無駄な努力をやっていたのは、お前らが作れって言ったからか。」(ガジ)
「あー、そうだ。で、博士のジャーはできそうだったか?」(ケダ)
「その製作は中止だ。俺が止めさせた。」
「えっ、どうしてさ。儲けるかどうかはともかく、あれば良いと思うけど。」(私)
「よく考えてみろよ。ウルトラの米1粒を炊く炊飯ジャーなら、既に市販されている業務用の大型炊飯器が使えるだろうよ。」(ガジ)
「あっ、そうか。そういえばそうだ。ジャーは既にあるんだ。」(私)
「あっ、そうか。そういえばそうだ。って、博士も同じこと言ってたよ。」(ガジ)
「だったら話は早いぜ。米だけを売りゃあいいんだ。すぐできる。」(ケダ)
「いや、それにだな。ウルトラの星へ行くのは時空を超える旅になるから、トラックを持っていくことはできない。だから、人力で米を運ばなければならない。ウルトラの米はでかいから、背負ってもせいぜい5、6粒がいいとこだ。」(ガジ)
「あー、そうか。5、6粒では世界中には行き渡らないね。」(マナ)
「いや、5、6粒でもいいじゃないか。それを種籾にして地球のどこかに植えてだな、どんどん増やしていこうぜ。」(ケダ)
「ケダ、今日は冴えてるね。ねぇ、ガジ丸、そうできない?」(マナ)
「種を植えることは可能だ。だが、収穫でききる頃には、その稲は高さ20mくらいになるぜ。そうなるまで育てるのも大変だが、高いし、籾は重いし、収穫するのも難しいのさ。それに、種がたくさんあったとしても、十分な量を得るには広大な田んぼが必要だ。そんな広大な田んぼがあるんだったら、普通の稲を植えた方が良かろう。その方がはるかに管理しやすいし、1坪辺りの収穫量だってそうは変わらないはずだ。」(ガジ)
確かにガジ丸の言う通りであった。普通の稲なら普通に育てられ、普通の収穫量を得ることができる。その土地にはその土地にあった作物を植えた方が良いってことだ。地球には地球の規模に合った、人間には人間の大きさに合った作物があるというわけだ。
「博士の炊飯ジャーと同じく、お前らの考えも無駄な努力だったわけだ。」とガジ丸がきっぱり断じたあとは、その話題からきっぱり離れて、我々はまた、いつものようにバカな話で盛り上がって、愉快な夜を過ごした。マナは元気になっていた。
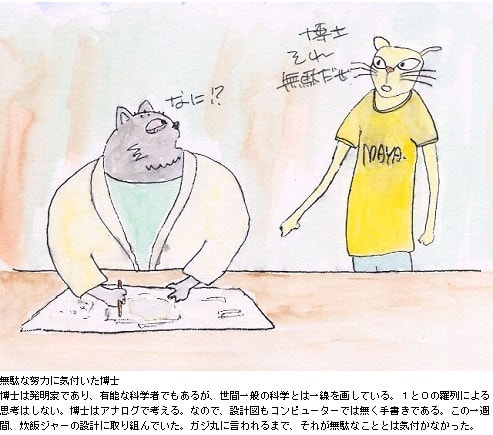
記:ゑんちゅ小僧 2007.5.25