
私は月曜日には必ず銀座へ行きます。で、火曜日は別の場所に勉強に行きます。六本木や、上野が今の美術の集積場所です。で、8月のある火曜日に上野に行きました。上野公園には美術館や博物館が一杯あるけれど、私が向かうのは都立美術館か、芸大美術館です。国立西洋美術館と、国立博物館より、そちらの方が新しい分野のものを展示しているからです。
博物館や美術館で展示をしているものは権威の定まったものが多いのです。立派なものですが、画集や美術全集で、デジャヴーのあるものが多いのです。最先端のものを見たい私が向かうのは、噴水を中心とすれば西側になります。
上野駅を降りたときからその日は、警官が一杯です。『変だなあ。何があるのだろう?』と思いますが、別に赤旗が林立しているわけでもありません。
噴水の傍に青く塗ったバスが三台あって、周りに警官がたむろしています。『あれ、このバス三台分の警官が来ているのだ。何があるのだろう?』とさらに不思議です。そのバスですがどうも警察のものらしいのに、どこにも○○署などの文字が無く、しいて探せば、『排ガス規制合格』と言うラベルがあるだけでした。
普通、警察のバスと言うとねずみ色で、窓のところにパイプがわたっているような、ゴッツイ物を見続けているので、その瀟洒と言っても良いブルーの外装のバスは、これまた不思議な感覚を与えられます。
~~~~~~~~~~~
さて、用事を済ませました。芸大美術館の前は相当駅から遠いのです。どうやって帰れば、一番近いかなあと、思案投げ首です。と言うのも私は重いA4のパソコンかそれでなければ自分の本を、20冊以上必ず持ち歩いている人なので、アテンダントバッグは引くのさえ重い感じです。歩く距離はなるべく小さくしたいと願っています。
で、黒門前の道路を線路に向かって真直ぐ歩く事にしました。国立博物館の塀の中から生い茂った樹木が頭の上をさえぎり、見通しは利きません。歩道は狭く、敷石はでこぼこしています。でもね、東京の都心にある道としては、きれいな道の一つでしょう。何でもきれいなものが好きな私は、『これを選んだ事は正解ね』と自己満足をしながら歩いていくと、突然木の陰から美形の青年が現れました。
それがちょっと普通の人と違うのです。夏なのにダークスーツ、だけど、ノーネクタイ、だけど、ポロシャツでもカラーワイシャツでもない、ホワイトシャツ。クールビズでしょうが、どこか改まった感じがある。なんか印象に残って、チラッと襟章を見ると、銀でできた菊のご紋章です。
『へえーっ。日本の会社で、菊のご紋章を使う事を許されているところがあるんだ。商標権とか、何とかで問題にならないのかしら? 宮内庁もさばけたものね。
日本の民主主義もここまで進んだのか』と感嘆しながらすれ違って、さらに歩き続けると、
突然視界が開けて、国立博物館の前が見通せる場所に出ました。50メートルぐらいの向こうに、2、30人の人が横向きに並んでいます。『あ、誰か今日は、有名人が来るのだわ。誰かしら?』と思った途端、ウエブニュースで見た、「秋篠の宮ご夫妻が伊勢神宮展を、ご覧になった」というニュースを思い出し、『天皇陛下がいらっしゃるのではないかしら?』と感じました。
~~~~~~~~~~~~
さて、ここから、先、天皇陛下が実際に国立博物館にお入りになったご様子とその近辺の事は一切抜かします。明日書きます。今日は別の論点から書きます。つまり、天皇陛下を警備するそのやり方について、実際の観察のみを述べます。今日は、批判もしなければ論陣も張りません。ただ、事実だけを淡々と・・・・・
~~~~~~~~~~~~
人々が、「どちらからいらっしゃるのかしらね。向こう(芸大の方)からか、こっち(JRの線路の方)からかしら? あ、あそこ(芸大傍の十字路)を封鎖した。もうすぐよ」と期待の声を上げます。
私はびっくりしました。上野公園だからかもしれないけれど、天皇陛下がいらっしゃる場合は、合計一キロぐらいは、道路が封鎖されて、普通の車両は通行できないのです。日本の警察はそういうことは微妙に上手みたいで、マラソンなどと同じように、封鎖されるのでした。しゃしゃしゃっとね。
でも、その封鎖された静か極まりない、きれいな道路にそれほどの数の警官はいません。だから、非常にスマートな警備と言っていいでしょう。ともかく、正門前には三人の警官しかいないのです。ただね、その三人の警官が道路封鎖の指導をしたようにも見えないのです。
ただ、ここにもダークスーツの男性たちがいました。ノーネクタイ、ワイシャツ。年齢構成は、熟年の人が一人、中年が一人、青年が数人。私はその人たちを注視しました。その一人の襟に小さな白い襟章がついていて、それがとてもきれいでした。が、私の知らない襟章でした。
私はその襟章に対して大きな興味を抱きました。襟章と言うのは究極のデザインだからです。凝縮したデザインだからです。昔から大きな興味を持っていて、三冊目の本にもそれを文章として描いて(または、書いて)います。
それで天皇陛下が国立博物館の門内にお入りになって、辺りの緊張が解けたときに、ダークスーツのうちの一人に近づいて「その襟章は何ですか?」と質問をしました。すると「警視庁です」とのこと。
~~~~~~~~~~~~~
そのときです。実際の私はのけぞるほどびっくりしました。だけど、と同時にさまざまな考察を瞬時に始めました。・・・・・私が脳を高速回転をさせているときには、無表情になるらしいです。それにもちろん、声も出しません。無感動で、何も聞いていないというか、理解をしていないように見えるらしいのです。
それで、その警視庁の人は、私に事情を正しく理解をさせるために、補足説明が必要だと考えたらしくて、「皇宮警察もいるんですよ。そちらは襟章が違うんです」といったのです。その途端、私はハッとわれに帰り、にっこり笑って「あ、有難うございます」といいました。
実際に、ある謎が解けたから、本当に感謝しました。つまり、300メートルぐらい向こうで、すれ違ったダークスーツの美形の青年が、銀の菊の紋章をつけていたのは、皇宮警察だったからでした。何の不思議も無かったのです。日本は急に民主主義化したわけではなくて、銀の菊の襟章は、民間会社のものではなかったわけです。単純な事でした。
そして、その人が芸大傍の十字路で、車を封鎖したわけでした。ケータイで指揮系統が伝わり、「後何分で封鎖しろ」とかいう、命令を受けたのでしょう。
警視庁の方は、銀ではなくて、エナメル(七宝)です。白い丸の中に櫻だと思う花が繊細な青の線で、描かれています。サイズも小さくてとても瀟洒なものです。で、その七宝の襟章の人は、私が要点を飲み込んだとみて、にっこり笑って去っていきました。
~~~~~~~~~~~~
さて、その人の前にいて、馬鹿みたいに無表情で無感動でいた、15秒ぐらいの間に、私が何を考えていたかをお話いたしましょう。それは、『え、警視庁にもブルーカラーと、ホワイトカラーの区別があるんだ。大会社と同じだ』と言うことでした。そのダークスーツの人たちは、ノーネクタイではあったけれど(それは現代の、特に真夏の流儀であり、昔ならネクタイつきで勤務するはずでした)、ピンストライプが入っているにしろ、いわゆるワイシャツであり、字義通りのホワイトカラーなのでした。
一方のおまわりさんです。黒いチョッキを着ている人たちは、いわゆる機動隊かな? 若い人が多い。それから、そのチョッキがない人は所轄所の普通のおまわりさんかな。中のシャツが文字通りのブルーなのです。
私以外の、そこに待っていた善男善女は、おまわりさんがすべての警備をになっていると、きっと考えています。私も、『そのダークスーツの人たちが、警察のホワイトカラーなのだ』と知る前までは、そう考えていました。でも、指揮系統は、その人たちが握っているのには、その日、気がつきました。
上野公園全山で、バス三台分の警官が詰めていても、総指揮は数人のダークスーツの人、特に眼鏡をかけた、熟年の・・・・・トップらしき人・・・・・が握っているのです。
そのときふと思い出しました。さきほど、噴水の傍で、三台のブルーに塗られたバスを見たときに、その傍にワゴンが、これも、ブルーに塗られて一台停まっていたのです。『あれに、この人たちは乗ってきたのかなあ』とも思いました。使う車さえ違うのです。
~~~~~~~~~~~
よくテレビドラマの中で、現場たたき上げの刑事と、大卒キャリアーの警視(?言葉が正しく使えませんが)が対立するでしょう。この前、テレビ朝日で、平塚八兵衛物語をやっていたのをチラッと見ましたが、やはりその構図が出てきました。
でもね、天皇陛下の警備の場合だけは違うのです。なんていうか、有無を言わせぬ、スピードで、ぴしゃぴしゃぴしゃっと決まっていく。ある一人の人の判断で、すべてがさささっと、片付いていくのです。驚きました。全く知らない世界をのぞいた気がしました。では、今日はこれで、終わります。
2009年9月1日 雨宮舜(川崎 千恵子)
博物館や美術館で展示をしているものは権威の定まったものが多いのです。立派なものですが、画集や美術全集で、デジャヴーのあるものが多いのです。最先端のものを見たい私が向かうのは、噴水を中心とすれば西側になります。
上野駅を降りたときからその日は、警官が一杯です。『変だなあ。何があるのだろう?』と思いますが、別に赤旗が林立しているわけでもありません。
噴水の傍に青く塗ったバスが三台あって、周りに警官がたむろしています。『あれ、このバス三台分の警官が来ているのだ。何があるのだろう?』とさらに不思議です。そのバスですがどうも警察のものらしいのに、どこにも○○署などの文字が無く、しいて探せば、『排ガス規制合格』と言うラベルがあるだけでした。
普通、警察のバスと言うとねずみ色で、窓のところにパイプがわたっているような、ゴッツイ物を見続けているので、その瀟洒と言っても良いブルーの外装のバスは、これまた不思議な感覚を与えられます。
~~~~~~~~~~~
さて、用事を済ませました。芸大美術館の前は相当駅から遠いのです。どうやって帰れば、一番近いかなあと、思案投げ首です。と言うのも私は重いA4のパソコンかそれでなければ自分の本を、20冊以上必ず持ち歩いている人なので、アテンダントバッグは引くのさえ重い感じです。歩く距離はなるべく小さくしたいと願っています。
で、黒門前の道路を線路に向かって真直ぐ歩く事にしました。国立博物館の塀の中から生い茂った樹木が頭の上をさえぎり、見通しは利きません。歩道は狭く、敷石はでこぼこしています。でもね、東京の都心にある道としては、きれいな道の一つでしょう。何でもきれいなものが好きな私は、『これを選んだ事は正解ね』と自己満足をしながら歩いていくと、突然木の陰から美形の青年が現れました。
それがちょっと普通の人と違うのです。夏なのにダークスーツ、だけど、ノーネクタイ、だけど、ポロシャツでもカラーワイシャツでもない、ホワイトシャツ。クールビズでしょうが、どこか改まった感じがある。なんか印象に残って、チラッと襟章を見ると、銀でできた菊のご紋章です。
『へえーっ。日本の会社で、菊のご紋章を使う事を許されているところがあるんだ。商標権とか、何とかで問題にならないのかしら? 宮内庁もさばけたものね。
日本の民主主義もここまで進んだのか』と感嘆しながらすれ違って、さらに歩き続けると、
突然視界が開けて、国立博物館の前が見通せる場所に出ました。50メートルぐらいの向こうに、2、30人の人が横向きに並んでいます。『あ、誰か今日は、有名人が来るのだわ。誰かしら?』と思った途端、ウエブニュースで見た、「秋篠の宮ご夫妻が伊勢神宮展を、ご覧になった」というニュースを思い出し、『天皇陛下がいらっしゃるのではないかしら?』と感じました。
~~~~~~~~~~~~
さて、ここから、先、天皇陛下が実際に国立博物館にお入りになったご様子とその近辺の事は一切抜かします。明日書きます。今日は別の論点から書きます。つまり、天皇陛下を警備するそのやり方について、実際の観察のみを述べます。今日は、批判もしなければ論陣も張りません。ただ、事実だけを淡々と・・・・・
~~~~~~~~~~~~
人々が、「どちらからいらっしゃるのかしらね。向こう(芸大の方)からか、こっち(JRの線路の方)からかしら? あ、あそこ(芸大傍の十字路)を封鎖した。もうすぐよ」と期待の声を上げます。
私はびっくりしました。上野公園だからかもしれないけれど、天皇陛下がいらっしゃる場合は、合計一キロぐらいは、道路が封鎖されて、普通の車両は通行できないのです。日本の警察はそういうことは微妙に上手みたいで、マラソンなどと同じように、封鎖されるのでした。しゃしゃしゃっとね。
でも、その封鎖された静か極まりない、きれいな道路にそれほどの数の警官はいません。だから、非常にスマートな警備と言っていいでしょう。ともかく、正門前には三人の警官しかいないのです。ただね、その三人の警官が道路封鎖の指導をしたようにも見えないのです。
ただ、ここにもダークスーツの男性たちがいました。ノーネクタイ、ワイシャツ。年齢構成は、熟年の人が一人、中年が一人、青年が数人。私はその人たちを注視しました。その一人の襟に小さな白い襟章がついていて、それがとてもきれいでした。が、私の知らない襟章でした。
私はその襟章に対して大きな興味を抱きました。襟章と言うのは究極のデザインだからです。凝縮したデザインだからです。昔から大きな興味を持っていて、三冊目の本にもそれを文章として描いて(または、書いて)います。
それで天皇陛下が国立博物館の門内にお入りになって、辺りの緊張が解けたときに、ダークスーツのうちの一人に近づいて「その襟章は何ですか?」と質問をしました。すると「警視庁です」とのこと。
~~~~~~~~~~~~~
そのときです。実際の私はのけぞるほどびっくりしました。だけど、と同時にさまざまな考察を瞬時に始めました。・・・・・私が脳を高速回転をさせているときには、無表情になるらしいです。それにもちろん、声も出しません。無感動で、何も聞いていないというか、理解をしていないように見えるらしいのです。
それで、その警視庁の人は、私に事情を正しく理解をさせるために、補足説明が必要だと考えたらしくて、「皇宮警察もいるんですよ。そちらは襟章が違うんです」といったのです。その途端、私はハッとわれに帰り、にっこり笑って「あ、有難うございます」といいました。
実際に、ある謎が解けたから、本当に感謝しました。つまり、300メートルぐらい向こうで、すれ違ったダークスーツの美形の青年が、銀の菊の紋章をつけていたのは、皇宮警察だったからでした。何の不思議も無かったのです。日本は急に民主主義化したわけではなくて、銀の菊の襟章は、民間会社のものではなかったわけです。単純な事でした。
そして、その人が芸大傍の十字路で、車を封鎖したわけでした。ケータイで指揮系統が伝わり、「後何分で封鎖しろ」とかいう、命令を受けたのでしょう。
警視庁の方は、銀ではなくて、エナメル(七宝)です。白い丸の中に櫻だと思う花が繊細な青の線で、描かれています。サイズも小さくてとても瀟洒なものです。で、その七宝の襟章の人は、私が要点を飲み込んだとみて、にっこり笑って去っていきました。
~~~~~~~~~~~~
さて、その人の前にいて、馬鹿みたいに無表情で無感動でいた、15秒ぐらいの間に、私が何を考えていたかをお話いたしましょう。それは、『え、警視庁にもブルーカラーと、ホワイトカラーの区別があるんだ。大会社と同じだ』と言うことでした。そのダークスーツの人たちは、ノーネクタイではあったけれど(それは現代の、特に真夏の流儀であり、昔ならネクタイつきで勤務するはずでした)、ピンストライプが入っているにしろ、いわゆるワイシャツであり、字義通りのホワイトカラーなのでした。
一方のおまわりさんです。黒いチョッキを着ている人たちは、いわゆる機動隊かな? 若い人が多い。それから、そのチョッキがない人は所轄所の普通のおまわりさんかな。中のシャツが文字通りのブルーなのです。
私以外の、そこに待っていた善男善女は、おまわりさんがすべての警備をになっていると、きっと考えています。私も、『そのダークスーツの人たちが、警察のホワイトカラーなのだ』と知る前までは、そう考えていました。でも、指揮系統は、その人たちが握っているのには、その日、気がつきました。
上野公園全山で、バス三台分の警官が詰めていても、総指揮は数人のダークスーツの人、特に眼鏡をかけた、熟年の・・・・・トップらしき人・・・・・が握っているのです。
そのときふと思い出しました。さきほど、噴水の傍で、三台のブルーに塗られたバスを見たときに、その傍にワゴンが、これも、ブルーに塗られて一台停まっていたのです。『あれに、この人たちは乗ってきたのかなあ』とも思いました。使う車さえ違うのです。
~~~~~~~~~~~
よくテレビドラマの中で、現場たたき上げの刑事と、大卒キャリアーの警視(?言葉が正しく使えませんが)が対立するでしょう。この前、テレビ朝日で、平塚八兵衛物語をやっていたのをチラッと見ましたが、やはりその構図が出てきました。
でもね、天皇陛下の警備の場合だけは違うのです。なんていうか、有無を言わせぬ、スピードで、ぴしゃぴしゃぴしゃっと決まっていく。ある一人の人の判断で、すべてがさささっと、片付いていくのです。驚きました。全く知らない世界をのぞいた気がしました。では、今日はこれで、終わります。
2009年9月1日 雨宮舜(川崎 千恵子)












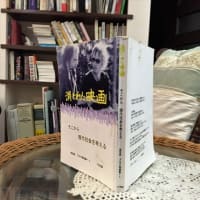


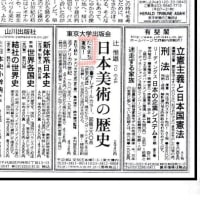
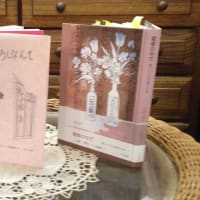



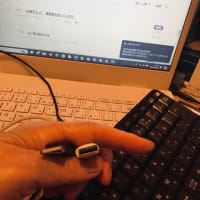






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます