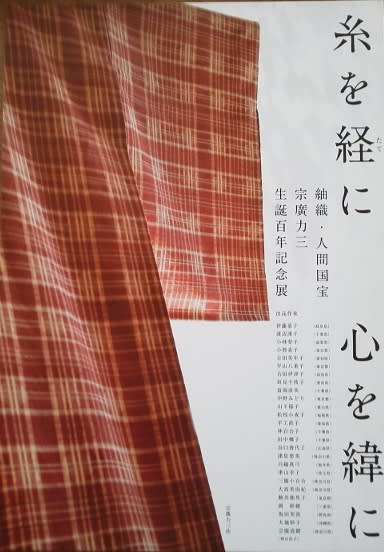三年前に上梓しました作品集『樹の滴――染め、織り、着る』の出版記念をかねた個展「美しい布を織る‘15」がお陰さまで無事終了しました。
お忙しい中ご都合をつけてご来場くださいました皆様、関係者の方々ありがとうございました。

たくさんの方と作品や着物、自然について話をすることができました。
作品集を読んで内容に共感して下さりお越しくださった方も何人かいらっしゃいました。
実作を当てていただいたり光にかざして見ていただきました。

観る方の鑑賞力やコメントも私には大変参考になりました。
その中で「静かだけれど力強い」という画廊経営の方の言葉が特に端的に捉えられていて印象に残りました。そういう織物をこれからも織っていきます。
また着物や帯を織る時の最初の織り出し部分を使って仕立てた袱紗やミニ額装などもしっかりご覧いただきました。こういうものは拝見に値する内容がなければなりませんが好評をいただきほっとしました。

林まさみつさんの竹かごバッグも丁寧な作りで着物の時に使ってもこれなら生地を痛めたりしないと大変好評でした。私も使わせてもらいます。今後の展示会の予定などは林さんのブログをご覧下さい。

連日夏日、真夏日となった5月下旬でしたが三枚の自作の紬の単衣に帯を毎日替えて8日間を過ごしました。
蒸し暑い時こそ単衣の真綿系紬の真価は発揮されるのですが、それでも少しでも涼しく着るひと工夫についてなどは後日アップします。
着物や帯などをお求めくださった方には私たちのこれからの糧もいただきました。
心より御礼申し上げます。ありがとうございました。
若い織り手の育成とともに、私自身もやりたい仕事がまだまだありますのでこの道を切り拓くべく精進してまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
 大塚文庫の庭先にて
大塚文庫の庭先にて
お忙しい中ご都合をつけてご来場くださいました皆様、関係者の方々ありがとうございました。

たくさんの方と作品や着物、自然について話をすることができました。
作品集を読んで内容に共感して下さりお越しくださった方も何人かいらっしゃいました。
実作を当てていただいたり光にかざして見ていただきました。

観る方の鑑賞力やコメントも私には大変参考になりました。
その中で「静かだけれど力強い」という画廊経営の方の言葉が特に端的に捉えられていて印象に残りました。そういう織物をこれからも織っていきます。
また着物や帯を織る時の最初の織り出し部分を使って仕立てた袱紗やミニ額装などもしっかりご覧いただきました。こういうものは拝見に値する内容がなければなりませんが好評をいただきほっとしました。

林まさみつさんの竹かごバッグも丁寧な作りで着物の時に使ってもこれなら生地を痛めたりしないと大変好評でした。私も使わせてもらいます。今後の展示会の予定などは林さんのブログをご覧下さい。

連日夏日、真夏日となった5月下旬でしたが三枚の自作の紬の単衣に帯を毎日替えて8日間を過ごしました。
蒸し暑い時こそ単衣の真綿系紬の真価は発揮されるのですが、それでも少しでも涼しく着るひと工夫についてなどは後日アップします。
着物や帯などをお求めくださった方には私たちのこれからの糧もいただきました。
心より御礼申し上げます。ありがとうございました。
若い織り手の育成とともに、私自身もやりたい仕事がまだまだありますのでこの道を切り拓くべく精進してまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
 大塚文庫の庭先にて
大塚文庫の庭先にて