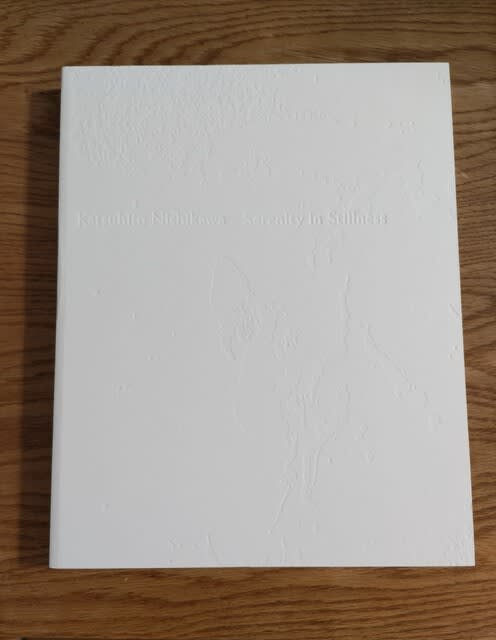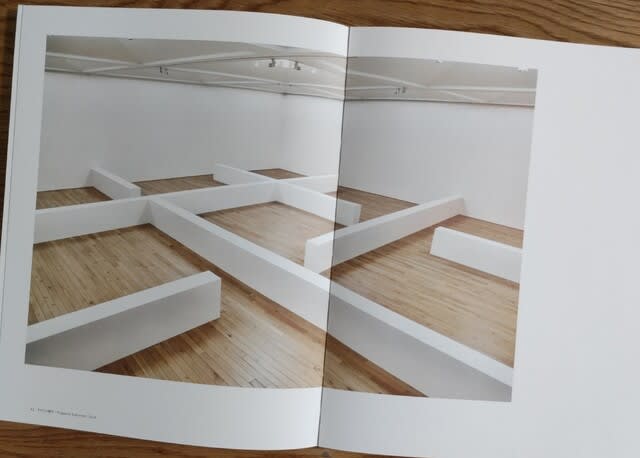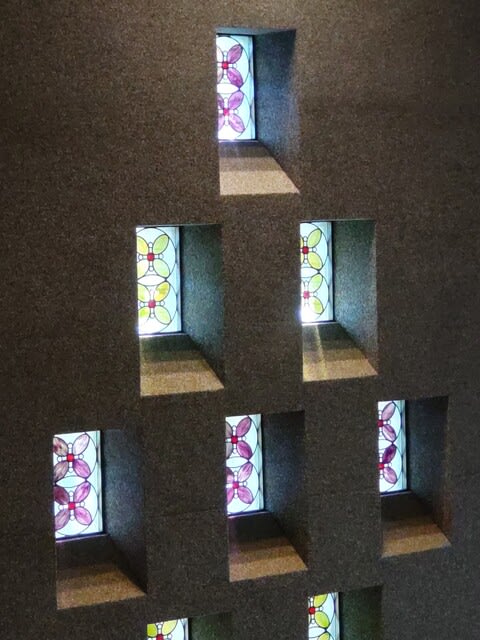昨年4月にスタートして1月まで、8回の講座を1セットとし、「紬基礎コース」として開催しました。
今期は関西方面から3名、埼玉、東京など、6名の方の参加となりました。
時間は2時間半ですが、内容は盛りだくさんで、全てを吸収することは無理だとは思います。
ただ、何か大事なことを感じ取っていただければそれでいいと思います。
知識も大切ですが、私は感性を目覚めさせることのほうがもっと大事だと思っています。刷り込まれた情報を一度捨てて、無垢な目、こころで臨んでもらいたいと初回にもお伝えしました。
こちらもなるべく五感に働きかけるような、実際に見てもらう、触れてもらう、植物の匂いをかいでもらう、機の音を聴いてもらう、指先を動かしてもらうなどの内容にしています。
私たち日々の暮らしの中、ものを作ることも、文字を書くことも、歩くことも、自然に触れることも少なくなり、ネットや、SNSの自分の好みの情報、あるいは行動データに基づいたアルゴリズムに導かれ、多数へ流れ、流される。
ものを浪費し、使い捨て、目の前のゴミが無くなればきれいになったと勘違いし、考えたり、工夫したり、汗をかくこと、苦労したりすることもない。
簡単、便利、安いが人を幸せにするのでしょうか?
そんな中、手仕事だの、草木染だの、紬の着物だのと、優雅なこと(!?)を学びに来る人はよほど恵まれた人たちと思われてしまいそうですが、紬塾の内容は紬織の知識だけではなく、私たちはどう生きればいいのか―、着物とどう向き合へばよいのか―、というところまで辿りつきたいと、それを学ぶ講座です。
それは紬の着物を始め、善く着ること、着ると言うことは何か、までつながることです。
初回に、最後に学びのレポート提出をお願いしておりました。
文字数など制約を設けず、自由に書いていただきました。
長文が多いですが、自分で感じたことを自分で考え、自分の言葉で綴って下さっています。
表現はそれぞれ違いますが、講座の熱気、真剣さが伝わってくる内容だと思います。紬塾のエッセンスだけでも共有していただければ幸いです。
25年度も前向きに検討中です。
以下、6名の方のレポートです。
お時間あります時に最後まで、じっくりお読みいただきたいです。
*******************
紬のこと、着物のことだけでなく、日々の暮らしの中での大切なことをたくさん学ばせていただきました。それは昔から日本人が大切にしてきた物事、生活の知恵、自然や環境を守ることなど多岐にわたり、その根幹にはそれらを作り出し大切に受け継がれてきた日本人の心があること。私たちはそれを大切にして未来に繋げていくために、今の自分の便利さを基準にせずに何が大切かを考え選び取っていく知恵と力を身につけることが大切であることを強く感じました。
『糸、色、織』では、繭から紡いだ糸を見せていただき、糸を取る体験させていただきました。繭から引く一本の糸の儚い細さ。けれど糸を引くときに感じる繭の重さは、蚕が命をかけて吐き出した貴重な糸であることを実感させてくれましたし、貴重な真綿と長年積み重ねられた人の技で紡がれ織られる着物の価値について改めて実感しました。
『とことん着つくす』は、先生が大切に使っていらっしゃる布を見せていただき、物を大切に使うための様々な工夫を知りました。運針で直線に縫われた古い布が生活の中で大切に引き継がれ使い込まれて力強く生き続けていることと、子どもが好きな服や柄を生活の中で使える形で残したお母様の愛情も大切に伝わっている素晴らしさにも感動しました。
『帯揚げを染める』
草木染めを初めて体験。工程は意外と簡単で楽しく、自宅の庭の木や葉を使って自分でもやってみたいと思いました。けれど作品作りとなると、色や濃さなどを素材に合わせて調整し思う通りに染め上げることは、とても神経を使う繊細な作業であり、作品として世に出せるまでに先生が重ねたご苦労を考えると、先生が作られた着物それぞれがどんなに貴重な一枚かを改めて考える貴重な体験になりました。
『運針で何かを縫う』
正しい運針を身に着けることが大切であることを教えていただきました。糸の使い方や縫う姿勢にも、日本の手仕事の知恵からくる美しさや無駄なく物を大切にする心が生きていることを学びました。
『日本の取り合わせ』
これはもう目から鱗。今までなんとなく同系色を合わせて安心していた私は、第7回以後、小物合わせが難しく頭を抱えてしまっていますが、それがまた楽しい! 自分のコーディネートに自信が持てないのですが、先生のブログや本も参考にセンスを磨いていきたいと思います。
『自然で楽な着方とは』
自然で楽な着付けについてのお話も聞くことができたこと、着物や帯の寸法や半幅帯の結び方のお話もありがたかったです。毎回、先生の素敵な着姿を拝見させていただけるのもうれしい時間でした。
手つむぎの糸を使い、染液を作り、染め、織りあげる。それを一人でされて作品を作られる先生の、紬に対する愛情を感じた9か月間でした。
作り手の人となりや、作品にかける思いも知って、良いものを見極められる目を持ちたいと思いました。
先生をはじめ、皆様にも心から感謝申し上げます。 (Y)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
茶道をきっかけに着物を着始めて、12年になります。きれいなかたちに着たいとがんばって着付けてきましたが、外側だけ整える着物との付き合い方に物足りなさを感じていました。仕事で疲れて心に余裕がないときほど「着物が着たい!」という叫びが体から響いてきて、もっと自分に根ざした着物との付き合い方を模索したくて、紬塾に申し込みました。
特に楽しかったのは、着物の更生の回です。先生のお父様の絣の泥大島が、先生の雨ゴートに変身した姿がとても新鮮でした。着物の更生とは、かたちを変えることで着物が前よりいっそうかがやくこと! と気づきました。
繭や植物、本当に上質な織物にふれたのも貴重なことでした。夜空に向かって深呼吸するような、見せていただいたお母様の古い弓浜絣の反物、深い藍色。また、桜で染めた先生の単衣紬の血のかよったピンクのうつくしさ。
着物は、体とたましいが帰る所、やすらぐ所と思いました。
「着物の寿命は自分の寿命より長い」という先生の言葉も大事な事実を含んでいます。いろいろなデザインの着物や反物に目移りしそうになっても、同じ着物をいつまでも飽きずに、心地よく着つづけることが本当の豊かさです。長く私の人生により添い、こなれるほど肌触りがよくなって、さいごは他のだれかに手渡したくなるような一着をもつ方が、ずっとぜいたくで幸せな着物との付き合い方だと思います。それは自分や着物と対話し、それらを知りつづける過程でもあります。
幸田文著「きもの」も、先生や他の受講者の気づきの話から、たくさん考えるヒントをもらい、良い織物を見て、みずみずしい植物からどんな色が出るかの冒険があって、そしてさいごの打ち上げは美味しくて!
本当に良い機会をありがとうございました。 (S)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
綿から糸を紡いで草木染をし、機織りした布を着尺に仕立てるということを学んでいた頃に、先生の紬織りのインスタグラムに出会いました。様々な色合いの着尺や帯に心惹かれ拝見している中で、紬塾のことを知り滑り込みセーフで塾生になりました。
昔の生活では誰もがしていた手仕事。確かに非効率的だけど、素材から携わり一つ一つの工程をへて布や着物になる。時間はかかるけれどもとても心豊かなひとときで、手間暇かけるというのは贅沢な宝もののような時間。
その大事な布を、形を変えてでも最後まで使い切る、無駄にしない。生活全般において言えること。
紬塾で書ききれない大切なことを沢山教えて頂きました。なんでも工夫して少しずつでも生活に取り入れたいです。
先生、皆様とても楽しい時間をありがとうございました。 (D)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一つ一つの講座が本当に充実していて、時間が経つのがあっという間でした。加えて、夏休みを過ぎた当たりから、その一つ一つが一本の線で結ばれて着物を着ることに向かって行くような感覚を実感し、どんどん楽しくなって張り切って出席しました。
①東洋的と西洋的
私は、第一回の自己紹介の時に、「決心しないとなんとなく着物を着て出掛けられない」、ということを話しました。この講座に参加するうちに、それは、もしかしたら洋服を着る心で和服を着ようとしていたからではないか、と思うようになりました。先生のお言葉の中に、キーワードがありました。再生、ありあわせ、着崩れることを恐れずに楽に着る、野暮と粋の取り合わせの違い、季節感、自然の色、植物の色など…。先生は俳句もされるそうで、そういう日本の伝統文化を通して、そのキーワードのことを学んでいきたいと切に思います。
②副読本「きもの」幸田文著
本を購入したのは、随分前ですが、小説としての読み方しかしておらず、どうやって読むのか不安でしたが、毎回、一人ずつ順番で読んで感想を言う中、先生がご指摘してくださることを頼りに、なんとなく着物を着ることの教則本のような読み方が出来るようになりました。色々なヒントが詰まった本だ、と改めて感じました。
るつ子にとってのおばあさんのような人が、私にも身近にいたら良いのに、と思いました。
衣替えのことが書いてある箇所があり、それはその家の主婦の家政技術を示すとのことで、「衣」がとても重要な時代だったと感じました。この本の時代設定は関東大震災前後なので今から100年位前、運針で家庭の女が着物を縫っていたことが、もう、日本昔話のようです。何だか、この100年の間に、大切な手仕事、手技を忘れて失ってしまったのだと悲しい気持ちになりました。
③運針
今回、受講するに当たり、運針は絶対にできるようになりたいことでした(過去に何度も挫折しているので)。実際に教えていただき、家でも動画を見ながら練習して、また針の長さを短いものに変えて、何とか型のようなものが出来るようになりました。とても嬉しいです。これからも、忘れないように日課にします。
私は運針というと、衿つけとか和裁に関係するものを縫うと思い込んでいましたが、先生が「布巾でも袋でも、なんでも縫えば良いのよ。」と言われて、目から鱗でした。それから、先生が、昔の着物は解くことを前提に縫われているとおっしゃって、それも縫い直してモノをトコトン使うことの表れだなと感じました。
私も、色々工夫して作り替えて、ものを大切にしたいです。 (Mk)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
偶然(きっと必然)辿り着いた紬塾のブログ。その中で目にした先生のお着物の画像に、なんて素敵なんだろう、、、と心を奪われ「中野先生のお話が聴きたい!」と思い立ったのが紬塾参加のきっかけでした。
関西からいざ上京。
初めて先生の紬に袖を通した時の高揚した気持ちが思い出されます。初回の緊張感も吹っ飛んで舞い上がるような気持ちを皆さんと共有した瞬間だったように思います。着物を自然光で見るということ、光や角度でも色が違って見えることをこの時に教わりました。
草木染めでは、お庭で蚊と格闘しながら皆でチップを作ったり、キッチンで染液を煮だしたり、全ての工程が新鮮で楽しい経験でした。
取り合わせのワークショップでは、(帯揚げや帯締めの)微妙な色の違いでこんなにも雰囲気が変わるものかと、取り合わせの妙に驚いたり感心したり。そして素晴らしい紬のお着物や帯を前にうっとり、ため息の連続でした。
私が紬塾の中で特に印象深かったのは意外にも「着物の更生・運針」の回でした。「意外にも」と言うのは、私は取り合わせやワークショップの回をとても楽しみにしていたからです。
更生の回に見せていただいた写真集「襤褸の美」(額田晃作)は圧巻でした。ボロと美、貧しさと豊かさ、一針一針に込められただろう想いに感性が揺さぶられました。運針の回では、先生のお母様がてんとう虫のワンポイントを活かして作られた傘袋がとてもチャーミングでその後の創作意欲が刺激されました。
自分で縫った、端切れを利用した花瓶敷は不揃いながらも赤い糸の縫い目が気に入っています。
ものを大切に使い切ることは、買わずに我慢するといったマイナスの行為ではなく、とてもクリエイティブなことだと感じることが出来ました。
今回、紬塾を通じて着物文化や紬の奥深い美しさの「入り口」に立つことが出来ました。同時に創意工夫して日々の暮らしを楽しむこと、先人の知恵を受け継ぎ、人や物や自然を慈しむこと、といった大切な気づきを得て、着物を着ること、日本文化や手仕事文化に触れることがますます楽しみになっています。これからは鈍った五感をフル稼働させて毎日を豊かに過ごしたいと思います。
中野先生、素晴らしい学びの時間をありがとうございました。 (K)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<受講の目的>
きもの雑誌に5年籍を置き、逸品に触れ基本的な染織知識も得られましたが、そこから自分の目指す「きも
ののおばあさん」になるまでに、見えない壁を感じました。
取材でお目にかかって、密かにあこがれた中野先生にヒントをいただければと、「今年で最後(かも)」と
いう言葉が一押しとなりました。
<各講義の感想>
■第1回 オリエンテーション
週末の楽しみとして比較的軽い気持ちで参加したため、先生の厳粛な雰囲気、受講生の生真面目な態度に緊張してしまいました。これは〝本気のやつ〟だと遅ればせながら気づいた次第。
■第2回 糸、色、織について
早くも欠席を申し出て皆様にご迷惑をお掛けしました。この頃は「全編通じてひとつの体系に触れられる」講座の特性が理解できておりませんでした。無事参加でき、ひとつの繭から皆がお土産の糸をいただき、ありがたみを感じました。いまも出窓にいるカバの置物にリボンとして飾っています。あのか細い糸が代々人間を守ってきたとは神秘的ですし、あのか細い糸から衣類を作りだした人間も驚異的です。
■第3回 とことん着尽くす
長年衣類が好きで、だからこそ和洋問わず次々と欲しいものが現れ、欲望に従い入れ替えてきましたが、その習慣を見直すことになりました。1度手に入れた布は最後まで生かし続ける責任がある。襤褸の迫力からそんな戒めを受け止めました。
■第4回 半衿、帯揚げを染める
わいわいと楽しかった思い出。意のままにならない植物染料を前に、慣れない生徒を抱え、手慣れた先生も焦り気味でいらしたのが面白かったです。半面、何度経験していても一回ごと真剣な先生のすごさもちゃんと感じました。
■第5回 運針で何かを縫う
第3回に続き、日々の生活へ戒めを感じた回です。「布目を通す」概念を初めて知りました。縫う前に真っ直ぐ整える姿勢が、思いのまま裁断する洋裁と対照的に感じます。
裁縫は下手でも嫌いではないので、よい暇つぶしとなり無事職場の先輩への贈り物が完成しました。
■第6回 日本の取り合せ
取り合せの前提として季節やシーンを明確にする教えに、きものは自己主張より調和のために着るとよいと感じました。
日頃「場に馴染むように」「同席の方に揃えて」という教えには共感しませんが、もっと広く「景色、自然、地球の一部である自分」を意識すると素敵だなあと。
■第7回 自然で楽な着方
紐を使わないお太鼓結びの方法にびっくり。現場では締められましたがそれ以降はうまくいきません。
しかし、補整具やプラスチックの衿芯やコーリンベルトなど、何となく違和感をもっていた道具を先生はやはりお使いにならず心強く感じました。
■第8回 上質の半幅帯を愉しむ・仕立について
半幅帯をキュッと結んで出る着慣れた感じに憧れますが、何度習っても、覚えられないのです。
そんなことより最終回は、打ち上げでの情感豊かな歌声とほろ酔いの会話が心に残りました。
<全体>
仕事上どうしても「新たにきものを買うこと」に興味が向いていましたが、それよりも「いまある布と向き合う姿勢」「きものが寿命を全うするまで共に生きる覚悟」が大切と感じました。
きものを着ることは、布の来た道を知り、着た後(自分が死んだ後まで)の処置を考える、そういう地味な責任を果たすことと一体なのだと思います。
しかし性懲りもなく、先生の美しい作品がやっぱり欲しい私です。 (My)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・THE END