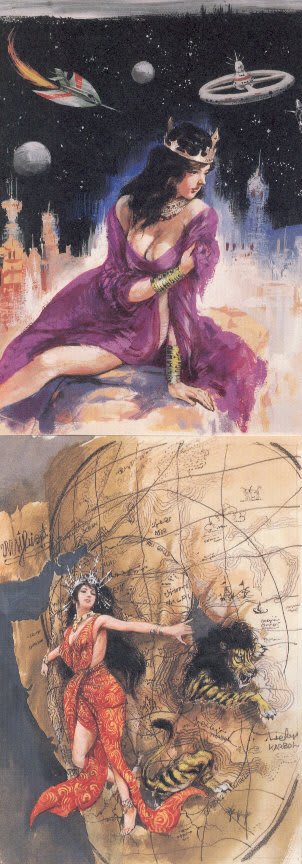姜尚中はその著「悩む力」で、夏目漱石やマックス・ウェーバーの生きた1900年前後の時代とほぼ100年後の我々が生きる今の時代がよく似ているという。今、引きこもりや鬱が社会現象になっているが、100年前社会問題になった神経衰弱という心の病が漱石の小説によく登場するし、世紀末的病的な文化や猟奇的な事件が起こったことも現代と似ているという。そして、100年前にその時代を見通していた二人の書いたものから、現代の悩みを解決するヒントを見つけ出そうとする。
1.
自我(とは自分とは何かを自分自身に問う意識)は他者との関係の中でしか成立しないのだが、自我が肥大すると、すなわち自尊心、エゴ、自己主張、自己防衛が過大だと社会から孤立し、鬱になったり宗教や
スピリチュアルに助けを求めたりするようになる。「心」の先生は昔自分と今の奥さんをめぐって争った友達が失恋のために自殺したのではなく自分との友情を失くした孤独感で死んだと知ったときに自ら命を絶つ。漱石も自我のために何度も神経衰弱になり胃潰瘍を患った。自我の悩みを解決する方法は、まじめに悩み、まじめに他者と向き合うほかないという。
2.かつて
お金は労働の報酬であったが、今やお金のためにお金が回り、回れば回るほど増えていくという”金融寄生型(パラサイト)資本主義”になり、これこそが先端的とされている。「それから」や「明暗」には親の金で暮らす人間が出てくるし、「明暗」や「道草」には”たかり”が出てくる。彼らはいわば資本主義のパラサイトである。”金はあるところにはあり、だから取ってもいいのだ”という論理である。我々の世界は100年前よりも金融寄生型の仕組みにがっちりと組み込まれていて、株、保険、預貯金、年金などすべてマネーゲームの所産である。我々はもはや清貧には生きられないので、”できる範囲でお金を稼ぎ、できる範囲でお金を使い、心を失わないためのモラルを探りつつ、資本主義の上を滑っていくしかない”という。
3.科学や合理化は人間本来の生き方について何も教えてくれない。わけもわからないまま時代に流されるのはいやだが、だからといってそれにこだわって旧時代に生きるのはもっと愚かであると「夢十夜」は教えてくれる。情報過多の時代では、身の丈に合った
知識を身につけていくことが大切だ。
4.「三四郎」は美禰子からストレイシープという言葉を突然ささやかれる。
青春とは未熟で不器用だけど純粋に何かを探し求めることである。青春は、挫折があり、失敗があるからいいのであり、年齢とは関係ない。
5.
宗教は、私はなぜ生まれてきたのか、私はなぜ不幸なのか、なぜ病気になったのか、なぜ人を敬わなければならないのか、なぜ働かなければならないのか、死とは何なのか-----といったことに予め答えを用意してくれている。だから、信仰に入ると人は悩む必要がなくなる。「門」や「行人」の主人公のように宗教に頼らず、漱石もウェーバーも、自分の知性を信じて自分自身と戦いながら気が狂いそうになりながらも独力で立ち向かった。一人一宗教的に自分を信じ、自分でこれだと確信できるものを見つけるまでまじめに悩み続ける。
6.「それから」の代助は”金があるから働かない”という。
働くことの意味は、”社会の中で自分の存在を認められる”ことにある。働くことで自分が社会の中で生きていていいという実感を得ることができる。
7.漱石は小説の中で不毛の
愛を描いているが現在はもっと不毛になっている。現代人は誰を愛するのも自由、何を愛とみなすかも自由になったが故に、判断基準を失っている。誰もが口にする”自分が幸せになりたいから”という考え方で選ばれた愛は代替可能な愛であり、愛が消耗品になっていく可能性がある。代替可能な愛を選んだあと、”ちょっと違う”と気づいた人は、”本物の愛はどこにある”ということになり、ティーンエージャーの時に卒業したはずの純愛や即物的な性愛という極端な行動に走ってしまう。
漱石は妻にときに厳しい、時に思いやりあふれる手紙を書いていて、小説の主人公たちの愛も一生懸命で決してお手軽ではない。愛とは、そのときどきの相互の問いかけに応えていこうという意欲のことで、そのときどきで愛の形は変わり、幸せになることが愛の目的ではない。
8.「硝子戸の中」で漱石は、悲痛な身の上にある女性の生きるべきか死ぬべきかという問いに対し、
死の尊厳を尊びはするが自分の命は自分のものではなく父祖から与えられたものという考えから”死なずに生きていらっしゃい”という。現在、この考えに説得力はない。人とのつながりを求めることで生と死を考えてほしい。自分が相手を承認し、自分も相手に承認され、そこでもらった力で生きることができる。生きている意味に確信が持てたら鬱にはならない。
9.老人力とは、撹乱する力である。死を引き受ける力である。小悪党とかプチナショナリストとかプチ潔癖症とかちょい悪おやじとかが流行っているが、”小”や”プチ”や”ちょい”などはやめて、横着にスケール大きな二生目を生きたい。若い人にも大いに悩んで突き抜けたら横着になって破壊力を持ってほしい。
読み飛ばした後は姜尚中の言いたいことが、ピンとこなかったけど、こうして書いてみると何となくわかってくる。何となくわかったと思ったことは、実は姜尚中の言いたいことではなく、自分の思い込みに合致する言葉を意識せずに巧妙に拾いだしただけなのかもしれない。別に読書感想文に点数が付けられるわけじゃないので、それでもいいや。